- 「環境改善活動と本来業務を一体化する」
企業があるいは企業で働く者が行っている環境改善活動において、業務でないものがあるのでしょうか? 単に人気とり、企業のイメージを良くし評判をあげようとしてやっていることであっても、それはやはり業務の一環であり、従事者は業務命令として行っているはずだ。
たとえて言えばサービス残業とか、接待ゴルフといえど、賃金が支払われるか否かに関わらず、仕事の一環であるという認識はあるのと同じだ。
会社の仕事・業務と関わらないことをしているとすれば・・そんな会社は何を目的にしているのでしょう?
似たようなものに「業務目標と環境目標を一致させる」なんてのもある。
うーん語っている意味が全然わかりません。私にとってはロゼッタストーン?
こんなことをおっしゃる方は、企業で仕事をしたことがないのでしょうか?
- 「EMSを導入する」
ここでEMSとは環境マネジメントシステムのこと。私には「EMSを導入する」という意味がわかりません。と言いますのは、どの会社にもマネジメントシステムというのがひとつあるそうです。そのマネジメントシステムの一部で環境管理を行う部分をEMSというそうです。(参照ISO14001:2004 3.8)
ということは、EMSのない会社はないことになります。「導入する」ということは、今までなかったところに取り入れるという意味の日本語かと思います。今まで存在していたなら「導入する」必要はないというか、「導入する」こと自体不可能で前述の文章は言葉の矛盾でしょう。
これまた似たような不思議な言い回しに「EMSは有用である」と語るお方もいらっしゃいます。
従来から存在していたEMSが有用な会社もあるでしょうし、有用でない会社もあるでしょう。すべての「EMSが有用である」はずはなく、そう語った人は嘘をついているのか、語ったのではなく騙ったのかもしれません。
- 「ISOを企業戦略に反映させる」
ISOってものは企業戦略を超えるものだったのですか!?
するとISO(ISO規格のことだと思うが)を理解すれば、企業戦略はもう考えることなく策定でき、それを粛々と進めれば、輝かしい成功物語が・・なんてことがあるはずがない。
ISOなんてツールに過ぎない。企業がどのようにして社会に貢献するのかという理念がまずある、そしてそれを実現していくのが企業戦略である。そういう高度な経営の狙いや判断に比べて、ISOなんてのは数階層下に位置することは間違いない。
もちろん、企業活動を管理し事業を推進していくには、ISO規格に書かれていることを備えることは有効だと考える。だか、どう考えても「ISOを企業戦略に反映させる」なんて言ったら「おまえ、正気か?」と言われても仕方ないだろう。「ISOを企業戦略に反映させる」を文字とおり捉えると、ISO規格は企業戦略の上位にあるということですよ。
どうしても言いたいというなら、『ISOを企業戦略に活用する』くらいの表現をしてほしいところだ。
ちなみにISOと企業戦略の上下関係は私が語る前に多くの人が研究している。
- ISO取得
形があるかないかはともかくとして、ISOってもらえるものなんですか?
まあ、そんなことを言う人はチョー初心者だろうから、論評するまでもないか?
- プランドューチェックアクション
まっとうな本には書いてない言葉です。プランドューチェックアクションっていったいなんのこと何でしょうか? 別にカマトトぶっているわけじゃありません。
【カマトト】
知っているくせに知らないふりをして、上品ぶったりうぶを装ったりすること。また、その人。 蒲鉾(かまぼこ)は魚(とと)か、と尋ねたことに由来するという。
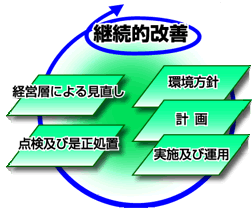
えーと、ISO14001の序文にはPlan-Do-Chech-Act(PDCA)とあります。序文の図には動名詞形でPlanning Implementation and operation Checkingという表現があります。
ISO9001にもPlan Do Check Action という語は見当たりません。
齢六十にして、いまだ学ぶことが多いと感じ入ります。 
- 「システム構築」
認証機関もコンサルもお猿さんも会社の事務局も、システム構築って言います。
システム構築ってなんでしょうか? システムを作り上げることでしょうか?
私は過去18年間にISO9000sが4回、ISO14001が4回、コンサルとか支援でなく認証の当事者として関わってきました。またISO認証のお手伝いはその二・三倍はしております。いずれの場合も、システム構築をした記憶がありません。なにをしたかというと会社の現実を調べ、そのまま文書化しISO規格を満たすことを明白にしただけです。
システム構築をされた方は、いったいどんなことをしたのでしょうか?
会社の定款の書き換え、職制の改革、職務分掌の全面見直しでもしたんでしょうか?
そうでなければ、システム構築なんて大言壮語はできませんよね?
何年か前、あるところで認証支援をしていて審査の時、審査員が「このシステムは何カ月動いているのですか?」と聞かれたことがあります。
この言葉、もう違和感120%でしたね。マニュアルに書いてあるシステムはもう何十年も動いているのです。ただそのシステムをマニュアルに文字として書き表したのはほんの2か月前でしたけど。武士道とは死ぬことと見たり、ISO審査とはバーチャルと見たり
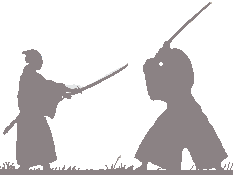
- 「マネジメントシステムはやはり人に尽きる」
ある雑誌に某認証機関の幹部が書いていた言葉です。これもまた非常に摩訶不思議な言葉と受け取りました。考えるまでなく、私はそう感じたのです。みなさんはそう感じませんか?
一般の企業の管理者が、部下の出来不出来を嘆くのは良くあること。もちろん平社員が上司の無理解、無能力を嘆くのもこれまたよくあることです。
しかしいろいろな人がいる組織を束ねて、一つの方向に協力させるということが上司の役割、これすなわちマネジメントです。そしてそういうことを個人的能力ではなく、仕組みとして作りあげ実施していくのがマネジメントシステムじゃないですか?
ましてや認証機関においてその業務推進が個人の能力に尽きるというなら、そりゃその認証機関のマネジメントシステムが機能していないということ、更にはマネジメント能力もないということを白状しているということです。
みなさ〜ん、幹部がこのようなことを語っている認証機関には絶対に審査を頼むんじゃありません。だってそんな認証機関が我々の会社のマネジメントシステムがあるべき姿か、有効かなんて判定できるはずがありません。
- 「環境経営の推進と環境ISOの運用は、本来同期化すべきものだが、社会の変革が激しい時は、目標設定などが乖離することもある」
へえーそんなふうになるのですか?不思議なこともあるのですね。私は単純に元々この会社の本来のEMSがISO用に見せているEMSと二重帳簿であったのだと思います。
通常は片方が変化しても他をそれに合わせる時間があるので二重帳簿がばれないのですが、変化が激しいとそれが追い付かないので乖離してしまうのです。
常にあるがままのEMSを審査で見せていれば、いかなる状況変化でも乖離しようがありません。
つまり、文書化される前に通知や議事録で仕事はどんどん進みます。教育訓練なんて絵に描いたようにしているわけないでしょう。内部監査だって定期的にあるわけはない。法違反だって起きるだろうし、事故も起きる。そういうお祭り騒ぎのような毎日が実態であり、その実際のEMSを見せて規格適合でしょうと説明していれば良いのです。バーチャルなものを見せているから「社会の変革が激しい時は、目標設定などが乖離することもある」なんてたいそうな言い訳を語るようになるのです。
「当社のISO用EMSは実際のEMSと違いまして、社会の変革が激しい時はその差をごまかしきれないのです」と言いなさい。
- 「環境ISOには2つの活用がある。1つは、既存の事業活動を所与として、環境ISOを当てはめるという消極的な活用。もう1つは、環境パフォーマンスを向上させるために、マネジメントシステムの仕組みを変革していく積極的な活用だ。」
私はこの理屈は間違いだと思う。以前、品質について語ったが、ISO規格ってそんなにたいそうなものなのでしょうか? 過去企業の先輩たちが、そして自らが知恵を絞り失敗を反映して作ってきたシステムを超えるものを提供するなんて思うのはおかしいといってもいいだろう。
どうしてもISO規格の価値を主張しようとするなら、「既存のEMSを改善するためにはISO規格を参考にすることは有効である」程度ではないのでしょうか?
私が20年前にISO9001:1987に出会ったとき、その中に見たのは私の度重なる失敗から得た教訓でした。それを超えるものは・・ありませんでした。エレガントに体系化されてはいましたけど・・
- 「ISO業界」
ISO規格は18000くらいあるそうです。するとゴムの規格、抜取検査の規格、公差の規格、図面の書き方の規格ごとに業界があり、業界団体があるのでしょうか?
私はマネジメントシステム規格で食べている団体しか心当たりはありません・・
ところでこの業界団体には、一般の営利企業だけでなく、大学の先生、財団法人、社団法人、個人経営からNPOまでからんでいるようです。不思議な業界団体です。
