2013.04.03
第三者認証制度というビジネスモデルについて書いたことは、過去いくどもある。
・
第三者認証というビジネスモデル
・
第三者認証というビジネスモデル 2
・
第三者認証というビジネスモデル 3
そんなことについては、もう書ききったとは思うけれど、最近、外資社員様と意見交換をしたことから思いついたことをまた書く。
お断りしておくが、外資社員様のご意見からアイデアをいただいたが、文責はすべて私おばQにある。
ビジネスとして成り立つということはどういうことだろうか? あるいはどういう場合なのだろうか?
ドラッカーとかポーターとかコトラーなどを引用すれば小難しい話になるのだろうけど、非常に単純化すれば「社会から必要とされること」が絶対というか最低の必要条件だろう。
私が子供の頃、2キロほど離れたところに一人のオジサンがいた。その人は、農家の次男か三男で田畑を相続できなかったので、ド田舎で便利屋のようなことをしていた。
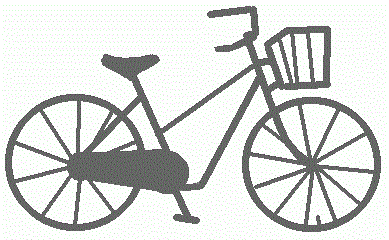
午前中に相当な範囲の農家を自転車で回って御用聞きをして、それから町に行って頼まれたものを買ったり仕事をしたりして、午後にはそれを配達とか返事を伝えていた。
具体的にどんな仕事かといえば、みそ・醤油、ソーセージ、歯ブラシ、野菜の種などを買ってくるとか、郵便局で郵便を出してくるとか(田舎は1日1回しか郵便物を集荷しない)、どこそこに荷物を届けるとかということであった。そういうことをして手間賃をもらい、それで奥さんと子供を養っていた。やがておじさんの自転車はバイクになり、いっときは順調に見えたが、1960年代末にそのビジネスは成り立たなくなった。
いろいろな変化があったからだ。その頃になると田舎にも小さなスーパーができて日用品が買えるようになったこと、農家の人が軽トラを持つようになり自分で街に買い物に行くようになったこと、各家庭に電話が普及して直接お店に注文できるようになったことなどがある。
 |
各家庭に電話が普及したのは1975年頃である。それまで福島県では電話局の能力がなく、電話をつけたいといっても何年も待たされることは珍しくなかった。今では想像もできまい。
豊かさというのはいろいろな尺度があるが、日本は時間と共に情報通信、道路、信号機などのインフラも整備されてきて豊かになってきたということを実感する。今の人はそれが当たり前だと思っているだろうけど
|
その後おじさんは近隣の農家の手伝いなどしていたが、暮らしは大変だっただろうと思う。子供の頃からそのおじさんを知っていた私は同情した。
時代が変わって商売が成り立たなくなったというものはそれに限らず数多い。
「おじいさんのランプ」なんてお話もある。詳しくはリンク先を読んでいただくとして、ランプを売って儲けた人が、電気が来るようになって仕事がなくなったというお話である。
逆に時代によって、いっときでもものすごく儲けたという事例もある。
私が生まれた近くの町の葬儀屋のご主人は、体格が貧弱で兵隊検査で
丁種とされたという。
甲乙丙丁の丁で、要するに戦争たけなわの時でも兵隊にとられないほどの虚弱体格だった。もっとも徴兵検査判定基準では丁種とは「目・口が不自由な者、精神に障害を持つ者」とあるが、その人は近眼で体は小さくきゃしゃではあったが、まともな頭脳と運動能力を持っていた。
徴兵検査判定基準
| 区分 | 基準 | 兵役区分 |
| 甲種 | 身体頑健 | 現役に適する |
| 乙種 | 第一 | 乙であっても現役を志願する者
抽選で当たった者 |
| 第二 | 抽選で外れた者 |
| 丙種 | 身体上欠陥の多い者 | 現役には不適だが、国民兵役には適する |
| 丁種 | 目・口が不自由な者、精神に障害を持つ者 | 兵役に適さない |
| 戊種 | 病中または病後など | 兵役の適否を判定出来ない
|
太平洋戦争も激しくなり、その町からも近隣の田舎からも若者がどんどん出征し、多くの戦死者がでた。そこには葬儀屋が1軒しかなく、その葬儀屋は大儲けした。その奥さんは「亭主にするなら丁種にしろ」と語っていたそうだ。もちろん私が生まれる何年も前のことだ。
その後、その葬儀屋は儲けで周辺の土地・家を買って葬儀屋ばかりでなく大きな商店になった。街の人は陰で「あそこの店は人の命で儲けた」と悪口を言っていた。私が中学生の頃は、大きな店のほかに蔵もあったし何軒も別宅があり、田舎の典型的なお金持ちだった。もっとも21世紀の現在は孫の代になっているが、その町にも別の葬儀屋が2軒あるし、最近は葬祭互助会のシエアも大きくなり、葬式を独占していたなど昔の話である。持っていた別宅もだいぶ手放したようだ。栄枯盛衰は世の流れか・・・
おっと、話がドンドンそれていく。ここで言いたいことはどんなビジネスも商売も、世の中から必要とされないと存在できないということだ。
では必要とされれば存在できるのかといえば、必要とみなされることは事業継続の必要条件であって、十分条件ではない。十分条件とは企業として継続できるだけの利益が確保できることである。
どんなビジネスでも提供する製品あるいはサービスが、必要なもの、代替えが聞かないもの、独占的なもの、供給側が価格を決定できることが望ましい。
購買者にとっては好ましくないけどね
では第三者認証というビジネスモデルをいろいろな観点から考えてみる。
経営戦略とは一般的に次のようになるらしい。
| 経営戦略 | |
| 成長戦略 |
|


|
|
競争戦略 |
|
 |  |  |  |
| ドメイン | 資源展開 | 競争優位 | シナジー |
| バリューチェーン | |
さて、振り返って認証の現状を考えよう。
ISO認証企業が少なくなったとはいえ、認証件数はQMSで4万、EMSで2万あるわけだ。これだけ多くの認証企業があれば、認証とか規格の解釈という情報はあふれていますから、そういうことについての情報の価値は下がる一方です。ISOコンサルなんて必要性が下がる一方、手足を動かす代行業でないとお金にならないのかもしれません。
また市場経済では価格は需要と供給のバランスで決まります。認証企業が減って認証機関が減らないなら審査料金は下がるのは必然です。審査が減って審査員が多いなら日当が下がるのも当然です。
これはどんな製品にもサービスにも共通する原理で、パソコンでも、大型テレビでも同じです。ここで問題というか重要なことは、通常の製品やサービスにおいてはこのプロセスにおいて、製品の質が上がり値段は下ります。大型テレビは、同じサイズのテレビの値段が下がっただけではなく、大型化して画質も上がったのに値段は下がる。質が変わらず、値段が下るだけでは、市場競争に勝てませんし、単に値段を下げるだけではシェアを増やせても、最終的には事業として生き残れません。それが市場原理でしょう。
ではISO認証というビジネスにおいてそこのところはどうなのか?
つらいのは提供するサービスはグローバルスタンダードで差別化が困難ということです。差別化するとしても審査というサービスそのものではなく、サービスの周辺しか差別化できません。例えば夜間とか休日の審査をするとか、腰の低い審査員を派遣するくらいしか工夫する余地がない。しかし、考えてみるとタカピーな審査員が存在したということ自体、異常なことではある。
|
タカピーも死語となってしまった。若い人のために言うと、タカピーとは「高飛車」と「people」を組み合わせた言葉で、「高飛車な人」のこと。
|
認証事業の参入障壁は低い。認証機関のえらいさんが引退すると、自分で認証機関を作ってしまうケースもあるが、そんなことは普通の業界では考えられない。商社などで人脈が広い方が引退してその人脈を利用する会社を作るとしても、商社そのものではなくコンサルとか情報提供というサービスくらいだろう。
認証機関にいて、ひいきのお客さんがいたり子分がいたりすると、独立して認証機関の社長になるということは特異なことだ。ご本人は社長になって得意だろうけれど。
リソースであるが、私が過去あいまみえた審査員の多くは、例えば品質なら品質保証に詳しいとか、環境の審査員なら環境管理に従事していたという方にあったことはほとんどない。品質の審査員なら、せいぜいが品質管理とか製造部門の管理者が多かった。それを悪いとは言わないがせめて品質保証の審査なら品質保証について詳しい人であってほしい。
|
まさか品質保証と品質管理の違いくらいは分かっているのだろうなあ?
某E塚教授はその違いを知らなかったようだけれど・・・
|
環境の審査員で公害防止管理者をしていました、省エネで頑張ってました、公害を出した時は行政との対応や近隣に謝りに行ったりしました、という経験のある人に私は審査してほしい。大手企業の環境部長でしたとか、ISO認証の中心として活動しましたという人にまっとうな審査ができるとは思わない。
だが審査員の質は審査員に責任があるわけではない。認証機関の責任であることはもちろんだ。今はある程度、市場原理が通用しているが、20世紀は業界とか親会社、あるいは顧客からの要請などで、依頼する認証機関が決まってしまうというしがらみがあったから、派遣する審査員の質がどうあれ認証機関はあぐらをかいていられたのだ。
いや正直なことを言えば、業界設立の認証機関は業界傘下の会社の管理職の受け皿としての性格を持っていたと思う。はっきりいえばそのために設立された認証機関はたくさんある。世間とあまりかかわりのない規模が小さいビジネスなら、それもあるかもしれない。だが認証ビジネスがある程度の規模になると、そのようなことのひずみが大きくなり市場の期待に応えられなくなったということなのだろうか?
そうならないためには、どこかでビジネスのありかた、認証機関の姿勢を正すことが必要だったのだけれども、認証関係者はぬるま湯から出ることも叶わず、ずるずると今に至ったということではないのか?
そういう認証機関が提供するサービスは当然ながら市場で通用せず、ましてシュリンクする市場においては取引先として選ばれなくなり存在できない状況であろう。
認証というビジネスを継続するためには、真に良いサービスを提供すること、そのためには他の認証機関が提供できないようなものでなければならない。だが参入障壁が低い状況では、そのようなことがそもそも可能なのかどうかもわからない。
あるいはISO認証というサービスは本質的に、廉価で陳腐なもので、優れたサービスとは無縁なのだろうか?
そうであれば認証ビジネスは、安売り認証機関にお任せして、人件費の高い認証機関は撤退することが社会のためになるだろう。携帯電話でも液晶でも半導体でも、同じ程度のしろものなら、韓国や中国の会社にコスト競争では負けてしまったように、それが市場原理なのかもしれない。
|
先日、同志名古屋鶏様から聞いた悪い冗談というか実話というか、韓国の太陽光パネルメーカーは製品の保証期間が25年だったけど、すぐに倒産したということです。倒産するなら保証期間が何十年でもいいわけで・・・それでも当面のビジネスでは勝利するでしょう。
|

本日予想するご質問
私が経営について詳しいのかというご質問があるでしょう。
白状しますと詳しくありません。でも一応私は、某大学から学士(経営学)という学位はいただいております。アハハハハ

本日の予言
外資社員様からツッコミがあるに違いない。
外資社員様からお便りを頂きました(2013.04.08)
おばQさま
私の判りにくい話を、改めて判り易い話として再生して頂き有難うございます。
このように、経営の観点から理路整然と説明頂くと、判り易いけれどツッコミが難しいですね(笑)
私の会社では、ISO17025の認証取得をしましたが、その認証会社では社長自ら営業し、説明し、審査をされておりました。 審査員として動く時は、当然 社長という肩書は無関係です。
審査では、別の審査員もおりますが、ISO17025固有の「あいまいさ」の規定について、実際の業務に則して、合理的な解釈と説明を頂き、大変参考になりました。
そんな事もあり非常に好感を持ちました。
私の会社は、中小企業ですから、社長が営業、技術として働く事は当然なのですが、大きな会社から天下った人には、出来ない事なのかもしれません。ですから、お書きのように頭の低い人というのが、評価される事自体が、体質改善の状態のリトマス試験紙なのかもしれません。
もしそれが当然になれば、別の観点:顧客業務への理解度、説明の判り易さ、審査の合理性などが評価のポイントになるのだと思います。
この項目が評価の中心になるようになれば、経営に貢献できるかを始めて議論できるように思います。
違和感を覚える人が多いかもしれませんが、あえてビジネスモデルで例えれば社労士に似ています。
社労士は、建前では会社に貢献とか、労使の良い関係を実現とその理想を言います。
しかし、実際には対価を払う会社に対して違法にならないラインを明示する事が重要なサービスです。
もちろん社労士に問題ありではなく、お客である会社が費用を払う価値の一つは、そこにあるという意味です。
社労士も、資格をもった「先生」ではありますが、今では偉そうにしている人は見たことがありません。
無茶をする会社、コンプライアンスなんて面倒と思う会社側に、いかにして法規との調整をするかに努力して、対価を貰っています。 なぜそうなるかと言えば、「違法だから駄目だ」と言った瞬間に、別の事務所に頼むからサヨウナラと言われるからです。
国家資格を持った社労士でもそうですから、認証会社が そうでなくていられるはずがないのだと思います。
様々にある認証会社の中で、生き残れそうな会社は、すでにサービスの質を問題にしており、それと値下げ(または対価以上の価値)を実現しているのだと思います。
そうした会社だけに、絞られてくれば、自ずと質は上がるのかもしれません。
そうなるには、本当は認証会社 自らが、自分を認証して、自分のサービスが何かを明示できて、他社との違いを説明できる必要があります。 それは、どのような業界にも共通したビジネスのあり方だと思います。本当は誰かに証明して貰うのが客観性がありますので、まともな会社は第三者による評価や、国を越えた相互認証、外資ならば本国機関によるオーディットなどを行っています。
となると結局、ISO認証もビジネスで特別でないのだ、と当たり前の事に、帰結してしますのですね。
|
|
外資社員様 いつもご教示ありがとうございます。
あるべき姿とか結論などは初めから見えているのですね。認証機関はサービス業である。サービス業といってもひたすら相手の言うことを聞くということではなく、役務を提供するということです。それは価値あるサービス(役務)でなければお金にならないことは言うまでもありません。しかしお金になる役務を提供できない会社が認証とか認定とかコンサルをしているということ自体が問題だということでしょう。
世の中はしがらみがあって、無駄金と知りつつそういうサービス業にお金を払っていたけれど、もうやってらんねーよと言う時点に至ったということかと思います。
おっしゃるように、世の中の通常の役務提供者、社労士などははじめからしがらみもなければ恩も義理ないから、まっとうな役務を提供できる人のみが仕事をしているということでしょうか。
人生不可解なりならぬ、ISO不可解なりなのでしょう。
|
うそ800の目次にもどる
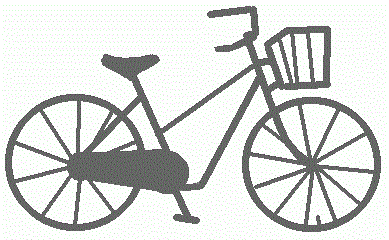 午前中に相当な範囲の農家を自転車で回って御用聞きをして、それから町に行って頼まれたものを買ったり仕事をしたりして、午後にはそれを配達とか返事を伝えていた。
午前中に相当な範囲の農家を自転車で回って御用聞きをして、それから町に行って頼まれたものを買ったり仕事をしたりして、午後にはそれを配達とか返事を伝えていた。

