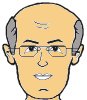16.09.19
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しここで書いていることは、私自身が過去に実際に見聞した現実の出来事を基にしております。また引用文献や書籍名はすべて実在のものです。
前回の続きである。
三木は小畑とまだファミレスで話をしている。小畑の話は三木の耳に心地よくはなかったがなるほどと思うこともある。
「小畑さんは著しい環境側面の決定はどのように指導しているのですか?」
| |||
「認証機関はどこかを聞いて、そこの考えにあわせます。認証機関を決めてないときは外資系を推薦します。外資系は変な理屈をこねませんから」
| |||
「認証機関の考えに合わせるということですか?」
| |||
「そうです。つまらないところで片意地張ってもしょうがないでしょう。どうせ結論は決まっているわけですし」
| |||
「それじゃあ点数にすることが多いわけですか?」
| |||
「そうですね、あれが一番もめなくてよいです。アハハハハ、まったくあんな方法に意味があると考えている人の頭の中を疑いますよ。当然カラッポでしょうけど」
| |||
三木は小畑の言葉を聞いて、カチンときた。 | |||
「点数法も方法の一つではありますね」
| |||
「方法のひとつではありますが、論理的でないでしょうね。 ずいぶん昔のことですが、ネットにいろいろフォーラムなんてのがありました。お聞きになったことありますか?」 | |||
「名前だけは・・・入会はしませんでした」
| |||
「ISO14001認証が始まった頃は、ISOについての情報が絶対的に不足していましたから情報交換の場としてはありがたかったですね。あるとき著しい環境側面を決めるのに点数は間違いだと私が書きこんだことがありました。そしたら間違いではない、その証拠に点数を計算したら今まで気が付かなかった著しい環境側面に気が付いたという反論がありました」
| |||
「なるほど、そういうこともあるでしょうな」
| |||
「三木さん、あなた、まさか本気でそうお考えではないでしょうね。 その方は環境管理をしたことがないのか、まったくノータリンなのか、初心者だったのか。いずれにしてもその程度の頭では他の仕事もまっとうにはできないでしょうなあ」 | |||
「小畑さんは点数ではだめだとお考えですか?」
| |||
「そうではありません。点数法と言っても正しいものもあるでしょう。点数に根拠があれば素晴らしい方法です。でも現実には99%うそっぱちです。見分け方は簡単です。電力の配点表を見ただけで意味があるかないか一目瞭然です」
| |||
「どのような?」
| |||
「電力の配点に一貫した理屈が通っているかどうかですな。そして他の側面もその理屈かどうかがあります。電力使用量と配点がリニアなら廃棄物もリニアでなければいけないし、対数ならみな対数とする必要があるでしょう」
| |||
「確かに・・・電力量が10倍になって点数が2倍というのは対数と考えるとおかしくないですが、その隣で廃棄物が2倍で点数が2倍というのを見るとアレレとなりますね」
| |||
「おっしゃる通り。もちろん多くの場合、そういう配点をするのはバカだからではなく、結論が分かっていてそれを導くのに四苦八苦しているわけで。 点数が階段になっているのもちょっとと思いますが、まあそれは妥協したとしても階段の区分が理屈もないのがありますね、アハハハハ」 | |||
「私の見たものに、エクセルのセルに関数を入れ込んで配点を計算しているところがありました。点数を見ていて何か変な気がしまして、エクセルのセルの計算式をずーっと眺めていったら途中いくつかセルの式が異なっているものがありました」
| |||
「三木さんのことですから勧進帳を分かってあげたのでしょう、アハハハハ 要するに点数法というのはいろいろな観点で配点して総合的に判断するわけですが、現実の点数法というのは結果を出すためにいろいろな観点の点数をいじっているというまったく意味がないんですよ」 三木は風向きを変えようとした。 | |||
「小畑さんはトラブルがあると支援もするとおっしゃいました。差しさわりのない範囲で、具体的な事例を教えていただけませんか」
| |||
「そういうことならたくさん在庫がありますよ。そうですねえ、今指導している会社でのこと、ISO認証を担当している総務の方がノイローゼになりましてね、そこの部長がウチからの出向者だったもので私に助けてくれと話が来たのです」
| |||
「ISO担当者がノイローゼとかウツになるのはよくある話ですね」
| |||
「よくある話ですか・・・ 普通、総務の人間といえば総会屋対応、行政とのやりとり、近隣住民との交渉、組合対応などリスクコミュニケーションには慣れているし、メンタルもやわじゃない。その会社だって東証二部に上場していて従業員数千人もいて、その担当もそれなりに鍛えられていたのですがね」 | |||
「ISO担当者がウツになる原因の多くはリソース不足だと思います。ありていに言えばオーバーロードです」
| |||
「まあリソース不足というケースもあるでしょう」
| |||
「それ以外の原因と言いますと」
| |||
「その部長から話を受けてすぐに出向いて担当者と話をしました。原因ははっきりしていました」
| |||
「なんでしょう?」
| |||
「論理の問題です。というか論理不明瞭だったのです。ヤーさんと交渉するにはやーさんの価値観があります。行政と交渉するときは法律があります。組合だって法と協約と慣習の積み重ね、要するに交渉のルールがあるわけです。 ところがISO審査員が語ることにはルールがありません」 | |||
「まさか、私たちがそんな審査はしません」
| |||
「その総務担当者はバカじゃありません。ISO認証しろと言われたとき本を読み講習を聞きに行きました。新しい法律ができたときと同じアプローチですね。何事にもセオリーがあります。セオリー通りでダメな時もありますが、セオリーをことごとく否定されることはめったというかまずありません」
| |||
「ISO審査でそのセオリーが否定されたってことですか」
| |||
「そうです。まずマニュアルに『このマニュアルは当社の最高の文書である』と書いてないのがダメと言われた。どうしてダメなのか? 何に決まっているのか?と質問したそうですが、『審査員が言うのだから間違いない』という回答だったそうです」
| |||
「まあ・・・ありがちですな」
| |||
「この道20年の私が言いますが、『このマニュアルは当社の最高の文書である』と書けと言われた話は何度も聞きました。その根拠を聞いたことは一度もありません。 それからマニュアルに規格のshallすべてを書き込みかつそれを実行すると書いてないからダメなんだそうです。ISO14001にはマニュアルを作れという文言もないのですが」 | |||
「まあ、それもありがちですな」
| |||
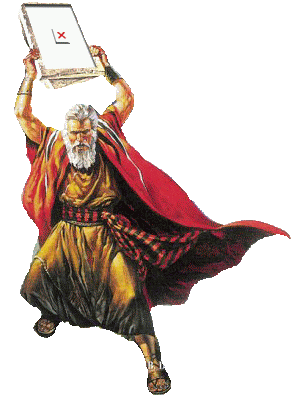 「その会社はだめだと言われたものは数十か所ありました。そして不適合の全部が根拠不明瞭でした。ヤーさん対応なら話が合わない時はどうするか、市民対応ならとセオリーがありますが、ISO対応では途方に暮れたそうです。
「その会社はだめだと言われたものは数十か所ありました。そして不適合の全部が根拠不明瞭でした。ヤーさん対応なら話が合わない時はどうするか、市民対応ならとセオリーがありますが、ISO対応では途方に暮れたそうです。神対応という言葉があります。菅官房長官のようなことをいうんでしょうかね。神対応とは普通は神のような対応をする人のことです。ところがISO審査では神様に対応しなくちゃならんわけですよ。私は神である。神の語ることは絶対である。行動原理に原則がないという神様に普通の人が対応するのは無理ですな。 アハハッハ、あのね、ISO審査のトラブル処置もルールがあります。ご存知でしょう」 | |||
「はあ?」
| |||
「ISO審査はISO9001やISO14001で行われるわけではありません。ガイド62やガイド66で行われます。今はISO17021ができましたな。そしてJABはそれをJAB基準に展開しています。それによると審査の前に異議申し立てを説明しなければなりません。認証機関が独自ルールを定めたときは、文書にして公開しなければならない。まあ最低限審査を受ける企業に配布しなくちゃならんでしょうね」
| |||
「はあ〜」
| |||
「だけど異議申し立てを説明しない認証機関は多々あります。お互いの見解が異なったときどうするか、そういうことを説明せず、規格と違うことを要求し、私は神だ、私に従えと言えば、対応に困ります。我々は民事で裁判起こすしかないのかねえ。 三木さんならどうしますか?」 三木は突然自分に振られたのでびっくりした。 | |||
「確かに途方にくれますよね」
| |||
「ともかく総務の方に会って話をするとウツってわけではなく、途方に暮れた、参ったなあという程度でした。部長が心配していただけで、」
| |||
「で、どうされたのですか?」
| |||
「現在進行形なのですよ。正直今日はその会社からの帰り道です」
| |||
「聞いてよろしければ認証機関はどこでしょう、審査員の名前は?」
| |||
小畑はウィンクして言う。 | |||
「答えてよろしいなら、認証機関は御社で審査員は朱鷺さんといいましたね」
| |||
朱鷺は三木の先輩で、彼とは何度も一緒に審査した。いつも彼の根拠のない言いがかりに近い審査にハラハラした。CEAR誌に環境目的と環境目標の二つの実施計画が必要という記事を寄稿して、読者から批判を受けても断固自説を変えなかったお人だ。とはいえあれからもう何年も経っている。少しは考えを変えたかと思っていたのだが。 | |||
「一番の問題は、審査員は裁判官ではなく検事であると理解していないことではないかな」
| |||
「すみません、私は審査員は裁判官であると理解していましたが」
| |||
「うーん・・・あのね、検察は被告の有罪の証拠を提示し、裁判官はそれが妥当か否かを判断します」
| |||
「ですから審査員は企業側のエビデンスが妥当かどうか裁くのではないですか」
| |||
「基本的なことですが、審査員はオーディターといいます。調査員ですね、決裁者ではないのです。認証を与えるか否かの決定は御社の経営者ということになっています。ああ、これは私の主張ではなくISO17021にそう書いてあります。私は審査員じゃないですから根拠のないことは言いません、アハハハハ」
| |||
「そう言われると確かに審査報告書の結論は『認証を推薦する』とか『認証継続を推奨する』と書いてました」
| |||
「そうでしょう。審査員は規格要求事項の適合を確認し認証を推薦することが仕事です。 そして不適合は証拠と根拠がなければなりません。 ええっとそれから問題はたくさんありますが、大きなのものとして審査が密室で行われるということです。本来なら公明正大に第三者立ち合いを認めるべきでしょうね。だから審査員がごり押ししてもそれを咎める人がいない」 | |||
「陪席を認めないのはどの認証機関も同じでしょう」
| |||
「私は本社の立場、関連会社のときは親会社が立ち合いすると言って陪席しています。そこんところはコンサルさんよりは有利ですね。普通のコンサルだと審査に立ち合いさえできませんからね。 そんなわけで私は審査見物を楽しんでます。本音は怒り狂っているということですよ」 | |||
「どのような・・・」
| |||
「最近のことですが、一昨年この手順はまずいから直せと言われた、昨年別の審査員が来て直した手順がだめだから更に改訂しろという、今年の審査でまただめだから直せと言われ、元の方法に戻ったってのがありましたね」
| |||
「そういうお話は2000年過ぎに聞いたことがありました。あれから10年経ちましたが今でもありますか?」
| |||
「私の目の前でありましたね。会社側もアホらしくなったようで、過去のいきさつを説明しましたが、言うとおりにしろということでおしまいでした。あれは苦情をいわなくちゃなりませんね」
| |||
「おっしゃるとおりですね」
| |||
「しかしすごいですよね。サッカーしようと言いながらルールを説明せず、自分が負けそうになったら自分に有利な判定をして、文句を言われたら俺が言うんだから間違いないと押し切る、これじゃ絶対負けなしですよ、アハハハハ ISO認証の信頼性が低下しているなんてJABとか消費者団体が語っています。どっかの大学教授は企業が審査で嘘をついているからだとほざいていました。でもね実態を知ったら、認証機関のレベルが低いからだと分かるでしょう。 私が認証請負だけでなくトラブル対応もしているというのはそういう問題が多いからです」 | |||
「大変申し訳ありません」
| |||
「お宅は当然JABやUKASの認定審査を受けているわけですが、審査で苦情処理はどうなっているのですか? ああ、お宅の帳簿上は苦情そのものがないのでしょうな」
| |||
三木は苦虫をかみつぶした。小畑というのは嫌な野郎だ。ビールがまずい。 小畑は三木の想いを気にせずに話を続ける。 | |||
「審査がこんなことなので認証をやめようという声もあるのです」
| |||
「ええっと、お宅様のグループ企業ではいまだに認証しようという企業があまたあるということでしたが」
| |||
「それも事実です。しかし認証後何年も経過したところでは返上したいという声もあるのも事実です。カゴの外の鳥は中へ入りたがり、 カゴの中の鳥は外へ出たがるってのと同じですかね? 少し前、1年位前かな、執行役会議にそんな話が出まして、認証返上希望状況を調べたことがあります」 | |||
「ほう、結果はどうでした。ぜひ知りたいですね」
| |||
「ウチの事業所が約40、国内関連会社で認証しているところが約120社、都合160の内やめたいという回答は約30拠点でしたね。本音はもっと多いと思いますが、止めたときのデメリットがわからないので止める決断ができないようでした」
| |||
「その結果、認証返上したのは何社でした?」
| |||
「正直言って3社でした。あれから1年くらいたったわけですが、やめた会社で困ったことはないそうです。ウチではそういう情報は共有化していますから、今後入札などと関係ないところは返上すると予想しています。そうですねえ〜最大に見積もると2割くらいかなあ」
| |||
「残るのは、やはり国交省関係ですか?」
| |||
「あ、2割というのは私の勘ですから根拠はありません」
| |||
「なるほど、今国内のISO14001認証件数は2万とんで500というところですか。16,000くらいに減るということですかね」 | |||
「私の予想が日本全体に適用できるかどうかは怪しいですが、まあそんなものでしょう。とはいえそれ以上減るとも思えない」
| |||
「なぜでしょうか?」
| |||
「国交省関係もあるでしょうし、環境経営度などの評価に関わると懸念するところもあるでしょう。例えばウチの本社は認証返上はできないと思います。年400万なら交際費と考えればしょうがないでしょう。中小ではブランドどころかプライズと考えているかもしれない」
| |||
「なるほど、しかしお話を伺えば伺うほど認証とは無意味ですな」
| |||
「大変いいにくいですが、こういう状況に至ったのは御社とは言わんですが、認証制度側の振る舞いがもたらしたことは否定できないでしょうね」
| |||
「まあルールが徹底されないところもあったかもしれません。しかし審査の倫理問題とかルールもできましたし、審査の厳密性もだんだん改善されると思います」
| |||
「三木さん、それはあまり期待はできません。そもそも基本がなっていないのです。 まず、審査員がISOMS規格をしっかりと理解してそれに基づいて審査する力量が必要です。審査員の思い込み、勘違い、先輩が言ったからなんてのはお断りです。 それからISO17021やJAB基準類を暗記するほど読み込んで、それに基づいて審査を行わなくちゃなりません。オープニングで異議申し立てを説明するのは基本ですね。
あのさ、オープニングで異議申し立てを説明しないってことが異議申し立てを受けるって知らないから説明しないんでしょうね。まさか異議申し立てされると困るから説明しないなんてことはないですよね」 | |||
実を言って三木も以前は異議申し立ての説明をすることを知らなかった。教えてもらったことがないし、オープニングで先輩が説明しないからそういうものだと思っていた。あるとき認証を受けている会社からクレームをどこに言えばいいのかという問い合わせがあった。社内でいろいろあったようだが、その結果ウェブサイトに苦情はこちらというメールのリンクを付け、オープニングのパワーポイントの1ページの下の方に小さな文字で「審査やその判定に異議あるときは認証機関に申し立てすることができます」という1行が追加になった。とはいえそれについて審査員に説明も指導もなく、三木は今も異議申し立てについて説明していない。仮に企業側から異議申し立てを説明しないという苦情があればパワーポイントにありましたとかわすのだろう。 小畑の話には、今まで三木が知らなかったことがたくさんあった。 ただ・・・小畑のようにダメだダメだと否定されると感情を悪くする。とはいえ、企業側の人は毎回の審査でこれ以上のいやな思いをしているのだろう。その原因は認証機関側の怠慢、傲慢、上位意識そして無知なのだ。盲目の殺戮者という言葉が三木の頭に浮かんだ。これじゃどちらがお金を払っているのかわからない。 | |||
「小畑さんのおっしゃるとおりです。先ほど誰からお金をもらっているおかという話がありましたが、審査員も認証機関も、企業からお金をもらっているとは思ってもいないようです」
| |||
「もちろん真の顧客は一般消費者とかBtoBなら納入先なのでしょうけど、ISO17021では依頼者は審査を受ける企業ですからね。金を払う人にはまっとうなサービスの提供をお願いじゃなくて要求しますよ。認証機関は客におもねるのではなく、まっとうで厳しい審査を提供しなければお足はいただけません」
| |||
「小畑さんのお言葉を忘れずにまっとうな審査をするよう心がけます」
| |||
「間違いは人間でも機械でも確率的に発生する。だから審査で漏れやミスがあってよいんですよ。ただ審査員も間違えることを認識して、間違えたら是正してほしいんです。 審査結果、是正処置をするのは常に企業側ってのはあり得んですわ。先ほどグループ企業に認証の要否を問い合わせたと申しましたが、認証を継続するか否かだけではなく審査の問題とかその対応状況についてもアンケートを取ったんです」 | |||
「その結果を知りたいですね、秘密でなければ」
| |||
「一番多かった不満は態度ですね。審査判定の間違いは誰にでもあるけれど、それに苦情を言われたとき論理的に対応できるか、逆切れしてしまうかということです。 今でも倫理的な問題はあります。しかし意外かもしれませんが企業側にとってはあまり苦にならないですよ。取引先を接待するのは普通のことですし、地元のお土産でもレアな販促品でも欲しいならご用だてするのは大した手間じゃない。 問題は不適合でないのに是正しろとか、法違反ではないのに行政に詫びに行けと言われても困りますわ、アハハハハ 私は親会社の本社の立場ですから、工場や子会社の人と認証機関に行って是正をお願いすることが多いのですが、耳を貸してくれません。正直いって認証機関を変えたくなります。ま、それは最終手段ですね」 | |||
結局、三木が知りたかった認証の価値とか意味の議論まではいかず、耳にタコができるほど審査の苦情を聞かされた。三木は小畑が好きになれなかったが、小畑が嘘をついていないのは間違いない。 |
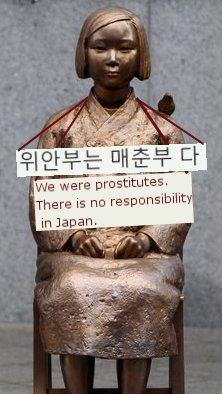
今回の文を書いていたら、過去に審査トラブルをどんどんと思い出した。私の恨みが深いのはそれなりのわけがあるのだ。
といっても私は韓国人ではないのでこの恨み1000年忘れないなんてほど執念深くはない。これを書くまで忘れていたことも多い。あと2年もしたら完璧に忘れてしまうだろう。
名古屋鶏様からお便りを頂きました(2016.09.19)
去年だったかなぁ 「何で点数法を止めたんだ?止めていい理屈なんて無い!」 と審査員がヒステリーを起こしたのを目撃したのは。 もはや、腹が立つ事もなく「こいつアホだな」と呆れる感情しかありませんけど。 |
|
名古屋鶏さん毎度! おお、すばらしい、審査員閣下は適合判定だけでなく指導も評価もしてくれるなんて♥ |
審査員物語番外編にもどる
うそ800の目次にもどる