昨年、JQAのCSR報告書は、あまりにも素晴らしい()から、もうコメントしないぞと書いた。
と言いつつ、怖いもの見たさには勝てない。今年も10/16に発行されたと知って、すぐにプリントアウトして眼光紙背に徹するように眺めた。その結果、思ったことは昨年と変わらず、とても素晴らしく()読む価値がないことを再確認した。
真面目に読んだので一言書きたくなった。よって簡単に読書感想文を書く。
p.2〜p.3 見えない価値をみえる証に
報告書の表紙をめくると毎度同じ絵がある。「農業」という文字が増えてはいる。この報告書だけ見た人にもJQAの事業を知ってほしいということだろうが、芸がないと思う。
年年歳歳花相似たり、歳歳年年報告書同じからず……ではなかろうか。なんだかな〜という感じはぬぐえない。
まあ、どうでもいいか、
p.4〜p.5 トップメッセージ
理事長が変わったので中身は当然変わっている。
石井理事長のたまわく、「GXに関しては、ISO14001、ISO50001等のマネジメントシステムに係る審査・認証の他(後略)」とある。
ISO14001はJQAの認証件数は3,000件ほどあるようだが、EnMSの認証件数はゼロのようだ。それでも認証を実施していることになるのだろうか?
注:GX(グリーントランスフォーメーション)の略で、化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のこと。
いろいろと書いているが、サスティナブルにつながるのは「事業活動で使用するエネルギーのスリム化と再生可能エネルギー導入を積極的に行っています」センテンスだけのようだ。
事業そのものでのサスティナビリティへの貢献とかはないのだろうか? JQAの使用エネルギーはたかが知れている。己の使用エネルギーが増えても、社会全体の省エネに貢献すればよいと思うが、そのへんはどうなんだ?
しかも後で出てくるが消費エネルギー量も大して減っていない。というか2021年より2022年は4%ほど減っているが、2020年に比べれば15%も増えているのだ(本報告書p.30)。
理事長、しっかり自分の組織の状況を把握してよ、
p.08 社会に貢献し続ける組織を目指して
 以前から違和感があるのだ、社会貢献とは何だろう? 金が余っているなら大盤振る舞い大いに結構である。
以前から違和感があるのだ、社会貢献とは何だろう? 金が余っているなら大盤振る舞い大いに結構である。
メセナとは企業が金を出して文化活動を支援すること。将棋のタイトル戦でも、マニアが大勢いるならそうなのだろう。だけどゴルフの冠大会がメセナとか言われると、ちょっとというか大いにしらける。
10年位前、エコプロダクツ展では、子供たちに自然を教えたり、どんぐりの細工をしたり、メダカを保護したり、トンボの回廊を作ろうというのが流行った。ああいうのを見て、私は企業の環境活動というものはそんなもんじゃないだろうと思った。
企業の環境責任は、まず「遵法と汚染の予防(ISO14001の意図だ)」に励み、製品やサービスの環境負荷削減にまい進することにある。
絵画展、見学受入れ、そういうものが悪いわけじゃないけど、もっと本質的なところに注力しないと……
事業においていかに社会貢献をしているかを知らしめる、それがCSR報告書の目的じゃないのか?
じゃあ、本業において、そしてその運用にかかわる環境負荷の低減はいかにとなるが……それは以下の文章を読んでいただければわかる。
p.13〜 JQAの事業
待ってました、これぞCSR報告書の本分である。
冒頭から理解できないことがある。
p.14 事業を通じた環境貢献
「JQA は、ISO 14001(環境)やISO 50001(エネルギー)などの環境関連規格の認証を通じて、組織の環境パフォーマンス向上に寄与し、環境保全・環境負荷の低減に貢献します。また、JQA 独自のサービスにより、環境経営を目指す組織がより効率的・効果的に活動できるよう支援しています。」
「認証を通じて組織の環境パフォーマンス向上に寄与し、環境保全・環境負荷の低減に貢献します。」
これは具体的にはどんなことを意味するのか?
企業が「環境パフォーマンス向上と環境負荷のために認証を受けます」といったとき、JQAは何を提供するのか?
非常に興味がある。
それはISO17021-1に反しないで、本当に価値あるものを提供してくれるのだろうか?
私は引退した身であるが、余生を送るにあたり、パフォーマンス向上と環境負荷低減のために個人であっても認証を依頼したくなった。
「組織のエネルギー管理を継続的に改善するための支援を行う」「マネジメントシステムの統合による効率化や有効活用を目指す組織のニーズに、これまで以上に応えます」
これは何なのか、ちょっと想像がつかない。期待に応えるとなるとコンサルだよね? 大丈夫?
ところで審査契約書にその旨の記載はあるのだろうか? 契約書に記載して実行できなければ契約違反になるが?
p.28〜 環境への取り組み
まずは過去のCSR報告書の数字と今回のものを並べる。
「環境負荷の低減」に関する環境目標
エネルギー使用量(原油換算)
| 対象年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 目 標 | 1500kL以下 | 1500kL以下 | 1500kL以下 | 1500kL以下 | 1500kL以下 | ? |
| 実 績 | 1394kL | 1399kL | 1488kL | 1721kL | 2057kL | 1974kL |
原単位(事業収入あたりエネルギー使用量)
| 対象年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 目 標 | 前年度比1%削減 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 実 績 | 3%削減 | 2%削減 | 6%増加 | 14%増加 | 13%増加 | 4%削減 |
注:CSR報告書に載っている実際の表は、今年度報告分(前年度実績)のみである。
前年度の実績は過去のCSR報告書の数値を引用した。
まず2020年、2021年の急増については過去何も言及されておらず、2022年に2021年比削減したとあるだけ。過去はどんなに暗くても明日は夢開く〜♪ そんなことはないだろう。
いったいJQAのエネルギー計画はどうなっていて、顛末はどうなのか?
わけが分からない。
そればかりではない。排水にしても、廃棄物にしても、年ごとに上下がものすごい。廃棄物は2021年は前年比12%増で2022年は前年比11%減、産廃は2022年も2022年は7%増である。通常なら関係者を集めて原因究明・対策策定となるところだ。この報告書では一言もない。重要と認識していないのだろう。
* 我が家では毎月の電気使用量、水道使用量はしっかりとチェックする。貧乏だからではない。
水道なら漏水がないか、外の蛇口を他人が使っていないか。電気だって漏電の懸念もあるし、待機電力に異常があるか、怪しい盗聴器があるかもしれない。ないだろうけど。
年によって7%違ったらおかしいわ
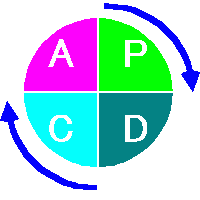 この組織は、改善計画をどのように考えているのか。単に数字を表に埋め、進捗を書き込んでいけば。それでおしまいか?
この組織は、改善計画をどのように考えているのか。単に数字を表に埋め、進捗を書き込んでいけば。それでおしまいか?
監視とは、是正とは何だろう?
分かったことはPDCAとは無縁であることだ。
p.29 事業を通じた環境貢献に関する環境目標
この件については、過去から何度も指摘しているが、今もって全く理解できない。わかる人がいたら教えてほしい。
事業部門ISOにおける
| 目標 | 登録組織の環境活動向上 | |
| 取り組み | ISO14001認証の拡大 | |
| 晴れ時々曇り🌥 |
「登録組織」とは「既にISO認証している組織」の意味である。
じゃあ既に認証している組織の環境活動を活発にするのに、どうしてISO認証させるのか?
二度認証することは可能なのか? わけわからない。
昨年は印刷屋が「未登録組織の環境活動向上」の「未」をミスで落としたのだろうかと書いた。しかしいくらダメな印刷屋でも2年連続で「未」を落とすとは思えない。
進捗状況は「🌥晴れ時々曇り」である。どんな判断基準で晴れなのか、曇りなのか、晴れ時々曇りなのか?
ちなみにJQAのISO14001認証件数は公表されていないが、JAB登録のISO14001認証件数は、2021年末13036件、2022年末は12757件の2%減である。JQAは全体が低調な状況でも増加したのだろうか? 晴れ時々曇りと判断した基準、根拠は不明である。
ISO事業だけではない。他の5つの事業すべてがワケワカランのである。
例えばJIS事業において
| 目標 | 次亜塩素酸水生成器に関する任意認証制度構築支援 | |
| 取り組み | 日本電解水協会で実施している次亜塩素酸水生成器認証の支援を行い事業化に向けた試行の実施 | |
| 🌞晴 |
支援構築が目標たり得るのか? 支援した結果の到達点でなければ目標にならないだろう。
取り組みとして「○○の実施」でよいのか? 実施した結果うまくいったとか、成功するまで実施したのか?
それで結果がどうだったのか? 「🌞晴」とどうして言えるのか?
JQAは環境報告書の環境報告書の環境情報審査をしているそうだ。このように目標もあいまい、手段は不明確、結果もわからないものでも適正であると表明するのか?
わけ分からない。
![]() 本日の評価
本日の評価
I can't give a score.
うそ800の目次に戻る
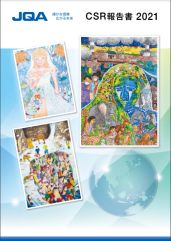 JQAのCSR報告書について書くのはもう何回目だろう。なぜ書くかというと、あまりにも突っ込みどころがあり、ひとこと言わねばと思うからだ。
JQAのCSR報告書について書くのはもう何回目だろう。なぜ書くかというと、あまりにも突っ込みどころがあり、ひとこと言わねばと思うからだ。
とはいえ、毎回同じことを書いているようで、今回を最後にしたい。間違いに気が付かない人に何度語っても意味がない。
もちろんこれからも眺めるから、良くなったときとか悪くなったときには、また報告しよう。
「JQA CSR報告書2022年版」を読んで変だな? おかしいぞ! というところが多々あるが、事業の紹介とかCSR関係については言及しない。純粋に環境報告部分を読んで、これは許しがたいということに限定する。
- p.2 見えない価値を 見える証に
昨年まで表紙の裏ページにあった「創業以来○○年」がなくなった。
昨年は2020年版が創立60年で、2021年版が創立65年と、1年で5年増えるのはおかしいだろうと書いたが、私のケチなウェブサイトをご覧になったのだろうか、修正というか創立何年目という記述はなくなっている。反省し見直すことは良いことだ。……と思ったのだが、前年、前々年に指摘したおかしな点が直っていない箇所も多い。ということは私のレビューを読んだのではなく、たまたまご自身が気付いて直したのだろうか?
本文にはもっとおかしなことがまだいくつも残っているのに、そちらに気づかないとは困ったわ
- p.28 環境マネジメントシステムの推進
「環境マネジメントシステムの推進」とはどういう意味なのか分からない。それはおいておく。注:「推進」とは、前に進めること、そこからものごとがはかどるようにする意味にも使う。
マネジメントシステムとはオブジェクトではなく仕組みであるから、それを進めるとはどういうことだろう? マネジメントシステムの改善を推進するのか? マネジメントシステムのパフォーマンス向上を推進するのか? 何であるのかはわからない。ともかく「環境マネジメントシステムの推進」の意味は不明である。ここでは種々の環境パフォーマンスの実績が図表に示されている。
一目見て、エッ、おかしいと思ったことを挙げる。図「環境負荷の低減」に関する環境目標
エネルギー使用量(原油換算)
対象年度 2017 2018 2019 2020 2021 目 標 1500kL以下 1500kL以下 1500kL以下 1500kL以下 1500kL以下 実 績 1394kL 1399kL 1488kL 1721kL 2057kL
原単位(事業収入あたりエネルギー使用量)
対象年度 2017 2018 2019 2020 2021 目 標 16年度比1%削減 17年度比1%削減 18年度比1%削減 19年度比1%削減 20年度比1%削減 実 績 3%削減 2%削減 6%増加 14%増加 13%増加 注:CSR報告書に載っている実際の表は、今年度報告分(前年度実績)のみである。
前年度の実績は前年のCSR報告書の数値を記載した。「エネルギー使用量」は2年連続で大幅未達である。「事業収入当たり原単位」は3年連続で目標未達である。それもほんの少しではなく、37%オーバーとか13%オーバーとか半端ではない。そしてそれらについてのコメントは一言もない。
こういう事態なら、早急に原因究明、その対策、次年度計画の再検討があってしかるべきだろう。少なくても3年連続して未達では、是正処置がなってないといわれるだろう。
そもそも目標を達していないのに問題だと記していないのは、担当者も管理者も問題がありそうだ。いや担当者も管理者も問題である。方法を見直す、目標を見直す、人を入れ替える、なんとかしなければならん。だが未達という記載はあるが、それについての見解は一言もない。そういうスタンスで良いのか? 私以外にもこれに気が付いて、変だなと思っている人は多いに違いない。
- p.29 事業を通じた環境貢献に関する環境目標
- ISO認証事業
目標:登録組織の環境活動向上
取り組み:ISO認証の拡大
進捗状況:60〜99%達成過去に何度も書いているが、上に転載した3行35文字だけ見ても大きな疑問がある。
 テーマは「ISO認証事業において事業を通じた環境貢献」である。そして目標が「登録組織の環境活動向上」である。このテーマと目標は対応しているのだろうか?
テーマは「ISO認証事業において事業を通じた環境貢献」である。そして目標が「登録組織の環境活動向上」である。このテーマと目標は対応しているのだろうか?
日本語を読める人なら、目標と取り組みが見合っているとは思わないだろう。「未登録組織の環境活動向上」のために「ISO認証の拡大」なら、まあ理解はできる。印刷屋が「未」を落としたのか?
もっともISO認証すると環境活動が向上するかどうかは議論が必要だ。私の経験では、ISO認証過程で環境活動は活性化するが、認証すると低調になるのが通例だった。所与の課題である「登録組織の環境活動向上」を実現させるための認証機関の取り組みとして、思い浮かぶこととなるとどんなことだろうか?
ISO認証事業においてであるから、ISO審査において被認証組織の環境改善活動をアシストするとか種々情報の提供をする、あるいはISO17021-1に反さないために審査とは別に、環境コンサル事業を始めるなどが思い当たる
(注1)。 具体例として、下記のようなものがあるだろう。
省エネ推進、廃棄物削減、提供する環境製品やサービスの環境性能の向上、新しい環境配慮事業の開拓、環境遵法の推進、環境事故の予防策などだがJQAが上げている取り組みは「ISO認証の拡大」である。ISO認証することはしないことより環境活動が向上するのかといえば、論理的にも現実的にもそうだとは言えない。
認証している企業は、認証していない企業よりも環境活動が著しいとかパフォーマンスが優れているという調査や論文があるだろうか(注2)。 私は知らない。
それに認証機関は審査において被認証組織のアドバイスや方向性を指示することはできない。そもそも「登録組織の環境活動向上」のために「ISO認証の拡大」である。新たに認証した組織があったとして、そのことが既に認証している登録組織の環境活動を向上させるのかといえば……全く無関係である。話のつじつまが全く合わない。
「目標」と「取り組み」がまったく無関係であることは明白だ。更に進捗状況は60〜99%とあるが、実行計画がどんなもので指標はなにか? その説明がない。いやそこまでCSR報告書に書く義務はないと思うが、目標と取り組みがまったくつじつまが合わないのだから、いかなる計画でどんな指標なのか、それを知りたい。JQAの人たちは目標達成に関係ない活動をするとは思えないから、きっとテーマ・目標・取り組みまでの論理的なプランがあるのだろう。そしてその達成具合は数値で表されているから、どんな指標なのかぜひ発表してもらいたい。一般企業に大いに参考になるだろう。
JQAとしても、目標、手段、達成度が明白になって次年度の活動に参考になるだろう。
- 安全
目標
各種技術基準・規格に基づいた製品試験や電磁環境試験など適合性評価事業を通して信頼性の高い製品の供給と安全な暮らしを支援し、環境負荷の低減に貢献する。ISO14001では「計画」という言葉が二つの意味でつかわれている。ひとつは「6.2.2環境目標達成の計画(以前の版では実施計画)」であり、もうひとつは「6.1.4取り組みの計画」である
(注3)。
安全部門の「環境目標」はこの「6.1.4取り組みの計画」と勘違いしているのではないだろうか? もっともJQAはISOの認証機関であるから、決してそんなことはないとは思う。2021年の進捗は100%以上である。
この目標が数値化できるとは思えないが、いかなる方法で100%以上と算出したのだろうか? ぜひともこのような定性的とさえ言えないあいまいなものを、数値化する方法をご教示願いたいところだ。
- 計量部門
目標
「温度計および湿度計の校正業務の拡大を通じて正しい温度管理、湿度管理を推進し、CO2の排出削減に貢献する」
品質であろうとコストであろうと「改善は測定から始まる」と言われる。だからJQAが行う温湿度計の校正によって、多くの企業におけるCO2削減に貢献しているのはなんとなく分かる気がする。 しかし取り組みが「正確な温湿度計の校正による顧客における使用エネルギーの削減」である。「正確な温湿度計の校正による顧客における使用エネルギーの把握」なら可能な気がするが、測定器が正確なら削減できるのか? もしそれが真なら省エネ活動とは高精度の測定機器を備えれば良いのか?(反語である)
しかし取り組みが「正確な温湿度計の校正による顧客における使用エネルギーの削減」である。「正確な温湿度計の校正による顧客における使用エネルギーの把握」なら可能な気がするが、測定器が正確なら削減できるのか? もしそれが真なら省エネ活動とは高精度の測定機器を備えれば良いのか?(反語である)
CO2濃度をいくら正確に測ろうとCO2は減らないと思うぞ、ところで「正確な温湿度計の校正による顧客における使用エネルギーの削減」が100%以上達成したとはいかなる方法で把握したのだろうか? 把握できるものなのだろうか?
ひょっとしてJQAの努力によって地球温暖化は止まったのであろうか ?
私の元の勤め先とか、知っているいくつかの会社がJQAにアスマン乾湿計の校正をJQAに依頼しているが、「温湿度計の校正によって工場の使用エネルギーが減りましたか?」なんて問い合わせがあったと聞いたことはない。ヒアリングしていないなら、どのようにして顧客企業で使用エネルギーが低減したと予測したのだろうか?
疑問は尽きない。教えてJQAさん !
- マテリアルテクノ
目標は「骨材試験の受注を拡大し、より多くの品質試験を実施して、正しい試験結果を提供することによりコンクリート構造物の耐久性の確保、資源の有効利用および廃棄物の削減につなげる」である。
そしてこの取り組みもまた「骨材試験の受注拡大」である。
これも計量部門と同じく、JQAの品質試験と廃棄物削減までの連鎖は「風が吹けば桶屋が儲かる」程度のあやふやなものであり、達成具合を100%以上などと表示できる気がしない。
正直言えば呆れるほかない。
- JIS部門と6.地球部門も以下同文である。
環境目標の設定、取り組みの計画、そして進捗の把握がこの程度でJQAは環境報告書の審査でOKを出すのだろうか?
ISO審査で「当社では出荷検査は厳しく行うから顧客は大事に使うようになり環境保護に貢献している」と説明を受けたら、審査員は「素晴らしい環境貢献をしていますね」とでも語るのだろうか?
ワケワカラン
- ISO認証事業
- p.30
2019年以降3年間、電気エネルギーが急速に増加している。昨年も増加の理由の説明がなかったが、今年は昨年に輪をかけて増加している。
PPCの使用枚数などどうでもいいから、電力量がこれほど増えたことの説明が欲しい。というかいまどきPPCの枚数を把握しているとは驚いた。一刻も早く紙ごみ電気を脱却してほしい。PPC1枚のお値段は0.7円から1円です。JQAでは2021年は前年より23万枚減らしました。素晴らしいといいたいですが、削減した金額は16ないし23万円です。
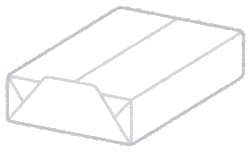
30ページの図でPPCの上にある電力量は131万kWhの増加です。この増加分はおいくらでしょう?
2022年秋からの値上げ前として、家庭ならほぼ27円/kWhですが、法人向けでは14〜17円/kWhですか。
JQAの場合131万kWh×15円として2000万円ですか……PPCの100倍です。
著しい環境側面とは言えませんね、PPCは……著しい環境側面の決定結果から、著しい環境側面を決定する方法は不適合と言ってよろしいでしょうか?
まさかCSR報告書で大々的にPPC削減を取り上げているのですから、PPCは著しい環境側面ではないとは口が裂けても言えないでしょう。
不適合判定に異議ある場合は、弊ウェブサイトに異議申し立てをすることができます。
- p.30 排出物
廃棄物のリサイクルが99%とあるが、この辺は内容を知らないと何とも言えない。実効ある処置をしていると期待する。
- p.31 JQAの概要
最後だが、昨年までは事業収入という円グラフがあった。今年はない。
普通、財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の三つをいう。JQAは貸借対照表だけは公開しているが、損益計算書とキャッシュフロー計算書は表に出ておらず、CSR報告書の円グラフで事業収入の中身を想像していた。
2022年のCSR報告書では、情報統制なのかどうか、まったくお金の出入りがわからなくなった。財団法人とはいえ、JQAは事業収入が168億もあるのだから、その内訳などを公開しなければならないだろう。というか、環境報告書で生産高(売上高)当たりの環境負荷が分からなければ意味がない。まさかISO認証事業の環境負荷が大きいとは思えない。
 ではどの事業でこれほどエネルギーが増加しているのか? マテリアルテクノなのか、校正事業なのか、あるいはオフィスなのか、それを知らなくては何も分からないし手も打てない。
ではどの事業でこれほどエネルギーが増加しているのか? マテリアルテクノなのか、校正事業なのか、あるいはオフィスなのか、それを知らなくては何も分からないし手も打てない。
いや、JQAは環境負荷が大きな部門を把握しているだろう。そして手を打っていると思う。とはいえ電力が過去3年連続未達であり計画を3割もオーバーしているとは……
![]() 本日の感想
本日の感想
環境報告書には国際基準としてGRIガイドラインがあり、国内では環境省環境報告ガイドラインがある。もちろんそういったものを満たすように作成しているのだろうと思う。
だが一読者として目標未達があっても何の説明もなく、翌年もまた目標未達ではCSR報告書を作る姿勢に不信感が募る。いや組織そのものが大丈夫かと疑う。
だってCSRとはCorporate Social Responsibility(企業の社会的責任)だ。Customer Satisfaction(顧客満足)ではない。自社の問題の解決して改善していく能力と意思がなければresponsibilityを果たさないんじゃないか?
また環境改善テーマと目標と取り組みが見合っていないの不思議でならない。
いや
目標設定をした担当者、管理者の頭と力量を疑うぞ。そしてそれを世の中に発表するという蛮勇もすごい。広報担当者その管理者そしてトップ経営者はチェックしているのか?
街の中小企業が、初めて環境報告書を作ってみましたというならまだ許せる。だが環境報告書の審査を行っている組織が発行するCSR報告書がこれで良いのか?
おって、
過去のJQA CSR報告書について書いた文もお読みいただければ幸いです。
・「JQA 環境報告書 2009」
・「JQA CSR報告書 2019」
・「JQA CSR報告書 2020」
・「JQA CSR報告書 2021」
注1 |
ISO17021-1:2015 5.2 公平性のマネジメント 5.25において、認証機関はマネジメントシステムのコンサルティングは禁止されている。だが省エネなどの固有技術に関するコンサルティングが禁止されているとは読めない。もっとも審査の場でコンサルの営業をするのはダメかもしれない。 | |
注2 |
CINIIで検索しても、ISO認証によるパフォーマンス改善についての論文はまずない。 20世紀には、認証した結果PPC使用量が減ったという大学院生の論文があったが、それをISO認証の効果といえばISO認証が悲しく(恥ずかしく)なるだろう。 | |
注3 |
ISO14001:2015 6.1.4でいう「取り組みの計画」は環境目標達成のための計画ではない。 これは取り組まなければならないものであり、その取り組みには、6.2 環境目標に設定して改善するもの、7.2/7.3 力量や認識を向上させる、8.1 運用計画や管理の対象とする、8.2 緊急事態への準備対応に反映する、9.1 監視及び測定の対象とする、などの方法をとるということである。 出典:「ISO14001:2015 要求事項の解説」吉田敬史、奥野麻衣子、日本規格協会、2015、pp238〜239 |
うそ800の目次に戻る
     |