*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
 午前中は転勤者との顔合わせをしてから、転勤者の本社ツアーをした。午後は各人の仕事の説明である。
午前中は転勤者との顔合わせをしてから、転勤者の本社ツアーをした。午後は各人の仕事の説明である。
午前中使った小会議室に、午前のメンバーから山内と上西を除いた
柳田からペットボトルのお茶の差し入れがある。
皆が座ると、磯原が話を始める。
![]() 「皆さんが本社に来てくれて、本当にうれしく思います。日々上を下への大騒ぎっていう状況で四苦八苦しておりました。皆さんに期待してます。
「皆さんが本社に来てくれて、本当にうれしく思います。日々上を下への大騒ぎっていう状況で四苦八苦しておりました。皆さんに期待してます。
おっと、残業が多いとか休日出勤が…とブラック職場かと心配されることはありません。日中7時間半しっかり仕事をすれば間違いなく終業時刻に離席できます。帰れないのは能無しの私だけです。
頭を使うとか体力を使うというよりも、突発的なことが多いので、その対応が大変です。もっとも常に突発的であれば、それは突発的じゃないですね。
まず現在の状況を説明します。今日の午前中の打ち合わせで、何かおかしいと感じたでしょう。
露骨に言っちゃいますと、管理者がしっかり管理してないのです。環境管理課の現状を理解してないと、仕事どころではありません。まずそこんところ分かってほしいです」
![]() 「そう言われても分かりませんが」
「そう言われても分かりませんが」
![]() 「磯原さん、はっきり言ってないとトラブルになりますよ」
「磯原さん、はっきり言ってないとトラブルになりますよ」
![]() 「うーん、みなさん大人だから言っちゃいますよ。私の話の真偽は皆さんが考えてください。
「うーん、みなさん大人だから言っちゃいますよ。私の話の真偽は皆さんが考えてください。
まず、環境管理課の組織上の位置づけですが……このフロアのトップは大川専務です。大川専務は執行役専務であり生産技術本部長です。我が社は委員会設置会社ですので、取締役は執行役の監視であり会社の業務には関わりません。会社のトップは執行役社長でその下に執行役会があります。大川専務は我が社のナンバーツーかスリーの偉い人です。
まあ、そんなことは我々下々には関わりありません。重役が取締役と呼ばれようと執行役と呼ばれようと誰であろうと、特段どうということもないです。
大川専務は生産技術本部長で、その下にいくつかの部と研究所があり、そのひとつ生産技術部が本社にあります。生産技術部の中に我々の属する環境管理課があるという階層構造になっています。
工場の場合は階層が深くなっていますが、本社の場合は階層が少ない。
上西課長は工場なら部長レベルになります。本社は人数が少ないから階層を深くしなくても管理できるということです」
| 社長 | ||
| 生産技術本部長 | 事業本部長 | |
| 生産技術部長 | 工場長 | |
| 環境管理課長 | 部長 | |
| 課長 | ||
| 係長 | ||
| 担当 | 担当 | |
注:組織の階層の数は、基本的に人数と管理の限界(スパンオブコントロール)によって決まる。管理の限界とはひとりの管理者/監督者が指揮監督できる人数のことで、通常単純作業であれば30〜50名程度、高度な仕事では数名とされる。また仕事が標準化されているかとか情報ネットワークのツールによってその人数は変わる。
例えば1万人の軍隊なら最小の部隊を50名として、それを3〜4個ずつまとめると5階層になる。小隊、中隊、大隊、連隊、旅団、師団と5階層くらいだろう。もちろん歩兵だけではないので単純ではないけど。
本社業務のようなオフィスワークなら管理の限界は4〜6名だろうから、今までの環境管理課が3名なら、ひとりの管理者ですむ。今後4名増えて7名となると二つに分けるかどうかは微妙なところになる。
![]() 「環境課長の上司は生産技術部長になります。生産技術部長と生産技術本部長は一文字違いですが、片方は従業員、他方は役員と大きな違いがあります。
「環境課長の上司は生産技術部長になります。生産技術部長と生産技術本部長は一文字違いですが、片方は従業員、他方は役員と大きな違いがあります。
2年前まで環境部門は生産技術部と同格の環境部という位置づけでした。それが2年前の職制改正で環境部は解体されて、公害防止と廃棄物とエネルギー関係だけが残り、環境管理課として生産技術部に入ったわけです。
さて、ここから微妙な話になりますが、知っておかないと仕事をする上で差しさわりがありますからご記憶ください。
組織表上は環境課長の指揮監督は生産技術部長になりますが、過去2年間 生産技術部長が決裁したことは一度もありません。今まで指揮命令はすべて生産技術本部長から受け、報告は生産技術本部長にしてきています。
なぜか?と言われても私は分かりません。職制が変わってから2年間そうだったということです」
![]() 「環境管理課になったのは今年4月、半年前じゃなかったっけ?」
「環境管理課になったのは今年4月、半年前じゃなかったっけ?」
![]() 「そうです。ただそれは職制変更ではなく、部門の名称が変わっただけとご理解ください」
「そうです。ただそれは職制変更ではなく、部門の名称が変わっただけとご理解ください」
![]() 「となると決裁はすべて重役の大川専務になるのかい?」
「となると決裁はすべて重役の大川専務になるのかい?」
![]() 「いえ、生産技術本部長は本部長室というスタッフ組織を持っていますので、本部長室の山内さん、今朝の会議に出席されていた方です。山内さんの肩書はないですが元研究所長で、工場長レベルの方です。
「いえ、生産技術本部長は本部長室というスタッフ組織を持っていますので、本部長室の山内さん、今朝の会議に出席されていた方です。山内さんの肩書はないですが元研究所長で、工場長レベルの方です。
その山内さんが環境管理課の担当になっています。環境管理課の報告は山内さんへ、指示は山内さんから受けるとご理解ください」
![]() 「なるほど、どういう経緯かは知らねど、そういうものだということだね」
「なるほど、どういう経緯かは知らねど、そういうものだということだね」
![]() 「ええと、環境管理課のとりまとめは上西課長ということで良いのだね?」
「ええと、環境管理課のとりまとめは上西課長ということで良いのだね?」
![]() 「そこが非常に微妙でありまして、環境管理課の担当者といっても増子さんと私しかいないのですが、山内さんから仕事を命じられることがほとんど、まあ9割です。その場合は、山内さんの指示に従います」
「そこが非常に微妙でありまして、環境管理課の担当者といっても増子さんと私しかいないのですが、山内さんから仕事を命じられることがほとんど、まあ9割です。その場合は、山内さんの指示に従います」
![]() 「なるほど微妙だなあ、上西課長から指示されることも1割あるわけだが、そのときは?」
「なるほど微妙だなあ、上西課長から指示されることも1割あるわけだが、そのときは?」
![]() 「現実には……ほぼゼロでしょうか」
「現実には……ほぼゼロでしょうか」
![]() 「なるほどおかしな状況だというのは分かった」
「なるほどおかしな状況だというのは分かった」
![]() 「正直申しまして、それは職制表とか文書になっているわけではありません。私が仕事をしていてそういうものだと理解したということです。
「正直申しまして、それは職制表とか文書になっているわけではありません。私が仕事をしていてそういうものだと理解したということです。
それに私は環境部解体後にここに転勤してきましたので、それ以前の状況は存じません。もし過去の経緯を知りたいなら、環境管理課で一番古い庶務の柳田さんに、地階のコンビニでケーキでも買ってきて、一緒に食べながら事情聴取をしてください」

![]() 「ケーキよりタルトが良いわ」
「ケーキよりタルトが良いわ」
![]() 「アハハ、柳田さんと仕事するのは楽しそうだ」
「アハハ、柳田さんと仕事するのは楽しそうだ」
![]() 「みなさん社内で働いていたからご存じと思いますが、会社では公式な職制だけでなく、非公式な人間関係とか力関係を理解していないと泳いでいけません。私の話だけでなくよく状況を把握してほしいと思います」
「みなさん社内で働いていたからご存じと思いますが、会社では公式な職制だけでなく、非公式な人間関係とか力関係を理解していないと泳いでいけません。私の話だけでなくよく状況を把握してほしいと思います」
![]() 「了解した。話はこれで終わりではなく、まだプロローグなんだろう?」
「了解した。話はこれで終わりではなく、まだプロローグなんだろう?」
![]() 「左様です。仕事の話をする前に必要な情報はまだまだあります。
「左様です。仕事の話をする前に必要な情報はまだまだあります。
今申しましたように今朝の会議で雰囲気は感じたでしょうけど、環境管理課は上西課長が仕切っているのではありません。山内さんが仕切っています。決して山内さんが悪い人とか越権行為ということではありません。
何事かの決裁、判断と言い換えても良いですが、決裁が遅くなったり間違えたりすれば大きな影響があり、場合によってはリカバリー不可能なこともあります。そういったことがあると、本社では工場以上に影響が大きい。
上西課長が来て半年になりますが、そんなことが何度か起きて、山内さんが実質的に環境管理課を動かすようになったのです」
![]() 「ほう〜」
「ほう〜」
![]() 「ということで環境管理課の指揮系統に戻りますが、職制表は左図のようになっていますが、実質的には右図のように動いています」
「ということで環境管理課の指揮系統に戻りますが、職制表は左図のようになっていますが、実質的には右図のように動いています」
| 職制表 | 実際の体制 | |||||||
 |
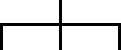 |
|||||||
注:これは第55話で問題にしたことが、課長が変わっても解消しなかったということだ。
仕事というのは職制表を書けばその通り動くのではなく、メンバーの能力と意思によって決定される。それが現実の職場の指揮系統である。建前と実際は一致すべきであるが、現実はそうではない。
![]() 「今朝の会議で感じたのだが、上西課長は山内さんから信頼されてないようだね」
「今朝の会議で感じたのだが、上西課長は山内さんから信頼されてないようだね」
![]() 「私もそう感じた。とはいえそれが磯原さんの言うように判断が遅いとか誤ったからかは分からない。
ともかく彼が積極的に動かない人ではあるようだ」
「私もそう感じた。とはいえそれが磯原さんの言うように判断が遅いとか誤ったからかは分からない。
ともかく彼が積極的に動かない人ではあるようだ」
![]() 「確かに積極性が乏しいようだね。それが彼の性格なら、手を打たないとだめかな」
「確かに積極性が乏しいようだね。それが彼の性格なら、手を打たないとだめかな」
![]() 「おっと、ストップ。話を戻します。
「おっと、ストップ。話を戻します。
仕事について話をさせてもらいます。
まず全員共通で大事なことです。山内さんから指示あった場合は、その指示に従ってください。そして一応課長にも話をしておくこと。報告は正(to)を課長宛て、そして漏れなく写(cc)を山内さんに送ること。報告に限らず情報はすべてそうしてくれたほうが良いですね」
![]() 「あのう、機密以外の種々の情報は環境管理課全員に写を送ることにしませんか。お手間でしょうけど、漏れなく情報の共有化するためにそれが良いと思います」
「あのう、機密以外の種々の情報は環境管理課全員に写を送ることにしませんか。お手間でしょうけど、漏れなく情報の共有化するためにそれが良いと思います」
![]() 「そうですね。前言を撤回します。機密以外の情報は正を課長、写を山内さんと課員全員に送ることにします。出張報告や工場で何か起きたなどについて、情報共有しましょう。
「そうですね。前言を撤回します。機密以外の情報は正を課長、写を山内さんと課員全員に送ることにします。出張報告や工場で何か起きたなどについて、情報共有しましょう。
柳田さんは庶務担当ですが、課のすべてを知ってもらうために、プライベートを除く業務連絡メールはすべて柳田さんにも送ってください」
![]() 「ちょっといいかな、山内さんに送る必要性は分かるが、細々したものでなく取りまとめたものを送らないと、山内さんが困るのではないか。つまりこのメンバーの報告とかやりとりを磯原さんがとりまとめ、山内さんと課長に送るのが良いのではないだろうか」
「ちょっといいかな、山内さんに送る必要性は分かるが、細々したものでなく取りまとめたものを送らないと、山内さんが困るのではないか。つまりこのメンバーの報告とかやりとりを磯原さんがとりまとめ、山内さんと課長に送るのが良いのではないだろうか」
![]() 「私もそう思います。見た聞いたというレベルのことを工場長レベルの人に送るのもなんでしょう。やはり情報のとりまとめというか、結論的なものを山内さんに送るべきでしょう」
「私もそう思います。見た聞いたというレベルのことを工場長レベルの人に送るのもなんでしょう。やはり情報のとりまとめというか、結論的なものを山内さんに送るべきでしょう」
![]() 「趣旨は分かりますが、微妙なんですよ。それにとりまとめるなら、私より職階から言って田中さんが適任です」
「趣旨は分かりますが、微妙なんですよ。それにとりまとめるなら、私より職階から言って田中さんが適任です」
![]() 「職制が機能していないのが最大の問題だな。これじゃ今回の4名の補強も有効に働けるのかどうか……
「職制が機能していないのが最大の問題だな。これじゃ今回の4名の補強も有効に働けるのかどうか……
まあ、当面は先ほどの磯原さんのお話で行きましょう。
岡山さんと石川さんはよろしいかな?」
![]() 「私は磯原さんの指示で仕事するということでよろしいのですね?」
「私は磯原さんの指示で仕事するということでよろしいのですね?」
![]() 「当面はそれでお願いします。
「当面はそれでお願いします。
石川さんは増子さんの指示で仕事をしてもらい、増子さんは石川さんの分もまとめということでお願いします」
![]() 「承知しました」
「承知しました」
![]() 「そうなると、私と坂本さんも磯原さんから指示を受けて、磯原さんに報告という形が筋じゃないの」
「そうなると、私と坂本さんも磯原さんから指示を受けて、磯原さんに報告という形が筋じゃないの」
![]() 「それじゃまたまた前言撤回で、石川さんは増子さんの指示で動き、増子さんに報告する。
「それじゃまたまた前言撤回で、石川さんは増子さんの指示で動き、増子さんに報告する。
石川さん以外の人は、増子さんを含めて私宛に報告するということにしてください。私がとりまとめて、正を課長、写を山内さんに送ります」
![]() 「了解した。難問が解決したね、アハハ」
「了解した。難問が解決したね、アハハ」
![]() 「仕事の前提を決めるだけで1時間かかりましたよ。お茶でも飲みましょう」
「仕事の前提を決めるだけで1時間かかりましたよ。お茶でも飲みましょう」
皆は配られたペットボトルのお茶に口をつける。
![]() 「あっ、漏れていたけど、課長から指示あるときはその仕事をどうするのかな?
「あっ、漏れていたけど、課長から指示あるときはその仕事をどうするのかな?
本来ならそれが仕事の基本だろうけど」
![]() 「まず皆、定常業務を持っています。更に山内さんからの指示があればそれもしなければならない。
「まず皆、定常業務を持っています。更に山内さんからの指示があればそれもしなければならない。
 その上に上西課長から突発的な仕事を言われたら、負荷的に対応できるかどうか検討が必要です。できないなら山内さんを含めて対応を決める必要があります。
その上に上西課長から突発的な仕事を言われたら、負荷的に対応できるかどうか検討が必要です。できないなら山内さんを含めて対応を決める必要があります。
困ったことがあれば、私に声をかけてください。山内さんと課長とでプライオリティを決めます」
![]() 「了解した。イヤハヤ、なかなか面白そうな職場だ」
「了解した。イヤハヤ、なかなか面白そうな職場だ」
![]() 「磯原さん、話は変わるけど、噂では熊本工場の……あっ、熊本工場の漏洩については、事故の経過の説明と各工場で点検せよと指示が出てますが、それじゃなくて、そもそも防油堤が破損したとき、安易に大丈夫と判断したのが発端だという噂が広まってますが、あれって本当なのかい?」
「磯原さん、話は変わるけど、噂では熊本工場の……あっ、熊本工場の漏洩については、事故の経過の説明と各工場で点検せよと指示が出てますが、それじゃなくて、そもそも防油堤が破損したとき、安易に大丈夫と判断したのが発端だという噂が広まってますが、あれって本当なのかい?」
![]() 「本当というか事実です。それについては皆さんにもご注意を願いすることがあります。
「本当というか事実です。それについては皆さんにもご注意を願いすることがあります。
先ほども申しましたが、職階が上がるほど、また担当者であっても工場より本社の人の判断は影響が大きい。
本社の仕事というのは……それはこれから話す予定ですが……工場や関連会社に対する指導と統制です。指導はわかるでしょうけど、統制とは目標やルールを与えてそれを守らせる、達成させるよう監督することです。言葉は悪いですがはっきり言えばそうなります。
本社には日々工場や関連会社から、多数の報告と問い合わせや相談が来ます。それを受けてどう判断し回答するのかは課長の仕事です。ですが今までは工場や関連会社からの問い合わせは、私が毎朝見て対応しています。これからはそれを田中さんにお願いするつもりです」
![]() 「そう聞いている。任せてくれ」
「そう聞いている。任せてくれ」
![]() 「よろしくお願いします。ともかく問い合わせ、相談を受けたら回答しなければなりません。相手は困っているのですから、対応しなければ問題はだんだん大きくなります。
「よろしくお願いします。ともかく問い合わせ、相談を受けたら回答しなければなりません。相手は困っているのですから、対応しなければ問題はだんだん大きくなります。
また放っておけば本社の言うことを聞かなくなる、『御恩と奉公』、『義理と恩』と理屈は同じです。世話になれば恩に感じて言うことを聞く、恩恵がなければ敬わない、それは当たり前です。
ということで工場や関連会社から相談や問い合わせがあれば早急に回答する、助けを求められれば対応する。もちろん適切なアクションでなくちゃ更なる問題を引き起こします。
事故とか苦情であれば、法律や会社規則に則って判断と対応をしてほしい。
ところでご質問の熊本工場の件は、いろいろなミスが重なり問題が大きくなりました。
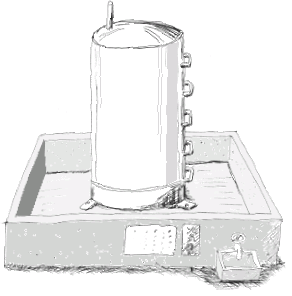 坂本さんのおっしゃったように、工事業者のトラックが防油堤を破損したとき、よく調べずに問題ないとOKした。
坂本さんのおっしゃったように、工事業者のトラックが防油堤を破損したとき、よく調べずに問題ないとOKした。
しかし防油堤がヒビ割れしただけでなくタンクの脚も破損していて、日数が経ってタンクが倒れて油漏れしたとき、防油堤のヒビ割れから公共水域に流出した。
公共水域に漏れたときは法令で行政への報告を決めてあるのに市役所に報告しなかったこと、また本社報告に該当するのに本社報告しなくてよいかと問い合わせしてきました。すべてが後手後手でした。
当初は本社では防油堤が壊れたことも、公共水域に油が漏れたことも知りませんでした。
今後はそういう隠し事をさせないように、情報伝達は速やかにするように、まずは法令や会社規則通りに運用することを徹底しなければなりません。
ですから田中さんのところにそういう情報が入ったら、法に基づく対応をしたかどうかの確認、またどうしたら良いか分からないという問い合わせなら、法規制や会社規則をめくって指示してほしいのです」
![]() 「なかなか責任重大な仕事だね。身が引き締まる思いだ(笑)」
「なかなか責任重大な仕事だね。身が引き締まる思いだ(笑)」
![]() 「ハハハ、私が転勤してくる前は、誰もそういった工場や関連会社からの問い合わせというか支援要請のメールを見てなかったそうです。それじゃ環境部の信用は下がるばかりです。
「ハハハ、私が転勤してくる前は、誰もそういった工場や関連会社からの問い合わせというか支援要請のメールを見てなかったそうです。それじゃ環境部の信用は下がるばかりです。
私は毎朝、始業1時間前に来て、前日退社してからの着信メールを始業時までに片づけることにしています。日中来たのは退社する前に片づけています」
![]() 「私も1時間前に来なくちゃいけないのか?」
「私も1時間前に来なくちゃいけないのか?」
![]() 「いえいえ、そんなことはありません。私の場合は、定時内は自分の仕事をしなくちゃならないので、余計な仕事は就業時間外にしていたということです」
「いえいえ、そんなことはありません。私の場合は、定時内は自分の仕事をしなくちゃならないので、余計な仕事は就業時間外にしていたということです」
![]() 「余計な仕事か、アハハハ……でも1時間で片付けられるものなのか?」
「余計な仕事か、アハハハ……でも1時間で片付けられるものなのか?」
![]() 「確かに毎朝数十件のメールが来ていますが、事故とか違反という緊急事態は年に両手はありません。多くは工場の環境定期報告とか行政に届けるための役員のハンコが欲しいとか、定常的な仕事です。
「確かに毎朝数十件のメールが来ていますが、事故とか違反という緊急事態は年に両手はありません。多くは工場の環境定期報告とか行政に届けるための役員のハンコが欲しいとか、定常的な仕事です。
それに1時間というのは私の場合で、田中さんなら就業時間内に行うのは当然です」
![]() 「それにしても毎朝数十件もメールが来るのだろう。簡単には片付かないだろうね。まして法律を調べたり行政に問い合わせしたりすることも多いだろうし」
「それにしても毎朝数十件もメールが来るのだろう。簡単には片付かないだろうね。まして法律を調べたり行政に問い合わせしたりすることも多いだろうし」
![]() 「そこは田中さんのお手並み拝見です。私が片手間にしていたのですから大丈夫ですよ」
「そこは田中さんのお手並み拝見です。私が片手間にしていたのですから大丈夫ですよ」
田中は腕組みして目をつぶった。磯原は馬鹿でもなく手も遅くないのだろう。
![]() 本日は慣熟の話
本日は慣熟の話
完熟ではありませんよ
メールの処理スピードは慣れによって大きく向上する。
慣れのひとつとして、多数のメールを扱って報告される問題のカテゴリーが一巡すれば、それ以降は考えることなくサッサと処理できるようになる。
「重油が漏洩しました」と聞けば血の気が引くかもしれないが、何度か経験すれば待ってましたという気持ちになれる。
もうひとつはメールを読む・手を動かすということが習慣化すると、同じメールを読むのも打つのも物理的スピードが速くなる。
私は引退してからテキスト入力数が大きく減少して、ブラインドタッチは忘れないものの、キーを叩くスピードはものすごく低下した。
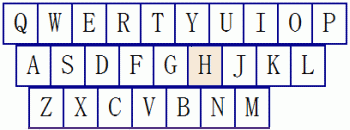 打つ文字数が少なくなっただけでなく、うそ800に来る問い合わせなどへの返事もすぐにしなくても間に合うことが大きい。
打つ文字数が少なくなっただけでなく、うそ800に来る問い合わせなどへの返事もすぐにしなくても間に合うことが大きい。
早く処理しなければならなければ、考えるのも速くなり、キー入力も速くなる。
まあ狭い日本そんなに急いでどこへ行くというから、急ぐこともないのだけれど。
おっと慣熟低減曲線とは昔少量生産における加工工数の推計で習った。例えば飛行機を生産するとき、第一号機生産にかかった工数に比べ、50機目くらいになるとかかる工数は3割くらいまでに減る。
戦いは数だよ、兄貴 !
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |