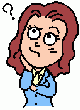第79条5項 (2003.01.06)
第79条5項 (2003.01.06)
「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。」
本条項は最高裁判事には定年があるよという定めです。
憲法で定年を決めているのは裁判官だけです。最高裁以外の判事については80条で定年があることを決めています。ちなみにその定年は最高裁と簡裁が70歳、その他が65歳だそうです。裁判官以外の公務員、たとえば首相をはじめとする閣僚、国会議員、知事、市町村長、自衛官、警官、先生、などなど多種多様ありますが、それらの公務員については定年、つまり一定の年齢になったら退職するという制度を『日本国憲法』では決めていません。
これまた非常に興味があります。最高裁と簡裁は肉体的に楽なので高齢まで勤めることができ、その他は厳しいのでそれより早く退職するのでしょうか??
なぜ、裁判官だけわざわざ憲法で定年を決めているのでしょうか?
裁判官という能力が年齢によっておおきく左右されるのでしょうか?
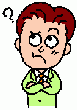
関係ないですが医師には今後定年といいますか、健康保険医としての年齢制限をすると聞きます。これは技量や判断能力が落ちるのを懸念してのことでしょうか?
それとも後がつかえているためなのでしょうか?
もし裁判官の能力が年齢によって低下するというなら、まったく同等の職務である弁護士、検事についても憲法で定年あるいは職業に従事できる年齢を定めておくべきではないでしょうか??
検事には定年はありますが、憲法では定年を決めていません。この違いはなんなのでしょうか?
いや、政治家は現実的には裁判官以上に世の中に影響を与えています。ところが県知事も国会議員も超高齢でがんばっておられる方がいます。
突っ込みを入れますと、年齢によって特定の職業に従事できないとするならば、憲法14条1項あるいは22条1項や27条1項に違反するのではないでしょうか?大日本帝国憲法でもアメリカ憲法でも定年に関する定めはないようです。ところがマッカーサー原案では定年
70歳 であったそうです。
マッカーサーはどこから定年という制度を持ってきたのでしょうか?
本日のまとめ、
裁判官だけに憲法で定年を決めている理由がわかりません。
裁判官に定年を設けることを憲法で定めるならば、他の法曹資格あるいは公務員にも定年があることを明記すべき、
裁判官だけに言及するのはおかしいですよね、
IQ88様から、裁判官定年制の解釈をいただきました。
日本国憲法の目次にもどる