15.05.11
審査員物語とは毎日というと大げさだが、三木は週に3日は審査に出張していた。審査の最終日が昼終わりとか3時終わりということもあるが、通常は5時までかかり、家に帰りつくのはほとんど真夜中だ。
 |
| 三木の家内の陽子です。私の登板は年に1回しかないのよ ♥ |
一昨日から名古屋のサービス業の審査に来ていて今日は5時終わり、名古屋駅6時の新幹線に乗ることができた。「のぞみ」に乗ると新横浜まで行って戻ることになるが、それでも小田原に停まる「こだま」よりも家に着くのが40分程度早い。この分だと今日は9時前には家に着くと思うとうれしくなる。
週末ではなかったので自由席はけっこうすいていた。一人だけしか座っていない3列シートがあったので、一言断って空いているところに座る。車中で資料を出すのはご法度だから、名古屋駅で買った剣豪物の文庫本を読むつもりだ。特に時代劇が好きだというわけではないが、暇つぶしに読むには他愛のないのが一番良い。飲むのと食べるのは帰宅してからだ。
先住者が恐る恐るといった風情で声をかけてきた。
「あのう、三木さんではありませんか?」
| ||||
三木はハットして顔をあげた。 3年くらいも前になるだろうか、三木がISO審査員に出向せよと内示があったとき、妻の知り合いで審査員をしているご主人にお会いして話を聞いたことがある。座っていたのはあの六角氏であった。その後も数回、メールのやり取りなどをしていろいろと審査員の仕事や生活などについて教えてもらったことがある。 | ||||
「おお、六角さんですね。これは気がつきませんで、失礼いたしました。あのときは大変お世話になりました。おかげさまで今はなんとか審査員を務めております」
| ||||
「いやいや、お世話なんてしてませんよ。どうですかお仕事の方は?」
| ||||
「なんとかというところでしょうか。いろいろとお話ししたいことがあるのですが、ここではなんですから降りてから居酒屋かどこかでいかがですか?」
| ||||
六角は腕時計を見て | ||||
「今6時半か、新横浜で7時半、辻堂8時過ぎ。そうしましょう」
| ||||
 横浜からの戻りの東海道線はひどく混んでいた。もし三木が審査員にならず、子会社に出向していたら毎日この電車に乗っていたのだろう。出張も大変だが毎日通勤電車に乗るのも大変だと三木は思う。
横浜からの戻りの東海道線はひどく混んでいた。もし三木が審査員にならず、子会社に出向していたら毎日この電車に乗っていたのだろう。出張も大変だが毎日通勤電車に乗るのも大変だと三木は思う。駅前の居酒屋で幸い個室が空いていた。まあここなら仕事の話をしても良いだろう。 二人はビールと肴をみつくろって頼んだ。 | ||||
「早速ですがいろいろとお尋ねしてよろしいでしょうか?」
| ||||
「分ることなら、とはいえ三木さん審査員になられてもう3年4年になるでしょう。今更わからないことなどないじゃないですか?」
| ||||
「いえいえ、単刀直入にお聞きしますが、環境目的の環境マネジメントプログラムと環境目標の環境マネジメントプログラムは別個に必要なのでしょうか?」
| ||||
「そりゃ初歩的というか基本的なことですね。三木さんはどうお考えなのですか?」
| ||||
六角はウッチャリが得意だ。 | ||||
「初歩的とおっしゃいますとその通りですが、CEAR誌に質問した審査員もいますから私が分らなくても恥ではないようです。 正直言いますと、ウチの社内ではボス的な人がいましてね、その人がこれはこう解釈するのだというと他の審査員、まあその人から見て目下はそれに従わなくちゃならないような雰囲気でして」 | ||||
「まあ、それはどこでも同じでしょう。審査員に限らず営業だってそうじゃないですか」
| ||||
「それはそうですが、ともかくその人の意見は二つ必要というのです。実際の審査の場では、まあいろいろですね」
| ||||
「いろいろと言いますと?」
| ||||
「私が参加した審査で、環境実施計画がひとつしかない会社はいくつかありましたが、向こうが理屈を通してきたときは適合判定していましたし、こちらの意見に納得したというか不適合を認めた会社には軽微な不適合としていますね、私自身こんなことでよいのかと悩んでいます」
| ||||
「アハハハハ、節操がない話ですね。実を言って、そういったことはあちこちで聞きますね。ツクヨミでは目的と目標を達成するのに必要十分ならひとつで良いとしていますね。書き物というか計画がひとつかふたつかということは本質的な問題ではないでしょう」
| ||||
「私もそう思います。しかしそのボスが語るところは、計画書がひとつではダメ、二つなければ不適合ということです」
| ||||
「そう言い切ってしまうとアブナイというか・・・ともかく間違いでしょうねえ まあ、どこの認証機関でも内部ではいろいろあるでしょうけど」 | ||||
「六角さんのお考えはふたつに拘らなくて良いということですね?」
| ||||
「それはそうですよ、審査で判断するときは規格に書いてあることしか基準になりません。有名な審査員が本に書いていたとか、上司が言っていたからとかは参考にはなるかもしれませんが、審査基準じゃありません」
| ||||
「そんなふうな表現を伺いますと、裁判官のような立場に思えますね。裁判官は上司や上級裁判所から独立していて、そういったものからの指示に従う義務はありませんからね」
| ||||
「裁判官ですか・・・ちょっとというか、大きく異なるように思います」
| ||||
「違う? とおっしゃるのは審査員は裁判官ほど知識とか見識がないということでしょうか?」
| ||||
「いや、知識も見識もある審査員もいるでしょう。違いは三木さんがおっしゃったことそのもの、つまり審査員は裁判官のようには上司や認定機関から独立しておらず、その指示に従うからです。先ほど三木さんがおっしゃったことそのままですよ」
| ||||
三木はしばし黙っていた。六角はジョッキが空になったのを見てボタンを押してウェイターを呼び焼酎のお湯割りを頼んだ。 | ||||
「話しは変わりますが、著しい環境側面の決定方法には点数法以外でもOKなんでしょう?」
| ||||
「三木さんもとうに主任審査員になられていますよね。そのような基本的なことでお悩みなのですか?」
| ||||
「そう言われるとお恥ずかしいとしか・・・。ともかく実際に審査の場で見かける方法は9割以上が点数法ですね。そしてそれ以外の方法ですと、これまた先輩や同僚が徹底的に質問攻めして点数法に導いているというのが実態です。当社の場合はですが・・」
| ||||
「確かに実際の審査では9割が点数法ですね。私も人並みには環境側面に関する本を読んでいるつもりですが、そういった本では点数法以外にも方法があるとは書いているものの、具体的な方法を示していないです。ただ昨年、2004年にBV社という認証機関の土屋さんという方が書いた『環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き』という本では、該否判定で決定する方法をメインに説明していましたね」
| ||||
三木は手帳を取り出して六角の言った本のタイトルをメモした。 | ||||
「六角さんは点数法以外の方法でもOKするのでしょうか?」
| ||||
「もちろんですと言いたいところですが、やはり上司から客観性とか公平性それに誰が評価しても同じ結果になるかとか言われますね。点数法の場合はほとんどフリーパスです そう考えると、御社と同じことなのかなあ〜」 | ||||
「なるほど、表だって言うか言わないかの違いですか」
| ||||
「また聞きですが、ナガスネさんでは営業の方が点数法でなければだめですと説明しているとか聞いてます」
| ||||
三木は驚いた。そこまで言うのはいささかまずいのではないだろうか? | ||||
「六角さん、そんなこと言うのってまずいんじゃないですかね。万が一認定機関とかに知られたら・・」
| ||||
「まずいでしょうね。実を言ってウチの営業からナガスネさんの営業がそんなことを言っていたとかいう話を聞いたことがありました」
| ||||
「まあ、それが現実なら問題になってもしょうがありませんね それはそうとして、六角さんは著しい環境側面を決めるにはどういう方法が良いとお考えでしょうか?」 | ||||
「ご存じと思いますが私は営業出身です。公害防止とか廃棄物の実態とか、どうすれば省エネになるかなんてわかりません。ですから工場をながめてもこれが重大な管理項目だとか、これは非常に危険だとか、今に事故が起きるなんてわかるはずがありません。」
| ||||
「といいますと?」
| ||||
「現実問題として点数法が一番楽だということです。こういう論理で重みを付けて計算した結果こうなりました。上から何位までが著しい環境側面ですといえばだれでも説得するでしょう」
| ||||
「でも審査では決定した環境側面が適切かどうか評価しなければなりませんよね」
| ||||
「そうです。だからこそ点数法なんてのが流行ったのだと思いますよ。決定された環境側面が適切か否か判断できない審査員が、自分が納得するため、そして判定委員会を納得させるために取った手段が点数法だったのです。 三木さん。廃棄物100トンと重油20トンの環境影響が同等か否かなんて、私にわかるはずがありません。三木さんはお分かりになりますか?」
| ||||
「そりゃ難しいですね。というか正直わかりませんね」
| ||||
「規格では環境側面に点数を付けろとか順位を付けろなんて書いていません。あるのは著しい環境側面として取り扱わなければならないということですよね」
| ||||
「というと?」
| ||||
「つまり目的目標にとりあげるとか、運用の手順や基準を決めろとか、監視をしなければならないとか、そういう管理対象にしなければならないものが著しい環境側面というだけでしょう」
| ||||
「えっ、そういうことなんですか? いや、環境側面とはそういうものなのですか?」
| ||||
「ええ、三木さん冗談をおっしゃっては困りますよ。一体なんのために環境側面を調べるのですか?」
| ||||
「いや、そうでしたね。そのとおりです」
| ||||
「以前、三木さんとお会いしたときに鬼軍曹の話をしたと思います。そういえばあのあと三木さんから鬼軍曹に会いたいというメールを頂き紹介したはずです」
| ||||
「ああ、あの節はお世話になりました」
| ||||
「鬼軍曹に会った感想はいかがでしたか? もう忘れてしまいましたか?」
| ||||
「どうも・・・なんというか・・・彼の言葉があいまいで、正直言ってもっと直接的・具体的なアドバイスが頂けるかと思っていたのですが・・」
| ||||
「お役にたたなかったですか。それは残念です。彼はものすごい人ですよ。実を言って今私が語っていることは、彼が私に教えてくれたことです。環境側面を決定する方法をひねくりまわしても、そのことに価値はありません。要するに管理しなければならないものを認識することなんです」
| ||||
「認識するとは?」
| ||||
「身をもって感じるということでしょう。公害防止を長年している人が、あなたの仕事でなにを管理しなければならないかと聞かれたら、計算するとか順位を付けて考えると思いますか?」
| ||||
「もちろんそんなことをするまでもなく即答できるでしょうね。そうでなければ仕事ができないでしょう」
| ||||
「そうすると点数を付けるとか順位を付けるという意味はなんでしょうか?」
| ||||
「でも六角さん、公害防止とおっしゃいましたが、環境側面とは公害ばかりではありません。電力とか廃棄物などだけでなく、製品もサービスもありますよ。それから環境配慮事業もあるでしょうし・・ そういったことを包括的に評価し考えるには・・」 | ||||
「もちろん包括的に考える必要はあります。でも製品が重大だから廃棄物を無視して良いとか、電力の環境影響がはるかに大きいからPCBは忘れても良いということがありますか? それに工場の公害対策と、製品の担当者とサービスの担当者は同一人物じゃありません。公害防止担当が工場のことを手のひらのように知っているように、製品の担当が製品の環境側面をしっかりと認識していればよろしいじゃありませんか」 | ||||
「でも管理項目が多すぎれば管理ができなくなります。環境側面を上位何件と決めるのはそういうことがあるからでしょう」
| ||||
「ちょっとちょっと、三木さん、勘違いしてはいけません。管理しなければならないものがたくさんあっても管理しなくちゃ問題が起きるなら管理しなくちゃなりません。 電力もPCBも廃棄物も騒音も製品も部品材料のロジスティクスも、みんな管理しなくちゃならないのです」 | ||||
三木は黙って考える。確かに電力が一番影響が大きいからPCBは著しくないとか、製品の影響が大きいから工場騒音を無視して良いということはない。飲酒運転のほうが罪が重いからと、スピード違反を気にしなくて良いというわけにはいかない。 | ||||
「そうすると環境側面というのは数限りないということになるのでしょうか?」
| ||||
「まあまあ、法規制に関わるもの、事故が起きたら重大な影響のあるもの、事業上や金額的などを考慮すれば、環境側面は無限ではないでしょう」
| ||||
「なるほど、おっしゃることがわかりました」
| ||||
三木はしばし黙って今の六角の話を反芻した。 | ||||
「すると・・・私の理解が間違っているかもしれませんが、設計や営業が製品の環境側面を考えて、資材や物流部門がロジスの側面を考え、工場管理部門が公害やエネルギーについて考えるということになるのでしょうか?」
| ||||
「そのように部門・部門が自分の管理下の環境側面を明確にすることでもよろしいでしょう。あるいは誰かが全体を考えても良く、各部門のものをひとつにまとめても良い」
| ||||
「えっ、組織つまり認証範囲の環境側面をとりまとめておかないといけないはずですから、ともかく組織の環境側面を一覧にしなければなりませんね」
| ||||
「三木さん、規格は組織の環境側面を取りまとめろとは書いてませんよ。まとまるのは審査員が一覧できるようにするための企業側のサービスです」
| ||||
「ええ、そうなのか、そうとばかり思い込んでいました。 しかしそうなると一体どんな管理になるのだろう。無政府状態になるのでは?」 | ||||
「ISO認証が始まる前を考えてください。1995年以前だって環境管理はありましたよ」
| ||||
「公害防止はあったと思いますが、製品やロジスはどうでしょう? そういった業務では環境という発想さえなかったと思います」
| ||||
「そんなことはありません。製品だって昔から省エネ競争はありましたし、省エネ法もありました。化学物質の忌避というか使用制限もありました。 ロジスまあ運送を考えれば、物流効率化を追求して輸送ルート、運転手の回し方、途中発生する廃棄物の効率的処理など、十分に環境配慮していたはずです。もちろん環境というキーワードはなく、在庫削減、納期短縮、費用削減、事故防止なんていうテーマだったかもしれませんが、 要するに環境配慮というのは公害防止だけでなく製品でも流通でも全方位において考えていました。環境という言葉とか意識がなくてもです。もちろん今よりも規制が甘かったことはあるでしょうけど」 | ||||
「つまり?」
| ||||
「つまりですね、過去から各部門は担当する業務や製品、サービスにおける環境負荷を認識し、それを管理してきたのです。 管理といっても公害防止のような管理もありますし、そうですね、営業部門なら他社品の仕様や、顧客要求を把握して、それを設計にフィードバックしていた。そしてまた営業活動においては、当社製品の環境性能をアッピールしてきたというわけです。それが環境配慮であり対象となる項目が環境側面ですよ」 | ||||
「それって、単なるビジネスのためですよね?」
| ||||
「はあ? ISO14001の目的は、遵法と汚染の予防ですよね。規格の序文に書いてありますよね。それはビジネスの持続可能のためでしょう。うーん、なんと言ったらよいのでしょうか、現実のビジネスにおいて、会社が永続していくためにはあらゆる方面において様々な手を打たなくちゃならない。ISO14001はそのほんの一部、環境のそのまた一部についての実施事項を記しているだけだと私は考えています」
| ||||
三木は驚いて六角を見つめた。聞けば当たり前のことでしかない。しかし環境側面の意味というのを初めて聞いたように思った。今まで三木は環境側面とは架空の指標のように思っていたのだ。そうではなく、実際の事業活動において重要だと判断したものが環境側面だったのだ。 | ||||
「なるほど、環境側面とはそういうものだったのですか・・・ 私は審査員研修を受けましたし、今では主任審査員になりましたが環境側面の意味というものを真面目に考えていなかったようです。しかし、」 | ||||
「しかし?」
| ||||
「六角さんのお話を聞いて正直目からうろこという感じですが、そのような発想ではナガスネでは仕事をしていけませんね。ウチではバーチャルな環境マネジメントを審査しているだけのように思えます。私は従来からのバーチャルな審査を続けるより仕方ないようです」
| ||||
「まあ、そこんところは三木さんが解決するしかありませんね。私には三木さんの関わりない悩みもあるわけで」
| ||||
「六角さんに悩みがあるとは思えませんが」
| ||||
「何をおっしゃる。いやね、三木さんは有益な環境側面というのを聞いたことがありますか?」
| ||||
「ええ、最近はやりの言葉ですね。半年ほど前、CPDのために審査員研修機関に行ったとき初めて聞きました。斉藤さんという講師でした。有名な方のようですね。 ええと、今までは環境に悪影響のあるものばかり取り上げていたが、これからは環境に良いこと、環境負荷を低減することをとりあげるべきだ。それを有益な環境側面というということでしたね」 | ||||
「そのとおり、と言いたいところですが、それって間違いだと思いますね」
| ||||
「間違いとおっしゃると?」
| ||||
「環境側面とは有益も有害もありません、いやないと思います。それはISO規格にも書いてありますが、有益な環境影響も有害な環境影響も漏れなく調べて環境側面を決めろって書いてありますよね」 | ||||
「とすると有益な環境側面を把握は、以前からしなければならなかったということですか?」
| ||||
「いや環境影響には良い影響、悪い影響というのがあるでしょう。しかし環境側面とは組織とまわりの環境の境界、環境影響が出入りする窓と考えられます。窓から出入りする影響に良い悪いがあっても窓そのものには良い悪いはないということです」
| ||||
三木は六角の話を聞いてもまだピンとこない。 | ||||
「その講習で聞いたたとえ話ですが、従来タイプのエアコンをインバータに替えると省エネになるからインバータは有益な環境側面だとしているのですが」
| ||||
「ハハハハ、笑い話ですね。講師の頭をかち割って、中身を見たいものです。たぶん脳みその代わりに麦わらでも詰まっているのでしょう」
| ||||
「はあ?」
| ||||
「そいじゃインバータエアコンをやめて扇風機にしたらもっと省エネになりますよね。そのときインバータエアコンは悪い環境側面に、扇風機は良い環境側面になるのでしょうか? 環境側面とはそんなあいまいというかいいかげんな概念ですか?」
| ||||
「うーん、それは・・・すると今有益な環境側面と言われているものは比較の結果にすぎないということですか?」
| ||||
「いやそうではありません。有益な環境側面というのは正しくは環境側面ではなく、環境改善活動とか環境配慮することを間違って側面と呼んでいるに過ぎないと思います」
| ||||
「なるほど・・・いや、待ってください。今まで環境側面に取り上げていたものも、今六角さんに教えられたことから類推すると似たようなものもありますね」
| ||||
「ほう、どんなことでしょうか?」
| ||||
「私が審査したところでしたが、廃棄物業者各社を個々に評価して、A社は著しい環境側面だ、B社は著しくないとしていた会社がありました」
| ||||
「なるほど、それは・・・まあ、間違いでしょうなあ、アハハハハ それは単なる業者の評価ではないでしょうか。やはり環境側面は廃棄物でしょう。 いや、廃棄物というものが環境側面だと言い切れるかどうかも考えないといけないかもしれません」 | ||||
「廃棄物はどう考えても環境側面でしょう?」
| ||||
「考え方によって何を環境側面とするかが変わります。 例えば製造部門において工作機械とかコンプレッサーあるいは走行クレーンは著しい環境側面でしょう。おっと著しくないときもあるでしょうけど、まあ環境側面であることは間違いない。 しかし工場全体から考えると、工作機械とか騒音発生源というくくりで見てもおかしくはない。製品も個々に分けるのではなく、まとめて考えるということになるかもしれません。 更に本社の立場からみれば、工場の指導や管理が本社の環境側面という見方もできます。いやそうでなければおかしいですね。なぜなら環境側面とは、目的目標にとりあげるとか、運用の手順や基準を決めろとか、監視をしなければならないとか、そういう管理対象にしなければならないものなんです。 本社においては個々の工作機械などどうでもよい・・・というわけじゃありませんが、管理できません。本社が管理するのは工場なのです。 フフフフフ、同僚の審査員が審査の場で『本社であっても工場の機械設備を十分把握して管理しなければならない』なんて語っていた人がいます。彼は管理というものを知りませんね。そんな論理なら部長・課長・係長というハイラルキーをどう考えるかという基本まで戻って勉強しなければなりません」 | ||||
三木はバカではない。一瞬にして六角の言わんとすることを理解した。 | ||||
「六角さん、わかりました。つまり環境側面とはそういうことなのだ。とすると点数法というのはまったく意味がない。そしてまた有益な環境側面というものがありえるはずがない」
| ||||
「お分かり頂いてうれしいです。おっと、これも私の考えではなく鬼軍曹のお教えですがね、アハハハハ」
| ||||
「しかし、ちょっと待ってください。環境側面がそのようなものだとしたら、我々、いや失礼、私のように実際の環境管理をしたことのない人間は、どのように審査をしたらよいのですか? 私のような人間は、審査をしてはいけないということでしょうか?」
| ||||
「そもそも審査員の仕事は何かといえば、JAB基準に書いてあります。我々はその基準に従い、審査する組織が、どんな方法で著しい環境側面を決めているか、そのとおり行っているかを確認すればいいだけでしょう。それであれば我々にも判断できるのではないでしょうか。むしろ点数法であるとその点数の精粗に気を取られ、結果が常識的か否かの検証を怠ってしまうのではないですか」 この時点で有効であった「EMS審査登録機関に対する認定の基準」についての指針JAB RE300-2006」G.5.3.21.(a)に 組織が環境側面及びそれに伴う影響のうちどれが著しいものかを決める手順が適切なものであり、また、守られているかどうかを審査するのは、審査登録機関の仕事である と定められていた。 | ||||
三木はしばし沈黙し焼酎を飲んで今までの六角の話を思い返した。 なるほど、通り一遍というか思い込み、固定観念の上でいくら考えても真理にはたどり着けないのだなと思う。そして六角がいうように鬼軍曹、名前はなんといっただろう、そうだ佐田とかいったなあ、そんなことを思い出した。 | ||||
「なにか有益な側面で話が長くなってしまいましたね。そろそろお開きにしましょうか。お互いに家に帰るのは数日振りでしょうから」
| ||||
「いや今日はとてもためになるお話ありがとうございます。また機会あればぜひともお願いしたいです。 おおそうだ、先ほど六角さんのお悩みとかいう話でしたが・・」 | ||||
「まあ大したことじゃありません。 実は数週間前のことですが、審査に行きましてね、私ではなく別の方がリーダーでした。そこで有益な環境側面がないという不適合を出したのです。言い訳ではありませんが私ではありません。 そしたら先方はそれを諾とせず、異議申し立てをしてきたのです」 | ||||
| 「ほう! 異議申し立てなんて実際にあるのですか?」 | ||||
「ありますとも、実を言って私も異議申し立てではないですが苦情を受けたことがあります」
| ||||
「非常に関心があります。どのような苦情だったのでしょうか?」
| ||||
「態度が悪いというか口のきき方が失礼だということでした。まあ我々は客商売ですから、自分はそういうつもりじゃなかったといっても意味がありません。李下に冠を正さず、誤解を招くようなことをしてはいけないと肝に銘じますよ」
| ||||
「なるほど、私もしっかりと心に刻んでおきます。 ところでその有益な側面についての異議申し立てですが・・」 | ||||
「そうですねえ、リーダーをされた方がどうするのかわかりませんが、有益な側面がないという指摘は微妙でしょうねえ 環境側面をすべて網羅していないという証拠を上げるか、有益と有害を分けて考えることが正しいということを立証し、更に有益な環境側面で該当するものがあるのに取り上げていなかったとか、審査側が不適合を正当化するにはハードルが高そうです。それにISOTC委員の寺田さんは環境側面に有益も有害もないと講演してましたし・・」 | ||||
「なるほど」
| ||||
「これは私の責任問題ではありませんが、次の審査でそのような問題が起きたらどうしようかというのは私の悩みです」
| ||||
「ツクヨミさんでは有益な環境側面があるとしているのですね」
| ||||
「そうなんですよ、それも困ったことにウチが発行している登録企業向けの季刊誌で理事長が『審査では有益な環境側面を把握しているかを確認する』なんて明言しちゃってますからね。参りましたよ」
| ||||
三木はどこの認証機関も規格解釈がまっとうだとはいえないのだなと知って少し安心した。 |
私はただ過去の経験とか思い出をだらだらと書いているつもりはない。日本のISO審査をくだらないものにしたアホな審査員たちを揶揄することにより、彼らが世の批判を受け恥を感じ過去を反省して世の中に謝罪をすることを求めている。
もっとも
ハインラインの小説はひとりの主人公がいろいろな体験というか冒険をするものが多いが、アジモフの小説はある世界を設定して何人もの登場人物がでてくるものが多い。それらの登場人物はどこかで他の登場人物と関わりがあって物語が進む。この駄文(駄作)も現実にありそうなそんな相互作用を書きたいと思っている。
山田太郎と佐田一郎が知り合って、佐田が六角を教育し、六角が三木と交流する、そんなものにしたいなと・・
P様からお便りを頂きました(2015.05.11)
実を言いまして、下記はP様とのメールのやりとりをダイジェストして私が文章としたもので、P様のご了承は得ております。
おばQ様 初めまして。 2年ほど前の当社の審査で次のような事例がありました。 まず当社は本社といくつかの工場があり、本社とそれぞれの工場は別個にISO14001の認証を受けています。それぞれの認証機関はひとつではなく複数です。 ある工場で小規模の重油の流出事故が起きました。その事故は地方紙で報道されました。 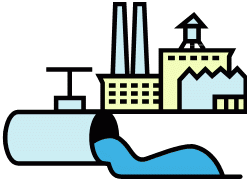 翌年の本社のISO審査で、工場の重油タンクが著しい環境側面になっているか質問を受けました。しかし工場の重油タンクは本社の著しい環境側面にはしていませんでした。その代り工場の環境管理の指導監督を本社の著しい環境側面としていました。その結果、工場の重油タンクが本社の著しい環境側面になっていなかったのが不適合だと言われました。
翌年の本社のISO審査で、工場の重油タンクが著しい環境側面になっているか質問を受けました。しかし工場の重油タンクは本社の著しい環境側面にはしていませんでした。その代り工場の環境管理の指導監督を本社の著しい環境側面としていました。その結果、工場の重油タンクが本社の著しい環境側面になっていなかったのが不適合だと言われました。当社としては重油流出事故の後に、本社の環境管理部は他の工場へ現場の一斉点検と管理基準の見直しをさせて不備のあるところには指導を行いました。また事故を起こした工場については再発防止の指導とフォロー、設備改造の資金計画などを行っています。なお本社はオフィスビルだけで重油タンクはありません。 ですから工場としては重油タンクは著しい環境側面ですけど、本社にとっては工場の管理が著しい環境側面であること、私たちは本社の機能として工場の環境管理についての(外部)コミュニケーションを取り上げており、工場の環境管理を本社の著しい環境側面にして、実際に指導監督をしているので本社のしていることはISO規格の通りであることを説明したのですが審査員はなかなか納得しませんでした。 だいぶ議論がありましたが、結果として工場の重油タンクを本社の著しい環境側面にすることが観察になりました。 私たちはその観察に対応しませんでした。次回審査でその件がフォローされましたが対応しないことにしたと回答し、若干議論がありましたがそれっきりになりました。 これはどうお考えになりますか。 |
P様、お便りありがとうございます。 結果からいえばそれでよかったのではないのでしょうか。審査側としては一層の改善(と彼らが考えたこと)を観察にして、組織側がそれを検討したけど採用にしなかったというだけと思います。 環境側面をどう考えるかは一意には決まらないでしょう。その審査員が持っていたイメージあるいは過去の経験から、本社が工場を細かく管理すべきだ、できるはずだと考えたとして、それが勘違いであったかどうかはともかく、審査側が改善提案をすることは悪いことでも越権でもありません。また企業側が提起された観察を採用しようとしまいと企業が判断することです。 まあ御社の対応を拝読しますと、完璧でケチを付けられず、しかし審査員も現実に事故が起きたわけで、少しは何か言わなくてはならないと考えたのかも知れません。あるいは昨今の情勢から、認証機関の意向として事故が起きたからには不適合を出すとあらかじめ決めてきたのかもしれません。 御社としては、観察にもしたくなかったかもしれませんが、それはまあ仕方ないでしょう。世の中妥協も必要ですから、お書きになったあたりが落としどころ、妥協点ではないかと思います。 指摘事項だとなると、「工場の重油タンクを本社の著しい環境側面にした場合とそうでない場合、どう対応が違うのか?」という議論になるでしょうけど、審査員が大人だったと思うことにしましょう。 |
審査員物語の目次にもどる


