ISO14001は繰り返し読んでいるが、おかしいなあ〜とかばかばかしいと思うこと、多々ある。そんなもの読んでいるより、人間もっと生産的なこと、ポジティブなことをしなければならないと思う。そもそも規格を読めばごりやくがあるのか? と疑ってしまう。
ということで今回は規格の価値を考えたい。
 |
そんなわけでISO規格をひたすら読む人は多い。
だが規格を読んでためになったとか、改善につながったということはあまりというか、全然ないんじゃないだろうか?
というのはISO規格はshallがあるだけで、howはまったくない。当たり前といえば当たり前で、ISO規格は「こうあるべし」「達成すべし」ということのオンパレードである。方法とか道順を示すものはひとつもない。まあそれが規格要求事項といえばそれまでだ。
例えれば、「東京に行くべし」とあるだけで、「車で行け」とか「電車を利用しろ」もなく、その道順も費用をどう見繕うのかともない。そして東京に行けばどんないいことがあるのかも書いてない。そんなISO規格を崇めることは……ないと思わないか?
ISOの考えはキリスト教の世界、ISO規格は聖書と同じなんて語る人もいる。
現実には、ちょっとというか大いに違う。旧約聖書にしろ、新約聖書にしろ、神あるいはイエスが語ることは、到達点ではなく、行動すべきことを具体的に語っている。
シナイ山でモーゼにつかわされた有名な十戒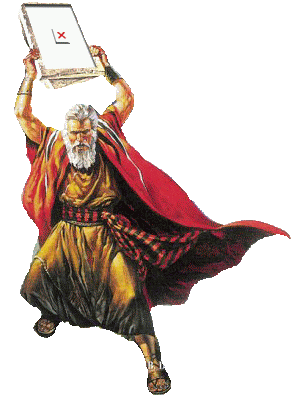 それを行うのが難しいか否かはともかく目的だけを示したものはひとつもない。すべて方法とか行動である。
それを行うのが難しいか否かはともかく目的だけを示したものはひとつもない。すべて方法とか行動である。
イエスが語った、敵を愛せ、迫害する者のために祈れと聞くと心が折れ実行不可能に思えるけど、具体的なことしか語っていないのは事実。
不倫した女をどう処罰しましょうと聞かれて、イエスは自分に罪がないと思う人から石を投げなさいという
イエスが語ることに判じ物、禅問答、解釈に困るもの、そんなものは一切ない。
旧約も新約も言葉がすべて、しかもその言葉は具体的、即物的であり、あいまいなことなどひとつもない。
それに対してISOMS規格は聖書と違い、明確なことは一切なく、曖昧模糊である。ISO規格は聖書と同じでは絶対にない。
ましてやJAB理事長の語ることが絶対なんてことは絶対にない。ユダヤ教では法治主義は3000年以上前からあるのだ
ともかく規格をひたすら読んでも、裏から読んでも、暗記しても、あなたがなにごとかを行うときに役に立つアドバイスがISOMS規格から得られるわけではない。規格に書いてあることは要求事項、つまり仕様だ。その仕様を実現する方法はまったく記してない。
例えばなにかの設備を導入して管理手順を作ろうとしたとする。それは設備の操作方法とかメンテナンスだけでなく、それを運用する管理体制、従事者の資格要件、法規制対応など多様な項目について手順や基準を決めることだ。
ISO規格をながめても管理手順を決める手掛かりは……ない!
例えば法規制を把握せよとあっても、そのhowもないし、whyもないのだ。人が仕事をするには目的/理由を知ることが大事だと語ったのは誰だ?
ISO規格の7.3 認識に、働く人にはa)方針、c)各個人の貢献(責任でもある)について共通認識を持たせなければならないとある(注4)。
ISOMS規格とそれが定めることは違うと言われると違うんだろう。ともかくISOMS規格にはKnow-howもKnow-whyもKnow-whatもない。あるのはshall be/doだけだ。
いや、それが悪いとは言わない。何度も言うが、ISO規格は到達点を示すだけで、いくらISO規格を読んでもそこに至る道はわからないということだ。道は開けない(注5)。
だから手順を作るにはISO規格を離れて、メーカーの仕様書とか関係法規制とか、費用とか、社内規定などをすべて調べて、自分なりに5W1Hを決めていくしかない。そして決めたことを文書に定めることになる。
で、そのときに手順書が要件を具備しているかどうかということの確認には、ISO14001は使えるだろう。その段階というかその用途には、ISO規格に書いてある「○○を考慮せよ」とか「○○を定めよ」とかあるから、あなたは作った文書が「○○を考慮したか」とか「○○を定めたか」が織り込まれているかどうか参照することはできる。
出来上がったものに漏れがないか、重複がないか、ということを確認するにはISO14001は役に立つこともある。ということは役に立たないこともある。
これは当たり前のことであるが、よく考えれば当たり前のことではない。
それならISO規格から出発するとかISO規格を満たそうとするのではなく、ISO規格はプロジェクト完了時の点検に過ぎない。それを変と思わなければそれはおかしい。
そして更なる問題だが、ISO規格要求を満たしていれば必要十分であると、ISO規格自身が言ってないのだ。これ重要、
私の基本的な考えとして、会社とISO14001とどっちが重要かといえば、会社が重要である。会社といっておかしければ会社の業務と言おう。
すべての会社はそれぞれの事業をしている。製造業ならその事業は開発設計、調達、加工、営業などに分かれて推進される。それは法規制、技術的な制約、顧客要求、需要、その他多様な制約条件がありそれを満たして動いていくためのルール、判断基準、品質基準などがあり、それを達成し維持していくという手順である。
そこにISO規格が入り込むすきなどない。いやISO規格に基づかねばならないという理由もないし、そんなことをしてうまくいくはずもない。
いや、ISO規格を骨にしてシステム(体制)を作らねばならないと考える人もいるかもしれない。過去にISO規格を読んで感動し、会社の就業規則から何からISO規格に合わせて見直したと書いている人がいた。
アホか? そんなことできるはずがない。
だってISO規格に人事管理とか業務管理のことが書いてない。私が思うに、その人はISO規格に自分が思い描いていたことを書いてあると行間を読んだに違いない。規格が漠然としているから、月の地表の色合いからウサギに見えたのと同じじゃないかな?
まともな人なら、まず思いもしないことではある。
ISO規格で会社の仕組みが作れるはずがない。いつも言うことだが、お金の流れ管理については全く言及していない。
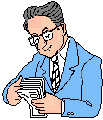
経営者の責任として「資源を提供する」とあるが、それを完璧にできる会社が存在するとは思えない。仮に余裕でできるなら、それは経営が最善を尽くしていないことになる。
人の管理もそうだ。いやいや、製品・サービスに関してもISO規格はあまりにも漠然としてどのように現実とつながるのは定かでない。
ISO規格は必要条件でもないし十分条件でもない証拠として、必ず序文でエクスキューズを書いている。
ISO9001:2015 序文
組織はこの規格に基づいて品質マネジメントシステムを実施することで、次のような便益を得る可能性がある。
ISO14001:2015 序文
この規格の採用そのものが、最適な環境の成果を保証するわけではない。(中略)二つの組織が、同様の活動を行っていながら、それぞれの(中略)到達点が異なる場合であっても、共にこの規格の要求事項に適合することがあり得る。
遠慮深い規格である。いやいや、規格に力がありませんといいながら、要求はしっかりするとは盗人猛々しいというべきか?
そう考えてくると、ますますISOMS規格のありがたみが薄れてくる。なもの日永一日読むほどのこともなさそうな気がしてきたぞ。なにかシステム(制度や仕事の仕組み)を作るとき参照するまでもなく、チェックするに使うまでもなさそうな気がしてきた。もとよりどの会社にも新規設備の導入時のルールがあるだろう。そういうしくみを作れと安衛法にある
また新しい手順やコンピューターシステムを更新するときに、どうするかってことくらい決めているはずだ。
とすると設備導入やシステム変更や見直しの際にISOMS規格をチェックリストに使うまでもないような気がしてきた。
ISOMS規格のレゾンデートルはいずこにあるのか?
もちろんISOMS規格に意味がなかったわけではない。
ISO9001に品質保証規格の国際標準を作ったという意味はあるだろう。ただ30年もの間 運用されてきた結果、そのままじゃまずいと業種対応のことを追加したセクター規格とか、セキュリティのような特定分野への特殊化というか進化したものもある。
またISO14001においては、従来からあった法規制は公害防止に限定されていたから、環境管理全般を対象を製品やサービスまたオフィスとか運輸などに拡大する元となったという成果はある。また環境法規制が十分整備されていなかった国において、環境保全のための活動のひとつの基準を示したという意味はある。
だがもう3分の1世紀が過ぎた今、ISOMS規格がなければならないという状況ではないだろう。
セクター規格が必要なら業界が独自にやれば良い。環境法規制が整備されてくれば、難しいことを考えず、法順守をしっかりすれば間に合うだろう。
ビジネスのライフサイクルには衰退期しかないかもしれないが、マネジメントシステム規格には発展的解消という終息もあるのではないか。
![]() 本日の内部事情
本日の内部事情
今回の駄文は短すぎるぞ! それに深みがない!
そう言わないでくださいよ。
金曜日に「武士の絵日記
あらすじを考えて、キーボード叩くには多少時間がいります。更にhtmlにするにも40分、できれば1時間は欲しい。
まあ、そういうことで、
ちなみになぜ「武士の絵日記」という本を読んだのかというと、連鎖が長いのです。
そもそも昨年「日本語の歴史」という文を書いたら、外資社員様から「漢字と日本人」を薦められ、それを読んだら著者 高島俊男がおもしろそうだと同著者の「漢字と日本語」、「お言葉ですが(全部で20冊くらいある。そのうち3冊読んだ)」読みました。
するとその中の1冊で「武士の絵日記」を引用していたのです。私は図書を読んでいて、
 本文が気になると末尾の引用文献をみて読むようにしております。何事も裏を取らないといけません。「Aさんが書いている」とあっても本当にAさんが書いているかどうか、その出典を確認するのが大事です。「Aさんが書いている」と書いてあるのを見て、私がそのまま引用して間違いだったら恥をかくのは私です。
本文が気になると末尾の引用文献をみて読むようにしております。何事も裏を取らないといけません。「Aさんが書いている」とあっても本当にAさんが書いているかどうか、その出典を確認するのが大事です。「Aさんが書いている」と書いてあるのを見て、私がそのまま引用して間違いだったら恥をかくのは私です。
残念ながら「武士の絵日記」には引用文献がありません。となるとその本が引用している出典がトレースできず、当然信用できません。
だから私はこの駄文でもイエスの言葉とか、ISOMS規格の序文とか、読者がどこにあるのかたどれるように末尾に引用元を記しています。
実際に先日「師のたまわく」と論語から引用したようなものがあって、本当だろうかと探しましたが、見つかりませんでした。危うく論語詐欺に引っかかるところでした。
そんなわけでまっとうな論文や書籍になると引用文献が相当量になります。論文なら引用文献リストが何十ページもあるのが普通です。ちょっとした専門書でも引用文献のページが全体の1割くらいになります。全体の3割が引用文献リストって本もあります。一般人対象の新書でも引用文献リストが全ページの1割を超えるものもある。そこまでいくと行きすぎかな?
注1 |
旧約聖書、出エジプト記、第20章、1節〜17節 | |
注2 |
新約聖書、ヨハネによる福音書、第8章、7節 モーゼの律法では不倫(姦淫)した女は石で撃ち殺すと定めてあったらしい。 | |
注3 |
モーゼはB.C.13世紀の人といわれる。 | |
注4 |
MS規格の種類によって記述の詳細は異なるし、さらにはJISに翻訳するとき若干の違いがあるが、共通テキストだから皆同じ項番に同じことが書いてあるはずだ。 | |
注5 |
私はカーネギーの「道は開ける」を高校生の時から読んでいる。まさにhow toの塊であり、書いてあることを実行すると間違いなく天国に…いや成功に至ると信じるに足る。もっとも実行することは大きな努力がいる。 過去行くたびも翻訳がある。最近はコミックにもなっている。 | |
注6 |
労働安全衛生法には体制を作れ(第3章)、安全衛生(第4章)、設備(第5章)などフレームワークが決めてあり、その下位文書として多数の規則がある。 日本においては、ISO14001なんぞ要らないよね。 | |
注7 |
「武士の絵日記」、大岡敏昭、角川ソフィア文庫、2014 実はもう一冊「幕末下級武士の絵日記」というのを借りてきた。続きものかと思ったのだ。実際は大判で出した後に文庫本にしたというだけで中身は同じだった。 「幕末下級武士の絵日記」大岡敏昭、水曜社、2019 |
うそ800の目次にもどる