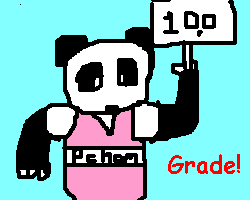
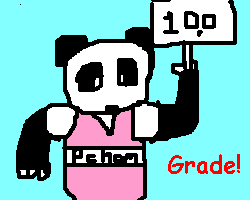
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』、
10月11日までの採点は『プライベート・ライアン(3)』、
10月14日までの採点は『プライベート・ライアン(4)』、
10月25日までの採点は『プライベート・ライアン(5)』
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
ドット(10月29日)
n-tomoo@mtj.biglobe.ne.jp
盛り上がっているようです。プリン(10月28日)
まずおもしろいおもしろくないで言うと「かなりおもしろい」映画だと思う。
星は5個です。
印象としてはこれで終わりなのだけれど、映画についてあれやこれや言うのもまた映画の宿命だと思うので。みなさんの感想を全部読んだ訳ではないのでもう決着の付いている内容かもしれないけど。
この映画の斬新さは、とにかく「人は撃たれたら死ぬ、そしてほったらかし。」の世界があるんだということを体現させてくれたこと。残酷だと感じる前に人がばたばた死んでそれがさしたる悲しみも驚きも感じ得ない世界が戦争なのだということ。(もしかするとキューブリックの「フルメタルジャケット」もそんな映画かもしれないけどだいぶ前に見たので忘れました。)スピルバーグって親米的なストーリーで本心を隠しているような気がする。この映画の最初と最後はただの付け足しに見えてしょうがない。見なくていいですよと合図しているようなものだ。
戦争の正当性やアメリカ軍の強さを知らしめるような意図はさほど見えてこない。お決まりのアメリカ万歳的な印象はなかった。ドイツ軍を悪役と想定している風にも見えなかった。ライアン二等兵を助けるとか何とかそれさえもどうでもよかった気がする。
結局人道的主義者的に描かれたアパムは助けた捕虜を殺した。戦争ってこういうものだよね。捕虜だから助けるだとかそんな生やさしいことはない。他の捕虜は逃がしたけど、そのまま逃げられたかどうか、、。
いわゆる西側諸国のジャーナリストが中国とか中近東の民衆迫害の様子をすっぱ抜いたりするけれど彼らにそんな大きな顔できるのだろうかと常々疑問に思う。スピルバーグも、もしかするとそういう意見の持ち主ではなかろうか。我々は彼らを批判するほど民主的なのかということ。「シンドラーのリスト」にしてもシンドラーがユダヤ人を助けたことよりドイツ兵がユダヤ人をいとも簡単に殺していくのが印象に残った。つまりかつてそうやってばたばた人が殺された「事件」があったことをリアルに表現したかったのではなかろうか?そうなるとアメリカとドイツのどっちが悪い的な趣旨ではなく戦争自体がおかしいという趣旨になる。アメリカの正義さえも疑問の対象なのだ。
オリバーストーンも確かにアメリカに批判的な映画は作るがそれはかつて巨人の堀内が解説者やってたころジャイアンツの選手にやたらと厳しい批評をしていたような「悪口を言っているようで実はただの巨人ファンであり、親心のつもりですよ。」的な印象を感じるのだ。ずっと前、筑紫哲也がオリバーストーンとのインタビューで「あれだけ批判的な映画を作っている人でも結局アメリカナンバーワンなんですね。」と述べていたことを思い出したから。実際映画もそんな風に見える。
アー眠くなってきた。この続きは次回に書くとしましょう。
はじめまして、プリンと申します。ダグラス・タガミ(10月28日)
皆さんの感想を読んで、是非私も一筆書き残したくなりました。
以下、その感想です。この他にも色々と考えたり感じたりしたのですが、その全てを記すのは不可能なので、感じたことをいくつか徒然に書いてみたいと思います。
1 やはり、スピルバーグはあくまでもエンターテイナーなのだな、と思った。とはいっても超一流だから、毎回深く読まれる要素を残すのだろうが。
見終わって最初に感じたのは、疲れたということ。消耗したというのではなくて、疲労したというかんじ。この映画の最大の特長というのは、心理劇ではなくその‘仕掛け’にあるのでは?
ジェットコースターに乗る感覚、とでも言おうか。
映画を観て非日常を味わう。世の中にはこんなこともあるのだなあ、こんなことも起きえるのだなあ、と気付く。しばらくの間はそのことについて考えたり悩んだりするのだけど、日常の瑣末な出来事について処理をしていくうちに、そのことについては忘れてしまう。
2 この映画を戦意昂揚映画とみるか、反戦映画とみるか、それについては様々な見解があるだろうけど、これは少なくとも反戦映画ではないだろうと思う。もしこれが純粋な反戦ものであったとするなら、ミラー大尉はあのようにヒロイックに描かれていただろうか?アパム、彼は反戦のための人であっただろうか?あくまでもリアリティをだすための装置なのでは?(個人的には彼に一番シンパシーを感じたのだが。どこかティム・オブライエンとだぶってみえてしょうがなかった)
かといってこれが戦意昂揚の映画であると言い切れるかというと、答えはノーであろう。ではいったい何なのか。
ここに、スピルバーグのうまさ、あるいはスピルバーグ性があるのではないだろうか?彼はあくまで戦争というものを、描いた。自身の限界は、限界としてそのままに。・・・おおげさか?
まあ、彼は一つの問題提起をしたわけである、と私は読む。
反論・批判などもありますでしょうが、これが私の正直なところの感想です。舌足らずな部分は御容赦下さい。
総合的な評価としては★★★☆、というところでしょうか。
上山さんの感想読みました。パンちゃん(10月27日)
何も言えないと言うのが正直なところです。
経験者がそう感じている。言われてみると言われた通りだと思います。
しかし、それを読んでも戦意高揚とも米軍が偉いとも思いません。
あくまでも、これを観た事で戦争(戦闘)の凄惨さだけが頭に 残っています。実際の戦争は、知らないけれど、その恐ろしさを肌身に 感じる事ができたということが、私としては得たものでした。
でも、聞けて(読めて)良かったです。
ただ、上山さんは、私達が「戦意高揚じゃないか」と気がつくべきだと 思ったのでしょうか。それとも、まさしく「反戦映画だ」と思っているほうが 良かったのでしょうか。若い人間の戦争感をどう思っているのか ちょっと知りたくなりました。
これからも、参加していただきたいですね。是非。
10月27日の上山さんの感想に、はっとしました。(私の書き込みの下にあります。書き込みは、上が最新のものになります。コメントが前後します。上山さんの書き込みを読んでから読んでください。)上山 弘(10月27日)
この映画は「戦争という名のゲーム」という指摘。
スピルバーグは確かに映画をゲームにしている。観客をいかに飽きさせないか。いかにスクリーンに釘付けにする。--そのことが確かにスピルバーグの一番の関心事なのだと思う。
「ゲーム」としての完成度は非常に高い。以前、この欄でも話題になりかけたが、あらゆるシーンが充実している。こんなシーンいらない、というような部分がない。人間性も部分としてならとても深い。
だが、だからといって、この映画が「優れている」とは手放しには言えない。
この映画は「戦争」を描いている。「戦争」を描いている以上、戦争を語るときに、題材になりうるか、ならないか。つまり、そこから戦争について何を語ることができ、語ることができないか、は重要な問題だと思う。
最初の30分の映像に驚き、これを「戦争」と思い込んでしまったけれど、この映像だけが「戦争」ではないだろう。
たとえば、大岡昇平の描いている、人肉を食べようとする右手を左手が抑える(左手を右手が抑える、だったか)という瞬間も「戦争」そのものであり、クロスした手の形のなかに、私は、主人公が見た教会の十字架を重ね合わせ、どきりとしてしまうが、そこから語り合えるような問題を提起するものが「戦争」というものかもしれない。
戦うことと人間の心理、非日常の人間の行動のなかにふいにあらわれる日常の思い(日常の奥に潜んでいる深いこころの動き)を、スピルバーグは描こうとしているとは思えない。
ここに描かれているのが「ゲーム」だとしたら、それは、この映画を「アメリカ礼賛映画」とか「戦意昂揚映画」と呼ぶことよりも、もっともっと厳しい視点だと思う。
「アメリカ礼賛」や「戦意昂揚」という批判は、映画そのものへ向けられているのに対し、「ゲーム映画」という批判は、この映画を「楽しんだ」すべての観客に向けられた批判だからである。
私は確かに楽しんだ。最初の30分に興奮した。水中を銃弾が動いていく--その動きが泡によって描かれ、兵士に銃弾が当たる瞬間がわかり、その瞬間血が噴き出すシーンなど、あ、すごいと感動さえしてしまった。
最初の30分の、その惨劇の映像に、私は酔っていた。
「悲惨」ということばはその瞬間、思い浮かばなかった。見おわったあと浮かんで来た。私には、確かに最初の30分は「ゲーム」だったし、それにつづくライアン救出も「ゲーム」だったのだと思う。
映画が「ゲーム」であるかぎり、前半の30分と後半のライアン救出劇が結びつかなくてもいいだろう。結び付ける物がなくていいだろう。スピルバーグは、そう考えているのかもしれない。
ただ、私自身は、やはり「ゲーム」とは思い切れない。だから、前半と後半の断絶が気掛かりなのだが、気掛かりだからと言って、私がこの映画を「ゲーム」のように見なかったということにはならない。
私は確かに「ゲーム」感覚で見てしまった。
そうした自分をつかまえることができなくて、ああでもない、こうでもない、と書き続けているのかもしれない。
西日本新聞10月27日朝刊に発表した『不気味な映画』というエッセイを批評欄に掲載しました。
あわせてお読みください。私が今まで書いて来たことをまとめたような文章です。
私の感じた不気味さは、上山さんに指摘されて「ゲーム感覚」の不気味さなのだと、ようやく気づきました。
今となっては書き直したい部分がいろいろありますが、(見た直後に書いたのだが、掲載が27日になった)、そのまま直さず転記しています。
反戦映画ではない・・・の私見に疑問を持たれた方々へ。ikuko(★★★)(10月26日)
もう一度、見てきました。いや、見直してきました。いやはや、私の早とちりだったようですね。
反戦だとか好戦だとか、そんな深刻な問題を提起しているのではない。単純に戦争という名のゲームをやってみせていた、あのスたーウォーズとおなじように。そう考えたくなりました。
あるはずがない、非現実的なあるいは劇画的な、または幻想映画ただし、ある種の願望を込めての・・・と思えてきました。かくて、私見は、撤回するのが正当な処置のようです。お騒がせしました。でも、年寄りの冷や水だ、なんて言わないでください。倅や孫らの冷笑を浴びるのは慣れてはいますが。
面白かったぁ、しかし、なんか考えさせられた・・・それでいいのでしょう。平坦な日常への警鐘と受け取ればと思っています。
パンちゃん、かもめサン、ダグラスさん、ますますのご熱弁を期待します。
大阪のおじいちゃんより ・・・・・・・・・・nagaodor
ああ、遅くなったけど、見れてよかった、プライベート・ライアン。上山弘(10月26日)
映画の感想を語るのは苦手なのと、映画の見方がシロートなので、 かなり的外れな感想かも知れませんが……。
せっかく見たので、少しだけ参加させてくださいね(^-^)。
いやに足が長くて、ガイジン体型のじいちゃんが墓地で回想をはじめるや否や、 いきなり戦場に連れ込まれてしまった私。
みるみるビーチは血に染まり、場面は有無を言わせぬスピードで、 命の終わりを見せつけます。うう、痛い。
すさまじい光景だけれど、とても美しい絵になっていましたねぇ。
私は戦争体験がないので、この画面がリアルかどうかなんて論じるわけにはいきません が、戦争で死ぬということがどういうことか、少しは見えた気がしました。
ストーリー的には、あらかじめ読んでいたみなさんの突っ込みが、 やっと納得できました(笑)。個人的には決して好きな作品ではありません。で も、この表現力はさすがスピルバーグと思います。なんといっても、映画に戦場 に連れてかれたのは初めてだし。
キャストの誰にも感情移入ができなかったというのに、最後まで見れたのは、 私自身が9人目の兵士にされてしまったからかも知れませんね。
問題のサンドイッチのシーンは、映画の意図はともかく、 私はかなり現実的だなあと思いました。
どんな場所でも、日常がある。
戦場にいても、ウンコ(ごめんあそばせ)だって出るでしょうし。
九死に一生を得たあとで、ヘルメット干したりしてるんじゃないかなぁ。
そうそう、私は5人の息子を全て亡くしてしまったおばあちゃんを、 間接的に知っているのと、私自身が2児の母だということもあってか、 トムハンクスが死んだシーンよりもなによりも、 ライアンのおかーちゃんのことを思うと、心底泣けます。
まちがっているでしょうか(^^;)。
戦争に対する捉え方も、価値感も、人種によって教育によって、 色んな意見がありますね。きれいごとかも知れませんけど、個人的には、 戦争をしなくても世界がまとまる、そんな未来であれと思います。
ひとつひとつに才能や個性のある、せっかく生まれた命の使い道が 戦争のコマだなんて、それはないだろうとやっぱり言いたい。
この映画のおかげで、柄にもなく色々考えさせてもらいました。
映像美と表現に2点、問題提起に1点、
気になってたビーチの障害物が見れた喜びに1点、
スナイパー君にミーハーの1点、ストーリーの手抜きにマイナス2点で
合計★3つ。という感じかなぁ……。
不用意に洩らした「戦意昂揚」の発言について、二三の方から質問を頂き、慌て て「プライベート・ライアン」に関する皆さんのご意見を、じつくり読ませてい ただきました。どれもこれも、もっとも、と感心し感動すら覚えています。この ようなページを作って世論形成の一翼を担っておられる「パンちゃん」さんに は、さらなる敬意を捧げるものです。kazu yoshihara(10月26日)
さて、なんとお答えしたものでしょうか。スピルバーグという方が反戦イデオロ ギーの持ち主であることは、私も承知しています。しかし、この映画に関して は、どうでしょうねぇ。時と所と人を忘れて宇宙学的にみれば、戦争なんてつま らない軍隊なんて要らない、政治の究極としての武力行使なんて、無意味だよ ・・・と訴えているとも読めますが、「たった一人の、それも無名の、それも二 等兵という最下級の兵士を、兵役を解いて、本国に帰還させるために、八人もの 練達の兵士を派遣する」という理由が、私にはまったく分からないのですよ。多 額の税金をかけて育成した八人の戦闘力(ノルマンディ上陸作戦の凄まじい犠牲 者の分を含めて)を、たかが一人の兵士の救出のために参謀総長までがかかわ る・・・なんてとは作り話としか思えないのです。やはり、これは軍のPRとしか 思えないのです。悪く言えばスピルバーグともあろう人が、米国陸軍の提灯をも ったとしか。もちろん戦前の日本軍では、絶対に、百パーセント考えられないこ とです。それをやるのが、やってきたのがアメリカという国だといわんばかりに 私には思えたのです。いまならともかく、五十年も前なら世界中の軍隊が、日本 と同じように、どんな事情があろうとも犠牲や損失は最小限にと考えたと思いま す。
この映画の前半には感心しても後半はどうもねぇ・・・・とおっしゃっている 方々が何人かいらっしゃいますね。私も、そうなんです。つまり前半の凄まじい 戦闘は、そんなに価値ある戦闘に参加し生き抜いてきた人々という値打ち付けの ための設定だと私は見ます。なにもかもが、ライアン二等兵を救うためには、こ んに莫大な投資をした、するのが米国です、それは世界の平和と自由を守るアメ リカの責務なんです・・・・という魂胆がミエ三ミエなんですが。
私の見方はひがみでしょうか。もし、そうお考えでしたら、たかが、私一人の異 論なんて無視なさって、どんどん次のテーマに進んでください。年寄りの出る幕 ではありませんから。ちなみに、私は潜水艦搭乗員としての訓練を受けている最 中に終戦を迎えましたので、戦闘経験はありませんし、戦争についての知識も中 途半端です。また、映画なんて年に数回ていどのシニアです。皆さんの貴重なペ ージに闖入した無礼を改めてお詫びします。言葉づかいや文字使いについて、い ろいろとお心づかい頂きましたが、私としては、むしろ恐縮に思っております。
どうか遠慮なく対等で、お付き合いのほど。
ぼくは世界中の人が楽しんでくれる映画をかってたくさん つくった。でもオスカーの話はてんでこなかった。東洋の 寅さんも同じらしい。そうか、反戦映画を作ればいいのだ。
そこで「シンドラーのリスト」を作った。
それまでの「ジョーズ」」や「ET」「未知との遭遇」 などがおもしろかったのに・・・。オスカーはぼくの思惑 通り「シンドラー」でたくさんもらった。これだと思った。
その後「ジェラシック・パーク」「ロスト・ワールド」など 楽しい映画を作ったが再びオスカーが欲しくなった。そこで 「アミスタッド」を作った。でもこれ米国の恥部でもある問題を とりあげていたので大受けしなかった。
そこで考えた。アメリカのプライドをくすぐり、かつ反戦 映画を作ったる。民主主義の原点たる個人を大切に するには1兵卒救出だ。そして世界の警察としての 戦意昂揚、どちらもアメリカの大儀だ。これなら戦争 体験のない奴ばかりが増加している世界へ発信 しても観てる奴は「スピルバーグなら反戦映画なの だ」と信じるに違いない。誰も文句を言う奴はいない。
70歳以上の奴が観たら「これちょっとおかしいぜ。 戦意昂揚の映画だ」と感じると思う。放っとけ。そんな 声は少ない。過激な殺戮シーンを30分も流せば誰 だって反戦映画を思うぜ。観客の大多数が15,6歳 から5,60歳の世代で本当に戦争体験した奴はいな いはずだ。誰も文句をいう奴はいない、多分「反戦映 画」と頭から信じている奴ばかりだ。それはそれでこの 映画を作った意義があると思う。ありがたい反応だ。
「戦意昂揚」より「反戦」と言って論評する方が勝つに決 まっている。戦意昂揚論を言った奴には「どのシーンが 戦意昂揚なの?言ってよ」なんて多分ぼくを弁護するだ ろう。ぼくの思うツボだ。
自分で言うのもなんだが、98年のオスカーは間違い ないね。負負負負負。
ある監督のモロローグ