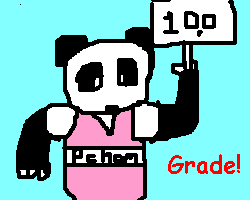
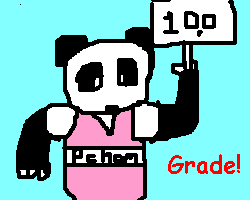
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』、
10月11日までの採点は『プライベート・ライアン(3)』、
10月14日までの採点は『プライベート・ライアン(4)』、
10月25日までの採点は『プライベート・ライアン(5)』
10月28日までの採点は『プライベート・ライアン(6)』
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
ふむふむ(10月30日)
huka1092@yominet.or.jp
思うのですが、映画ってそんなに難しく見なくちゃいけないものでしょうか。アレックスのパパ(10月30日)
「プライベート・ライアン」でかなりの論戦が行われているけども、わたしとしては、映画を楽しむ心に欠ける気がするのです。
昔、「史上最大の作戦」という映画を見たときに、一番印象深かったのは、今にして思えば、ノルマンディーの水平線に、それこそずらりと並んだ連合軍の軍艦でした。
そして、多分、驚くドイツ軍の兵士にあめあられと砲弾を浴びせ吹き飛ばしたでしょう。でもこの映画をわたしは嫌いではありません。
「好戦的だから嫌いだ」と思えば席を立てばいいのだし、-淦鐡Ľ世ǂ虧昇遏とは限りません。むしろ、わたしに言わせれば愚作が多いのです。
で、結論ですが「プライベート・ライアン」は確かに前半と後半の温度差が気になったけど、前半は「ほれ見ろ、人間の肉体なんて簡単にぶっちぎれるんだ」という眼(それにしても米軍ってモルヒネをいっぱい持って、いっぱい使うんだな)と手術後の痛みに耐え兼ねたわたしとしては強く思いましたね。
後半はすごかったですねえ。何がって、タイガー戦車ですよ。メッサーシュミットの急降下といい 、ドイツ軍の装備は(言わせてもらいますけど)かっこいい。モチロンあのスナイパーもゴルゴみたいで良かった。特にあの最後の「伏せろ」っていうところね。嫌いだったのは、ドイツ軍の降伏した兵を放すところだったな。もう感情移入してたからかな。
じゃあね。あ、自己紹介しておくと、わたしは「タイタニック」より「スピード」が好きでした。
パンちゃんから、お願い。
「文字化け」しました。時間があったら、その部分をお知らせください。
久しぶりに書き込ませていただきます。パンちゃん(10月30日)
折角の議論の深まりが、却って立場と立場の溝を浮き彫りにしてゆく。それは勿体ないことです。言葉を通した影響力の交換がもう少しあっても良いのではないでしょうか。
洞察の努力と、ねばり強い寛容をもって。
◆麗奈さん:
「日本人恐怖症」ですか。辛いですね。ニュージャージーの日本語補習学校で、長期滞在者や日系人の子弟に日本語と日本文化を教えている小生には、自分や生徒が、この「恐怖症」に罹らない為に、どう考え方を整理してゆくかは死活問題だからです。
こんな風に考えています。
日本では、言葉を通じて「価値value」というものを語ったり、確かめたりすることが完全に息詰まっているようなのです。
ですから、偽善の仮面を剥がす瞬間は大好きなくせに、プレーンな正義の前では恥ずかしがって硬直してしまうのではないでしょうか。
◆麗奈さん、パンちゃん、そしてみなさん:
その原因は色々あるようです。
(1)長い冷戦時代に、反米と一国平和、結果の平等だけが正しいという「革新」と、男尊女卑と不明朗な談合政治の汚辱にまみれたニセの「自由」主義。つまり「二種類の嘘」しか選択肢のない時代が続きました。その後遺症はまだ残っていて、ものごとを筋道立てて語ることが出来なくなっているようです。
(2)キリスト教を「性欲の抑圧」の象徴として馬鹿にする一方、アジアの宗教を現代に再活用する気風も、「オウム」への恐怖から停止してしまいました。
イスラムへの同情も、反米のテコにしようという、不純なバランス感覚に過ぎません。
宗教がここまで「死んだ」世界も珍しいのですが、「大前提」がないのですから、細かなことにも善悪と利害が混ざったままで平気なのです。
(3)「出る杭は打たれる」との恐怖心が、子供の頃から植え付けられています。
その結果、新しい世代が「新しい正しさ」を作って行く力が結集して行きません。
(4)日本語が弱くなりました。心に沁みるように相手を誉めたり、議論を合理的に整理したりする言葉が衰えています。照れくささに言葉の出し惜しみをしたり、恐がって結論をぼかす言葉ばかりが目立ちます。
◆Kazuさん:
ご本人は、無意識で言っておられるのかも知れませんが、Kazuさんがあんな風にスピルバーグに対して「不器用な」揶揄を言ってみたくなるのはこんな理由でしょう。
「価値value」を禁じられている日本人には、スピルバーグの真っ正面からの取り組みが眩しい、そういうことではないでしょうか。
それに、スピルバーグに象徴される、アメリカのショー・ビジネスの論理も日本人にはなじめないのかもしれません。日本では「メッセージを持つ者」は、商業的成功を禁じられて、ひたすら「メッセージの純度」を要求されて行きます。逆に「商業的成功を宿命づけられた者」は、軍国主義や「ヘア・ヌード」を使ってでも当座の金を稼がされるだけなのです。
一生をかけて自分のキャリアと資金力を築き、「メッセージ」を「ストーリー」や「キャラクター造形」を通じて大衆に届けてゆく。そうした手法が、見慣れないのでしょう。それが恵まれているとの眩しさを、強くお感じになられ過ぎているのではないでしょうか?
◆パンちゃん:
貴兄の告白されている、スピルバーグの演出への違和感。つまり「メッセージ」の純度と表出の技術の分裂。その結果として、観る側の「考えさせられる快感」と「酔わされる不快感」が分裂してしまう。これも同じことです。
「メッセージ」はそのまま受けとめ、語り口について過剰と感じられる部分は、一人でも多くの人にそれを伝えようとする心意気として応援する。それでは駄目でしょうか?
◆ドットさん:
ドットさんの反米的なコメントには、理念としての<アメリカ>と、その理念からほど遠い現実のアメリカを分けられない。つまり、現実のアメリカに支持できないところがあると、理念としての<アメリカ>も全否定したくなる日本の知識人の悪影響があるようです。筑紫哲也さんなど、ワシントン生活が長く、そうした切り分けをするお手本を示せる立場にある方でもそうなのですから。
けれども、ご本人は不愉快かもしれませんが、一つの「価値value」を育てたり検証するのではなく、「価値value」という押しつけがましいものは、総て壊してしまおう。壊すこと、相対化することが、「無垢なる絶対善」であって、ある種の「価値value」を認め、関与することは、自分の手を汚すことだ。そういうお考えもあるのではありますまいか。であれば、こちらの方が深刻でしょう。
非難をしているのではありません。それでは、この複雑な世の中で、自分の一貫性を保ちながら後悔のない人生を送る上で、不便この上ないのではないでしょうか?
◆灘かもめさん:
折角の素晴らしい文章なのですから、「知恵熱」とか「私的メールみたいで恥ずかしい」とか、どうぞ仰らないでください。
素敵な日本語が水で薄められてしまったようです。正しいことを言うのに、どうして言い訳が要るのでしょう。
それにしても、
>早く、二回目鑑賞後の自分に会いたいです。
素敵な言葉ですね。自分というものを、動き、そして深まってゆく「生きた」ものとして語っておられますね。感動しました。
◆再び麗奈さん:
今の日本は、苦しいところに来ていると思います。
けれども、「恐怖症」は悲しすぎます。
だからと言って、外圧もどきの「お説教」もしたくありません。
何故なら、日本社会の現状は、笑いごとではないのです。優越とか劣等とかでは片づかないものを含んでいるからです。
宗教や道徳が衰退し、その一方で当座の資金だけはある社会。そこでは価値観が崩れ、自尊心の怪物の横暴と、それに対する遠慮だけが徘徊する。
例外や異端を許容する力量を失った結果、折角の優秀な知性が内へ内へと閉じて行く。
それは、二十一世紀の世界が背負う苦悩の先取りのような気がしてなりません。
その苦しみ自体も、その苦しみを抜け出す努力も、尊敬できこそすれ、恐れたり忌み嫌ったりすべきものではないと思いますがどうでしょうか?
◆映画について:
観てから少し時間が経ちました。
時間と共に印象の深まってゆくシーンもありますね。
(1)ライアンに会って、ミラーが兄たちの戦死を告げた直後、"Which one?" "All of them."の辛いやりとりがありますが、ライアン本人には静かな表情をさせ、激しい落胆の表情は同僚達にさせています。これで、悲劇的な効果を増幅させながら、ライアンと同僚の間の精神的な絆を暗示させ、ライアンの戦線離脱拒否へとプロットが繋がります。
(2)ミラーへの致命傷となる銃撃は、遠くからの映像として提示されます。それが、ミラーが「英雄」であることを避け、普通の市民が殺戮の現場へ駆り出された悲劇を語っているように思われます。
(3)現在のノルマンディー墓参のシーンは、それ自体の映像としての説得力は抑えられています。けれども、"Earn this."という言葉の重みを噛みしめる時、こんな形でも、thisが示されているのは、時間の重みを含め、物語全体の構造がわかりやすくなって良かったと思います。
(4)音楽は、やや俗っぽいのですが、最近流行のアコースティックなものや、民族音楽の旋律を持ってきた凝った音楽より、プレーンで好感が持てます。最後のクレジットと共に流れるテーマ曲は、"Hymn to the Fallen(斃れし者達への賛歌)"というタイトルがつけられているそうです。ちなみに、戦闘シーンには音楽をかぶせない演出も効果的でした。
(5)前後しますが、戦線離脱を拒むライアンに、彼を見いだすまでに二人が戦死したことが告げられます。そこで、その戦死者二人の名前をライアンは尋ねます。一人一人の名前の尊重、「一人の生命」の価値には分け隔てのないこと。そんな思想が流れていると、思いました。
◆星について
やはり満点ですね。映画という媒体でなくては出来ないことを、誰もしなかった形で成し遂げています。
アレックスのパパさん、分析ありがとう。ドット(10月29日)
たしかに私には「メッセージ」を「メッセージ」として受け止める感受性と寛容さが欠けていますねえ。
反省しました。
麗奈さんが教えてくれた「体験の継承」、アレックスのパパさんがここで指摘している「戦死者への追悼」----それは確かにスピルバーグの「メッセージ」だと思います。
私は、そうした「メッセージ」を素直に受け取り、引き継ぐことができないことを恥ずかしく思う。
けれども一方で、やはり考えてしまう。
麗奈さんとアレックスのパパさんが教えてくれた「メッセージ」は二人が語ってくれることで初めて理解できたものです。
二人の指摘がなければ、私は、自分では気づくことがなかったと思う。
この映画で私が最初に感じたのは、「メッセージ」のまっとうさ、ということではなく、「メッセージ」が伝わってこないことへの苛立ちのようなものです。
「メッセージ」を圧倒して一人歩きをする「映像の力」(映画の力)そのものへの恐怖心です。
この「映像の力」(映画の力)に対する評価は、わかれると思います。
『ライアン』をめぐって、最初のころ、石橋尚平さんと対話(最後は、対話というより、私のせいでけんかになってしまったのは残念ですが)したのは、この問題です。
石橋さんは、「映画の力」が充実しているから、これは大変優れた映画である。「メッセージ」というような二次的なもので映画をくくるのは映画を抑圧することである、という主張でした。「映画」を「映画に関する話題」にすり替えようとしている、という批判でした。
私は「映画の力」は認めるけれど、「メッセージ」がうまく伝わって来ないのが不満だ、と書いたつもりなのですが、私のことばは、石橋さんには「メッセージ」をスピルバーグにかわって伝えようとしているものと受け取られたようです。「反戦」をスピルバーグにかわって伝えようとしているものと受け取られたようです。そうしたことをするのは「見苦しい」と何度も批判を受けました。
(アレックスのパパさんと、石橋さんとでは、私のことばの受け取り方が全く逆ですね。思いを伝えるのは、本当に難しい。)
で、最初にかえって、私の感想を書くと、
私にはやはりスピルバーグの映像力は不気味です。
それは、上山弘さんが「ゲーム」ということばで批評していた要素を抜きにしては、私には理解できない。
スピルバーグは、映像を、あるいは映画を映像と音によって完璧に仕上げようとする欲望がとても強い。映画の力を完璧にするために、「ストーリー」を作り上げてしまう。
それが私には、やはり、怖い。
ほっとする温かさが、私は欲しいのです。
その温かさは、「ストーリー」のなかで変化していく人間の輝き、たとえば『スウィート・ヒアアフター』の少女の嘘とか、『フルメタル・ジャケット』の「殺せ」というベトナム兵士のことばに躊躇する主人公の表情とか、あるいは『愛を乞うひと』の最後の最後に一瞬に見せる原田美枝子の笑顔とかなのです。
それがあれば、私は『ライアン』を本当に抱きしめるように愛することができると思う。
それを私は感じることができないのです。とても残念なことに。
「体験の継承」も「戦死者への追悼」も麗奈さんやアレックスのパパさんのことばとしては理解できるけれど、スピルバーグのことばとなっては響いて来ない。
もちろん、これは、私が「平和ボケ」していることとも関係があるのかもしれない。
そう思うからこそ、上山さんの指摘がとても耳に痛い。
映画を「ゲーム」にしたのは、スピルバーグではなく、見ている私自身ではないのか。この映画の前半の30分に「すごい、すごい」と声をあげている観客ではないのか。
戦闘シーンに「すごい、すごい」と声をあげながら、私たちはこの映画を「ゲーム」のように見てはいないか……。
堂々巡りになるのだけれど、
この「ゲーム」感覚を断ち切るには、やはり強烈な人間の命の一瞬が描かれなければいけない、と私は思う。
前半と後半をつらぬく人間の命の実相が描かれなくてはならない、というのが私の不満だ。
それを感じられたら「体験の継承」も「戦死者への哀悼」も含めて、私人自身のことばで、スピルバーグの「メッセージ」を代弁できると思う。
アレックスのパパさんは「メッセージは堂々と代弁すればいい」と言っているのだと思う。
石橋さんは「メッセージなど代弁するな、メッセージで映画を汚すな」と言っているのだと思う。
私は、「メッセージが理解できない、代弁できない」と、言い続けているのです。
なぜできないか。そこに登場する8人とライアンが、『スウィート・ヒアアフター』の少女、『夫メタル・ジャケット』のマーシュ・ディモン、『愛を乞うひと』の原田美枝子のように親身に感じられないからなのです。
少し別の角度から書きます。
スピルバーグの映画では、私は『未知との遭遇』が非常に好きだ。
そこにとても不思議なシーンが出てくる。リチャード・ドレイファスが子供の母と一緒に山の影から宇宙船を見ている。
ドレイファスが「もっと近くへ行こう、宇宙船の所へ行こう」と母に声をかける。母親は子供が心配だし、宇宙船にも驚いている。しかし、行かない。
彼女は自分がここにいる理由を、「子供が心配だから」と知っている。宇宙船からメッセージを受け取った子供やドレイファスとは違うことを知っている。母親は自分が「場違い」の存在であることを知っている。
その母親の気持ちに、今の私は似ている。
麗奈さんの書いていることもアレックスのパパさんが書いていることも理解できる。それは、『未知との遭遇』の母が、子供の情熱、ドレイファスの情熱を理解し、また宇宙船のメッセージを理解しているのと似ている。けれども、それは自分の「本心」ではない。
それは同様に石橋さんの見方に対する私の態度にも似ている。石橋さんの言っていることは全部理解できる。理解できるけれど、私の「本心」ではない。だから、母親がドレイファスの情熱を理解しながらも彼に与しなかったように、私も石橋さんには与できない。「理解しているのに与しないのは見苦しい」と私は批判され続けたけれど、やはり、できない。
どんなに「理解」できても、与できない、ということはあるのです。
上山さんの意見に対しては、これとは全く逆。
本当は否定したい、否定したいけれど、できない。スピルバーグの映画は「ゲーム」だ、ということを受け入れたくはない。しかし、私は確かに「ゲーム」のようにしてそれを見ていた。「ゲーム」を見るように、その映像の力に酔っていた。
そのことを反省しなければ、何も語れない。
麗奈さんに「体験の継承」という視点を教えてもらいながらも、それでも私の心のどこかに「ゲーム」の感覚が残っていた。
これはスピルバーグの問題というより、本当は私自身の問題だ。だからこそ、上山さんの指摘が胸にこたえる。ぐさりとくる。
「人間観」がどうしたこうした、と言いながらも、私は「ゲーム」のように、映画を見て、その力に酔っていた。
これは本当に反省しなければならないことだ。
おなじことばかり書かずに「結論」を書いたら? と言われそうだが、「結論」は、書けない。
ああでもない、こうでもあい、とあれこれ考えるのが私の、たぶん「結論」なのだと思う。だから、何度でも書く。
ビジターの意見を聞くたびに、何か書かずにいられなくなる。
盛り上がっているようです。れいな(10月29日)
まずおもしろいおもしろくないで言うと「かなりおもしろい」映画だと思う。
星は5個です。
印象としてはこれで終わりなのだけれど、映画についてあれやこれや言うのもまた映画の宿命だと思うので。みなさんの感想を全部読んだ訳ではないのでもう決着の付いている内容かもしれないけど。
この映画の斬新さは、とにかく「人は撃たれたら死ぬ、そしてほったらかし。」の世界があるんだということを体現させてくれたこと。残酷だと感じる前に人がばたばた死んでそれがさしたる悲しみも驚きも感じ得ない世界が戦争なのだということ。(もしかするとキューブリックの「フルメタルジャケット」もそんな映画かもしれないけどだいぶ前に見たので忘れました。)スピルバーグって親米的なストーリーで本心を隠しているような気がする。この映画の最初と最後はただの付け足しに見えてしょうがない。見なくていいですよと合図しているようなものだ。
戦争の正当性やアメリカ軍の強さを知らしめるような意図はさほど見えてこない。お決まりのアメリカ万歳的な印象はなかった。ドイツ軍を悪役と想定している風にも見えなかった。ライアン二等兵を助けるとか何とかそれさえもどうでもよかった気がする。
結局人道的主義者的に描かれたアパムは助けた捕虜を殺した。戦争ってこういうものだよね。捕虜だから助けるだとかそんな生やさしいことはない。他の捕虜は逃がしたけど、そのまま逃げられたかどうか、、。
いわゆる西側諸国のジャーナリストが中国とか中近東の民衆迫害の様子をすっぱ抜いたりするけれど彼らにそんな大きな顔できるのだろうかと常々疑問に思う。スピルバーグも、もしかするとそういう意見の持ち主ではなかろうか。我々は彼らを批判するほど民主的なのかということ。「シンドラーのリスト」にしてもシンドラーがユダヤ人を助けたことよりドイツ兵がユダヤ人をいとも簡単に殺していくのが印象に残った。つまりかつてそうやってばたばた人が殺された「事件」があったことをリアルに表現したかったのではなかろうか?そうなるとアメリカとドイツのどっちが悪い的な趣旨ではなく戦争自体がおかしいという趣旨になる。アメリカの正義さえも疑問の対象なのだ。
オリバーストーンも確かにアメリカに批判的な映画は作るがそれはかつて巨人の堀内が解説者やってたころジャイアンツの選手にやたらと厳しい批評をしていたような「悪口を言っているようで実はただの巨人ファンであり、親心のつもりですよ。」的な印象を感じるのだ。ずっと前、筑紫哲也がオリバーストーンとのインタビューで「あれだけ批判的な映画を作っている人でも結局アメリカナンバーワンなんですね。」と述べていたことを思い出したから。実際映画もそんな風に見える。
アー眠くなってきた。この続きは次回に書くとしましょう。
やはりアメリカで育った人とそうでない人では見方が違うようですね。私の知ってる限り、この映画を見て、あ〜アメリカは偉いなんて思った人は一人もいません。アメリカはここまでしてライアンを救った、偉い!なんて思うより、救わなくてはならない事態を避けよう!と思うほうが多いようです。私もアパムの様な少年を戦争に行かせるような世界は作りたくないと思いました。私の主人は先祖代々米国陸軍将校で、先祖は独立戦争に参加するまで遡るくらいの職業軍人家庭ですが、この映画を見たあと、自分の息子は絶対に軍人にはしないと誓ってました。トム・ハンクスの死を見て英雄の様に思うより、あんなちゃんとした人間を死なせてしまう戦争はやめよう、そう思いました。私はこの映画をゲームのようだと思いませんし、戦意昂揚映画だとも思いません。私自身、軍人家庭で育ち自分も軍に入ろうと志願していたのですが、この映画を見て、「ほら、やっぱりアメリカ軍は偉い!」なんて思いませんでした。反対に大将達は戦地に赴くことも滅多にせず召集された兵士達の命を粗末に扱う、軍の顔をたてるためライアン救出に8人もの命を犠牲にできる軍に疑問を感じました。パンちゃん(10月29日)
kazuさんの投稿は今まであることに気付かず、読んでませんでしたが、冗談にしろスピルバーグがオスカー狙いでシンドラーを撮ったなんて失礼すぎると思います。自らがユダヤ人である彼がどんな思いでこの映画を撮影したことでしょう。日本の方でもユダヤ人虐殺について本当に詳しく知ってる方も多いと思いますが、ユダヤ人の多いロスアンゼルスでは学校に収容所の生き残りの人を呼んで話を聞くことがよくあります。中には今だに憎しみを持って生きている人もいれば、ドイツ人が悪かったのではない、ヒットラーが悪かったといってドイツ人と仲よく、明るくやってるおばちゃんもいます。私の友達もアウシュビッツで両親を目の前で火あぶりにされた人もいます。そういう人達と交流があれば、シンドラーのような映画をオスカー狙いなどと呼ぶ事はできないと思います。ジョークでもこんなことを書いて問題にならないなんて信じられません。また、日本人恐怖症になりそうです。
上山さんの「ゲーム」ということばには、私は本当に驚かされた。灘かもめ(10月29日)
この映画は確かに「ゲーム」そのものではないし、麗奈さんが以前書いていたように、「体験の継承」という意味もあると思うけれど、あまりに見事にできているので、どこかで感覚が追いついて行かない部分がある。「普通の善良な人が犠牲になる」という戦争の実相を描いているし、その悲惨さは確かに伝わって来るのだけれど、あまりにスムーズに伝わって来るので、感覚が素直に受け入れてくれない。
「現実」というのはもっと退屈というか、つっかえつっかえでなかなか進まないものだと思うけれど、スピルバーグにかかると、なぜかすーっと進んでしまう。
『アミスタッド』の感想に書いたけれど、映画が「ストーリー」になりすぎている。 『アミスタッド』のような「友情」「自由」「人権」というものが前面に出た映画では、「ストーリー」がストレートに表現された映画は単純に感動できるが、今度の『ライアン』のように、多くの犠牲者のシーンが登場する「戦争」映画では、そのストレートさがとても気になる。
スピルバーグはプロなのだから、スムーズな映画を撮るのはあたりまえなのだが、なぜか、この監督は、「映画は何よりスムーズな展開でなければならない」とどこかで感じてはいないだろうか、ということが疑問として浮かび上がる。
「人間」を描くためには、どこかで、そのスムーズな展開、なめらかなストーリーの展開を犠牲にする必要が出てくる瞬間があると思うのだけれど、そうした瞬間を感じることができない。
たぶんスピルバーグは、ストーリーを分断する人間性の噴出の一瞬を、石橋さんが指摘したような描写(トム・ハンクスが友人とイタリア戦線で出会った小人の兵士の話をする描写など)で表現したのだと思うけれど、そうした分断さえも、なぜかストーリーをよりスムーズに見せるための描写のように感じてしまう。
ストーリーの分断によってストーリーが見えなくなるのではなく、もっとよく見えるようになってしまう。
そこが、スピルバーグの映画の一番の不思議さ。ある意味での不気味さ。
スピルバーグは何よりも、映画の完成度を目指しているように感じてしまう。
「現実」は「完成度」では測れない。けれども「ゲーム」なら、この作品は「完成度」が高いとか低いとかいう評価ができる。
上山さんの指摘していることは、そんなことかもしれない。
私はそんなふうに感じ、上山さんの「ゲーム」という指摘に、目が覚めた。目が覚める感じがした。
スピルバーグは「体験の継承」をしようとしているのは確かだろうが、その「継承」を、ストーリーにしすぎている。ストーリーを突き破ってうごめく人間の命の不思議さにまで到達していない……。
私の不満はたぶん欲張りな不満なのだと思う。それは、スピルバーグの映画が、思わず欲張りな感想を引き出してしまうほど、ずぬけた何かを持っているということでもあるのだが。
何かとてつもないパワーと優れた感覚がそこにある、と感じながらも、最後の瞬間、この映画を抱きしめたい、という気持ちになれない。(『アミスタッド』でも、そう感じた。--『激突』や『ジョーズ』『未知との遭遇』では、抱きしめたい、という感じになった。『E.T.』以後、何かが不満として残るようになった。)
*
違った視点から言うと……。(違ってもいない感じもするが。)
『スウィート・ヒアアフター』で少女が最後に嘘をつく瞬間、その映画では、それまで動いて来た時間、全員が救済されるというストーリーが破綻してしまう。何もかもが水の泡になってしまう。それなのになぜかとても救われた気持ちになる。少女を抱きしめたくなる。嘘をついた少女を抱きしめ、彼女の体のなかを流れている血潮の温かさをじっと感じていたい気持ちになる。
ところが、『ライアン』では、多くの犠牲のうえに、ライアンが救出され、ライアンはそのことを意味を確かめるように自問する--そこには完全な救済があるはずなのに、なぜかほっとしない。ライアンを抱きしめ、「一緒に生きよう」と伝えたい気持ちにならない。
何か本当に救われた気持ちにならない。
スピルバーグは、ストーリーのどこかで、人間のこころの動きの本当の部分を見落として来ている。見落としているという自覚があるから、たぶん、最後に「心情」というものをライアンの涙で表現したのだと思う。
人間の心情を振り落として突き進んでしまうものが「ゲーム」のストーリーだと思う。
「心情」を一つ一つ積み上げて行くと、どうしても、何かがずれ始める。『スウィート』の最後の嘘のようにとんでもないものにぶちあたってしまう。
そうした人間性というものをスピルバーグは描いていない。
*
目的が違う。スピルバーグの描こうとしているものと違ったことを、私が批判している、ということはわかる。
しかし、批判せずにはいられない。
批判しないことには自分が落ちつかない。
たぶん、酔っているのだと思う。スピルバーグの作り上げた映像と音に酔っていて、「体験の継承」という、現実に根ざした気持ちになかなかなれないのだと思う。
「反戦映画である」「戦意昂揚映画である」「体験を伝える映画である」--それがどういう評価であれ(というのは、少しいい加減すぎるかもしれないが)、そうした「評価」ができるのは、この映画と自分の現実をつないで考えることができる人だと思う。
ところが私には、その接点が見つからない。
『未知との遭遇』さえ現実に思えるのに、なぜか『ライアン』は現実には思えない。
どこか現実を遊離した世界に思える。
この現実と遊離した感覚を、上山さんの「ゲーム」ということばが明らかにしてくれた。
「ゲーム」という批判は、スピルバーグ自身に向けられたことばというより、その映画を見て興奮している私自身に向けられた批判だと感じた。
上山さんは、また女子中学生たちのことも最初に書いていたが、上山さんから見れば、その少女たちも「ゲーム」をするようにこの映画を見てはいないか、という批判をしているのだと思う。
上山さんからの三度びの感想読みました。
ご指名(笑)頂いたからには、是非にも発言せねば!!と意気込んできましたが、まだ2回目の鑑賞をしておりません。やっぱり、同じ条件で語りたいので、今度の休みにまた観にいってまいりまーす!ですから、今日は皆さんの感想の感想を書こうと思います。
はじめのあたりと、ここ最近では感想の雰囲気が違いますね。
最初は、驚き、あっけにとられ、じょじょに落ち着いてきたら細部の感想から全体を捉えようと試み、今は作品自体をどう観るかというところまできています。
すごい。壮大だ。一作品でこんなことができるのか。
「ライアン」をどう観るか、どう感じたのかを語るという行為が、自分の思考や 好み、ものの見方、捉え方、人生観、歴史観、思想哲学にまで発展していて、 とっても・・・・何といったらいいのか・・・・すごい。←あぁ、陳腐なことば(^^;)
「どのシーンが好き」か、語るだけで「そのひと」の一部が見えてくる。
それは、そのひとの価値観だ。(おっ、なんだかパンちゃん風だ・・)
語らずにはいられないのか、反論せずにはいられないのか。 とにかく、思ったこと、感じたことが外に向かってあふれだす、 そんな作品にはめったにお目にかかれないです。
いまのところ、私にとって「ライアン」はそんな映画です。得難い映画。 でも、上山さんの感想が変化していったように、私も見直してみれば感想が 変わっていくんでしょうねぇ。
「変化」といえば、アパムの変化を「成長」と表現した人がいました(別サイトで)。
そのひとの真意はわかりませんが、あれを「成長」と位置付けるなら、「戦意昂揚」 映画かもしれない。けれど、一人前の兵士になるってああいうことか、と思えば思うほど悲しくなってしまうのも偽らざるワタシの思い・・。
パンちゃんの、アパムに好意を感じたくだりを読み返して、思い出したまんが があります。
太平洋戦争をはさんで展開される、北海道室蘭にあった女郎屋の女たちを描いた 作品です。愛した女に撃ち殺された男性の死体が発見される。野次馬のひとりが、 「こんな死体なんか、戦場にはゴロゴロある。知らない敵に殺されるのはイヤだ、 こいつのように好きな女に殺されたい、そういう意味ではこの死体は幸せだ。」 というセリフがあるのです。(←この発言者は非国民とののしられる) アパムには、彼を殺す「理由」があった。個人的な理由があった。
そんなアパムに好意を感じた自分にどきりとした。・・なんて、パンちゃん、 ぜんぜん大丈夫!ですよ!「理由無き殺人」が肯定されるのが戦争の実態だと思います。毎日、大量にひとが死んでいく。何故、と聞いてもこたえは出ない。だれも、それが不思議と思わなくなる、それが「戦争」。(だから「交通戦争」も「受験戦争」も戦争なんですね。)殺人に動機が有るほうがまだ、救いがあると思います。
わぁ〜〜、知恵熱(笑)が出そうなくらい、いろいろ考えて、行きつ戻りつしながら やっとここまで書けました・・。
なんだか、私的メールみたいで恥ずかしいなぁ。
他の方の目に耐え得る程度の文章だと思われましたら、アップお願いします。
・・・早く、二回目鑑賞後の自分に会いたいです。