長谷部恭男を読む 2009.05.22
わが師KABU先生がそのブログで「護憲派最終防御ライン」と長谷部恭男を呼んでいる。
私は別に自慢するわけでもなく、恥じることもなく、長谷部恭男という名前を聞いたことはあるが、その方の著書を読んだことがない。でも、おまえハセベも読まずに憲法を語るのか? なんて言われてもまったく動じるつもりもない。
社会人はすべてを学ばなければならないという義務はなく、私が学んだことで皆さんが知らないこともあるだろう。私はそれを批判するつもりはない。そして憲法を論じるのに憲法を読む必要はあるだろうが、憲法を論じたものを読む必要はないと考える。もっとも読んだ方が良いとは思う。というのは他人が考えたことで参考になることもあるだろうし、いちから考えるのではなくブースターがあった方が楽なのはロケットだけではない。
ともあれ、わが師が認めるほどの大人物らしいので、ハセベを読んでみるかという気になった。
私の本の読み方はひとつのテーマに最低10冊くらい集めて乱読し、考えるという方法である。もちろん読む過程で相手を見切ったならそれまでではある。
さっそくアマゾンで長谷部というのを探した。まあ高い本から新書まである。過去6年間位に発行されたものを10数冊頼んだ。
|
実を言って失敗もあった。頼んだ本が来たのを見ると中に「情報法」なんてのもあったのだ。値段は2200円か、居酒屋で焼酎が何倍か飲めたのにと思うとちょっと残念だ。これからアマゾンで注文するときはチェックをしっかりすることにしよう。
|
そして現在読書中である。全部読むと夏になるとは冗談だが梅雨が明けてしまうだろう。
とりあえず本日は1冊目の新書を読んだ感想である。
 「憲法とは何か」
「憲法とは何か」 2009.05.22
| 著 者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 定価(入手時) | 巻数 |
| 長谷部 恭男 | 岩波新書 | 4-00-431002-4 | 2006年4月20日 | 700円 | 全一巻 |
読後感として、学者は考えることは違うなあということであった。お間違えないように、褒め言葉ではない。その正反対である。
ではどこでそんなことを感じたのか、何を考えたのかを書く。
- 「ここでいう憲法とは、憲法典の内容すべてを指すわけではなく、国家の基本となる構成原理を指す。」(p37)
なんかおかしいというか、非常におかしい。私たちが環境法規制を論じたり、ISO規格を論じるとき・・それは論理の遊びや学問の鍛錬ではない・・法に違反するか、罰を受けるかという真剣深刻な論議である・・「ここでいう法規制とは、法文の内容すべてを指すわけではなく、その基本となる構成原理を指す。」なんて論は通用しない。
論理解釈でなんかはもちろんできない、全体的な文理解釈でさえない。文字解釈、一字一字を定義と照らし合わせて、適法か、違法かを判断する。
そういう仕事をしていると、「ここでいう憲法とは、憲法典の内容すべてを指すわけではなく、国家の基本となる構成原理を指す。」とはもはや憲法解釈とか憲法を論じるという範疇ではないと感じるのだ。「そうか、しっかり勉強してくれよ」と傍らから声をかけるくらいなものだ。
私にとって憲法とは「日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)」と称する1万字がすべてであり、それ以外のなにものでもない。
- 「戦争は国家間でしか発生しない」(p39)
戦争とは何か?といえば人の数だけ定義があるだろう。現実問題として、第二次大戦後、戦争は国家間で起きたことは少なく、非合法組織、地域、代理戦争、テロ組織の専業とさえ思われる。
国家間というならイスラエルが承認するまでのパレスティナ紛争は戦争ではなかったし、イラクの現在も戦争ではない。アラビア海の海賊も戦争ではない。
|
ブッシュは911の直後、「これは戦争だ」と語ったが、英語の辞書を見ると「国家間の武力行使」もあるが「an active military operation」というのもある。
|
戦争とは定義次第ではあるが、ならば「戦争ではない」と言えばあなたは安心するのか?安全になるのだろうか?
戦争ではないと定義したところで、いかなる武器の使用においても死者は出るし社会活動は阻害される。場合によっては社会は崩壊する。そういうことを踏まえると「戦争は国家間だけで発生するのではない」
そして、だからこそ国家は戦争を抑える力を持たなければ存在意義を失うのである。
「戦争は国家間でしか発生しない」という前提を置いての議論はもはや意味を持たない。
- 「たとえば、憲法9条の文言にもかかわらず自衛のための実力の保持を認めることは、立憲主義を揺るがす危険があるという議論があるが、これは手段にすぎない憲法典の文言を自己目的化する議論である」(p71)
うーん、ここまで言い切っては、はっきり言って論理的でないことは間違いない。私は憲法9条改正とか自衛隊賛否と全く関係なく、この文章はまったく論理的でないと断言する。
少なくとも、このような論を語ってはISOの世界では排除されてしまうだろう。誰からも相手にされず、話を聞いてもらえないことを保証する。
ISOは憲法よりは論理的なのである。
同様な記述はp129、p130他にもみられる。上位の法になるほど、文字解釈ではなく論理というか目的とする意図を読み取ることになることは私も同意する。しかし書いてあることと正反対の解釈、書いてないことを読むことはやりすぎというか恣意的すぎる。
それにこんな読み方では違憲裁判は裁判官の気分次第ということだ。
そしてその読み変え、意図的か否かにかかわらず意味のとり違いが、その場の論にとどまらず、次なる論の根拠となり拡大していくのを見ると、トッツアンやり過ぎだよと言いたい。
- 「憲法9条の定める平和主義」(p114)
おお!待ってました!
憲法9条のどこに平和主義が書いてあるのか私は知りたい。
|
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
|
憲法9条が述べていることは、武装の放棄、そして国家の防衛の放棄であり、無責任を宣言しているにすぎない。これを平和主義と読むなら、およそ論理的ではない。私はそう考える。
「憲法が定める」とあるが、通常「定める」に対応する英語は「define」であり、これは文字通り定義するということだ。
百歩譲って相手の意を汲めば「憲法の意図する」とか「憲法が目指す」ではないだろうか?
まあ、「定める」と言わないと強調にならないだろうけど・・
- 「(憲法改正が)そもそも、なぜ、3分の2の特別多数決が必要とされていたのか、それを考えることなく過半数の単純多数決に変更するのは控えるべきであろう」(p149)
この文章を読むと、ハセベセンセイは我らの先人が己の意思で日本国憲法を考え制定したようにみなしているとしか思えない。しかしこの憲法がマッカーサー憲法と呼ばれているように、日本国憲法はその改正手段とか基準など考える間もなくアメリカの連中に作られてしまったことを日本国民は知っている。
だから、憲法改正に3分の2以上の賛成が必要であることを是とするなら、その理論的根拠を示すべきであって、「憲法が作ったとき十二分に考えてそう決めたはず」という論は強弁である。
- 「この(3分の2以上)要件が単純多数決に緩和されたとき、同じように穏やかな改憲案が提案されるとは期待しない方が賢明ではなかろうか」(p151)
ほうらね、やっぱりとしか言いようがない。
要するにこのハセベセンセイは憲法を変えたくないということをいろいろな言い方をして補強しているにすぎない。
論文はトートロジーという言葉があったが、そういうことか。
- p157では憲法を改正できなくするさまざまな手段や基準を提案する。
「改憲の発議から国民投票まで2年以上置く」・・激動の時代にのどかなことです。
「国民投票にいたるまでの期間、改正に賛成する意見と反対する意見とに平等にしかも広く開かれた発言と討議の機会を与える」・・昔、小田実や土井たか子が形相を変えて唾を飛ばして議論したのを覚えている。サヨクは必至だなあ〜
- 「要するに公職選挙法の延長線上で憲法改正に関する国民投票を考えることは、大きな問題がある」(p161)
昔、成田空港問題で、某評論家が言った。「成田は政治的に決められたからいけないのです」
そうか!政治的だったからいけなかったのか!
評論家的に決めればよかったのだろうか?
アイドル投票で決めればよかったのだろうか?
教えて、あなた! 
- 「国境はなぜあるのか」(p169)
真面目に読んだが、読んだだけ無駄とういう気がした。この人は現実の世界を知らないのだろうか?
日本に不法入国しようとする中国人、韓国人、フィリピン人、イラク人・・・
国境を書物の中で理解しようとするのではなく、東南アジア、中東、東ヨーロッパどこでもよい、十分ご旅行を楽しんできてほしい。
最初に手に取ったのが新書だったから、中身がこども向けだったのかもしれない。
次は厚めの本を読んでみよう。なにせハセベセンセイの本の備蓄は十二分にある。
あらま様からお便りを頂きました(09.05.23)
ニッポンの教養
佐為さま あらまです
小生と同世代の憲法学者ということで、注視していました。
最初に目にしたのが、数年前の彼の新聞寄稿。こんなので、本当に東大の法学部の教授なのかと目を疑いました。
そして昨年、彼はNHKの「ニッポンの教養」と言う番組に出ていました。 お笑い芸人「爆笑問題」がホストを務めるこの番組は、その後、講談社から単行本が出るほどでした。
「NHK」「長谷部恭男」「太田光」という 3つのキーワードが揃えば、その内容は見なくても想像に難くありません。
その番組で彼らが言うことは、「法律」=「芸」、つまり、「法律家」は「芸人」であるということ。
この段階で、小生は完全に見切りをつけました。
彼らの手に掛かれば「憲法」も学問の対象というより、ネタであります。
|
あらま様 毎度ありがとうございます。
私のネットでの師匠であらせられますKABU先生に言わせると、長谷部は最大・最強の敵といいます。ほんとにそうなのかどうか?私にわかるはずがありません。
でも、そんなことはどうでもよくて、あらま様の憲法論よかったですよ。
次回作をお待ちしております。
KABU師匠からご指導を頂きました(09.06.06)
記事、読みました。私の言葉で言えば「論理の抽象度」の違いがあるのでしょうか。
長谷部氏の得意領域は、憲法の中でも川上も川上ですから。
ただ、それが(他の論者に基盤を提供することで、その一体の論理の流れが)川下に押し寄せてきた場合の存在感は敵ながらあっぱれです。
実は、私と彼とは大変似た「方法論の立場」にあるのでなおさらそう感じるのかもしれませんけれどもね。では今後ともよろしくお願いいたします。
|
KABU先生 わざわざご返事ありがとうございます。
長谷部氏の得意領域は、憲法の中でも川上も川上ですから。
うーん、私も法律に関係なくありません。行政法というレベルでしょうけど、それと比較してか、憲法が川上川下といわれてはいささか違和感があります。
憲法の条文一字一字を文字解釈で現実と比較検討しなくては憲法論は成り立たないと思います。
もちろん条文に落とし込む前の法の意図というか目的はあると思います。しかし「法の目的はこうだからこの文章はこう読むのよね」なんて言われたら、企業や行政で仕事ができるわけがありません。
憲法は別だというなら、憲法はどうして別なのでしょうか?
話がそれますが、ISOでは品質方針とか環境方針を作れと言います。
ここで方針とは理念とか社是とは違うのです。
経営理念とか家訓というなら、「社会に貢献する」とか「功ある者に碌、能ある者に地位を与えよ」(地元の会社の社訓)でよいのです。
しかし方針というのは、「当社は光通信事業と水処理事業を拡大する。そのためにどういった投資を行い、どのセグメントで優位を勝ち取る・・・」というようなものでないといけません。
私が憲法として想定しているものは「方針」に当たるものなのです。
KABU先生やハセベセンセイが考えているものは「理念」や「家訓」のようなものなのでしょうか?
しかし憲法が理念であるならば、違憲訴訟など成り立たないように思います。
またアメリカ憲法を読めば理念ではなく、実用レベルの文章である、私はいささかも疑問はありません。
まあ、素人の考えですが
 「憲法と平和を問い直す」
「憲法と平和を問い直す」 2009.05.26
| 著 者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 定価(入手時) | 巻数 |
| 長谷部 恭男 | ちくま新書 | 4-480-06165-7 | 2004年4月10日 | 680円 | 全一巻 |
この本を読んだ感想は
(1)この人は、憲法と現実社会との関わりには関心がないのではないか?
(2)自分に都合のよいことばかり引用している
(3)虚心坦懐な心を持っていない
ということを感じた。
というと冒頭から結論になってしまうのだが、以下そういう心証を持つに至った経過を述べる。
憲法とはなにか? と考えたとき、それは日本人の暮らしの形、日本という国の形をあらわすものだと考える。時代が変われば生活も変わり、人の暮らしが変われば価値観が変わり、人生についての考えも変わる。憲法が流行歌のごとく、あるはファッションのごとく移ろうのは困るが、時代に合わせて変化していかなければ憲法としての意味はない。
憲法というのが固い変化しないものであって、時代が変わったらその読み方を変えるとか、解釈を変えるということは憲法のあるべき姿ではないと私は考える。
日本国憲法
(一般にマッカーサー憲法と呼ばれる)が制定されてから62年、その間にアメリカ憲法は6回も改正されていることを思えば、憲法は変えてはならないという発想はありえないだろう。
このハセベさん、憲法とは頭の中で考えるもの、つまりお経とか神秘主義思想のように思っているのではないか?

今、北朝鮮が核開発をし、ミサイルを発射しているときに、静かに人生を考えているようだ。まあ、そういう人生もあって悪いわけではないだろうが、それが国家のあるべき姿であるといわれると日本人は大変迷惑する。
ともかく読むにつれ、ハセベさんは憲法とは概念を決めるもの、しかも現実社会を忘れて、国家のあるべき姿を極めるもの、あるいは理念を書きあらわしたものと考えているとしか思えない。
まず感じたことはかなり手抜きである(p54)
ハムレットもドンキホーテも「存在の耐えられない軽さ」も、ハセベさんが書いた他の本でも全く同じ流れで出てくる。まさかそれしか知らないわけではないだろうけど、手抜き、中抜き、朝飯抜き、本を買った人はババ抜きか?
国を愛する心が嫌いらしい。(p70)
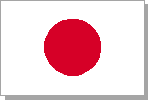 「国旗や国歌というシンボル」
「国旗や国歌というシンボル」がお嫌いらしい。まあ、好き嫌いは誰にでもあるが、外国で通用しないような論をあたかも正論のように日本で語ることはおかしい。
国家のシンボルを否定するなら、中国で国旗を愛する心は間違いだ、韓国で国歌を歌うのはおかしいと語ってほしい
ところで国家のシンボルが嫌いな先生が外国の国旗を燃やしたことについて、ハセベ先生はどうお考えなのだろうか? お考えを知りたい。
そういう誤ったこと、国際問題となるようなことを防ぐために日の丸に敬意を表することを教えることはおかしくないよ
天皇というシンボルも嫌いらしい。
「
多くの国民が、身分制秩序の中で生きる天皇を現在の日本の象徴と考える不自然さに気づいて、(p96)」
はあ!? 何が不自然なのでしょうか?
自然とか不自然とかこれまた主観的なことをおっしゃる。
国籍の意味を理解しているのだろうか?(p101)
このハセベさん、国境も国籍も固いものではなく、風にそよぐところか通り抜けできるような陽炎とか蜃気楼とお考えのようだ。そう考えるのはこれまた自由なのだが、現実はそうでないのもこれまた現実である。
現実を無視した、仮想的な理論を語るのもこれまた自由なのだが、それを聞いた人が信じないということもこれまた事実なのである。
国際法を知っているのだろうか?(p121)
偉大なる憲法学者にそんなことを言っちゃ失礼なことは知っている。しかしどうも頭が良い人が考えることは私にはわからない。戦争になったとき個人個人が抵抗運動をしろと野坂昭如が語って、国際法を知らないと叩かれたことがあったが、同じことを語っている。
テロとパルチザンについても語っているが、そんなこと考えるまでもなく、パレスティナに行ってテロを止めてほしい。止めることができないなら語ることもなかろう。
外敵への服従によってたとえ福祉が向上しないまでも、実力で抵抗するよりまだましだという判断もあり得る。(p143)
そうだろうか?
現実世界には、チベットの虐殺、西域のジェノサイドを見れば、降伏すれば奴隷になっても殺されずにすむはずがない。「降伏した方がよい場合だってあるのではないか」なんて石橋アホのようなのどかなことを言うわけにはいかないのです。
降伏しても虐殺されるなら、敵兵を一人でも殺して、殺すことができなくても噛みつくだけでもして殺される方を私はとる。
ハセベ先生の論は平和な日本においてのみ有効で、戦時あるいはテロが現実となった時は役に立たないのでしょう。
民主主義国家にとって憲法が持つ合理的自己拘束としての意味は、このオデッセウスの寓話にわかりやすく示されている。日本国憲法第9条も、こうした意味を持つと考えることができる。「国際社会への協力」や「自国の領土の保持」などという美しい歌声に惑わされることなく、日本の国民が将来に向けて、安全な航海をつづけていくことができるのか否かが、そこにかかっている。(p156)
うーん、もうボケているのか? 嘘を語っているのか? 夢を見ているのか? 私にはわからない。
間違いないことは、「日本の国民が将来に向けて、破滅への航海をつづけていくのか否かが、そこにかかっている。」の間違いであることだ。
ところでこれをオデッセウスが聞いたらなんというだろうか?
「そんなバカなことに俺の名を語ってほしくない」と苦情を言うのではないだろうか?
最後の最後になって素晴らしい文を見つけた。
憲法典の存在意義が、民主的手続きへの荷重負担を避けること、民主政治が自らの手に負えないことまで手を出さないように、ハードルを設けることにある以上、解釈が専門家の手に委ねられることには、十分な根拠がある。(p174)
そうか! 我々下々の民は憲法を語ってはいけないのだ。
由らしむべし知らしむべからず
お前たちは奴隷なるぞ、ハセベ大先生のお言葉を信じろ
ハセベ先生から見れば、我々は無学な民百姓である。頭をお白州にすりつけてひたすらハセベ先生の語ることに従うしかないのだろう。
本日 学んだこと
我々は憲法について語ってはいけないことが良くわかりました。

木下様からお便りを頂きました(09.05.28)
茶々です。
佐為様のお書きになった「憲法と平和を問い直す」その2 2009.05.26でありますが、佐為様の意見と長谷部氏の記述が両方とも青文字のため、多少わかりにくさを感じます。長谷部氏が何と書いているのかは著作権等に反してしまうのですか? あとオデッセウスの寓話とはどんなものでしたっけ?
(寓話=教訓または諷刺を含めたたとえ話。イソップの類ですね。メルヘンな先生でしょうか。)
|
木下様、ご無沙汰しております。
お元気でしょうか?
えーとですね、青文字はすべて引用であり私の意見ではありません。
木下様 すみません。
おっしゃることがわかりました。今後注意しましょう。
ところで、現実を見ていないメルヘンの王子様というご意見にはまったく同意です。 
タイガージョー様からお便りを頂きました(09.05.31)
違憲
拝啓 佐為様 いつも楽しいお話をありがとうございます。長谷部先生への論評を楽しく読ませていただきました。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/doyou/CK2007032402003183.html
http://www6.plala.or.jp/Djehuti/401.htm
長谷部先生は憲法9条のことを原理と説いています。つまり一つの憲法の中に原理と準則の二種類があるということでしょう。現実問題に憲法が適応できない場合が生じたときはその憲法を準則ではなく原理とし、必ずしも憲法遵守の必要は無いと言うことでしょうか。しかし憲法の中に守らなくてもよい物と守らなくてはいけない物が混在していると世の中が混乱します。さて、以下の憲法違反を犯している勢力は見逃すべきでしょうか?罰するべきでしょうか?
天皇陛下に戦争責任を問うことは日本国憲法39条違反である
太平洋戦争の終戦は1945年8月15日です。その時点では日本国憲法は存在しないのでそれを適応するのは39条に違反します。この時点では大日本帝国憲法が適応されます。大日本帝国憲法第3条によると天皇陛下を罰することはできません。天皇陛下が早期に戦争を終結できなかった事が本土の被害を招いたことは第8条に反するという考え方もできます。しかしそれでも天皇陛下に責任を問うことはできません。理由は大日本帝国憲法第76条にある通りです。天皇制の否定?これは明確に現憲法第1条の違反でしょう。
東条英機の戦争責任を問うことは日本国憲法39条違反である
東条英機の発言に責任を負わせることは、同じく大日本帝国憲法52条に違反します。
集団的自衛権を否定することは日本国憲法98条2項の違反である
貴サイトで 2002年4月31日(原文のまま)に「日本国憲法」で記載されているとおりです。
ソマリア沖の海賊に対して自衛隊派遣に反対することや、北朝鮮に対する援助停止に反対することは同じく日本国憲法98条2項に違反する
サンフランシスコ平和条約第5条a項?に記載されている「国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。」を遵守しないといけません。
佐為様、憲法学者が感情論やイデオロギーで憲法を語り、一般人がロジックで語るようになってはそれこそ順序が逆であります。いっその事、憲法学者は憲法哲学者と憲法改正学者に分類してしまった方が・・。
タイガージョー拝 敬具
念のために http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM
|
タイガージョー様 毎度ありがとうございます。
ハセベセンセイの語るお話はよくわかりません。
はっきり言うと理解できません。
▽憲法は、自分とは根本的に異なる価値観を持っている人々の存在を認め、そうしたさまざまな価値観の公正な共存を図るためにある
▽その手だてとして、生活の中の公的な領域と私的な領域とをきちんと区別する
▽憲法の条文には、ある問題に対する答えを一義的に定める「準則(ルール)」と、答えをある方向に導く力としてとどめる「原理(プリンシプル)」がある−となろうか。
これを読むと、憲法とはルールとかプリンシプルという論点ではなく、人々の生き方を規制するあるいは調整するもののように取れます。
私はそうではないと考えます。憲法とは国家を規制するものです。国家とはリバイアサン、暴力です。だから我々国民が国家の裁量範囲、行動できる範囲はどこまでかを示すもののはずです。
「みんなの憲法入門」でも「人はどう生きるべきなのかという事は、憲法は教えない。それは憲法の役目ではありません。」と語っているのをみると、この先生はまったくの勘違いをしているのかもしれません。もちろん勘違いではなくそのように読者を誘導しているのでしょう。
しかしながら、タイガージョー様の「憲法学者は憲法哲学者と憲法改正学者にわけるべき」というご提案にはいささか同意できかねます。
私は憲法を正しく読む学者と憲法を偽る学者に分けるべきかと・・
 「みんなの憲法入門」
「みんなの憲法入門」 2009.05.31
| 著 者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 定価(入手時) | 巻数 |
| 長谷部恭男・太田光 | 講談社 | 4-06-282621-1 | 2008年8月25日 | 780円 | 全一巻 |
著者に長谷部恭男の名があったので買ってはみたものの、実際にはハセベセンセイ個人の著ではない。キャストが政治的に明るいとみなされている漫才師と高名な憲法学者という組み合わせで、演出が自虐と捏造で
国際問題まで起こしているNHKとくれば、実質的な編者はNHKである。

まずこの本はち密に設計されていると感じた。
全頁の右上、右下、左上、左下には戦車の絵、日の丸を振る手、ピ−スマーク、そして漫才師と目される目の絵が描かれている。そして戦車と日の丸の関連性の刷り込み・・もう反戦思想ビンビンである。
各章のネーミングは過激である。しかし中の文章と無関係ではないがマッチしてもいないし、サマリーでもない。いわゆる週刊誌的なセンセーショナルなタイトルをつけて目を引こう、あるいはその章の結論がそうであると読者に思いこませようとしているように思う。
ところで章ごとというわけでもなく中の文言に関係もなく、ところどころにとりとめなく憲法の条文とそのコメントが載っている。そのページの上部には菊の紋がある。この意図するところは何だろうか? 日本を意味するなら桐ではないか?あるいは富士山ではないのか? 菊の紋から皇室を連想させ、そしてなにか先入観を持たせようとしているのか? 私には読み切れない。
おもしろい文章があったので紹介する。
太田光は語る。
「たとえば北朝鮮のような、もっと閉じた国がいっぱいあってもいいんじゃないかと。でもあれは、ならず者たという風にみなされて、民主化されなきゃだめなんだと・・」(p61)

この本は2008年8月25日に発行されている。北朝鮮が第一回核実験をしたのはその2年前の2006年10月であった。だからこの文章が北朝鮮の核実験を踏まえてのことはもちろんである。そして日本からの拉致については一言も言及していない。だとすると、太田光は恐ろしいテロリスト支持者である。
しかし、長谷部先生もNHKもそれについて一言もない。こりゃまずいと思って、コメントをつけるとか、後で削除しようという発想はなかったのだろうか? ハセベ先生も、NHKも太田の発言に同意したという事なのだろう。
そして、あとで批判がきても太田個人の意思ですとかわすつもりだったのだろうか?
|
「憲法9条を世界遺産に」でも太田光の素晴らしいセリフがあった。
「日本は原爆を落とされて戦争をやめました。あれこそがテロだと思うんですよ。日本は1回テロに屈したからこそ平和になったのだろうと」(p64)
|
しかし太田はさらに飛ばす。
「大衆を洗脳していくっていうようなことが起こりえるわけですよね」(p66)
それってまさにあんたがいましていることじゃないのですか?
「俺のやっていることは洗脳に近いんですよね」(p67)
洗脳に近いではありません。洗脳そのものです。
この本で「憲法を守る」という言葉があちこちに出てくる。そのときの意味合いは遵法という意味なのか、改正しないという意味なのか定かではない。
別のところでは「憲法を大事にしなければならない」(p130)という言い回しもある。
だがそういう個所のすぐそばに「憲法を守らなければなりません」とか「法律を破っても」という語句と並んでいるところを見ると、「憲法を遵守する」ということと「改憲しない」こととを意図的に混同させ取り違えさせようとしていると私は受け取った。
誰だって、「憲法違反するのは良いのか?悪いのか?」と問われれば「憲法は守るべきだ」と応じるだろう。そのとき「憲法を遵守する」というつもりが「憲法を改正しない」と同義と思いこませるのが目的ではないのだろうか?
おかしなのは太田光だけではない。ハセベセンセイも太田光に負けずにおかしなことを語る。
「人はどう生きるべきなのかという事は、憲法は教えない」
「それは各自で考えてください。各自で決めてくださいというのが、これが憲法学のメッセージだという事だと思います。」(p116)
それって全然おかしいです。誰も憲法に人生を問う人はいない。それに応えるのは宗教とか哲学の役目だ。私たちが憲法に期待するのは、日本人が物理的な意味、身体的に、経済的に、安心して生きていけることを求めるのである。
だからハセベセンセイの言葉の前半はともかく、後半の文章はまったく間違っている。
「人はどう生きるべきなのかという事は、憲法は教えない。それは憲法の役目ではありません。」と語らなければならないのである。
この小さな本は、見た目は過激ではないが静かに深く潜行して、しっかりと刷り込みをしようという、アジテーションとはこうあるべきだというテキストである。
この本を読んで感じたことは多い。
正論派もこれに対抗したアプローチ、作戦をとるべきなのだ。ハセベに対抗して渡部昇一、あるいは小室直樹をキャスティング、爆笑問題に対抗してゴルフの藍ちゃんとか水泳の北島の組み合わせではどうだろうか? イチローでは大物すぎる・・ハセベの役割になら似合うかもしれない。
ハセベセンセイのたまわく
憲法学は科学ではなく芸である。(p98)
そうか!
ならば、下々が語っても文句を言われる筋合いはない。
だがこの本の別のところ(p65)ではハセベセンセイは「
正しい判断ができそうもないときは専門家に任せるということも必要になる」と語っている。
憲法学は矛盾だらけでよいという事なのだろうか?
あらま様からお便りを頂きました(09.06.04)
みんなの・・・
佐為さま あらまです
「みんなの憲法入門」ですか・・・
「みなさまのNHK」「われわれの朝日新聞」。
なにか、そういった「たぐい」を感じます。
そういう表現をとれば、責任の所在が明確でなくなりますからね。
少なくとも、小生の憲法入門の書ではないことは明らかです。
|
あらま様 毎度ありがとうございます。
昔からありましたね〜
「我々はーーー」
「私たち消費者は・・・・」
「私たちは市民代表だ」
「私たちマスコミは」
そんなご謙遜してあいまいな一人称を使うことありません・・・
「私はこう考える」
「私は困っているのよ」
「私は報道する責任がある」
おっと、捏造する権利はありませんよね・・・NHKさん
憲法の目次にもどる
 「憲法とは何か」 2009.05.22
「憲法とは何か」 2009.05.22
 「憲法とは何か」 2009.05.22
「憲法とは何か」 2009.05.22
 「憲法と平和を問い直す」 2009.05.26
「憲法と平和を問い直す」 2009.05.26

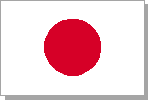 「国旗や国歌というシンボル」がお嫌いらしい。まあ、好き嫌いは誰にでもあるが、外国で通用しないような論をあたかも正論のように日本で語ることはおかしい。
「国旗や国歌というシンボル」がお嫌いらしい。まあ、好き嫌いは誰にでもあるが、外国で通用しないような論をあたかも正論のように日本で語ることはおかしい。
 「みんなの憲法入門」 2009.05.31
「みんなの憲法入門」 2009.05.31
 まずこの本はち密に設計されていると感じた。
まずこの本はち密に設計されていると感じた。 この本は2008年8月25日に発行されている。北朝鮮が第一回核実験をしたのはその2年前の2006年10月であった。だからこの文章が北朝鮮の核実験を踏まえてのことはもちろんである。そして日本からの拉致については一言も言及していない。だとすると、太田光は恐ろしいテロリスト支持者である。
この本は2008年8月25日に発行されている。北朝鮮が第一回核実験をしたのはその2年前の2006年10月であった。だからこの文章が北朝鮮の核実験を踏まえてのことはもちろんである。そして日本からの拉致については一言も言及していない。だとすると、太田光は恐ろしいテロリスト支持者である。