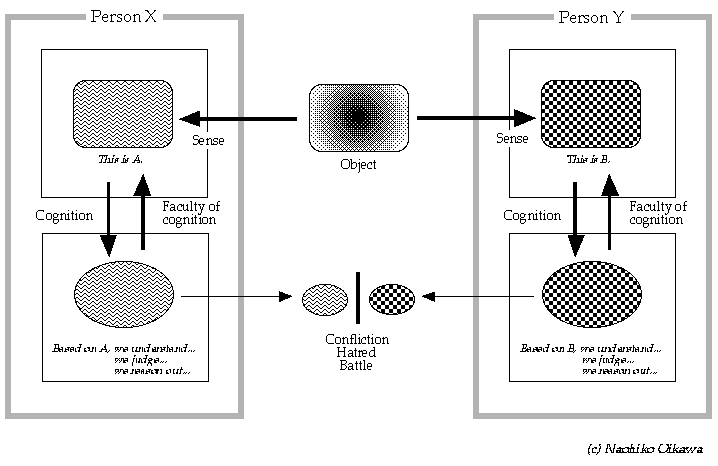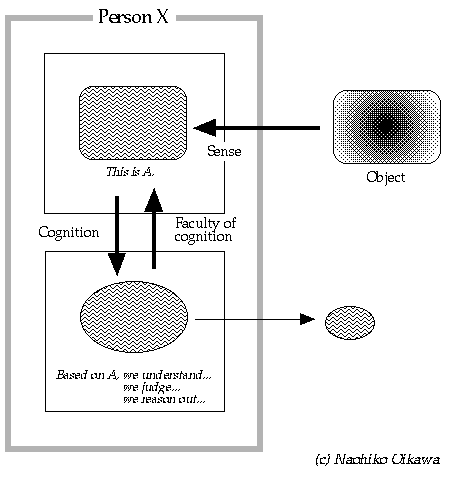
Xさんに感覚を通じてもたらされたものは、「これはAである」として認識される。
このAという認識を素材として、それに基づいてXさんの理解や判断、推論がなされ、認識の構造が築かれる。
ここで認識を可能にしているものは、純粋な感覚ではない。Xさんが感覚の情報をどのように編集するかは、それまでのXさんの中に築かれてきた認識の構造に基づくものである。
認識を素材として認識構造が築かれ、認識構造によって認識が規定されるわけである。
ここで問題は、Xさんの認識構造が自分の都合にしたがって認識を歪ませたり、あるいは勝手に創ったりしてしまう事態である。こうなるとXさんの認識は対象から閉ざされ、自分の中で閉じてしまう。すなわち独断論。