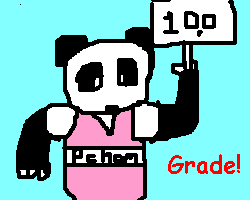
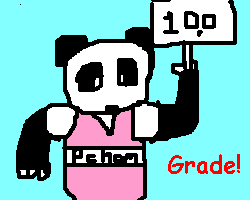
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』、
10月11日までの採点は『プライベート・ライアン(3)』、
10月14日までの採点は『プライベート・ライアン(4)』、
10月25日までの採点は『プライベート・ライアン(5)』、
10月28日までの採点は『プライベート・ライアン(6)』、
10月30日までの採点は『プライベート・ライアン(7)』、
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
灘かもめ(11月2日)
seagull@di.dion.ne.jp
2回目観てまいりました。アレックスのパパ(11月1日)
もうストーリーは解ってるし、今度は冷静に、客観的に観よう!
・・・・という観る前の決意は、やっぱり冒頭の30分で、ものの見事に崩れ去りました。私には、あの映像を「客観的に観る」高等技術は持っていないことが判明しました(笑)。
「・・もうこうなったら、とことん浸って観てやる!」と軌道修正し、
登場人物の表情、言動をあれこれ想像しながらその人物になったつもりで観ることにしました。おかげで、救出部隊の顔、名前はバッチリ!覚えましたよ!
ミラー大尉・・トム・ハンクス、元作文の教師、前任地はイギリス。ファーストネームはジョン。妻あり。
ホーバス軍曹・・トム・サイズモア、ミラー大尉とは歴戦の戦友。自分が戦った戦地の土を記念に(かどうかは分からないが)持ち帰っている。ミラーは「マイク」と呼んでいた。ノルマンディーでの銃撃戦で、走っていくジャクソンを見て「今のはお袋さんには見せられない」と言うが「おまえがお袋だろ?」とミラーに言われる。
ライベン2二等兵・・エドワード・バーンズ、皮肉屋さん。任務に反感を持ち、途中で離脱しようとした。入隊前の思い出で、巨乳のおばさんの話をしていた。リュックを背負わず、背中にI LOVE NY みたいなカンジの言葉を書いていた。
ウェイド(軍医?)・・根津甚八似のひと。休息をとるために入った教会の中で、母親との会話を自分から避けていたと話していた。「俺がバカだった」、眼に涙をためていた姿が痛々しかった。敵機関銃の攻防で射殺される。「ママ、ママ」と言いながら死んでいった。
メリッシュ二等兵・・ユダヤ人。捕虜のドイツ人達の列に「ユダヤ人だ」とアピールしてた。エディット・ピアフのレコードを解説するアパムの声で「催し」た(笑)。後に、アパムが助けたドイツ兵に刺殺される。
カパーゾ二等兵・・黒人。フランス人の少女を「姪に似てる」と言って連れていこうとした。建物に潜んでいたドイツ人射撃手(男前さん)に射殺されるクソン二等兵・・スナイパー君、スキート・ウーリッチ似のひと。「俺は天がつくった最高の兵士だ」「神が自分をヒトラーの近くに置いてくれれば、こんな戦争はすぐ終わる」
アパム伍長・・説明は不要かと思われる(笑)。ファーストネームはティモシー。地図作成のため配属された実践経験ゼロの新兵。タバコは吸わない・・が橋での攻防戦の前に「今まで断っていたのに」と、すぱすぱ吸っていた。
あっ、ヤバイ。今、全員の名前や言動を思い出そうとしていたら、涙が出そうになりました。・・どうしたっていうんだろう。今頃になって、ドッと感情があふれてきた。
いま、彼らをとても愛おしく思う。・・何故?彼らの運命を知っているから?
あんな死に方をするのだ、と知っているから?
客観的に観るどころか、ますます彼らを近く感じる。でも、それでいいと思う。
私は、一度目よりも、彼らを好きになれた。作品も、たぶん好きになれる。
分からない映画、でもそのままにしてはおけない、分かりたいと思う、そんな気持ちで観にいったのです。たぶんまだ「分かって」はいないのだろうけど、「好き」は理解への第一歩ですよね?
今回、観直してみて、ミラー大尉の物言いたげな表情のUPが多いことに気が付きました。例のサンドイッチのシーンもそうです。あれはDデイの三日後、あとからやってきた兵士がヒゲをそり、朝ご飯を食べてるところでした。
みなさんが、いろんな意見をおっしゃってましたよね。どのセリフをあてはめても、あの時のミラー大尉の気持ちだったと思います。
・・・もしくは、なんにも感じていなかったか。彼の「物言いたげUP」は、考えているのに、まとまっていない、なんにも感じていないうつろなものにも見えました。ミラーは「戦場で立派に指揮を執る」自分を、「本当の自分」とは違うと感じていると思う。彼はいつでもそうだ。ライアン救出を命じられ、自分は「立派な指揮を執れる」のに、こんな意味のない任務をしなければならない。「意味のない」任務と思っているから、見過ごせばいいのにわざわざ敵機関銃陣地を無理に攻撃する。少しでも、「意味の有る」ことをしたいからだ。
でも結果は、ウェイドの死。ミラーが泣いたのはこの時だけ。
「自分でない自分」に気をとられて、一番恐れていた、部下を死なすという結果を自ら作ってしまったからだ。情けなくて、悲しくて、つらくて・・。
けれど、逃げ出せない。
ミラー大尉って、きっと故郷ではいい先生なんだろうなぁと思う。
どんな立場になっても、「自分」を見失わないよう、一生懸命生きてるんだと思う。
そんな彼ですら、混乱させる「戦争」という怪物。
本当の自分にもどるために、「本当の自分を捨てて」戦場で戦う。
そりゃ〜混乱しますわな・・。
以上は私の勝手な推測です。彼の表情、言動から、きっとそうだろうと思ったのです。
こんな風に、ひとりひとり、気持ちを想像していくと、時間がいくらあっても足りない気がする(笑)。
あと、印象に残ったシーン。
ピアフのレコードを聞いていた、アパム、メリッシュ、ライベンが、地鳴りのする方向に一斉に顔を向けるシーン。カメラは、決してそれぞれの顔UPを写さない。
2、3秒後、戦闘態勢に散るんだけど、その一瞬は報道写真のそれでした。
「写真を参考にした」というよりは、スピルバーグが、「自分が報道カメラマンなら、こう撮る」と言ってるように感じました。
そうそう、レコードを聴く、で「ショーシャンクの空に」を思い出しました。
「うた」は自由、解放の象徴なんだなぁと、改めて思いましたね。
休息をとるために入った教会で、ミラーが、戦死した部下のことを思い出そうとしているシーン。
「這って走った」とか、笑いながら言っていた。他の部下たちは、家族やママの話ばかりなのに、彼は戦死した仲間の話しかしない。戦場においては「本当の自分」につながるものを排除することが、彼なりのバランスのとり方だったのだと思う。
だから、後にライアンに「奥さんとバラの話を」といわれた時、「それはおれの胸の内だけに」と言ったんだ。・・きっと・・。
・・あぁ〜〜〜、どうしよう、とまらない。
私にとって「プライベート・ライアン」は、中に入ってしまわなければ、わからない作品だ。きっと、もっと彼らを好きになるために、リピーター(笑)と化すのだろう。
でも、星はまだ★★★★。
じつは、減点1は私のつまんないこだわりのせいです。
青年ライアンが、老ライアンになっていくシーン、いまではモーフィング技術はSFXが目玉の作品じゃなくても、もはやあたりまえなんだけど、あまりにもスムーズに老人になっていくので・・・。あのシーンは、オーバーラップがいいなぁ・・・。余韻が欲しい。50年の歳月の流れを、あまりにも性急に現在につなげないで欲しい。
>アレックスのパパさん
私の文章を気に入ってくれて、ありがとうございます。
私を知らない人から、そう言ってもらったのは初めてですので、照れてしまいました。
「素敵な日本語」が使えるよう、さらに精進いたします。
>れいなさん
私も、あの投稿にはドキッとし、腹も立ちました。
でも、「モノローグ」とあるし、ヒトリゴトなら放っとこうと避けてしまったのも事実です。波風たてないように振る舞う、日本人の悪いクセが出てしまいました。
れいなさんの勇気に感謝&脱帽です。
そうそう、スナイパー君の祈り、2回目見て、れいなさんのお考えに賛成です。
やっぱり、恐かったんだと思います。神に祈る=神に自分を近付けることで、神に一番遠い行為である「命を奪う」ことの許しを得たかったのだとおもいます。
(「命を奪う」ことも、神の仕事なのだけど。)
>パンちゃん
「映画を観にいく」とは、「自分」VS「作品」だと思います。「作品」は変わりようがない。であるならば、こちら側が変わらなければ、見方も変わらないと思います。
二回目を観て、本当にそう思いましたし、実感しました。
でも、皆さんの感想を読んでいなかったら、観にいかなかったかも知れない。
パンちゃんに深く感謝します。
ライアンの持つ説得力の効果なのでしょう。力のこもった発言が続いていますね。井上俊夫(10月31日)
◆井上俊夫さん:
お一言、一言が胸に沁みました。
>戦争についてこれだけ喧々囂々の意見が出ると言うことは、今後、なにかの拍子で日本
> 政府が戦争に踏み出そうとしたとき、やはりインターネット上で、喧々囂々の意見がた
>たかわされるということでしょう。それがすばらしいとおもうのです。
> 今後、戦争をやりたいと思う政府は、これだけの意見と異見をまとめて、強固な戦争賛
>成の与論を形成しなければならない。それは非常に難しく、不可能にちかいのではと私
>は考えます。
インターネットを使い、守ってゆこうと思う人間にとって、これ以上の激励はありません。言論の自由無き中、お辛い戦争体験をされてこられた方の発言として一生忘れません。二十一世紀まで大事にしてゆきたい言葉です。
>私は『プライベート・ライアン』が、さまざまな兵士の死を描いてくれて、ほんとに良
>かったとおもいます。私たち戦争体験者が、若い人たちに戦争の話をするとき、一番困
>難を感じるのは、戦闘場面の説明です。わけても兵士の「あっけない死」が容易に分
>かってもらえなかった。
>でも、この映画をみた人には、もう説明する必要はありませんわね。
立場は違いますが、こちら米国での戦争体験者の方々の多くも、同じことを言われていました。
実際に戦争を体験された方にお伺いしたいのですが、小生は、「日米や日中の感情的なシコリに関して、実際に戦場へ行かれて戦友の死を経験されたご本人やその直接のご家族の世代に、総てのわだかまりを捨てろと言うのは無理であり、失礼だ。だから、若い世代にこそ真の和解の努力をする責任がある。スピルバーグのこの映画のように。」という思いがあるのです。
逆に、「交戦国や元植民地との関係で、<面倒な対立>や<向こうの一方的な正義>ばかりが継承されるのは不愉快だ。」という感覚を若い世代が持つのは責任逃れだと考えますが、如何でしょうか。傲慢な考えでしょうか。不要な考えでしょうか。それとも、役に立つ言い方と思って下さいますか?
◆ドットさん:
確認のための丁寧な質問ありがとうございました。まず、
>7)「日本語が弱くなっています。」とのことですが、アレックスのパパさんの文章を
>即座に理解できない私は「日本語が弱」いのでしょうか?
>8)アレックスのパパさんは日本語が強いのでしょうか?
からお返事したいと思います。
ドットさんと小生の日本語に関して言えば、一言で言って、ドットさんの日本語は強く、小生の日本語は弱かったと思います。
何故なら、ドットさんは、誤解を避けるために、実に丁寧な「日本語」で質問をされたからです。最近の日本では、知ったかぶりをする人や、その裏返しで、質問をすることを恥じる人が増えているようです。それは日本語を弱くします。ドットさんのような、的確で論理的な質問の言葉、これこそ大切にしなければなりません。
これに対して、小生の日本語には弱点がありました。言葉を飾りすぎて、昔の文学仲間の「内輪」言葉になってしまい、論理的ではありませんでした。勉強になりました。
>2)「「価値value」という押しつけがましいものは、総て壊してしまおう。」と私に
>勧めているのですか?つまりアレックスのパパさんは「価値という押しつけがましいも
>のはすべて壊したので」私にも「しまおう」と勧誘の表現を使っているのですか?
済みません。これは逆です。「価値Value」とは大事なものです。たとえ荒っぽくても押しつけがましくても、仮のものであっても、それを掲げ、その正しさを問い続け、必要があれば思い切った修正を加え、人に問いかけ、自分に問いかけ続けるものとして、壊してはなりません。何であれ、まず「価値value」がなければ、思考や議論の座標軸すら決められないでしょう。
>3)「「壊すこと、相対化することが、「無垢なる絶対善」であって、ある種の「価値
>value」を認め、関与することは、自分の手を汚すことだ。そういうお考えもあるので
>はありますまいか。であれば、こちらの方 が深刻でしょう。」「そういうお考えもある
>のでは、、」とお尋ねになり、それが「こちらの方が深刻でしょう」にかかる文脈がよ
>くわかりませんでした。「ありますまいか?」というお尋ね、仮定?のうえにもしその
>仮定が正しいとすると「こちらの方が深刻でしょう」という意味ですか?とするなら
>「ある種の価値を認め関与すること」は私にとって「深刻(な問題)でしょう。」とい
>う意味ですか?
これも逆です。「壊すこと、相対化することが絶対善」ではカラッポの世界です。価値を掲げることは「手を汚す」ことではありません。文法的に言うと「ありますまいか?」は「反語」のつもりでした。
(◆パンちゃんへ:言葉の専門家に伺います。こういう反語って、最近は使わなくなったんでしょうか?小生はやはり、英語に毒されてるのかなあ。)
>4)「ある種の価値」とはアレックスのパパさんが私に対して想定したアメリカ感のこ
>とでしょうか?
いえ、「価値」一般のことです。
>5)「非難をしているのではありません。それでは、この複雑な世の中で、自分の一貫
>性を保ちながら後悔のない人生を送る上で、不便この上ないのではないでしょうか?」
>「それでは、この複雑な、、」の「それ」とは「(アレックスのパパさんが想定した私
>のアメリカ感)では、、不便この上ない。」と言う意味ですか?
アメリカ観のことではありません。これも、「価値」一般のことです。
>6)「非難をしているのではありません。」と書いているが、アレックスのパパさんが
>使う「非難」とはどういう意味ですか?私の理解ではアレックスのパパさんが述べたこ
>とは「私に説法を説いたり生き方を変えろなどといっているのではない。アレックスの
>パパさんのような考え方もあるから参考にして。」という意味でしょうか?しかし全体
>の文面から「参考にして」という印象は感じられないのですが?
(A)非難してやる。認めないし、第三者への影響も阻止してやる。意見として抹殺してやるから、そのつもりでな。
(B)説法と思って聞け。俺の言ってることはとにかく正しい、お前が、心の底から納得するかなんて、知ったこっちゃない。とにかく生き方を変えろ。
(C)あんたはあんた、俺は俺さ。元から他人だもんな。俺の意見にカッカ来られても困るしさ。逆に大真面目に取られて、その後の責任まで取らされても困るからな。まあ参考にしろや。
(D)思想というのは、一人前の大人と、一人前の大人同士の言葉による直接の関わりだ。だから、言う以上は、相手に影響力を与えようと頑張る。でもそれを受けるか受けないかは、個人の問題だ。相手の人格を尊重するからこそ、主張にも力が入るってもんだ。もう一つ言うと、見解が違う同士が話し合うからこそ、そこから先に、両人が考えもしなかった、新しい発見もあるってもんだ。爽やかにやろうぜ。厳密なゲームだよ。でもさ、真剣勝負だよ。論理と論理のさ。
小生は、(C)が大嫌いです。でも、(A)とか(B)だと誤解されたとしたら、これも小生の言葉が弱かったからかなあ。(D)で行きましょう。
>1)アレクッスのパパさんがおっしゃる「理念としての<アメリカ>と、その理念から
>ほど遠い現実のアメリカ」の「両方のアメリカ」の説明をしてもらえませんか?私の理
>解では「その理念からほど遠い現実のアメリカ」のために長所も短所も含む「理念とし
>てのアメリカ」の長所の部分まで否定しているととらえたのですが?
これが本論ですね。
アメリカの失政、例えば、スターリンを甘く見ていたために、ソ連の対日参戦の気配に慌てて、広島長崎の大量虐殺に走ったこと。ベトナムやソマリアでの失敗。南北戦争の犠牲の結果を受けても、以後百年間、黒人の公民権問題を解決できなかったこと。日本の狂信的な軍国主義を民族の特性と誤解して、善良な日系人まで公民権を剥奪して収容所に押し込めたこと。最近では、インドネシアやロシアの失政を支えたり突き放したりの節操無き経済政策はひどいですね。
でも、それらは、総て「アメリカの為政者」の愚なのです。勿論、その瞬間瞬間では、操作された世論がそれを支えていたのも事実でしょう。けれども、そうした失政を暴き、正して行く「報道」や「草の根の世論形成」、特に、自己反省と自己修正のできる合理性はアメリカの強みです。敢えて言えば、アメリカの庶民の強みでしょう。
そして、移民国家としての成り立ちは、人種差別による国家分断の危険を常にはらんでいますが、同時に「異質な」人間達が共存してゆく知恵、つまり「機会の平等」と「社会全体の合理性」などを守ってゆかねばならない宿命となっています。
映画に即して言えば、スピルバーグ自身の問題としての、ユダヤ人としての誇りを守りつつ、キリスト教との共存が描かれていること。そして、何よりも「民主主義」を守った「神聖なる戦勝」を、世代が下ったとはいえ、ここまで冷静に描いた映画が作られていること。これもアメリカならではとは言えるでしょう。
とにかく、「多様性を許す」ということが、時には脅かされても、不思議な復元力をもって、二百二十年の間、この国の誇りでありました。そこに数パーセントの偽善があるかもしれない。そんなことは誰でも分かっています。けれども、明らかに多様性を許さない他の社会と比較した時、この「アメリカ」なるものを利用しようという気持ちにさせるのです。少なくとも、小生はそうです。
ドットさん。
それでも、アメリカを全否定されますか?ならば、何をお手本に、今の苦しい時代を乗り越えてゆこうとされるのですか?
ところで、
百聞は一見に如かずと言います。
映画という素晴らしい媒体を通じて、日本に居ながらにしてアメリカそのものを体験できる機会は沢山あるでしょう。
『トルーマン・ショウ』を貫く、個人の尊厳ということ自体が光り輝く様子。
『ホース・ウィスパラー』に出てくる傷ついた思春期の少女の心を、とにかく癒そう
そのために、無茶な話でも何でも作ってしまおうという、底抜けの健全性。
『ER』(テレビですが)に出てくる、誰一人として課題の解決がされない「複雑」な人生を背負い込まされながら、それでも生きて行く人間の有り様を「美しい」と思う、楽天的な感性。
『グッド・ウィル・ハンティング』に流れる、大学の権威や立身出世主義の下らないことを正直に前提にしてしまう「青臭さ」を、見事に暖かい話にしてしまう素朴さ。
別段、アメリカ映画だけが優れているわけではありません。けれども、こうした作品に流れる、アメリカの美点すらも認められない程に、アメリカは罪深いのでしょうか。
私は上山さんの友人です。このコーナーの存在は、上山さんから教えてもらいました。こんなにすばらしいHPがあるなんて! これから、せっせとアクセスさせてもらいます。ドット(10月31日)
『プライベート・ライアン』をめぐるみなさんのご意見を拝見していて、今更のようにインターネットってすばらしいなあ、と思ったことです。
『プライベート・ライアン』は映画だけれど、みなさんのご意見は自然と戦争論にもなっていますよね。戦争についてこれだけ喧々囂々の意見が出ると言うことは、今後、なにかの拍子で日本政府が戦争に踏み出そうとしたとき、やはりインターネット上で、喧々囂々の意見がたたかわされるということでしょう。それがすばらしいとおもうのです。
今後、戦争をやりたいと思う政府は、これだけの意見と異見をまとめて、強固な戦争賛成の与論を形成しなければならない。それは非常に難しく、不可能にちかいのではと私は考えます。
ということは、国民を戦争に引きずり込むのは、私たちの時代より遙かにはるかに難しくなってきているということでしょう。
ハイ、申し遅れましたが、私は第二次世界大戦のうち、日中戦争に4年間、従軍体験を持つ老兵です。
当時、私たちは戦争に対して絶対に批判することは許されませんでした。有無を言わさず戦場に引っぱり出されました。
ところで『プライベート・ライアン』は私も素晴らしい作品だとおもいます。私の評価は★★★★です。私は戦争映画となれば洋の東西を問わず必ず観てきましたが、今度のスピルバーク作品のすばらしさは、既に多くの人がおっしゃっているように、その戦場場面のリアルな描写にあります。
冒頭のノルマンディー上陸作戦で、アメリカ兵が、ドイツ軍の機関銃の餌食となって、虫けらのように死んでいく場面は特に印象的です。ス監督はこの場面を見せたいばかりに、この映画を作ったのだと私は思いましたね。
「7人の侍」ならぬ8人の兵士が、命がけでライアン二等兵を救出するところや、生きながらえたライアンが女房や子供を引き連れて、命の恩人であるミラー大尉のお墓参りをするラストシーンなど、うるさいくて怖いアメリカの在郷軍人会のオジサンたちの検閲をパスし、おまけに興行成績も大いにあげたいという監督の逞しい商魂にすぎないと思います。
「シンドラーのリスト」の時も、シンドラーという人物の陰に隠れて、ナチスの暴虐ぶりを見事に描いていたじゃありませんか。
ところで、中国軍と闘った私たちは、やはり一番怖かったのは、敵の機関銃と迫撃砲でした。まだ新米兵士の頃、はじめて戦場に立って、敵がバリバリと撃ってくる弾丸が頭上に飛んできたときの恐ろしさ。私は思わずオシッコを漏らしてしまいましたね。私の戦友の中には大便を漏らしたものもおりました。
だがらス監督が描いたような戦闘場面では、アメリカ兵もドイツ兵も両方とも失禁して、ズボンがベトベトに濡れていたはずです。
中国軍は鉄筋コンクリートで固めたトーチかの中に潜み、小さな銃眼から機関銃を撃ってくるのです。これを攻撃するのは高度な戦術が必要でした。バカな将校の命令で正面から突撃しようものなら、命がいくらあってもたりませなんだ。
ス監督も描いていましたが、実戦では下手な将校より経験を積んだ下士官の方が部下を死なせなかったのです。
敵弾にたおされるのは、ほんとにあっけないものです。私は何人もの戦友が倒れるのをみてきました。状況によっては戦友の屍を収容したり、荼毘にふしたりすることができず、指を切って持ち歩いていました。
中国軍の兵士が虫けらのように死んでいる姿もイヤと言うほど見てきました。はじめのうち、そうした死体をみると嘔吐したりして、めしが喉を通りません。しかし、馴れてくると、敵兵の屍が目の先に転がっていても、平気で飯盒の飯が食えるようになるのでした。
私は『プライベート・ライアン』が、さまざまな兵士の死を描いてくれて、ほんとに良かったとおもいます。私たち戦争体験者が、若い人たちに戦争の話をするとき、一番困難を感じるのは、戦闘場面の説明です。わけても兵士の「あっけない死」が容易に分かってもらえなかった。でも、この映画をみた人には、もう説明する必要はありませんわね。
最後にPRみたいになって申し訳ないんですけれど、私は「浪速の詩人工房」というホームページを開いて、おのが戦争体験などをアップしています。暇な時、見て下されば幸いです。以上。
http://www.vega.or.jp/~toshio/
私の映画観は「楽しければよい」というのが基本でそういう意味では「ふむふむさん」と同じ意見です。ですから最初におもしろいおもしろくないの採点をしました。これはその人の感じ方でなかなかなにがどうだったか言葉では表現しにくい。後の部分は好き勝手な感想です。でもこれってそういう好き勝手な感想を書いていいページですよね。
プライベートライアン、、しつこいようですが、やっぱり「リアルさ」に感動しました。これから3回目にチャレンジしようかと思ってます。あら探しの段階にはいるのよね。悲しいかも。トムハンクスはこの映画のために太ったのかなぁ、対照的にアパム役の人はいかにも品粗な体型でしたが、映画が進むにつれてたくましく見えてくるのが不思議でした。
スピルバーグの「ストーリーになりすぎている」映画は確かに時々腑に落ちないものを感じますが、私はもっと表層的なものの見方なので、もちろんできるだけおもしろい映画をみたいですが、ま、いいかで終わってしまう。情熱の度合いが違うのでしょう。
アレクッスのパパさん>プライベートライアンの感想の感想ありがとうございました。私の頭ではなかなか理解することが難しい文面でありました。
1)アレクッスのパパさんがおっしゃる「理念としての<アメリカ>と、その理念からほど遠い現実のアメリカ」の「両方のアメリカ」の説明をしてもらえませんか?私の理解では「その理念からほど遠い現実のアメリカ」のために長所も短所も含む「理念としてのアメリカ」の長所の部分まで否定しているととらえたのですが?
2)「「価値value」という押しつけがましいものは、総て壊してしまおう。」と私に勧めているのですか?つまりアレックスのパパさんは「価値という押しつけがましいものはすべて壊したので」私にも「しまおう」と勧誘の表現を使っているのですか?
3)「「壊すこと、相対化することが、「無垢なる絶対善」であって、ある種の「価値value」を認め、関与することは、自分の手を汚すことだ。そういうお考えもあるのではありますまいか。であれば、こちらの方 が深刻でしょう。」「そういうお考えもあるのでは、、」とお尋ねになり、それが「こちらの方が深刻でしょう」にかかる文脈がよくわかりませんでした。「ありますまいか?」というお尋ね、仮定?のうえにもしその仮定が正しいとすると「こちらの方が深刻でしょう」という意味ですか?とするなら「ある種の価値を認め関与すること」は私にとって「深刻(な問題)でしょう。」という意味ですか?
4)「ある種の価値」とはアレックスのパパさんが私に対して想定したアメリカ感のことでしょうか?
5)「非難をしているのではありません。それでは、この複雑な世の中で、自分の一貫性を保ちながら後悔のない人生を送る上で、不便この上ないのではないでしょうか?」「それでは、この複雑な、、」の「それ」とは「(アレックスのパパさんが想定した私のアメリカ感)では、、不便この上ない。」と言う意味ですか?
6)「非難をしているのではありません。」と書いているが、アレックスのパパさんが使う「非難」とはどういう意味ですか?私の理解ではアレックスのパパさんが述べたことは「私に説法を説いたり生き方を変えろなどといっているのではない。アレックスのパパさんのような考え方もあるから参考にして。」という意味でしょうか?しかし全体の文面から「参考にして」という印象は感じられないのですが?
7)「日本語が弱くなっています。」とのことですが、アレックスのパパさんの文章を即座に理解できない私は「日本語が弱」いのでしょうか?
8)アレックスのパパさんは日本語が強いのでしょうか?
れいなさん>そうですか、アメリカのしかも軍人の方の意見が聞けてうれしいです。「アメリカ万歳」的な印象が感じられなかった映画だったものですから。その点に関してはあなたとその周りの人たち印象を同じくしたようです。時々この方のようなアメリカで「実地に携わっている人」の意見を聞きたいものです。アメリカの映画をみる機会が多いし。