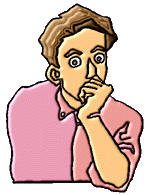- 管理責任者
2015年改定で規格から「管理責任者」というものがなくなった。
幸いなことである。というのはISO9001初版が制定された1987年以降、ISO9001でもISO14001でも、それがいかなるものなのかたびたび議論になった。議論になったのはそれが「いかなるものか、あいまいだった」からだが、そもそもの原因は翻訳がまずかったからだと思う。- 日本で管理責任者という語が使われているのは、下記の10本の法律である。
- 文化財保護法
「管理責任者」が定義されている - 廃棄物処理法
「特別管理産業廃棄物管理責任者」が定義されている - 電気通信事業法
一般語として「管理する責任者」とある - 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
「雇用管理責任者」が定義されている - 銃砲刀剣類所持等取締法
「銃砲の管理責任者」が定義されている - と畜場法
「衛生管理責任者」が定義されている - 建設業法
一般語の「経営業務の管理責任者」とある - 国家公務員宿舎法
一般語として「官署の管理責任者」とある - 船員法
一般語として「検査業務の専任の管理責任者を選任」とある - 船舶安全法
一般語として「検査業務の専任の管理責任者を選任」とある
但し下記の法律に書かれた管理責任者を引用している法律を除く。法律で頭に何もつかない「管理責任者」が定義されているのは文化財保護法ひとつだけで、それは我々にはまったくなじみがないものである。環境担当者が知っているのは「特別管理産業廃棄物管理責任者」だけだろう。これは職階としては担当者であり、ISO規格が求めていたような業務ではない。
 「衛生管理者」はなじみがあるが、「衛生管理責任者」は我々には無縁だ。これは家畜を
「衛生管理者」はなじみがあるが、「衛生管理責任者」は我々には無縁だ。これは家畜を屠殺 する場所の衛生管理の責任者なのだそうだ。企業のISO担当者の中には、審査を受けるのが屠殺場に引かれる思いの方もいるのではなかろうか。
そこは気持ちを強く持って、メインイベントに登場するチャンピオンのつもりになろう。あなたの行く手には勝利が待っている。話がそれた。
とにかく我々になじみのある法令では、管理責任者なんて語句が使われていない。
だからISO規格…正確にはJIS規格に「管理責任者」が登場したとき、それがどのような職階なのか、業務なのかを想像することができなかったのは当然だ。
というか、法律でも見かけない「管理責任者」という語をひねり出したのは、いったいどういう風の吹き回しだったのか? それが疑問だ。そもそも管理責任者の原語はmanagement representativeである。直訳すると「経営層の代表」とか「経営層の代理者」になる。その言葉からは社長あるいは執行役をイメージするかもしれない。それがどうして「管理責任者」という和訳になるのか、非常に不思議だ。「管理責任者」と聞けば、ロッカールームの管理責任者か、危険物貯蔵所の管理責任者を思い浮かべるかもしれないが、社長とか執行役は普通は思い浮かべないだろう。
「management」は「管理」と思う人もいるだろうが「representative」が「責任者」でないのは間違いない。
単純になにごとかの責任者ならperson in charge/responsible person(担当者)、ロッカールームの責任者ならcare taker(管理人)とかjanitor(用務員)か?- 英英辞典を引くと英米ではmanagement representative は経営関係では熟語として使われるらしい。U.S.A.のGoogleではこんな解説があった。
「トップマネジメントに任命されて、担当する業務の運用、評価、改善を図り、トップマネジメントに報告する」
これは単なる責任者ではなく、事業部長とか工場長のイメージだろう。担当者でないのはもちろん課長クラスでもない。ご存じだろうが、普通、辞令は上司の上司からもらう。課長なら部長ではなくその上、まあ工場長か?
トップマネジメントといっても会社によっていろいろだろうが、仮に執行役(執行役員でなく)から辞令をもらうなら、工場長レベル、つまり部長の上以上だろう。暇に飽かせて英英辞典とかGoogleを見ているとmanagement representativeに関するチャットとかQ&Aなどがいろいろ見つかる。
- 面白い定義(?)がある。
「監査員に同行し監査員から宿題を出され是正する役目の人」
これはISO対応で考えたようなかなり自虐的な定義だね。
- U.S.A.の品質保証のフォーラムのQ&Aに次のようなものがあった。
Q:Standard Requirement states, appoint member of management who, irrespective of other responsibilities.(ISO9001:2008 5.5.2)
Can anyone elaborate and define?
規格は「組織の管理者層の中から、与えられている他の責任とかかわりなく、管理責任者を任命しなければならない」と要求している。
誰かこの意味教えてください。
(和文はおばQ訳。「」内はJIS9001:2008を引用した)A:It means that this member of management can have responsibilities other than being a management representative. In other words: being a management representative does not have to be this person's sole responsibility.
それは、この経営層のメンバーが担当している以外の責任を持つことができることを意味します。 言い換えれば、管理責任者であることは、専任である必要はありません。このQ&Aからは、英文の意味は、管理責任者が兼務できないという理屈は間違いのようだ。
任命対象の「member of management」が経営層なのか、管理者層なのか、どうなのか?
これは参考になった。
まずアメリカでもirrespective of other responsibilitiesということに疑問を持つ人がいるということだ。
でも疑問は解消する。兼務ガー、社長ハー、担当者デモー、そんな悩みはもう無用です。
もっと詳しくはこちらを参照ください。
外資社員様からコメントをいただきました。是非お読みください。
- 文化財保護法
- 環境
- ISO14001で「環境」の定義は
- 1996年版
大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの - 2004年版/2015年版
大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの
と変遷があった。
まずひっかかったのは、「水」と「水質」は違うのか?
「ISO14001:2004要求事項の解説」という本で、ISO14001の最高権威 寺田さんが「この場合のwaterは媒体としての水を指している」と書いている。
「媒体」という言葉から推察すると、汚染物質を含んだ水とか冷却水(熱交換)とか化学反応の溶媒を意味するのか?
では「媒体」でない水とは何だ? 飲用水とか防火用水などは、水そのものが主役だから媒体とは思えない。となるとそれらは水に入らないのか 😃
「媒体」の対義語は何だろうと考えると「本質」なのか「本体」なのか? 英語で「media」の対義語ならempty(無)、divest(割り当て)、liability(負債)、ちょっとピンとこない。
よくわからん?
ISO14001の対象は一般的な水でなく、特定用途あるいは特定性質の水をいうのだというなら、あいまいを回避するために、「○○の用途に用いられる水」「不純物○○mg/m3以上/以下」とか「○○を含有する水」など対象を明確に示すべきだ。
こんな言い訳は無責任だ。そもそも英語が改定されていないのに、「water」の翻訳を「水質」から「水」に変える意味があったとは思えない。改定したトリガはなんだ? ISO14001認証企業にアンケートでも取ったのか(反語だよ)。
意味のないことをしてはワシは怒るぞ!もっと本質的なことだが、定義を見ると「人およびそれらの相互関係を含む」のだから、職場の人間関係も入ることは間違いない。規格本文を読むと環境はフィジカルのものに限られるような気もするが、メンタルなものを想定しても矛盾はない。
そもそも職場環境というと、現代では空調とか照明ではなく、人間関係の意味でつかわれることが普通だ。ブラックだ、パワハラだ、うつの人がいる、そんなイメージですよね。ISO14001でパワハラ、セクハラ、コミュニケーションの改善をすべきなんでしょうか?
更に「組織の活動をとりまくもの」なのだから、審査の際の審査員も環境に含むことに異存はない。すると審査が環境側面になる。一般企業において認証機関/審査員あるいは取引企業との関係を、環境側面に含めたところはないと思う。だがトラブルになることは多い。
ここはひとつはっきりしてもらいたい。組織の活動をとりまくものを考えると、売り掛けの回収とか、採用なども入りそうだ。えっと「環境」の定義を正しく理解すると、環境マネジメントシステムではなく、包括的なマネジメントシステムになってしまう。ということは環境だけ切り取るということはそもそも無理ということになるのか?
ひょっとして現在ISO14001の認証企業は、すべて事業とか人間関係の環境側面を見逃しているのではなかろうか?
それとも環境の定義が間違っているのか? 私はそんな気がする。
 いや、映画って本当に面白い……失礼、環境マネジメントシステムって本当に面白い……いやいやおかしいでしょう。
いや、映画って本当に面白い……失礼、環境マネジメントシステムって本当に面白い……いやいやおかしいでしょう。
- 1996年版
- 継続的改善
これは翻訳がおかしい。継続的とは国語辞典を引くと- 前から行っていることをそのまま続けること。また、そのまま続くこと。
- 以前からのことを受け継ぐこと。継承。
継続的の原語はcontinualで、英英辞典を引くとcontinual 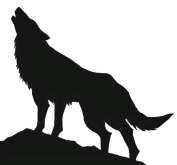 継続的あるいは定期的に何度も発生すること。
継続的あるいは定期的に何度も発生すること。
オオカミが一晩中吠えているような状況。continuous  時間が経過しても中断せずに継続すること。
時間が経過しても中断せずに継続すること。
コンピュータの冷却ファンがずっと音をだしているような状況。concontinual は継続的じゃない。継続的改善と翻訳したのは間違いです。断続的改善と訳すべきでした。
なことどうでもいいだろうって?
どうでも良くありません。審査を受ける企業にとっては大きな問題です。環境方針で「工場省エネ、廃棄物削減、省エネ設計」に努めますとあると、今年の計画に廃棄物削減がないと不適合にされてしまうのです。
規格の「continual improvement」の意味は、断続はあっても改善を進めていくという意味なのです。ですから今年は工場省エネ推進、来年は廃棄物削減、次は省エネ設計推進という活動でも完璧に適合です。
ところが継続的改善では、絶え間ない改善をしなければならないのです。今年も来年もその次も、工場省エネ、廃棄物削減、省エネ設計すべてを推進しないとペケです。
2015年改定で定義が「recurring activity」が「recurring process」に代わりましたが、継続か断続かについては翻訳も変わってないし注記もありません。
審査員が日本語訳でなく英文で審査をするのを期待するだけです。私の経験では半々でしたね、
こちらもご参考に
・継続的改善とは
・継続的改善
- 環境側面
初版のときから環境側面とは、漢字からは想像がつかないものだった。まずaspectに側面を当てたのがまずかったのではなかろうか。これは誤訳ではないが、悪訳であったのは間違いない。
香川照之なんて悪役が似合う俳優だったけど、最近は良い人ばかり演じていてつまらない。あっ、役違いだ!
現在でも真に側面を理解している審査員やコンサルは少ないように思う。
俺は環境側面じゃない
だって丸いんだもん
私は「白熱電球を蛍光灯電球に変えることは有益な環境側面です」とか「省エネ活動は有益な環境側面です」と語る、数多くの審査員やコンサルに会った。彼らは今「蛍光灯電球をLED電球に変えることは有益な環境側面です」と語っているのだろうか?
注:プラスの環境側面という人もいる。
自分が話していることの矛盾に気づかないのだから、アホというしかない。だから有益な環境側面を語る人はみなアホである。
その原因は環境側面という言葉が不適切だからだ。だが今となっては絶対に翻訳語を変えることはないだろう。
老婆心ながら
このウェブサイトをご訪問された方々は上記を読んで、アハハハと笑っていると思うが、訳が分からない人がいるかもしれない。そんな人たちのために説明する。
白熱電球を蛍光灯電球に交換することはズバリ省エネ活動です。いいですか「活動」です。環境側面ではありません。
エネルギーあるいは電気の使用という環境側面についての改善活動なのです。ゼーッタイ環境側面じゃありません。
当然ですが有益な環境側面なんか間違ってもありません。
口で有益な環境側面があると語るのは録音でもしてなければ後に残りませんが、書籍に書いて出版している有名な審査員やコンサルもいる。一生恥を背負って生きてください。有益な環境側面を語る人に限らず、環境側面とは何かを理解していない人が多すぎます。その原因はやはり環境側面という翻訳がまずかったと私は断じる。
じゃあ、どう言えば良いのかとなれば、単純だ。「環境と相互に作用する,又は相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素」と現行の定義をそのまま用語としたらよかった。
長すぎというなら、環境アスペクトといえばよかったじゃないか 自分に都合の良いときはカタカナ、都合が悪いときは漢字か?
自分に都合の良いときはカタカナ、都合が悪いときは漢字か?
解説すれば長くなるのでこちらを見てください。
・環境側面はいまだ誤訳なり
・環境側面の誤訳
・有益な環境側面(2018年調査結果)
 ISO14001の基本である環境側面を理解せずに審査員やコンサルをしようなんて、100年早いとしか言いようがない。言いようがないのだが、そういう審査員やコンサルがザクザクいるのが信じられない。
ISO14001の基本である環境側面を理解せずに審査員やコンサルをしようなんて、100年早いとしか言いようがない。言いようがないのだが、そういう審査員やコンサルがザクザクいるのが信じられない。
聞くところによると審査員研修機関の講師でさえ「有益な環境側面」を語っているというじゃありませんか。世も末というのでしょう。
- 環境パフォーマンス
「環境パフォーマンス」は初版から定義されているが、その定義は改定のたびに転々とした。転々したのはともかく、どう変わったのだろう?- 1996年版
自らの環境方針、目的及び目標に基づいて、組織が行う環境側面の管理に関する、環境マネジメントシステムの測定可能な結果 - 2004年版
組織の環境側面についてのその組織のマネジメントの測定可能な結果 - 2015年版
環境側面のマネジメントに関連するパフォーマンス
注:内容については、和訳は英文通りで違いはない。
各版の定義を並べただけで、まじめに考える気が失せたのは私だけだろうか?
だって「マネジメントシステムの結果」と「マネジメントの結果」は同じ意味なのか? 同じならマネジメントとマネジメントシステムがイコールであり、ISO規格のすべてのmanagement systemをmanagementに置換しても問題なく、その逆もOKのはずだ。こんなことを世界中から集まった、いい歳をしたおじいさんたちが議論したのかと思うと……
おっと、寺田さんは前出の2004年改定の解説本で、パフォーマンスの定義を決めるには種々事情があって妥協の産物だと書いている。
だがそんなことは関係ない。結果がすべてだ。妥協したからちょっと変なんですよとか、事情があったので我慢してくださいというのは通用しない。
ISO審査で「弊社にも事情がありましてね」なんて通用すると思っているのか?
真面目にやれとしか言いようがない。I refuse it! - 1996年版