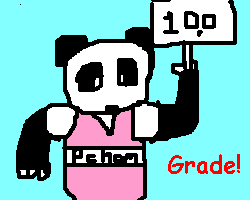
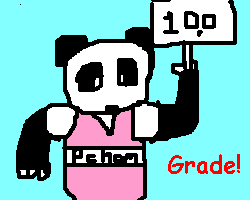
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』、
10月11日までの採点は『プライベート・ライアン(3)』、
10月14日までの採点は『プライベート・ライアン(4)』、
10月25日までの採点は『プライベート・ライアン(5)』、
10月28日までの採点は『プライベート・ライアン(6)』、
10月30日までの採点は『プライベート・ライアン(7)』、
11月2日までの採点は『プライベート・ライアン(8)』、
11月5日までの採点は『プライベート・ライアン(9)』
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
アレックスのパパ(11月13日)
dimsum@eclipse.net
◆パンちゃん:reina(11月10日)
貴重な場をありがとうございます。
日記でも書かれていた、「実際のアメリカ人」を知ること。確かに大きな要素なのかも知れませんが、「映画」はその代わりを果たすものでしょう。「映画」を通じて生きたアメリカ文化を、その善し悪しのどちらも含めて世界中に発信されている。それを楽しみ、こうして日本語で話し合うこと。とても大切なことに思います。
◆灘かもめさん:
「二度目を観た自分に会いたい」、そう言われていましたが、もう三回になったのですね。美しい日本語で、そして大切な発見を教えて下さいました。ありがとうございます。
◆ドットさん:
論理と感情の分離をと主張していながら、小生の主張にも強い感情が交じりがちです。そして、ドットさん、あなたのコメントにも、確かにあなたなりの論理と感情の混ぜ方があります。この両者が噛み合わなくなると、折角の議論がお互いへの影響という生産の効果ではなく、貧しい防御と醜い攻撃の言葉へと転落してしまいます。
少しその危険を感じていますので、そろそろ区切りをつけてみたいと思います。
特に朝鮮戦争の真因を巡って罵り会うのは、この場ではばかげています。何千字を費やしても、言えば言うほど人間の愚かしさに突き当たるだけです。
但し、先のコメントでお尋ねの内容には、少しコメントさせていただきます。
>しかしそれでも私の解釈では「反米意識を煽るマスコミや政治家はいるが、日本政府
>はそれにもかかわらず、アメリカの言いなりであることが多い。」となります。
そうでしょうか?貿易問題での数値目標などの、「霞ヶ関の既得権益」を守る内容(悪しき外圧)はホイホイ受け入れる癖に、自由な市場や機会の均等はいつまでもこれを受けれない。それが現在の日本社会の低迷の原因だと思います。
>アメリカは朝鮮の人のために戦ってくれたのかなぁ、それよりもアメリカの定義する
>社会主義、共産主義が侵出するのを恐れていたから戦ったのではないかなぁ。
どちらでも同じでしょう。歴史は、労働者を神格化するウラで一部の人間が権力を握り、統制経済の結果、貨幣のシステムを崩壊させた20世紀の社会主義の敗北を語っています。別に「歴史の終わり」だと言って、その冷戦の終結を手放しで喜ぶつもりはありません。現在も市場経済や通貨システム、資源の利用や環境問題と国家の枠組みなど、深刻な課題は山積しています。
但し、申し上げたいのは、冷戦の時代に逆戻りして「西側」にアジアの自尊心への侮蔑があり、「社会主義」にその美しい自尊心があったと信じられた時代に戻っても何にもならないということなのです。
>しかしついさっきまで国全体が倒産寸前だったのはなぜか?
韓国の危機は深刻でした。自国通貨への不信任、弱小財閥を巻き込んだ過剰投資、日本以上に脆弱で前近代的な土地本位の与信システムが、国家ベースでのキャッシュフローを窒息寸前に追い込んだのですから。
けれども、現大統領の施策は、抜本的なもので、既に失業率の頭打ちなど、本当に効果を上げています。日本の政策担当者も、馬鹿にしないで学んでみる価値があると思いますよ。
>見た目は立派だが屋台骨のぐらついた高層ビル、
三豊百貨店ビルの倒壊、聖水大橋の自壊などをご存知なので、そう見えるのでしょう。けれども、事故の後の徹底的な責任追及と原因究明の為、現在は自体は改善しています。あまり先入観でご覧にならないで下さい。
>粗悪な電化製品、
そうでしょうか?価格と品質を考えた場合、韓国の電子産業の競争力は、日本を越えた部分が多くあります。iMacに採用された15インチのディスプレイ、三星やLGの液晶、メモリなど、世界のトップクラスです。
実際の民生用家電にしても、ソウル旧市街のロッテ・デパートをご覧になったり、テレビのコマーシャルでお分かりになると思いますが、出回っている製品の品質は、日本と変わりませんよ。
>外国車はほとんど走ってないのにすさんだ国産車産業。
外国車ね。あれは「規制」してるんです。入れないように。但し、OECD加盟以来日本と同じように規制緩和を進めていますよ。業界自体が荒れているのは事実ですし起亜のように倒れるところも出てきました。けれども、現代と大宇はアメリカ市場でもウォン安を武器に戦っています。
>経済の発展という意味では、かなりの重症だと思った。
確かに昨年秋以来、本当に苦しんでいますね。けれども、日本のように「豊かになりきって、自分たちの生き方を変えられない」ところに行く少し前に、大きな問題に直面し、否が応でも社会を変えなくてはならなくなった。そして、今のところ、苦しみながらも、その方向性を信じて「変化」をしようとしている。そのことは立派なことだと思うのです。それが「正しさ」と言う意味です。
どうぞ、折角観光に行かれるのなら、地元の人たちとの意見交換などを通じて、生きた社会を経験することをお勧めします。
>ベトナムは奇跡を必要とせず着実にいろんな意味で発展するでしょう。あの国にはそ
>の強さと賢さがある。蛇足ですが「ホーチーミン」は私の最も尊敬する政治家です。
確かにそうですね。ハノイのホーチミン廟のそばに、今でも彼の書斎が残されています。共産党の幹部の人が説明してくれたのですが、「ホーおじさんには、多くの蔵書はない。少ないが真に大切な本を何度も何度も読んで、思想を深めた。」そう説明してくれました。指導者の生き方、そして伝説の守り方として立派です。
ベトナムは、タイ、インドネシアの低迷が響いて、当初描いた成長スピードには乗れていませんが、自分で輝いてゆくでしょう。
>「もしフセインが勝ったら、石油の値段があがって先進国の経済にダメージを与え
>る。それでもいいのか。」確かに、家計が苦しくなる。いやだなぁ。しかしもしそれ
>で人が死ななくて済むなら、平和に解決できるのなら多少の辛酸は我慢しましょうと
>私は言う。
では、毒ガスに追われたクルド人はどうなるのですか?国を失ったクウェートは?スカッド・ミサイルで脅されながらも自制したイスラエルは?
別に絶対の「正しさ」なんてないんです。でも、血塗られていてもこの現実というものがある。
「サダムが悪だから」だなんて、誰も言ってません。「俺たちが困るから」に変わりはありませんよ。
>「ソマリアは失敗でした。」とのことです。もうそれで私は納得しました。
そう簡単に納得しないで下さい。作戦として失敗し、局地的な人心掌握にも効果が弱かった。そう言っているだけです。
それでは、アフリカの部族抗争で大勢の人々が死んで行くのに、「あれは勝手にやっているだけだ」と傍観するのが良いのでしょうか?過去に冷戦を口実に、双方が武器を売って商売をした。その罪は重いです(東西両陣営とも)。ただ、傍観が正しいとは言えない。実に苦い教訓なのです。
>キング牧師とマルコムXについて
>もう疲れた、我慢できない、100年たってもかわんねー、それじゃ黒人だけの世界を
>作ろう。どちらかというと私はこの考え方に共感できる。そういう意味です。現実的
>かどうか、受け入れられたかどうか、正しいかどうか(誰にとって)、それは私には
>わからない。でも共感するかしないかこの点に関してはキング牧師も評価はするもの
>の、マルコムXに傾いている。
済みません。何の情緒も論理も共有できませんでした。
>ドイツと日本の賠償金について
>なぜ1ドル360円だったのか?
様々な理由があります。が、戦後の日本が基礎的な産業の競争力をつけるために、このレートが、輸出産業にとって有利だったのは事実です。
>なぜアメリカの製品をあんなに買ったのか?
貿易の均衡は、日本の輸出超過、アメリカの輸入超過となって久しいものがあります。戦後、日本経済が脆弱な際に、米国製品の購入を押しつけられ、その為に、外貨の流出や、自国産業の弱体化が起こったとは言えないでしょう。
>なぜ日本はアメリカの政策に大抵同調するのか?
>以上賠償金どころの話じゃないですね。
経済の国際化とナショナリズムを混同されていますね。経済には、とりわけ経済成長には「双方に取ってメリット」のある話があるのです。
確かに、米国に取って、債券市場や投信市場に日本の資金が流入していることは、市場として歓迎すべきことでしょう。けれども、それを「賠償金」云々はおかしいと思いますよ。では、製造業を中心として稼いだ日本の国富はどこへ行けば良かったのでしょうか?日本国内では、土地をベースにしたマネーゲームが破綻し、人件費の高騰で「中程度」以下の付加価値産業が海外流出し、教育の失敗で「高付加価値」を生み出すような新しい産業が育っていません。当座のマネーはドルに向かうのは自然でしょう。それが全てアメリカの陰謀とは思えません。
内容が映画とずいぶん離れてしまいました。
そして、自分も含めて、灘さんが丁寧に映画をご覧になって語られているような「大切なこと」から議論が離れつつあるような気がしています。
◆ドットさん:
この続きは、別のアメリカ映画を「丁寧に」観て語ることで、角度を変えてやってゆくというのでどうでしょう。
灘かもめさん--3回も見たなんてすごい!見ているときはそう気にも止めなかったンですが、ライベンがライアンの横顔を見て納得するのは「こいつも自分と同じような人間なんだ」そして「こいつを守ることが自分の任務なのだ」ということを認識したのではないでしょうか。こいつだけ国へ帰るなんて許せないと考えていたのが、一緒に戦場に立って、こいつだけでも帰してやりたいという気持ちに変わったんだと思います。あと、回想シーンがなかったのは素晴しいことに気付きましたね!これは、兵士達が昔を思い出そうとしても本当に感情までその昔に浸ることができなかったことを表現しているのでは?思い出してもそれは一瞬のことに過ぎず、すべてを忘れて回想している暇がなかったことを表わしているんだと思います。映画ができ終わったあとで、あれはこういう意味だああいう意味だというのは簡単だけど、最初にこうしようと思いついたスピルバーグはやっぱり偉い!灘かもめ(11月9日)
ごめんなさい、しつこいのは分かってます、でも書かせて・・。ドット(11月8日)
三回目、観てまいりました。
今回、自分のなかで、何点か変化がありました。
なんと!最期のテロップが流れると同時に、大泣きしてしまったのです。
1、2回とも、うるうる程度はしたけれど、ハンカチで目を覆って、顔も上げられず、しゃくってしまったのは初めて。自分でも、とてもびっくりしました。
なぜかはわからない。ちょっと、今はまだ自己分析したくない。
(心のどこかを、強く揺さ振られたような。)
(たくさん与えられて、たくさん奪われたような。)
今まで私は、ライベン二等兵をあんまり意識して追っ掛けてませんでした。
(アパムの変化の方が(比較的)分かりやすかったし。)
でも、今回は彼について、たくさん見落としてたなーと思ってしまった。
ライベンは、始めっから「ライアン救出」の任務がイヤだった。ミラー大尉に最初に文句を言ったのも彼。「計算が合わない・・」云々。
それでも、納得したふりができたのは、ミラー大尉を信頼しているから。
「中隊長も納得していないけど、上官の命令でしかたなくやってるんだ」から自分もそうしなきゃ、と。
それが、どんどん崩れていく。
途中で、仲間が死んでいく。中隊長も、言動がヘンになってきた。仲間を殺したドイツ兵は生きながらえる。「計算が合わない」。
ライベンは、これもみんな「ライアン二等兵」のせいだと思う。
そして、爆発。「営倉にぶちこまれても」いい、とまで思う。
憎い「ライアン」。
けれど、橋での攻防戦のさなか、「ライアン二等兵」にぴったりくっついて守ったのは彼なんだなぁ。タイガー戦車が迫ってくる直前、瓦礫のかげにライベン、ライアン、ミラーの三人が並ぶ瞬間がある。その時、ライベンがライアンの横顔をじいっと見つめる。
気付いて振り向くライアンの視線の先に、ライベンの顔が映し出される。
なんだか、静かな、納得したような顔だった。
どう納得したのかは・・ちょっと、わからない。もう一ぺんぐらい観ないと(笑)。
とにかく、この瞬間でライベンが「この任務を全うしよう」と腹が決まったのは 間違いないと思う。作戦遂行に忙しく立ち回るミラーに替わって、ライベンが、 彼を守った。(今、思ったけど、この攻防戦では、ミラー自ら動いてますねぇ。それまでの戦闘ではGO!GO!って部下を追い立ててたのに。)
ライベンの受け取ったカパーゾの手紙、彼もまた、だれに言われる迄もなく、手紙を ミラーの胸ポケットから取り出したのです。
カパーゾの手紙は、ちゃんと父親のもとに届いたのだろうか。
「思い」を伝え、届ける。「継承」「後継」とは、「後続」とは違う、という言葉を 思い出しました。「後に続く」のではなく、「後を継ぐ」のだと。
ライベン君、ごめんなさい。今まで気付きませんでした。あなたの役割に。
それもこれも、スピルバーグの突き放した演出のせいだぁ。(と、監督のせいにする)
これも、三回目で気付いたことですが、作品中、回想シーンが一切ない!
それぞれが、思い出を語る場面はたくさんあるけど、すべて言葉のみ。
映画ならば、いくらでも映像が入れられるのに・・。現場のスローモーション以外、 イメージ的な映像は出てこないのです。「アミスタッド」ですら、シンケの妻の イメージが映像として登場したのに。
これは、絶対意味がある。と思うのですが、どうでしょう。回想としての映像を入れることによって、「この人物は、今こう思っている」とか、「この場面はこう捉えるべきだ」としてしまわないための方法だったのでは?
(余談ですが、最近の(とくに民放)ドキュメンタリー風の番組って、どうしてあんなにナレーターがよく説明しちゃうんでしょう。緊張した人物をUPで写しながら、 「彼の表情に緊張が走る」なんて、語るんですよね。見れば分かりますって。)
あくまでも、兵士の側から描いた戦争、当事者と同じくらい悩んでくれ、と監督が言ってるみたいです。
もうひとつ、私にとっての変化と言えば。
始めは、ノルマンディー戦が一番こわかった。
でも、三回目、とてもラクな気持ちでこの30分を過ごしてしまいました。
あぁ〜〜、とうとう私も慣れてしまったのかぁー!!
・・・と、かなりショック・・でした。
ところが、ところが!!最期の戦闘が、恐くて恐くて・・。マジで固まってました。
同じ三回目なのに、ノルマンディーは慣れて、橋での戦闘に恐怖を感じるなんて!!
一体どーゆーこと!?
思うに、それは、後者が全くの接近戦だったから。
そして、大好きな彼らが次々死んでいくから。
お互い、弾が尽き、向かい合ってナイフを突き付ける。相手にライフルを投げ付け、 ヘルメットまで投げ、拳銃で至近距離で撃ち合う。
くっつき爆弾をもったまま、爆発してしまった味方の兵士もいた。
ついさっきまで、静かにレコードを聴いてたのに・・。
飛行機の出現で、ようやく緊張が解けました。
ほんの少しだけ、ミラーの気持ちに触れたような気がする。
あぁ、「天使」かぁ・・・。(ちょっと涙・・)
ところで、肝心のライアン君。
今までの私の感想のなかに、あまり彼に対する感想がないことに気が付きました。
なんか、あるはず・・と思って、いろいろ考えましたが、・・・ない。
おかしいなぁ、どうしてなにもないんだろう。
救出部隊はこんなにも鮮明に出てくるのに。
そのうち、出てくるのを待ちましょう。
PANちゃん、いつも載せてくれてありがとうございます。あなたの日記の文章はわたしくしの思考の鮮度を保つのにもってこいです。アレックスのパパ(11月6日) dimsum@eclipse.net
このページを開いて私の文章を読んでしまったみなさん、「プライベートライアン」じゃないのか?なんじゃこりゃと思われても仕方ありませんが、許してね。
アレックスのパパさん、ご返事ありがとうございます。箇条書きにしてちょっと整理してみましょう。
1)グットウィルハンティングについて
この映画について感心したのは、精神療法についてよく調べてあること、虐待を受けた子どもが立ち直っていく姿がわかりやすく描いてあること、ストーリがそれなりにおもしろかったことなどです。これらを受けてアメリカはときどきこうした映画が作れるよなとやや感心しました。上の世代の映画人が若い人を引き立てたことが事実であるなら、確かにそれもアメリカ文化の一部としてすばらしいことだと思う。「主権国家アメリカ合衆国」とは切り離して考えていただきたいとのことです。切り離して考えるように努力しますが、論理としてはそれが正しいことは解っていますが、アメリカの政策の一部が私にとって目に余るのでときどき「理念としてのアメリカ」まで否定したくなると書きました。アメリカ文化の中に、大衆の中にすばらしいものがあるのはわかっています。それを取り入れなければならないこともわかっています。つまり「理念としてのアメリカ(私の解釈では文化に限らず科学的な発見、学問の先進国、他にもあるけど今思いつかない、等も含む)」の一部は認めそれを吸収するべきであるが、「対外的な政策の一部」については疑問を感じる、さらにそれが大勢の人の生き死ににかかわることなので憤りを覚え、「それでもアメリカ文化の一部はすばらしいよ。」と寛容な気持ちでいることが時々不可能になる、というのが私の意見です。アレックスのパパさんの意見を私なりにまとめますと「時々失政はあるけど、理念としてのアメリカのすばらしさはもちろんのこと、主権国家としてのアメリカもすばらしいものがあるのだからそれを解っていただきたい。」ということでしょうね。
2)「日本人の、あるいは日本のマスコミにある、「思いこみの反米意識」のために、日本が損をしている。」ことについて
日本のマスコミが反米意識を煽っているために日本が損をしているということですね。例えば久米宏さんのごとくをいうのでしょうね。あるいは立場は違うけど、「NOといえる日本」だったかな、石原慎太郎のような人。マスコミが、どのくらいの割合のマスコミか解りませんが、反米意識を煽っていることは認めます。しかしそれでも私の解釈では「反米意識を煽るマスコミや政治家はいるが、日本政府はそれにもかかわらず、アメリカの言いなりであることが多い。」となります。これが日本にとって損になるのか得になるのか、ちょっと判断しかねる。何でもかんでもアメリカが先導しないとできないのかと感じる人もいるだろうし、アメリカが先導してくれるから日本は安心して未来に向かっていけるのだ、と言う人もいるし。私の中でまだ結論が出ていない。
そのあとにつながる「特に、日本の差別されている、女性、若い世代の立場が改善されずに損をしていると思っていました。」については、煽られた反米意識のために日本の女性や若い世代が損をしていると言うことだと思いますが、ちょっとよく理解できなかったのでコメントできません。
3)朝鮮戦争について
アレックスのパパさんによれば1)朝鮮戦争の最初の一撃は北側からであったこと=最初に始めたのは北である。仕掛けた方にまず責任がある。2)国連軍としてのアメリカの介入はある程度北から責められてからのこと≒それまでアメリカは待ったのである。平和的解決を模索していたから?3)多くの人が死んだけれどそれは戦争それ自体の宿命であり、南は北と比べておおいに発展し豊かになったではないか。以上の点からアメリカを中心とした国連軍の行動は失政とは言えない、ということでしょうね。1)と2)に関してはアメリカ側の理屈としてはもしかして納得できるかもしれない。ただ、国対国の戦争において個人的ケンカと同様の理屈がそのまま適応できるかは疑問です。中国や北の見解はどうなのだろうか?発展し豊かになったかは、北と比べてという意味では正解ですが、アメリカが守ってくれたおかげで私たちは発展できたと例えば今の南の大統領は考えているだろうか?もしご存じでしたら教えて下さい。
しかしながらまあ「失政であったかどうかは南北朝鮮の人が決めること」でしょうね。例えて言うと、アメリカ政府は日本への原爆投下について、戦争を早期に終結させるために必要だったとのべています。これはアメリカ政府側からみて失政ではないと言うことでしょう。(アメリカの国民はどうだろうか?)しかし落とされた側の日本人から「アメリカは戦争終結のためにすばらしいことをしてくれました。」などと言うだろうか?言う人もいるのかなぁ?竹村健一とか言いそうだなぁ。俺は言わないな。アメリカは朝鮮の人のために戦ってくれたのかなぁ、それよりもアメリカの定義する社会主義、共産主義が侵出するのを恐れていたから戦ったのではないかなぁ。
今の韓国が「正しさ」を乗せた国づくりをしているかどうか?確かに北と比べて豊かなことは事実です。しかしついさっきまで国全体が倒産寸前だったのはなぜか?本当に奇跡だったのか?実は最近韓国に観光旅行に行ってきました。この国がいわゆる先進国と呼ばれるのはずっとずっと遠い先のことだと思った。見た目は立派だが屋台骨のぐらついた高層ビル、粗悪な電化製品、外国車はほとんど走ってないのにすさんだ国産車産業。どこかの国の物まねと言うより「まねのそぶり」。ガイドが「日本とほとんど変わらないでしょ」というたびに悲しかった。経済の発展という意味では、かなりの重症だと思った。ただそれは韓国の人の幸せ度とはあまり関係ないかも。発展してなくても幸せだと感じられる国民はたくさんいるよね。韓国の人たちに「君たちは経済発展してないから不幸だ。」とは言えないのです。
以上から失政だったとは言えないとおっしゃるのはあくまでアメリカ側からみた視点ですよね。あるいはそれに組みする近隣諸国もそう言うのかな。私はアメリカ人ではないので少なくとも正しかったと積極的に感じることができないのですが。しかしそれとて朝鮮の人に押しつけることはできない、判断するのは彼らだと思うから。
4)ベトナム戦争について
ベトナム戦争については確かに失政でしたと書いておられる。まあその一言で私は納得しました。しかしながら朝鮮戦争とベトナム戦争においてアメリカの意図していたことは同じではなかったのか?すなわち「アメリカの想定する共産主義の打倒」。しかし一方は失政ではないと主張し一方では失政だとおっしゃる。なぜだろう?ベトナムは中国とさえも争わなくてはならなかった。なぜだろう?ベトナムは奇跡を必要とせず着実にいろんな意味で発展するでしょう。あの国にはその強さと賢さがある。蛇足ですが「ホーチーミン」は私の最も尊敬する政治家です。
アメリカの反戦運動家の話は知識として聴いておきます。失政のおかげで多くの人が死んだという事実の前ではさほどの説得力をもたない。日本の反戦運動家に関してはその人たちに「そのように」言って下さい。私に対する意見としては道理が合わない。
5)湾岸戦争について
「サダムフセインは悪者だ。」確かにね。しかしなぜ彼のような人が存在してしまったのか?アラブ地域の歴史について高校の教科書程度の知識があればわかるでしょう。詳しいことは忘れてしまったけれど。
サダムフセインの独裁を倒すため、戦争になったのだろうか?フセインが勝っていたら日本も結構打撃を受けたでしょうね。石油の値段が大分上がったろうし。
主たる思惑を隠すために何らかのスローガン、イメージが作られることがある。こういう言い方なら納得できる。「もしフセインが勝ったら、石油の値段があがって先進国の経済にダメージを与える。それでもいいのか。」確かに、家計が苦しくなる。いやだなぁ。しかしもしそれで人が死ななくて済むなら、平和に解決できるのなら多少の辛酸は我慢しましょうと私は言う。俺は我慢できないというならそれはそれで意見として成り立つ。サダムフセインの侵略が悪だから戦争が起こったと言うより侵略によって「俺たちが困るから」どーにかしよう、というのが正しいのでは?戦争が起こる時ってみんなをまとめるためにスローガンが必要になりますよね。それについては日本はかつて大変苦い経験をしたはずだから、ちょっと考えればからくりがわかると思うけど。
日本の立場は悲しいよね。お金もたくさんだしたのに。勝ってもまるで評価されない。
6)「ソマリアは失敗でした。」とのことです。もうそれで私は納得しました。あなたの立場としては「それでもアメリカを応援する」わけですよね。私の立場は「それだから「(特に政策に関する)現実のアメリカ」を応援しないわけです。
7)キング牧師とマルコムXについて
いやー話が長くなりますよ。いいですか?キング牧師を評価してないと言うわけではないのです。高校生の頃、夏休みの宿題で彼の簡略化された自伝の翻訳をさせられました。「I have a dream」も10回くらい聴きました。いずれも感動しました。体制へ認められた人物として何もかも切り捨てるというわけでもありません。私の解釈では彼は「アメリカ国内で差別する側と差別される側の融合」を目指していたと思います。
これに対してマルコムXは「黒人の独立」を目指していたと思われます。アフリカに行ってもうちょっと広い視野にたったようですが。無理矢理アメリカに輸送されて、差別され踏みにじられ(ここである一群の人たちがよく反論する手としては黒人をアフリカから引っ張ってきたのは黒人だと述べる戦法。しかしこれは支配者の常套手段なんですね。例えば南アフリカでは黒人を扱うのに白人側についた黒人を利用していた。しかしほんとに悪いのはやっぱり白人だ。普通そう考えるよね。)もう疲れた、我慢できない、100年たってもかわんねー、それじゃ黒人だけの世界を作ろう。どちらかというと私はこの考え方に共感できる。そういう意味です。現実的かどうか、受け入れられたかどうか、正しいかどうか(誰にとって)、それは私にはわからない。でも共感するかしないかこの点に関してはキング牧師も評価はするものの、マルコムXに傾いている。
8)ドイツと日本の賠償金について
賠償金の払い方の問題ですね。なぜ1ドル360円だったのか?なぜアメリカの製品をあんなに買ったのか?なぜ日本の学校の給食はアメリカ産の小麦粉を使ったパンだったのか?なぜ戦争が起こると日本が大枚をはたくのか?日本にあるアメリカの軍事基地、誰がお金を払っているのか?平和憲法のくせに当初の自衛隊はなぜ存在したか、そのお金は誰が払ったのか?今のアメリカのバブル経済は大本をたどると誰のお金なのか?(これは最近NHKのラジオでどこかの大学教授が話しているのを又聞きしたのですけど、日本の大量の円がアメリカにドルとして流れた(貸した?)らしいですね。)なぜ日本はアメリカの政策に大抵同調するのか?以上賠償金どころの話じゃないですね。
私の誤りを認めるとすればドイツがこのように間接的にじわじわと賠償金のようなものを払っていたのかどうか確認してなかったことですね。並列に並べてしまった。実際どうなのかな?
9)スピルバーグについて
「「反米的」=「主権国家アメリカの利益に反する」だから良い。ということでしょうか?」良いとか悪いとか私は書いてないし。反米的という言葉を、さほど意識して使ったわけではないし。まあ、あとから「いやこれこれはこういう意味で使いました。」とくっつけるのは道理に合わないし、なんとコメントしましょう。あなたのご意見はうかがいました。それでいいですか?
大変長くなりました。
最後に「日本だっていろいろ悪いことしてるじゃないか。日本に住んでいるおまえにそんなこという権利があるのか。」について。日本が悪いことしていた、いまもしているという事実は認めるけど、では日本に住む人はみな日本政府とあるいはかつての日本政府と同じ考えなのか?と問いたい。私は政府関係者でも政治家でもない。公人ではなく公人としての発言をしたわけでもなく、PANちゃんさんのご好意に甘えて発言しているただの個人です。意見を述べてはいけないですか?「けなしている」かな、まあそうとる熱心な愛国者もいるでしょう。
アレックスの文章を読むともの知りだなぁと感じます。またいろいろ教えて下さい。
◆ドット様:
お返事ありがとうございました。
何よりも、論点を絞って、明確に立場を述べて下さっている点に感謝致します。議論を深め、前へと進めてゆけるからです。
少し視点を変えてみましょう。
『グッド・ウィル・ハンティング』にあるアメリカの美点は認めても、尚、アメリカは「罪深い」とおっしゃいましたね。
これは、少し悲し過ぎます。あの映画に流れている思想は、当然、「国家」なんて糞くらえ(失礼)というものでしょう。小生の書き方が悪かったですね。あのお話は、「アメリカ文化」である前に、マットとベンという二人の若者の作品でしょう。特定の「国家」に対する好悪と関係させて語るのは不適切でした。
けれども、あのように無名の若者二人の脚本を、ロビン・ウィリアムスを始めとした、上の世代の映画人たちが、引き立てて行った経過。そして、何よりも、あのアメリカ英語の作り出す、饒舌ながら毅然とした対話の世界。これは「主権国家アメリカ合衆国」ではなく、「アメリカ文化圏」の強みでしょう。
小生の主旨は、その二つをどうぞ切り離して考えて頂きたい。どんなにアメリカの外交政策に反対であっても、それは別のものであって、切り離して評価できるものだと思うのです。
後は、個別の点についていくつか。
やはり、大勢の方が読む媒体(ですよね。パンちゃん。)ですから、明確にすべき点は明確にしておきたいのです。
意を尽くそうと推敲している間に、麗奈さんが先に尋ねて下さいました。主旨はほとんど同じで、そうなると議論を包囲することになるようですが、それは本意ではありません。
とにかく、正確な議論を続けたいと思うのです。それだけです。
小生は、日本人の、あるいは日本のマスコミにある、「思いこみの反米意識」のために、日本が損をしている。特に、日本の差別されている、女性、若い世代の立場が改善されずに損をしていると思っていました。
ドットさん。
あなたは、必要な冷静さと言葉を兼ね備えた方のようですから、どうぞ、もう少し議論を続けさせて下さい。
>朝鮮戦争がありながらベトナム戦争があり湾岸戦争があってクリントンはアフリカの
>どっか?にミサイルを打ち込む、のでしょうか?現実のアメリカのあまりの傲慢さに理
>念のアメリカまで否定したくなるのです。
朝鮮戦争の最初の一撃は北からでした。国連軍としてのアメリカの参戦は、韓国軍が、慶尚南道(釜山付近)以外の総てを金日成サイドに制圧された時点でのものでした。その後、仁川上陸作戦の成功の余勢を駆って、国連軍は鴨緑江まで攻め込みましたが、中国軍の本格介入を招いて、三十八度線の睨み合いに終わり、現在に至っています。その、どこが失政なのでしょうか。勿論、半島全体が戦火に苦しんだばかりか、一つの民族が、同胞相憎み合う、悲惨な歴史を長きに渡って固定化した。それは二十世紀の大きな不幸として次の世紀へと語り継ぐべきでしょう。けれども、アメリカを中心とした国連軍の行動を、失政とは言えないでしょう。この犠牲の上に「漢江(ハンガン)の奇跡」と呼ばれる、韓国の経済成長があり、金大統領がその上にアジア的ながら「正しさ」を乗せた国作りをしています。
ベトナムは、確かに失政でした。誤った反共思想とアジア人蔑視が原因と言うことはできるでしょう。けれども、もし、あの時「南」の政権に腐敗や圧政がなく自由主義経済の定着が図れたら、今頃「ドイモイ」などとは言わず、日本と同様の豊かな繁栄を実現していたかもしれません。失政との間は紙一重でありました。
そのことを知ってか知らずか、けれども、アメリカの反戦運動家の多くは、いや帰還兵でさえ、戦後に旧南ベトナムを中心に命からがら脱出をした、いわゆる「ボート・ピープル」に対して、丁寧な救援をしました。日本の反戦運動家で、同じ努力をした人がいるのでしょうか。限りなくゼロに近いのではないでしょうか。
「デザート・ストーム(砂漠の嵐)」に関しては、簡単な言葉では言い尽くせませんが軍事力による国境の侵犯、そして一つの国家を消滅させる行為に対して、では、サダムに対してどうすれば良かったのですか。
アメリカも傷ついています。けれども、苦しみ、悪者にされながらも、これを失政と言い切ることは出来ないでしょう。
ソマリアは失敗でした。それも苦いものでした。けれども、この「教訓」に従って、アメリカが、今、NATO地域での軍事プレゼンスを弱めれば、コソボの人たちは、もっともっと殺されて行くでしょう。
血塗られた、嫌な話です。
けれども、その血塗られた時代に私達は生きているのです。
私達自身の生活、それ自体も血塗られている。そう言って、自身を責めたり、現在の世界の秩序をニセモノと思う気持ちも分かります。
けれども、流された血を思う時、辛酸をなめた上の世代の記憶を思う時、現在ある相対的な平和も、その血の代償として大事にしなくてはならないのでしょう。
"Can you earn this?"
>キング牧師とマルコムXについていわせてもらうなら、マルコムXの方を尊敬します。マ
>ルコムX的な意味合いでの庶民の強みならかなりの程度信じます。
これはどういう意味でしょう。キング師が余り尊敬できないような書き方にも読めますが、だとしたらとても気になります。
残念ながら、アメリカでの人種差別は根絶されていません。その中で、キング師は、誕生日が祝日になったり(銀行は休んでも、証券業界は休まないようですが。)して、「美化」されているのがお気に召さないのでしょうか?
お気持ちが良く分かりません。亡くなった後とは言え、体制に「認められた」ことへの反発から、何もかもを偽善として切り捨てていたら、何も残らなくなると思うのです。歴史というのは、少しづつでも前へ進んで行くものなのです。まして、その為に命を失った先人のこと位、素直に理解して頂けないでしょうか?
それでも駄目だとおっしゃるのなら、やはり、それを詳しく説明して下さいませんか?
>ひとつ気になる表現があります。それは「なによりも「民主主義」を守った「神聖なる
>戦勝」とはプライベートライアンで描かれた「アメリカ、イギリス対ドイツ」の戦争の
>ことを指すのでしょうか?
そうです。そうですが、括弧つきで「神聖」と言っているのは、小生の意見ではないという意味です。括弧書きをすれば皮肉っぽく見える。これは昔の文学論などの、狭い世界での書き方でした。済みません。
>いずれにせよ、あの戦争は民主主義対独裁主義ではないと思う。植民地の取り合いの結
>果生まれた単なる国同士のケンカだと思う。
その通りです。けれども、同じ帝国主義でも、「遅れて来た」方は悪、そして、前から取っていた植民地も民族自決の精神で独立させる。その結果として、我々の戦後秩序というものがあるのです。そのことを、笑ったり、怒ったりすることは可能でしょう。ですが、訂正を求めることは不可能に近いものがあります。割り切って受け入れる勇気の方がはるかに生産的だと思います。
戦争犯罪人の裁判についても、そんなことが「絶対善」でないことは分かり切っています。「人道に対する罪」という言い方も、言葉として単純すぎます。
けれども、そこまでしても、憎しみを終わらせ、流血を終わらせなければなりませんでした。そして、とにかく、終わらせたのです。たとえ、憎しみを完全に溶かす作業は、より若い世代にゆだねられたにしても、です。
>それは戦後ドイツがどうなったか、日本がどうなったか考えれば解りますよね。ケンカ
>の敗者には重い罪が課せられました。「民主主義」の勝利の結果「民主主義」の枠の中
>で大衆から高い賠償金を効率よくとりました。
これは歴史的事実とは違います。第一次大戦後、戦敗国に過酷な賠償金を課して、経済を壊滅させたことが、次の大戦の原因となった教訓を踏まえて、第二次大戦後の日本とドイツには、特別な資金提供がされたのです。それが、両国の復興の原動力になりました。勿論、その背後に冷戦という血塗られた背景があったにせよ、この資金援助のことは否定できません。
>「(前略)、、、アメリカの在郷軍人会の、、、興行成績も、、」には同感ですね。た
>だ私はそれゆえスピルバーグは「反米的」という印象を持ちました。
「反米的」=「主権国家アメリカの利益に反する」だから良い。ということでしょうか?でも、そこまで国家にこだわって好悪感情を先に、論理を後にしていては、どうしても説明が弱くなります。
「国家と個人」、「主権国家と文化圏」、それをはっきりと分けることで明確になるもの。それはとても大切なことだと思うのです。