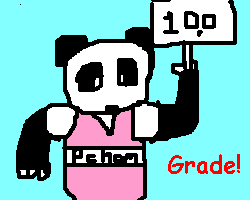
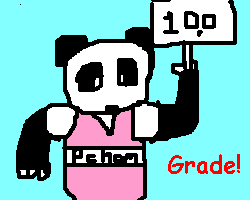
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』、
10月11日までの採点は『プライベート・ライアン(3)』、
10月14日までの採点は『プライベート・ライアン(4)』、
10月25日までの採点は『プライベート・ライアン(5)』、
10月28日までの採点は『プライベート・ライアン(6)』、
10月30日までの採点は『プライベート・ライアン(7)』、
11月2日までの採点は『プライベート・ライアン(8)』、
11月5日までの採点は『プライベート・ライアン(9)』、
11月13日までの採点は『プライベート・ライアン(10)』
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
ad(1999年8月18日)
nise@mail.adress.co.jp
戦争は、不条理に満ちている。ノルマンディ上陸作戦も、見方によったら単なる特攻。いはんや、世論操作のために名もなき2等兵を救出、をや。彼等を前線に残しておけば、戦争は2週間早く終わっていた。kaeru(1月23日)
そんな状況にもかかわらず、ミラー大尉は、ひたすら前向きに、為し得る最善を探し続ける。自らを推し進めるため、懸命に、不条理の中に意味を見い出そうとする。「ライアンを無事送り届けたことを、妻に誇りたい」・・・ささやかな願い。
その願いを踏みつぶすように、彼の眼前にタンクが現われる。ピストルを向ける彼。しかし、たとえ、銃弾がタンクの経絡秘孔を突きひでぶったとしても、彼の願いが叶う可能性は、無い。・・『瀕死』の彼。それでも彼は、彼にできる唯一の抵抗を続ける。
か細い銃声が、規則的に響きわたる。そして、虚しく空に抜ける。・・・「意味ないじゃん」と、茶髪女子コーセーが斜め前でつぶやく(注:泣き声)。そのとき、天使が降臨する。天使の出現は、奇跡でも、御都合主義でも、マンガでもない。彼が、毅然と、そして執拗にライアンを追い続けた、その足跡が、天使を導いたのだ。・・・・・と思いたい。
戦争は不条理だ。言うまでもない。不条理の中を前向きに生きぬいた幾多の意志の積み重ねの上に、僕達は在る。言うまでもない。・・・そう、不条理なのは戦争ばかりではない。僕達が向き合っている現実社会もまた、不条理に溢れている。困難に直面し、心の中の弱虫が疼きだす。「意味ないじゃん」と呟く。そんな時、ライアンは、自問したはずだ、「私は立派な人間か?」
以上が、前頭葉によって導き出された解釈です。以下は、雑感(つーか、本音)。
いくら「不条理の中の前向き」を際だたせるためとはいえ、例のシーンはむやみに長いし、むやみに緻密だよなー。戦闘や爆発を描きたいがためにOVAを創るアニメーターっているよなー。他に必然性を探すなら、賞獲りかなー。例のシーン無いと、単なる「スピルバーグの創るヒューマンドラマ」だしなー。それにしても、そんなに賞って欲しいかなぁ。昔もらえんかったこと、まだ、引きずってんのかなー。ま、僅かな実績を賞で飾ろうと画策する演歌歌手の気持ちは、分からんでもない。けど、おまえは、もう、ええやろ。ゆるしたれ。あんたがそこに固執することによって、followerが同じ思いを味わってんだぞー。気付いてんのか? 気付いてたら席を譲れ!!
とはいえ、スピルバーグの本音が「俺のシカバネを超えて行け」にあるのだとしたら、私は、感服致します。でも、「スピルバーグの創るヒューマンドラマ」を観る限り、それは無いかな。
作品は★★★★
この映画には好きな人にも嫌いな人にも繰り返し思い出さずにはいられないような力があり、その意味で問題作だと思っています。石橋 尚平(12月20日)
私はフランスの映画館でフランス語吹替版をみたので、乏しい語学力と翻訳のせいでセリフの微妙なニュアンスがわかりませんでした。皆さんの分析で初めてわかったところがたくさんありました。
舞台がフランスなのでフランス人観客の反応についてまず書きます。ノルマンディ上陸作戦には特別な思い入れがありますし、前評判も高く映画館は満員でした。ドイツ兵が倒されると歓声が上がっていましたが、途中のフランス人家族のエピソードで周囲の反応が冷めてしまいました。いかにもセットという街並みがよくなかったのか、あの父親の行動に納得できなかったのかはわかりません。私がいるアルザス地方は独仏語のバイリンガルが多いので(過去何度もドイツに併合されていますし、アルザス方言はドイツ語の一種なのです)、アパムをめぐるストーリーは日本人である私以上に思うところがあったと思います。友人たちに後で感想を聞いたところ、「疲れた」「夕食後見るには重過ぎた」「ノルマンディの墓地がきれいだった」(これは最初にライアン一家が訪れた墓地のことらしいです。アーリントン墓地だったのですか)というものでした。
私自身の感想ですが、最初の戦闘シーンがつらかった、それぞれの物語の情報が多すぎて消化不良になった、後半からラストにかけての展開が納得できない、等が不満として残りました。まず、最初の戦闘シーンはみなさん言及されているので割愛します。
次に、各兵士の物語が、宗教、人種、それぞれの背景において多様性に富んでいるため、かえって感情移入できませんでした。最初の戦闘シーン、ライアン救出を決定し彼の母へ告げにいくエピソード、ライアン探索中の兵士の葛藤、最後の橋をめぐる攻防、ライアン一家の墓参および星条旗の映像、どれも大切だとは思うのですが、とにかく全部を詰め込むと長すぎるのです。テレビ・シリーズでそれぞれをじっくり描いたらよかったのではないでしょうか。
ラストですが、対戦車の攻防シーンがポーランド映画「地下水道」を想起させ、ミラーが元教師というのもイタリア映画「エーゲ海の天使たち」を連想させ、最後の彼の死ではドイツ映画「Uボート」を思い出しました。考えてみれば中盤は「コンバット」ですね。このあたりから緊張の糸がきれてしまい、タイガー戦車が人喰い恐竜に見え、友軍の飛行機がドイツ軍戦車を爆撃した瞬間、「インディ・ジョーンズ」のテーマ曲が頭の中に鳴り響いてしまったのです。空爆でかたがつくなら靴下爆弾なんていらなかったのでは…。そのうえライアンの顔がSFXで変化し、星条旗が再びはためきリンカーンの手紙が朗読されるにいたって、当たり前のことながら「アメリカ人観客を念頭において作ったんだなあ。」という印象が残ってしまいました。
私はスピルバーグの映画が好きなので、どうしても過去の作品の名場面がふとした瞬間に浮かんできてしまいます。多くの感動的なシーンがあったのですから、スピルバーグ以外の監督だったら良かった、もしくは私にスピルバーグ作品という先入観がなければ良かったのだと思います。やはり長くなってしまいました。ごめんなさい、お目汚しで。
逆光の暗い星条旗がはためいた後、老いたJ・ライアンが共同墓地へと向かう足元が映る。低いショット。しっかりとした歩み。実際のアーリントン墓地は小高いところにあるが、この歩みの行程は終始平坦である。カメラは彼と彼の家族の胸から上のショットを前方から映し、到着後、白い十字架の前に跪くJ・ライアンの姿を映す。みさき(11月30日)
シーンはオマハ・ビーチの波打ち際に変わる。ライアンの墓にしゃがむ姿勢はこのシーンで映されるすべてのものが余儀なくされる伏臥の姿勢を暗示していた。戦場では頭上の空間を抑圧される。ヘルメットに銃弾が当たり、命拾いした兵士が刹那、脱帽した頭を撃ち抜かれることで、伏臥姿勢の強要は延々と続く。もぎられた自分の腕を拾い上げることがやっとだ。海中に身を沈めても銃弾は水圧に勢いを幾分奪われながらも無音で襲ってくるから、我々は身体を垂直に伸ばすことが全く許されないことも知っている。垂直上の空間の抑圧。伏臥あるのみ。命を乞うには伏臥の状態で僥倖に賭けるしかない。この映画は冒頭から、映画館のシートに腰を下ろす我々に身体の萎縮を無意識に余儀なくさせている。
浜辺は水際であり、地形を刻々と変化させる。冬の海。白い飛沫を立てて寄せては返す波。平坦で広がる砂浜。それが歴史的なオマハ・ビーチであっても、浜辺は浜辺である。浜辺は想像を絶するばかりに平坦なのだ。平坦であるが故に夥しい銃弾は、人と物の密度が高いながらもどこか間延びしている平坦な浜辺の空間を恣意的に飛び交う。勿論、前方にはドイツ軍の塹壕が砂丘の小高い所に聳える。しかし、この高みは嘘のようだ。塹壕側からの4度の俯瞰ショットが眼下の平坦な浜辺を映し出す。いまここにある空間は、抑圧された身体の周りの空間と、浜辺の平坦さである。絶え間なく地形を変容させる浜辺のある秋の日のできごと。身体の周りの空間は単調な浜辺の間延びとは対照的に縦に萎縮している。
約25分というこの冒頭の戦闘シーンの時間は、ちょうど生理的な息吹の集中力の持続が尽きんとするところにある。我々は一息ではこの長い長い平坦なシーンをこなせない。生理的な抑圧感に耐えきれないと、我々は抑圧が伴う無為の単調さを無意識に観念で色づけてしまう。この映画が『戦争の悲惨さ』を描いていると猥雑な言葉で意識し始めると、我々は目の前の身体的な収縮感と空間の間延びを忘却し、目の前に展開する映像に陰影をつけ、折り合いをつけてしまう。これには気をつけねばならない。目の前に広がるのは、観念の戦争ではなく、戦場という身体的に抑圧された空間なのだ。両者は似て非なるものだ。これらを混同してしまうと、これからの展開が単なる平坦な間延びにしか感じられないかもしれない。しかし、我々が冒頭で目にした浜辺は平坦ではなかったか。その後も我々は身体の圧迫を生理的感覚で感じる一方で、これから物語の宙づり状態にさらされることになる。そう作用するのがこの映画なのだ。
上陸後の小隊で最初に死ぬのはカパーゾである。彼は雨の中で緩慢な死を迎える。緊迫したスナイパーの照準を定める間の静かな応酬と緩慢な死。米兵スナイパーは神の許しを乞う。このシーンは冒頭のシーン以上によくできている。右横には半壊したフランス人住居。彼は二階に身を潜める家族から女の子を安全な場所に連れていくことを請われて階下に引き降ろしていたのだ。理不尽な要請。理性を欠いた請け合い。直後に狙撃され階下に雨中の泥濘に仰臥するカパーゾ、階下に身を隠す米兵たちと女の子。階上のフランス人家族。前方の高所からスナイパーに狙われる中、カパーゾを介抱しようとはやる軍医。我々はここで時間の『宙づり』状態になっていることに気づく。空間と時間。一層深まる抑圧。半壊した建物、敵のスナイパーの高さ、それらと対照的に地に仰臥して悶えるカパーゾ。
空間と時間はモノローグによって幾分弛緩する。繰り返されるスナイパーの神へのつぶやきだけではない。ミラー大尉のモノローグ。彼はイタリア人レンジャー隊員だった、変人ヴェッキオの話をする。小便でVの字を軍服に描くヴェッキオ。この話の唐突さと脈絡のなさに我々は面食らう。匍匐前進の方が走ることよりも速いチビのヴェッキオ。この身体的な奇形性の記憶が空間の抑圧をミラー大尉の脳裏に去来させる。彼はカパーゾの死を想起する。また、終盤のクライマックスの戦闘シーンの直前、エディット・ピアフの曲が蓄音機で流れる廃墟の中、ライアン二等兵はまるでスラプスティックのような兄たちの納屋での光景を思い出す。ヴェッキオ同様、醜い兄の逢瀬の相手。納屋に身を潜める逢瀬。喜劇のようなドタバタ。ミラー大尉同様、我々の与り知らぬ話に没入するライアン。いずれも内的なモノローグ。いずれも身を潜める奇形たちを誰かがみつめている。レンジャー隊が、兄弟たちが。実は会話ではあるが限りなくモノローグに近いダイアローグ。物語は宙づりになっている。
それではこの映画ではドラマの大きな要素である会話はどうなっているのか。会話は常に単純な法則が支配する。相手の行動を左右するものが上部から声を発するのだ。冒頭と最後のシーンでのJ・ライアンが墓の白い十字架に語りかけるように。ライアンに間違われた二等兵は、ミラー大尉が腰掛けているにも関わらず、彼よりも低いところに顔をもってきている。ミラー大尉が自らの職業を明かして、諍いを止める時、彼は小隊の中で最も高い位置に立っている。ライアン二等兵がドイツ軍との橋の攻防のためにしばらくその場にとどまる意志をミラー大尉に告げる時、彼はその防御すべきアーチの丸みがかかったより中央部分に近い高いところに立っている。ライアン二等兵の意志を確認した後、これまで同じ戦場で戦ってきたホーヴァス軍曹は、橋のたもとに座るミラー大尉に、立った姿勢からともにこの場で戦うことを説得する。まるで彼らの運命を、頭上に聳えていたドイツ兵の塹壕が支配するかのように。冒頭の映像の支配力は依然衰えない。
前方に敵のレーダーがある牧場のシーンでは、アパムは牛の死骸に身を隠し、敵に向かって前進していく仲間たちの姿をライフルに付属するスコープで覗く。仲間たちの戦闘のロング・ショット。前方のレーダーは、冒頭の戦闘シーンのドイツ軍の塹壕のように、やはり小高いところにそびえている。ただしスコープ越しの仲間は伏臥の姿勢ではない。レーダー付近の塹壕に向かって駆けて行き、コメディのパイ投げのような手榴弾の投擲を交わす。ここではアパムの見たスコープの像の中だけで、身体的な抑圧が幾分解放されている。
しかし、この直後、肝臓を撃たれた軍医のウェイドが悶え苦しむ。仲間が彼を囲み、勇気づけ、モルヒネを大腿部に注射する。だが、無情にも仲間が覆う事で垂直上の空間は抑圧される。仰臥するウェイドの空間の圧迫感はより増している。彼は死ぬであろう。肝臓を撃たれたことの意味を理解する軍医としての彼のように、我々も空間の圧迫の意味を理解している。その彼の墓穴を掘るのは、生き延びたドイツ兵である。アメリカ兵に命乞いする彼は、シャベルを振るいながら、低い穴の中に立ち、アメリカ兵に囲まれ、アメリカのマンガを模写し国家をハミングする。ここでも彼の頭上の空間は抑圧されている。釈放される彼は、なおも抑圧され続ける行く末を暗示するかのように牧場の傾斜を下っていく。
ライアンはあまりにあっけなくみつかる。この映画は艱難辛苦の捜査の物語ではない。ミラー大尉が駄目で元々のつもりで誰ともなく空挺部隊の兵士たちに大声で声をかけると、難聴の兵士が所属を教えてくれる。ドイツ軍の斥候が乗る装甲車を追いかけて、斥候を銃殺すると、ライアンたちと鉢合わせになる。 あの激しい戦闘のあった浜辺が単調で平坦な場所でしかないように、あまりにあっけなくライアンを発見できるゆえに、事態の不条理がいっそう強調される。ドラマは宙づりになったまま終わっており、脈絡がない。
最後の戦闘シーンで米兵たちは鐘楼を狙撃の拠点としてスナイパーに待機させるが、タイガー戦車が緩慢に砲身をスナイパーの方向に向けると、嫌な間を置いて鐘楼は簡単に倒壊してしまう。アパムは半壊した建物の二階に陣取る仲間から伝令を頼まれるが、階上と階下を往復できずに終わる。短刀で仲間を殺害して建物から逃れるドイツ兵に報復することもできずに、狭い階段の階下に近いところですれ違う。彼には敵が間近にある。その度に身を低くして姿を隠す。敵国語であるドイツ語ができる彼が、最も強い空間的な抑圧に耐えている。
この映画では、上空からの突然の対地上攻撃機群の飛来がクライマックスを終結させる。その前のクライマックスの戦闘シーンでは小高い背景からタイガー戦車が兵士たちの背後に着地する。最後まで上部からの身体的な抑圧は続いているのである。これまでのスピルバーグの作品でもクライマックスでの高低は意識されてきた。燃料がギリギリで坂を登り切ろうとする自動車、船尾から沈みゆく漁船(転がる酸素ボンベ)、頭上から飛来する巨大なまばゆい宇宙船、浮遊する自転車。お気に入りの物体(玩具)がいずれも非日常的な動きをすることで、我々はクライマックスの解放感を得ていたのである。しかし、この映画では最後まで『玩具』はダイナミックではあるが抑圧的な働きをする。逆光の星条旗に政治的な意味を見いだそうとする人もいるが、これはある種の物理的な『幕』なのだ。これまでスピルバーグが魅力的に描いてきた『玩具』を収納する玩具箱の覆いである。物をつつみ覆い隠す『幕』である。この幕にもやはり抑圧的な余韻が残る。シーンは最後に冒頭の墓地に戻り、起立している老ライアンの涙を描いた後、微かに空間は膨張を取り戻すが、それを暗い星条旗が再び包んで、この映画は終わるのである。
misaki@ceres.dti.ne.jpみさき(11月29日)
アパムファンクラブのみさきです。つづきです。
前にもなにかに書いたことがあるが、あたしは映画を途中から見るのにそんなに抵抗 はない。終わってトイレ行って、飲みもの買って、席にもどって、予告編見て、最初 のシーンから見覚えのあるシーンまで見る。時間があれば最後まで見る。
今回、戦闘シーンの途中から最後まで見て、もう一度、見損なった冒頭シーンに戻る と、また別の感慨があった。
そこにいた兵士たちの顔がきれいすぎるのだ。
そりゃあ、D−DAYからの8日間(だっけ?)で、ひげはぼうぼう、髪はくしゃく しゃ、戦闘服もよれよれになっていくんだけど、上陸間際の顔はつるんつるんで、お ひげも剃り立てでイイ男たちなのよ。船酔いしてゲロまいてる奴もいたけど、ま、い いや。
十字架にキスして祈るジャクソンには、かの『ディアハンター』のクリストファー ウォーケン様の面影がだぶってしまって、いいぞお。ミーハーな自分に気づいたけ ど、まあいいではないですか?
最後まで見てから、もう15分。時間に余裕のあるかたはぜひお試しあれ。
二度目を見ました。映画が少し始まっていて、もぎりのおっちゃんが「はじまっ ちゃってるかも……」というので「いいの。2回目だから」というと会員割引で15 00円をさらに200円引いて「1300円でいいよ」っていってくれたんです。う ふふ、田舎はいいなあ。Colles(11月22日)
新事実を発見してしまいました。それも、かなり重大な発見。
いままでのページにもし書いてあったらごめんなさい。書いてないようでしたので投 稿しました。 兵士の名前を覚えまちがえていたことや、ライベンの顔を忘れていたことは鑑賞ミス だったなあ。それよりもだ。最後の銃撃戦でミラー大尉を撃ったのは、あの(通信所 にいた)ドイツ兵だった。ということが、とても重要だ。
腰がひけて銃撃戦に参加したくてもできないアパムだけが、瓦礫のかげからそれを見 ていた。アパムは目を見開いて、銃をかまえるドイツ兵たちと、撃たれて倒れるミ ラー大尉を見る。カメラが確認するように、この3点を往復したから、間違いない。 アパムは、信じられない! というような表情をする。
そこへ援軍が到着した気配。次のシーンのアパムは銃を投降した独兵たちに向けなが ら独語でなにかわめいている。
さあ、ここだ。今までわたしは、にやついた敵がへらへら「アパム……」と自分の名 前(なんと、名前だあ!)を呼んだから、彼の屈辱と怒りが頂点に達して引き金を引 いた、と思っていた。
ちがうのだ。
二度めに見たアパムの肩には、すでに殺意がうかんでいる。自分が一度は助けたと か、見逃してもらったとかは、もういい。メリッシュを刺し、ミラーを撃った相手へ のシンプルな憎しみに燃えている。もとはといえば通信所でウェイドを撃ったのも奴 だったかもしれないわけだろ?
さっきまで腰が抜けてたはずなのに、やけにきびきびと独語で指示をし、中央の独兵 にねらいを定める。少しの間。発砲。ずどん。
そして、銃を捨て、きびすを返す。
胸にひろがる絶望。
でもさあ、8人のライアン救出部隊のうち、3人までもおんなじ奴に(しかも、戦場 は2箇所)やられるなんて偶然は、ありか? ま、いいや。
それから、以前にも、この映画では名前というものがとても大切に扱われてい る、と書いた。
今回、橋のたもとで帰らないというライアンに誰かが
「こっちだって2人、なくしてるんだ」というと、ライアンは
「2人の名前は?」って聞く。「カパーゾ」が聞きとれなくて、「カピ? ん?」な んて聞き返して、そしてうつむく。
名前がわかんないと冥福も祈れないか? 自分のために死んだ兵士の名前を聞こうと するなんざ、見上げたこころがけだと思った。ライアンえらいやん。
好きなシーンについて。
わたしはどうやら登場人物たちのこころが通じあってるなっていう場面が好きらし い。目と目だけでわかりあってるっていうような場面。
ライアンのいる橋のある町をめざすにあたって、地図を広げながら磁石をもったミ ラーの手がまたかたかたと震えている。音が出るから磁石の蓋をしめながら、ミラー とホーバスの目があう。なんかすべてわかりあったもの同士の視線だったなあ。う ん、よかった。
今日はここまで。感想つづく。
麗奈さんの質問に回答をします。麗奈(11月18日)
私は「帝国主義」という言葉を、軍事的・経済的に他国を支配していく拡張主義的な傾向を意味するものとして使いました。
また独裁的というニュアンスも私は感じていました。
しかし帝国主義は、政治形態としての独裁者国家を意味しません。
民主国家であった英国やフランスは世界中に植民地を持つ帝国主義国家でした。
一方で、 他国を植民地にしたり領土をとったりすることもまた、帝国主義の必要条件ではないと、考えます。
現代においては他国の領地をぶんどることは、ほぼ不可能ですしそうしなくても、軍事的・経済的に他国を支配することはできるからです。
気になって辞書をひきました。
広辞苑で帝国主義をひけば、「(1)軍事・経済上、他国または後進民族を征服して大国家を建設しようとする侵略的傾向。(2)19世紀末に始まった資本主義の段階。独占体と金融資本との支配がうみだされ、資本の輸出が特に重要性を持ち、国際トラストによる世界分割が完了している段階。レーニンが既定した。」とあります。
さて、アメリカは自らの帝国主義的な欲望を持って行動をしているのではないか? という疑問があります。
しかし「みんな知っている」と書いたのは事実と違いました。
帝国主義は悪なのか?。
簡単に悪と言えないと私は思います。
企業が利潤を追及するのは悪ではないでしょう。
国が利潤を追及するのも悪ではないでしょう。
どこから悪になるのか線をひくことが難しいです。
collesさんの投稿で驚いたのでちょっと一言。colles(11月17日)
「いまどき、アメリカ帝国主義って言葉が随分とまとを得ていることくらい、みんな知っている。」って書いてありましたが、本当ですか?
この場合の「帝国主義」とはどういう意味でしょう?アメリカ人は「帝国主義=悪」として捉えていると思うのですが、それは「帝国主義=独裁者国家」と考えているからだと思います(たとえば、ナポレオン、日本の軍国主義のような)。
☆☆灘かもめ(11月17日)
ラシャーヌという漫画のいいかげんな戦争のシーンでリーダーが「つっこむぞ、私につづけ〜」といって敵陣地につっこみ勝利するシーンがあった。
そんなのって漫画の世界だけだとおもってた。
味方を消耗品のように扱う、そんな非合理ことを日本軍がしたとしても米軍はしないものだと思っていた。
なのにこの映画ではこんなことの連続なのでびっくりした。
この点が一番印象にのこった。
多くのひとが指摘しているように、ストーリがきちんとかかれてないかんじ。
キヤラもあんましたってない。
それは、戦争ってものは、人間性を否定しちゃう恐ろしいものなのだというあらわれなのだと、いうことか。
ドイツ兵の扱いもわりあい公平なかんじがしたし。
冒頭とラストの墓地はよけいなかんじ。
また最後に星条旗がでてくるのもやめてほしいです。
いまどき、アメリカ帝国主義って言葉が随分とまとを得ていることくらい、みんな知っている。
ライアンが味方の空爆かなにかで、死んでしまって、そのうえにリンカーンの言葉が空虚にひびいたらよかったかも。
きょうは、「プライベート・ライアン」にまつわる話をします。(鑑賞の役には立たないと思いますが・・・)SIVA(11月16日)
私が「ライアン」を観にいった同じ時期、松山で「CAPA’S LIFE」という ロバート・キャパの全作品の写真展をやっていました。
キャパに興味はあったのですが、戦争写真家のイメージが先行しすぎて、 「きっと、悲惨な写真ばかりなんだろうな・・」と、尻込みしつつ見にいきました。
ところが、私の思っていたものとは違う「悲惨」と「悲劇」がそこにありました。
「悲惨な写真=スプラッタな死体の山」と勘違いしていたバカなわたし。
キャパの写真には「死体」はほとんど写されていません。そこには、生きているひとたちのありのままの姿がありました。キャパは、「戦死者の様子を撮ることが、真に戦争を写したものだとは言えない。むしろ、生きている人たちを撮ることによって戦争の悲惨さが伝えられるのではないか」と考えていたそうです。(この言葉どおりではなかったかも)全作品を見終えた後、本当にその通りだなと思いました。
戦死した息子の小さな写真を持って何かを叫んでる母、 傷ついた娘を抱きかかえる父親の表情、その娘の無表情、 凍てついたベルギーの大地を浅く掘り起こして仮眠をとっているアメリカ兵、 ノルマンディーの戦死者を埋葬する墓穴を、アメリカ兵に監視されながら掘らされてるドイツ人捕虜たち・・・・。どの写真も、今生きている「人間」を撮っている。
イタリアの農夫が、ドイツ軍が去った方向をアメリカ軍将校に教える場面を写した、有名な作品があります。農夫はかなりおじいちゃん。背もちぢんじゃって、指も農夫らしくとてもゴツい。その手はアメリカ軍将校の肩にかかっている。まるで、自分の孫にでも言ってるかのように。アメリカ軍兵士も、おじいちゃんの背丈に合わせてかがみこみ、おじいちゃんの指し示す方向を見る。兵士の左手薬指にはリング、そして飾りチェーンのブレスレット(時計かもしれない)。このおじいちゃんは、ひょっとしたら息子か孫を戦争で亡くしてるのかもしれない。この兵士は故郷に残した奥さんがいるんだ、ブレスレットは奥さんが持たせたのかもしれない、仲間内ではからかわれないのかなぁ・・・ 等々、いろんな事を連想してしまう。
とにかく、キャパの、人間を見つめる目の確かさ、やさしさ、真剣さが伝わってくる作品ばかりでした。
「プライベート・ライアン」もキャパ写真展と平行して観たので、私のなかで この二つは見事にシンクロしてしまった。三回目の「ライアン」では、ノルマンディー の場面で、キャパはどの辺りにいるんだろう、と、つい探してしまった(笑)。
逆に、キャパの、ベルギーのバストーニュという街で包囲された第101空挺師団の写真のなかにジミー・ライアンを探してしまったり。
(ちなみに、第17空挺師団の落下傘部隊は、士気を鼓舞するため全員モヒカン刈りに なってました。マット・デーモンがモヒカンで出てきちゃったら、ちょっと笑ってしまうな〜〜〜。)
ダグラス・タガミさんが、「スピルバーグはキャパの写真を超えようとしている、野心を感じる」と言われていましたね。私は、ちょっと違う感想を持ちました。
スピルバーグも、キャパと同じように兵士一人一人に焦点をあてていた。
「人間」を描こうとしていた。
そして、極力、意図的な演出をせず表現しようと試みた。
その結果、克明なノルマンディーの「歴史再現」に行き着いたのではないか。
ライアン救出部隊が「あの戦闘」を経験したのであれば、イメージの先行する 回想シーンとして表現するのでなく、真っ正面から表現しようと考えたのではないか。
「人間」を描くために取った方法論が、たまたまキャパの精神と一致した、と私は思った。「人間」を表現したい、という部分で、二人の出発点は同じとも言えるのではないか。
スピルバーグはおそれないひとだな、と思った。近い「戦争」を表現するには、それなりの批判にさらされるはずだ。自分の意図しなかった反応が返ることもある。場合によっては、命を狙われるかもしれない。それでも、あえてリスクをおそれず、とにかく創る、とにかく表現したいと思ってる。そして作品が世に出たあと、反応を見て次いこう、 ではなく、すでに次回作に取り掛かっている。(ルーカス君、ちっとは見習いなさい)
ほんとにエネルギッシュだなぁと感心してしまう。
昔からのファンの方は、スピルバーグが遠いところに行ってしまったようで 淋しく感じてるのでしょうね。私は以前の「映画ならではのおもしろさ」を 提供してくれた彼よりも、「映画ならではのメッセージの伝え方」を模索中の 今の彼の方が好きです。100人が誉めてくれても、101人目に批判されたら、 すべてを否定された気持ちになってしまうものです。それでも、彼はやるのです。
「ガツンと言っちゃうよ」なんて安全圏で勝手なこと言っているオヤジとは違う。
>パンちゃんへ
>しかし、「現実」は「理想」を抜きにしては語れないのではないか。「理想」という視
>点から「現実」を見つめ「現実」から「理想」を見つめ返すという往復抜きでは何も語
>れないのではないか。
日記に書かれていたこの部分に、深く共感します。
「理想主義」は、非現実的で「甘い」考えだ、と思われがちです。
「理想」を理屈の世界に閉じこめてしまえば、たしかにその通りです。
けれど、「理想」には、「現実」を転換しゆく種子がある、と私は思う。
「現実主義」には、できることからやる、という面もあるけど、「できないことをやってもムダ」という面もある。
「現実主義」に撤するところには、「変革」への努力が見失われがちになる場合が多いように思う。「なるようにしかならない」のであれば、「何もしていない」のと同じ事だと思う。そこには、もはや「あきらめ」と理想主義への「嫉妬」しかない。
逆に「理想主義」に撤してしまうと、どうか。まず、ひとがついてこなくなる。
「理想」の名のもとに、あらゆるものを破壊してしまう可能性すらある。
「理想」は思想と似たものだと思う。思想が、ひとから離れてしまえば、「現実」は 壊れてゆくしかない。
パンちゃんの「現実」と「理想」の関わり合い方に対する提言は、 その意味で深く納得しました。
戦争映画って言うと戦々恐々、賛否両論、いろいろありますが私は今回この作品に「星4つ」を送りたい。
昨日、見たばかりであまりに沢山の情報が頭に入ってきてどう、表現したらいいのか・・・
「ノルマンディー上陸作戦」世界史でしか、出会った事が無い事柄。
「オレンジビーチ」の意味や、魚の死骸と一緒に転がる死体、海に飛び込んでも突き刺さる銃弾。
最初に戦闘が終わる頃には涙は枯れていました。
戦争という情報を「情報操作」によって美化されて教育された私にはあまりに大量の映像。
否応もなく描かれている。
この、映像だけでも私は見た価値があったと・・・思っています。
良く分からない文章を書いてしまいました、お目汚し・・でも書かずにはいられない。そんな作品だったと思います。