 |
�T�̋�ԏ܂łԂ�������I�@�j��ŋ������o�[�ő��V�I
|
(2008.01.14) |

�l�����I�I�@�ʂ����Ă������̖�����̑傫���I
�@���s�ł����Ȃ���S�����q�w�`�͏��q�w�`�̂Ȃ��ōł��`��������ł���B��P��̂����Ȃ�ꂽ1983�N�����A���q�}���\�������X�ܗւ���̗p����邱�Ƃ����܂��Ă������A���{�̏��q�������͂���߂Ă�������Ԃ������B
�@�g���b�N�ł��������Ɏ��g��ł���I��͂قƂ�ǂ��炸�A��������ڂ��V�݂��ꂽ����ŁA�C���^�[�n�C�Ȃǂ�800�����Œ��̎�ڂ������B���łɂ��ď��q�}���\�����n�܂��Ă��鉢�ĂƂ���ׂđ傫�������������Ă����̂ł���B
�@�ނ�ĂƂ̗������̂��̂��A���{�ɂ����鏗���̎Љ�I�n�ʂƑ傢�ɊW���������B���������Ăł͒j�q�������Ȃ������n�[�h�ȃX�|�[�c�ɏ������i�o����Ƃ����P�[�X���ЂƂ̕����̂悤�ɂȂ��Ă���A���������n�k�ϓ��̒��������{�ɂ���Ă��Ă����̕s�v�c���Ȃ������̂ł���B
�@���{���q�������̈琬�͂�����������Ɩ����ł͂Ȃ������B���X�ܗւ̃}���\��������ɂ����āA���q�������̋����ɂƂ肭�܂Ȃ���c�c�B�Ȃ�Ƃ����E�Ƃ̋����߂Ȃ���c�c�B
�@���q�̃}���\���Ⓑ�����̑I�肪���Ȃ��킯�ł͂Ȃ������B���X�؎��b�A���c�����A���͂��߂Ƃ��āA���Ƃ��Ύ��ƒc�̈������Ȃǂł̓}���\���Ⓑ�������߂����I�肽���������̂ł���B�����A��P����𐧂����̂͐�t���������A���̑��c�����i��S��t�j���A���J�[�Ƃ��ėD���e�[�v����Ă���B
�@�������Ȃ���A�������̑I��w�������ɂ��n�ゾ�����B�ЂƂɂ���̑I�肾���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���������ă}���\���A���������߂����I��w�������Ȃ���A���E�ł͐킦�Ȃ��B
�@���w��������ƒc�̑I��܂ő���s���{���R�`���̏��q�w�`�́A���̂悤�Ȕw�i����Y�܂ꂽ�̂ł���B
�@���q�̒����������̂��߁A�Ȃ��ł��}���\���ł̐��E���e���݂���������ȃ��}����y���ďo�������̂ł���B
�@���ꂩ��25�N�A�܂�l�����I�c�c�ł���B���{���q�͋����Ȃ����B�I�����s�b�N�ł̓}���\���łQ�A���A�k���łR�A�����߂����܂łɂȂ����B���̂�����ɂ����Ă͋��ٓI�ȃX�s�[�h�Ő������Ƃ��Ă����Ƃ����邾�낤�B
�@���������g�[�^���ł݂��Ƃ��A�܂��܂����E�̈ꗬ���Ƃ͂����Ȃ����A���܂�j�q���͂邩�ɂ��̂��܂łɂȂ��Ă��܂����B�S�����q�w�`�̉ʂ����Ă��������͂���߂đ傫�����̂�����B
�@�k���I�����s�b�N�̂����Ȃ��鍡�N�A�S�����q�w�`�͊�����V�����l�����I�̏���ƂȂ�̂����A�����Ƃ��ɏ��q�������̈ꗬ�����߂������ƁA���ꂪ�V�����ۑ�ɂȂ�̂��낤�B
�P��̍U�h�����������߂�
�@�C���V�x�œܓV���悤�B���������āA�Ƃ�����Ⴕ���ꂪ�������Ȋ��X�Ƃ����_�䂫�A�����ɂ����s�̓~�炵����₦���������������ł������B
�@������n�̗��𖡕��ɂ����Ƃ����킯�ł�����܂������s�͋��������B���s�A���ɁA���R�̎O�ǂ����c�c�Ƃ݂Ă������A�t�^�������Ă݂���s�̋����͗\�z���͂邩�ɉz���Ă����B
�@�����͂P��ɂ��Č������B������A�ϐ킷�郌�[�X�Ƃ��ẮA�����������ȃ��[�X�W�J�ƂȂ��Ă��܂����悤�ł���B
�@���ɂ≪�R�����炵�Ȃ������Ƃ����킯�łȂȂ��B�ނ��돟���������Ă����B�Ƃ��ɉ��R�Ȃǂ͋��s���ӎ����āA�O���d���̃I�[�_�[�ʼnʊ��ɏ����ɗ��Ă����B
�@�P��͊e�`�[���̃G�[�X���̊炪�����Ƃ�����Ă����B�O�R�����i�����j�A���ƈ��i���Q�j�A�����͎q�i�É��j�A��������i�����j�A�K��ޕc�i����j�A�����F�����i���R�j�A�g������i�_�ސ�j�A�⌳�疾�i�������j�A�Ԑv���i���j�ȂǁA���̂�����ƒc�I�肽���A����ɂ͑�w�w�`�̃G�[�X�I���݂̖؍�ǎq�i���s�j�Ȃǁc�c�B
�@���R�Ȃǂ͖{���Ȃ�ŏI��ɔz���ׂ��X�[�p�[�G�[�X���A�����ĂP������Ă��Ă���A���s�̏o�@��@���ē����悤�Ƃ�����@�����肠��݂��Ă����B
�@�P�q=3:08�Ɠ���͂܂��܂������A�ŏ����璆���A�⌳�A���ƂƂ�������͂ǂ��낪�O�ɏo�ďW�c���Ђ��ς�͂��߂��B�����Ȃ���̂��ƃy�[�X�͑����Ȃ�̂ł́c�c�Ǝv��ꂽ�B
�@�������ԓ_�܂ł��悻27�`�[�����Ђ��߂������Đ擪�W�c���Ȃ��Ă���B�ނ���͂ǂ���݂͂�Ȃӂ��܂�Ă���B���s�̖؍���������肭�炢���Ă����B
�@���ԓ_�͂X��30�b�c�c�B���R�̒��������܂肩�˂�悤�ɑO�ɏo���B�����̏����A���s�̖؍�A�������̊⌳������ǂ������A�É��̏����A�F�{�̍]���C���q�A���Q�̐��ƁA�����̍O�R�����Ȃǂ����Ă������A�S��O���畺�ɂ̒������I�͂��肶��ƒx��n�߂��B
�@�S�q�����ɂȂ�Ɖ��R�̒������d�|���A10�l���܂�̐擪�W�c�������đO�ɏo���B�����̂��Ă����̂͋��s�̖؍�ƐÉ��̏����łR�l�͂T�q��16���Œʉ߁A�g�b�v�����͊��S�ɂR�l�ɂ��ڂ�ꂽ�B
�@���V�[�Y���A�����F�����̍D�����͂��킾���Ă��邪�A�����ł��c��R00���ŖґR�ƃX�p�[�g�A�ǂ������鏼���Ɩ؍��U������B�P�b�x��ŏ����A�R�b�x��Ŗ؍肪�Ƃт��B
�@���R�͗\��ʂ�ɂP��Ńg�b�v�ɗ��������A���C�o���̋��s���R�b�x��łÂ����̂͌�Z���������낤�B�G�[�X�𓊓���������ɂ͂P��̒����ŏ��Ȃ��Ƃ�30�b�ȏ�͂������ł������������ɂ������Ȃ��B
�@�t�ɂ����A���s�̖؍�ǎq�͑匒���I�@���ƒc�g�b�v�N���X�̒����ɂ킸���R�b����������Ȃ������̂ł���B������؍�̓��肪�A�Q��ȍ~�̋��s�ɐ����������Ƃ݂�ׂ����낤�B���ɂ�37�b�x���12�ʂɏI��������A�Q��̏��тŃg�b�v�ɏo��ɂ́A���Ȃ��Ƃ�����20�b���炢�͉҂��ł������������B
�A���Ă������їS���q�A���N���������I
 �@�����ł͂Q����d�v�ȋ�ԂɂȂ��Ă���B�R��̒��w���͌v�Z�ł��Ȃ�����A�Ƃ肠�����Q��ōD���Y���������Ă��������ƍl����͓̂��R�̂Ȃ�䂫�ł���B �@�����ł͂Q����d�v�ȋ�ԂɂȂ��Ă���B�R��̒��w���͌v�Z�ł��Ȃ�����A�Ƃ肠�����Q��ōD���Y���������Ă��������ƍl����͓̂��R�̂Ȃ�䂫�ł���B
�@���R�͉Y�c�������A���s�͓��c�F���A�����ĕ��ɂ͂Q��̃X�y�V�����X�g�Ƃ����Ă��鏬�їS���q�������B
�@�P��ŗ\�z�ȏ�ɍD�X�^�[�g�����������s�͓��c���ǂ��グ�ĂP�q�ł��łɂ��ĉ��R�̉Y�c�ɒǂ����Ă��܂����B�X�g���C�h�̂̂т�傫�ȑ���ł���B�Y�c���ЂƂ��т͔����Ă���C�ɂ͂䂩�Ȃ��B
 �@���ɂ̏��т����N�P�N�A���������ʼnw�`�𑖂�Ȃ���������𐰂炷���̂悤�ɔ����A�Q�q�ɂ���8�l�����A��C�ɂS�ʂ܂ł������Ă����B���ς�炸�X�P�[���̑傫�ȑ���ł���B�����g�b�v�����ɗ��ނɂ͏����b�������肷�����B �@���ɂ̏��т����N�P�N�A���������ʼnw�`�𑖂�Ȃ���������𐰂炷���̂悤�ɔ����A�Q�q�ɂ���8�l�����A��C�ɂS�ʂ܂ł������Ă����B���ς�炸�X�P�[���̑傫�ȑ���ł���B�����g�b�v�����ɗ��ނɂ͏����b�������肷�����B
�@�g�b�v�͂R�q�������Ă����s�Ɖ��R���͂��������荇���Ă������A�c��550m�ɂȂ��ē��c���X�p�[�g�A�ǂ������鉪�R��U�肫�����B���R���Q�b���̂Q�ʁA�����ĕ��ɂ̏��т��É������킵�ĂR�ʂɂ�����A�g�b�v�̋��s����35�b���܂ł������Ă����B�\�z�ʂ�ɂQ��łR���̂��낢���݂ł���B
�@���s�͂Q��ő������g�b�v��D���Ă��܂����̂����A���܂�ɂ��������āA���邢�͑z��O��������������Ȃ��B�t�ɉ��R�ɂƂ��Ă͍ň��̓W�J�ɂȂ��Ă��܂����B�P��Ńg�b�v��D��������ɂ͏��Ȃ��Ƃ����Ղ܂ł̓��[�h��ۂ����������͂��ł���B���Ղ������������A�ŏI��܂ł����W�J�ɂȂ�A���邢�͏��@�����������낤�Ǝv���邩��ł���B
�@���ɂ͂Q��ŏ��Ȃ��Ƃ��g�b�v�ɗ��������������Ƃ��낤�B�Q����I����ċt�ɋ��s����26�b��������ẮA���łɏ����͌����Ă����B
���s���Ƃ܂�Ȃ��B�O���ő������Ƒ��Ԑ��ɁI
�@�R��͒��w����Ԃł���B�g�b�v�ɗ��������s�̋v�n�I�́A�Ђ�ނ��ƂȂ��ϋɐ��̂��鑖��Ŕ�яo���Ă������B�D���Y���Ńs�b�`�������݁A�㑱���݂�݂�u���Ă䂩�ꂽ�B�P��A�Q��̗���Ő����������Ƃ݂�ׂ����B���̒��w���̑��肪�������苞�s�`�[�����悹�Ă��܂����B
 �@��납��ǂ��Ă����̂͐É��̓��c���}�q�ł���B�W���j�A�E�I�����s�b�N3000m�̃`�����s�I���̓��c�͕��ɁA���R���āA�Q��łЂƂ��тS�ʂɗ������É����ӂ����тQ�ʂ܂ʼn����グ�Ă����̂ł���B �@��납��ǂ��Ă����̂͐É��̓��c���}�q�ł���B�W���j�A�E�I�����s�b�N3000m�̃`�����s�I���̓��c�͕��ɁA���R���āA�Q��łЂƂ��тS�ʂɗ������É����ӂ����тQ�ʂ܂ʼn����グ�Ă����̂ł���B
�@�R��ŋ�ԏ܂�D�����̂͐É��̓��c���}�q�����A���s�̋v�n�͉��������B���c����킸���U�b�x��̋�ԂR�ʂł���B�Q�ʂɂ������Ă����É��Ƃ̍���27�b�Ȃ���A���C�o���̂R�ʉ��R�Ƃ̍���33�b�A�S�ʕ��ɂƂ̍���34�b�Ƒ傫���Ђ炢�Ă��܂����̂ł���B
�@���s�̂S��͐��E����}���\����\�̏���܂�ł������B�{���Ȃ�ŏI10��ɓo�ꂵ�Ă��Ă����������i�[���S��ɏo�Ă���B�Ȃ�Ƃ����������ȕz�w�ł���B
 �@����͂P�q=3:07�b�œ���ƁA�������̓x�e�����̑���Ǝv�킹�邳���Ō㑱�Ƃ̍����ǂ�ǂ�ƂЂ낰�Ă��܂����B�T���O���X�̉��̊ᒆ�ɂ́A���͂≪�R�����ɂ��Ȃ��������낤�B �@����͂P�q=3:07�b�œ���ƁA�������̓x�e�����̑���Ǝv�킹�邳���Ō㑱�Ƃ̍����ǂ�ǂ�ƂЂ낰�Ă��܂����B�T���O���X�̉��̊ᒆ�ɂ́A���͂≪�R�����ɂ��Ȃ��������낤�B
�@�㑱�ł͕��ɂƉ��R���Ȃ��ŐÉ���ǂ��グ�A�Q�ʑ������������Ȃ��Ă������A���͂⏬��͔ޏ��������E��������Ă����B
�@�S����I����ăg�b�v�̋��s�ƂQ�ʂ̕��ɂƂ̍��͂Ȃ��53�b�ɂЂ炢�Ă��܂����B
�@�Q�ʂ͋�Ԃ��Ƃɕϓ]����̂����A�P�ʂƂ̍��͂ǂ�ǂ�Ђ낪���Ă䂭�B���s�̃y�[�X�ɂ܂�܂ƃn�}���Ă��܂����̂ł���B
�Ȃ�ƂT��A���ŋ�ԏ܁I
 �@�S��̏���܂�͋�ԏ܂��l������ƁA���s�̐����͂��͂�Ƃ܂�Ȃ��B�T��ɂȂ�����~��o�������A����ȂȂ����Č����������Ƃ����s�b�`������Ō㑱���t���Ȃ������B�������Q�ʂ𑈂����R�ƕ��ɂ�K�ڂɋ�ԏ܁A����ɂU��͕��̑S�����Z�w�`�ŗD���e�[�v������|���������A�����ĂV��̈ɓ�����Â����B �@�S��̏���܂�͋�ԏ܂��l������ƁA���s�̐����͂��͂�Ƃ܂�Ȃ��B�T��ɂȂ�����~��o�������A����ȂȂ����Č����������Ƃ����s�b�`������Ō㑱���t���Ȃ������B�������Q�ʂ𑈂����R�ƕ��ɂ�K�ڂɋ�ԏ܁A����ɂU��͕��̑S�����Z�w�`�ŗD���e�[�v������|���������A�����ĂV��̈ɓ�����Â����B
�@�����ىF���g���I��������ċ�ԏ܂̉����ł���B�������ĂS���53�b���������Q�ʂƂ̕b�����T��ł͂P��02�b�A�U��ł͂P��27�b�A�V ��ł͂P��47�b�c�c�ƁA�ǂ�ǂ�Ђ낪���Ă䂭�̂ł���B���������V�L�^���P���ȏ������y�[�X�ł������B ��ł͂P��47�b�c�c�ƁA�ǂ�ǂ�Ђ낪���Ă䂭�̂ł���B���������V�L�^���P���ȏ������y�[�X�ł������B
�@�W��̒��w���E�v�n�G�Ƀ^�X�L���n�����Ƃ��ɂ́A���͂�ǂ��Ă��鉪�R�����ɂ��݂��Ȃ��������낤�B
�@���s�̐����͂Ƃǂ܂�Ƃ����m�炸�Ƃ����ׂ����B���w���̋v�n�������ْ����������đ��ꂽ�悤���B�I����Ă݂��47�l���B��A10�����^�C���œ��X�̋�ԏ܂ł���B���ł͉��R�ƕ��ɂ̂Q�ʑ������Â��Ă������A�ŏI�I�ɂQ�ʂɂ���Ă������R�Ƃ̍����Q��16�b�܂łЂ낰�Ă��܂��̂ł���B
�@�W����I������Ƃ���ʼn��R�ƕ�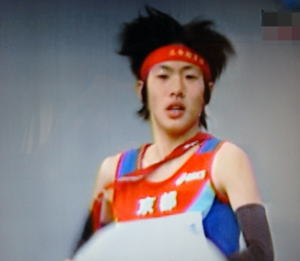 �ɂ̂Q�ʑ����͂�����Ƃ��ĂÂ��Ă������A���s�͂����͂܂��ɓƑ���ԁA���Ƃ͑��V�L�^�̍X�V���Ȃ邩�ǂ����c�c���A�œ_�ƂȂ����B�@����܂ł̋�ԋL�^��1�T����̌F�{���}�[�N�����Q����15��19�b�����A���̂Ƃ��͍ŏI10��̐��D�q��31��01�b�Ƃ����M�����Ȃ��^�C���ł������Ă���B���s�̃A���J�[���Ƃ߂�̂͑�w���̏�����b�����A32�����������Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��Ȃ肻�����B���݂̏����̗͂��炷��A�s�\�ł͂Ȃ��B�������đ��V�L�^�ւ̊��҂���C�Ɍ����������тĂӂ����ł����̂ł���B �ɂ̂Q�ʑ����͂�����Ƃ��ĂÂ��Ă������A���s�͂����͂܂��ɓƑ���ԁA���Ƃ͑��V�L�^�̍X�V���Ȃ邩�ǂ����c�c���A�œ_�ƂȂ����B�@����܂ł̋�ԋL�^��1�T����̌F�{���}�[�N�����Q����15��19�b�����A���̂Ƃ��͍ŏI10��̐��D�q��31��01�b�Ƃ����M�����Ȃ��^�C���ł������Ă���B���s�̃A���J�[���Ƃ߂�̂͑�w���̏�����b�����A32�����������Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��Ȃ肻�����B���݂̏����̗͂��炷��A�s�\�ł͂Ȃ��B�������đ��V�L�^�ւ̊��҂���C�Ɍ����������тĂӂ����ł����̂ł���B

�������͖���݂����A����ԉH�L�I�q�I
�@���s�̍ŏI10��͏�����b�ł������B�����w�w�`�ł͑��l�҂Ƃ����鑶�݂ł͂���B�������s�����������B��̑�w�w�`�ł�9.1�q�܂ł̋��������Ȃ��Ă��邪10�q�͏��߂Ă̌o���Ȃ̂ł���B
 �@���s�̗D���͂܂������Ȃ��낤���A���V�L�^�͂܂ł͂ǂ����낤���H�@�����A����Ȍ��O���ӂ��Ƃ����̂́A�Ⴂ�L�ѐ���̐����ƁA�w�`�̂��s�v�c�ȗ���Ƃ������̂��낤�B��������ɂȂт����āA�܂�Ŗ鍳�̂悤�Ȑ����Ȋ���A�����̑���ɂ͂�邬���Ȃ������B �@���s�̗D���͂܂������Ȃ��낤���A���V�L�^�͂܂ł͂ǂ����낤���H�@�����A����Ȍ��O���ӂ��Ƃ����̂́A�Ⴂ�L�ѐ���̐����ƁA�w�`�̂��s�v�c�ȗ���Ƃ������̂��낤�B��������ɂȂт����āA�܂�Ŗ鍳�̂悤�Ȑ����Ȋ���A�����̑���ɂ͂�邬���Ȃ������B
�@�I�n�����������̂͂Q�ʑ����ł���B���ɂ̘e�c���Ɖ��R�̔Ғn�������R�q�����肩�畹����Ԃł����B�e�c�͐�̓����{���ƒc�ŕG��ɂ߂Ă����B�ɁX�����������̂܂��Ō��Ă��������ɁA����̑���𒍖ڂ��Ă����B�������̐��E�I�茠��\�ɂȂ������͂̓_�e�ł͂Ȃ������B�Ō� �ɉ��R��U�肫�����̂͒n�͂Ƃ������̂��낤�B�̏�ɂ������ł������E�����\�����i�[�̕�������낱�т����B �ɉ��R��U�肫�����̂͒n�͂Ƃ������̂��낤�B�̏�ɂ������ł������E�����\�����i�[�̕�������낱�т����B
�@����Ɍ������́A��̓������ۃ}���\���𐧂��āA�k���̃}���\����\�ɓ��肵�Ă������݂����i�O�d�j���ґR�ƒǂ��グ�Ă����B16�ʂŃ^�X�L�����炤�ƁA�O���䂭�����i�[���Ȃ�Ԃ܂��Ȃ��ǂ������āA����H�ɂ͂���܂łɂ��łɂS�l�����ł���B�܂�ŃX�s�[�h���������Ƃ��������A�����ꂽ�����i�[�͒N��l�Ƃ��Ă��Ă䂯�Ȃ������B
�@�W�ʂƂ������܌����ɂ͂���Ȃ��������̂́A�Ō�͂V�l�����łX�ʂ܂ł���Ă����B�w�`�̂��߂ɓ��ʂȗ��K�͂��Ă��Ȃ������Ƃ������A�݂��Ƃȑ���A�������̓I�����s�b�N���_���X�g�����̂��Ƃ͂���B
�@����ɖ���̌������́A���̃}�}�����i�[�E�ԉH�L�I�q���ǂ��グ�Ă����B�ԉH���u���O�ɂ��ƕ��ׂ��Ђ��Ă���c�c�Ƃ���A���̉e�������O���ꂽ�B�������Ȃ������I����ēȖ�29�ʂ��������A�S�[���ł�20�ʂ܂ł������Ă��Ă����B
 �@�X�l�����ŋ�Ԑ��т͖���݂����Ɏ����Q�ʁA�������x��邱�Ƃ킸���X�b�Ȃ�Ό��������Ƃ����ׂ����낤�B�̒������S�łȂ��ɂ�������炸�A���[�X�ł͂���Ȃ�ɂ��������ʂ��o���B���V�[�Y���̍D�����𗠕t���錋�ʂƂ����ׂ����낤�B �@�X�l�����ŋ�Ԑ��т͖���݂����Ɏ����Q�ʁA�������x��邱�Ƃ킸���X�b�Ȃ�Ό��������Ƃ����ׂ����낤�B�̒������S�łȂ��ɂ�������炸�A���[�X�ł͂���Ȃ�ɂ��������ʂ��o���B���V�[�Y���̍D�����𗠕t���錋�ʂƂ����ׂ����낤�B
�@���āA���s�̏�����b�����A�Ō�܂ŏW���͂�ۂ��čŌ�܂ŗ͑������B���V�L�^�̃v���b�V���[�ɋ����邱�ƂȂ�����10�q�𑖂肫�����݂̂͂��ƂƂ����ق��Ȃ��B
�@�ޏ��̏I�n�Ђ����܂����\����̂͂S�{�̎w����ɂ������āA�S�A�e�̃S�[���ɂƂт��Ƃ��������B�@��Ԑ��т͖���A�ԉH�Ƃ������ƒc�̃g�b�v�N���X�Ɏ����łR�ʁA��������c��Q�q����y�[�X����������͂ɁA�ޏ��̂�����Ȃ�������������������ꂽ�B
���܂ő����H�@���s�A���ɁA���R�̂R���̐��I
�@�D���������s�͑I��w�������ɂ������������B���Z�w�`�̔e�ҁE�����ىF������R�l�A��w�w�`�̔e�ҁE�����ّ�ƂQ�ʂ̘ŋ��傩��P�l���A����܂�ⓒ�c�F�������ƒc�̃g�b�v�N���X�A����ɒ��w���������B�����ّ�w�̂����ꖇ�̃G�[�X�E����I�q�Ȃǂ͏o�開���Ȃ��āA�T���ɉ��Ƃ����ґł������B
�@�X�l�̂����T�l�܂ł���ԏ܁A�c��S�l����ԂQ�`�R�ʂ��߂Ă���B�܂������A�i�Ƃ������̂��݂���Ȃ��S�ǂ̕z�w�A25�N�̗��j��������݂Ă��A�ŋ������o�[�Ƃ����Ă������B����ɍ�N����w���w�����ׂď����ɂ������݂��������̂��낤�B
�@����ɂ��Ă����s�͂S�N�A����12��ڂ̐��e���Ƃ�������A�قڔ������������ŗD�����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���s�͂��̂Ƃ����т��Ē��w���A���Z���̋����ɂƂ߂Ă���B�������������̒n���Ȏ��g�݂��ő�̌����͂ɂȂ��Ă���B��w�w�`�ł������ّ��ŋ���̓g�b�v�N���X�ɂ���A���ƒc�ł̓��R�[���⋞�Z���[������B�Ȃ���s�̉����͂������₷���͗h�邪�Ȃ��Ƃ݂��B
�@�ߔN�͋��s�ɂ��킦�ĕ��ɁA���R�͂R�����`�����Ă��邪�A���ɂ����R���o�������������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɍ��Z���������A���R�͎��ƒc�������B��������ꂼ�ꎝ���������Ă����B�Ƃ��ɋ��s�ɂԂ��������Ă��܂������A����͋��s���������������ł���B
�@���s�A���R�A���ɂƂ������萨�͂Ƃ͗����ɁA���Ă̋����̒������ڗ��悤�ɂȂ����B�����i�U�ʁj�A�F�{�i�V�ʁj�A�������i11�ʁj�Ȃǂ͂܂������Ƃ��āA�Ƃ��ɍ�ʁi26�ʁj�A��t�i30�ʁj�̒����͂�����҂�҂����v��������B
�@����ӂ邳�ƑI�萧�x����������āA�������P�p���ꂽ�B�Ȃ�ǂł��ӂ邳�ƑI��Ƃ��ďo�g�s���{������o��ł���悤�ɂȂ����B����݂����A�O�R�����ɂ��Ă��A�����������x�ɂȂ������䂦�ɁA�{���ɏo��ł����̂ł���B
�@���w���⍂�Z�������i�[�͎��ƒc�̃g�b�v�ƂƂ��Ƀ��[�X�ɏo�邱�Ƃ͑傫�Ȏh���ɂȂ邾�낤�B�w�ԂƂ���������͂����B���������Ӗ��ŁA���x�̉����͎��X�����̂ł������Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�S�����q�w�`�̓`�����s�I���V�b�v�̑��ł͂Ȃ����A���q�������̃{�g���A�b�v�Ƃ����_���������ł���B���̂��߂ɂ�����̖���݂�����O�R�����̂悤�ɁA���{���\����悤�ȃg�b�v�N���X�̑I�肽�����ł��邾������݂��Ăق������̂ł���B
|
|
|
|
|
 |
|
| �o��`�[��&�ߋ��̋L�^ |
|
|
 |
| �� �A �T �C �g |
|
|
 |
|
