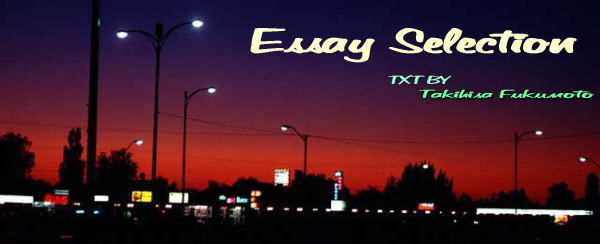 |
福本 武久
ESSAY
Part 1 |
福本武久によるエッセイ、随筆、雑文などをWEB版に再編集して載録しました。発表した時期や媒体にとらわれることなく、テーマ別のブロックにまとめてあります。
新聞、雑誌などの媒体に発表したエッセイ作品は、ほかにも、たくさんありますが、散逸しているものも多く、とりあえず掲載紙が手もとにあるもの、さらにはパソコンのファイルにのこっているものから、順次にアップロードしてゆきます。 |
| わが小説の舞台裏……さまざまな出会い |
|
| 初出:雑誌「こどもの季節」5月号(ブラザーショルダン社) 1979.05 |
親と子にかける虹
|
|
わが家にやってくるこどもたちの一人に、美恵(仮名)ちゃんという六年生の女児がいる。両親ともに仕事を持っていて、彼女は一日の大半を一人ですごしている。
「ひとりでさみしくない?」
ありふれた間をぶつけてみた。
「うん、なれてるもん」
彼女は表情さえ変えなかった。
幼ない頃から数え切れないほど同じ問いに接して来たのだろう。そのたびに精一杯微笑んで同じ応えを繰り返して来たにちがいない。
「一人でいて何か困ることはない?」
「うん」
彼女はこくりと頷いたが、その時ふいに表情が曇った。
「‥…そやけどカミナリが鳴るとこわいね。どうしょうかと思う」
すがるような眼付に一瞬、息を飲んだ。
その時の眼差しがいまも脳裡から離れない。
誰もいない家の中で、カミナリの轟音におびえ、逃げまどう彼女、閃光のたびに眼を閉じ室の隅で頭をかかえてうずくまる少女の姿は妙にリアリティがある。
こどもにとって親の存在とは何なのだろう。考えさせられてしまった。
こどもの眼には親はどのように映っているのか。そしてそこから親のありようを模索する上で興味深い調査結果がある。
「どんなお父(母)さんが一番、えらいと思いますか」 これは京都市教育研究所の実施した意識調査の設問の一つである。結果を小学校六年生六百一人のまとめから抜すいした。
よく働く 五一・七五(二九・二六)
何でも知っている 一五・六四( 三・四八)
好きなものを買ってくれる 七・八二( 五・三二)
子供の世話をよくしてくれる 一六・九七(四九・四二)
お金をもうけてくれる 七・一五( 二・三三)
(カツコ内は母・単位%)
また同内容の他の調査で「父母にどんなことをいちばんのぞむか」という設問があり、そこでは「なんでも相談にのってほしい」 という回答がトップを占めていたように思う。
いずれにしてもこれらの結果はこどものいつわらざる願望の顕われではないか。だとしたら現実はその逆だということになる。
わが国の世帯をみるに、その六割は勤労者世帯によって占められている。勤め人である父親を取り巻く環境はきびしい。
低成長時代といわれ経済界はいま新たな機軸を模索しているいわば混迷期の最中にある。
高度成長の洗礼を受け、その影を色濃く背負いこんだままの父親は自らの生き方に疑問を抱いて揺れている。「窓際族」「四五歳定年」といったエキセントリックなジャーナリズムの報道は、母親に対しても、母であることよりも、深く夫を理解するよき妻になることを強いようとしている。
父親のもつ不安はこうして母親をも巻きこんで家庭内に持ちこまれてくる。一方母親はというと、「三歳では遅すぎる」といった教育産業のPRに踊らされ、教育費のかさむ昨今、家計防衛もさることながら、家に閉じこめられて行く孤独感を解消するために、働きに出たいという潜在的な願望を具体化しようとする。
夫婦間の会話は薄ら寒いものとなり、親子の会話にしても「早く勉強しなさい」 「何! この成績」「‥…したらいいもの買ったげる」対応を拒否した短い一方的な会話になってしう。
感性の世界に生きるこどもは、そうした両親の内面を敏感に肌で感知してしまう。
生き方に対する父親の願望、母親の願望、そしてこどもの願望……このたがいに相克する基本的な要求を解決することは重要で深刻な問題ではある。
けれどもまず何よりも、いま一度自らの生括の場の足許をみつめ直すことが急務ではなかろうか。
両親とこどもが共有できる現実生活のレベルで何ものかを創り出すよろこびを見出すこと、たとえば、鍋をかついで野山や河原に出かけ、親子たがいに分担協力して料理し、ごった煮の鍋をつつく、そうしたささやかな試みが必要なのではなかろうか。ことばなんかいらない。目的を同じくした行為を通じて寄り添っているだけで、たがいに浸透して行く何かがあるはずだ。
カミナリにおびえる美恵ちゃんが切望するものは、たとえ両親がその場に居なくても、精神的に、ほとんど自分自身を抱きしめるようにしっかり抱きしめてくれる母親であり父親であるのではないかと思う。そのためにはことばでは捉えられない肌を通して浸透して行く信頼感を日頃から培い育むことが必要だろう。
美恵ちゃんの姿をみるにつけ、こどもの思考、想像の世界に入りこんで、飾りを捨て同じレベルで、ともに考え、ともに悩む姿勢の必要性を再確認する。父親と母親の個の人間としての生き方も案外そんなとこから展けてくるのではなかろうか (了)
|
|トップへ | essay目次へ |
|