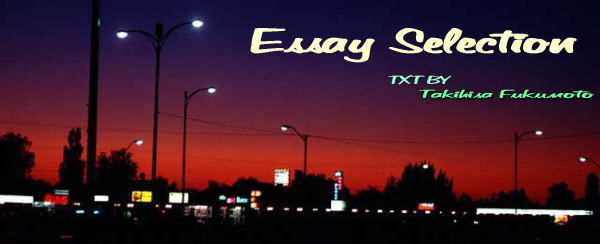 |
福本 武久
ESSAY
Part 1 |
福本武久によるエッセイ、随筆、雑文などをWEB版に再編集して載録しました。発表した時期や媒体にとらわれることなく、テーマ別のブロックにまとめてあります。
新聞、雑誌などの媒体に発表したエッセイ作品は、ほかにも、たくさんありますが、散逸しているものも多く、とりあえず掲載紙が手もとにあるもの、さらにはパソコンのファイルにのこっているものから、順次にアップロードしてゆきます。 |
| わが小説の舞台裏……さまざまな出会い |
|
| 初出:雑誌「刑政」(財・矯正協会)2001年11月号 2001.101 |
ボランティアの喜びとは?
|
|
いま、なぜ、ボランティアなのか!
電車から降りたあなたは駅のホームを歩いている。そのとき、すぐ前をゆく老人が、ふいにその場にうずくまってしまった。顔をゆがめ、何やら苦しそうである。……。
そんなとき心優しいあなたは、とっさに声をかけるでしょう。
「どうかしましたか?」
老人の顔は苦痛にゆがんでいる。何か体調に異変があったにちがいない。
そのように判断すると、あなたはさらに「だいじょうぶですか? 何か私にできることはありますか」と、親身になるはずです。
眼のまえに、困っている人がいれば、手をさしのべる。それは人間の本能のようなものであり、ボランティア活動の出発点ではないでしょうか。
近年、ボランティア活動への関心が高まってきています。たとえば阪神・淡路大震災では全国からたくさんの人たちが被災者支援のために駆けつけました。台湾の大地震でも日本人のボランティアが活躍しました。
活動の舞台はいまや国内だけにとどまらず地球規模におよんでいます。シニア海外ボランティアとして海外におもむく中高年の人たち、途上国に腰をすえて、組織的な救援活動に当たる人たち、寝袋ひとつで海を渡る若い人たちも現実にふえています。
たとえばベトナムのフエ市でストリート・チルドレンの支援活動をつづけておられる小山道夫さんのもとには、春休みや夏休みになると、きまって多くの学生たちが訪ねてくる。ボランティア志望の若い人たちが朝早くやってきて、小山さんはたたき起こされるそうです。
中高年の女性、若い人たちを中心にしてボランティア活動への関心が急速に高まってきている……。小山さんは自らの体験からそのようにとらえています。
人間はいくつになっても、社会とつながっていたい。社会との接点が断たれると、精神はかぎりなく荒廃してゆく。だからつねに現実社会との接点で、自分というものが生かされる活動に出会いたいものと希いつづけている。自分が生かされる活動に出会えば人間は成長します。「生きがい」「充足感」「達成感」というような精神的なものを求める傾向は、いくつになっても変わらない。そういう「心の豊かさ」をとりもどす仕組みのひとつとして、ボランティア活動が位置づけられているのだろうと思います。
心の豊かなサービスは、心ある人でしか実現できません。予算をモノサシにして動く行政ではとてもムリというものです。このように考えるとボランティア活動とは、「行政の目のとどかないところで、心ある人たちによって提供される心あるサービス」ということになると考えます。「心ある……」というところにポイントがあります。
最近、ボランティア活動に参加した人たちの手記や体験記が数多く発表されるようになりました。それらを読むたびに、年齢を超越したパワーに圧倒されます。みんな、どうしてあんなに心優しくて、血が熱いのだろう……と、ただひたすら驚嘆するのみです。
ボランティア活動に参加してよかった点として、「多くの人たちとのめぐりあい、ふれあい、新しい自分を発見した」「人間はひとりでは成長できない。たがいに支え合いながら生きていることがわかった」「生きがいを発見することができた」「活動を通じて数多くの友人や仲間ができた」などがあげられ、それぞれ実感をこめて生き生きと語られております。
みんないかにも心根がやさしい。世の中には善意のかたまりみたいな人がいるものだなあ……。けれども、そういう人たちが自ら書きおこした体験記を読みながらも、ふと言葉にならない違和の断片が私の脳裏をよぎることがある。
いったい何なのだろう……。
あれこれと思案するうちに、それは「サービスを提供する側」からしか語られないことへの異議申し立てのようなもの、あまり語られることのない「サービスを受ける」側の「心」は、いったいどうなのだろう?……という素朴な疑問ではないかと思いいたりました。
「やってあげる」と「やってもらう」
太宰治の作品に、『たずねびと』という短編小説があります。ひとくちで言えば、「ちょっといい話」という部類の物語です。
第二次大戦で日本の敗戦が濃厚となった一九四五年(昭和二〇年)、太宰は東京で焼け出され、疎開した甲府でも空襲に遭って家を焼かれ、妻子ともども着の身着のままで郷里の津軽に向かいますが、そのときの体験にもとづいて書かれた作品です。
物語そのものはいたって単純です。主人公の「私」は妻とともに五歳になる女の子と栄養不足で虚弱な二歳の男の子を連れて上野から列車に乗り込みます。食糧不足の当時、幼な子を連れての長旅がいかに過酷なものであったか。その厳しさは私たちの想像をはるかにこえたところにありますが、かれら一家はたまたま同乗した三人の乗客の善意によって危機を救われる。そういうお話です。
この作品は『東北文学』(一九四六年一一月)という雑誌に発表されましたが、その設定をそっくり利用するかたちで、作者は次のように物語を切りだします。
……この「東北文学」という文学雑誌の片隅を借り、
申し上げたい事があるのです。
実は、お逢いしたいひとがあるのです。お名前も、御
住所もわからないのですが、たしかに仙台市か、その附
近のおかたでは無かろうかと思っています。女のひとで
す。
続いて主人公の「私」は名も知らないその女性に「お嬢さん。あの時は、たすかりました。あの時の乞食は私です」と唐突に呼びかけるのです。この呼びかけは、もういちど繰り返され、結末でも現れてきて、まるで作品全体をつらぬくメインテーマのようにひびきわたっています。
上野で野宿した一家は、翌朝一番の列車に乗り込んだ。窓から這い入った車中は大混雑、そんななかで二歳の子はむずかりはじめますが妻は母乳が出ない。運よく近くに子持ちのおかみさんがいて、彼女が見かねて乳をのませてくれます。
ほっと一息ついたら、こんどは食糧の不安がもちあがります。せっかく持参したおにぎりも蒸しパンも暑気でみんないたんでしまっている。
「にぎりめし一つを奪い合いしなければ生きてゆけないようになったら、おれはもう、生きるのをやめるよ」
日ごろから、そのように宣していた「私」は、とうとう 「その時」が来たかと腹をくくります。すると、こんどは、桃とトマトの入った籠を持った別のおかみさんが現れてきます。彼女はたちまち乗客たちに取り囲まれてしまいますが、「私」はわざと素っ気ない顔を装う作戦に出て、まんまとその「おかみさん」を隣に座らせることに成功します。そして運よく桃とトマトをめぐんでもらうのです。
これで、上の子の食糧は手当がついた。だが……。「下の子がいまに眼をさまして、乳を求めて泣き叫びはじめたら……」と、また新しい不安の種に苛まれます。「私」は「ええ、もう、この下の子は、餓死にきまった。」と開き直りますが、現実は容赦がありません。仙台に近づいたとき、とうとう下の子が眼をさまし、不安が現実のものとなります。
「蒸しパンでもあるといいんだがなあ」
「私」が思わずつぶやいたときでした。
「蒸しパンなら、あの、わたくし、……」
不思議な囁きが頭上から聞こえてきます、後ろに立っていた若い女のひとが網棚からズック鞄を降ろしたかと思うと、蒸しパンの包みが「私」の膝の上に載せられます。さらに「これは、お赤飯です。それから、……これは、卵です」とつぎつぎにハトロン紙の包みが積み重ねられるのです。
「私」は「何も言へず、ただぼんやり、窓の外を眺めていました」という状況で列車は仙台に着いてしまいます。すると女のひとは「失礼します。お嬢ちゃん、さようなら」と言って、さっさと窓から降りてゆきます。
「私」も妻も一言も礼を言うひますらなかった。白い半袖のシャツに、久留米絣のモンペをつけていた、その「女のひと」に「私」は会いたいというわけです。作品の最後は次のようにしめくくられます。
逢って、私は言いたいのです。一種のにくしみを含め
て言いたいのです。
「お嬢さん。あの時は、たすかりました。あの時の乞食
は、私です。」と。
最後のわずか数行によって、状況はがらりと一変、読者の私たちは思わず息を飲みます。作品世界は単なる美談に終わらず、緊張感にあふれたものとなって結末を迎えるのです。誰しもが「一種のにくしみを含めて」というフレーズに引っかかって、立ちつくすことでしょう。
最後に現れた若い女のひとの善意は、どこからみても疑う余地がありません。主人公の「私」は「餓死にきまった」と腹をくくったわけですから、心底からありがたいと思ったにちがいありません。
実際、名前も告げずに爽やかな余韻を残して立ち去った「若い女のひと」の行動は実に水際だっています。しかしながら、彼女の文句のつけようのないボランティア精神こそが、同時に「私」は心を撃ってしまったのです。それが「一種のにくしみを含めて」という「私」の思いの実態というものです。
戦災のせいとはいえ、「乞食」同然になりさがった恥辱、家族をまもるためとはいえ、見ず知らずの人たちの「ほどこし」に頼るほかないというわが身のふがいなさ、そういうものが渾然一体となって胸にこみあげてきた。だからこそ「私」の内奥から発せられる悲痛な呼びかけが読者の胸にいつまでも強くひびきわたる。まさに迫真の結末だと思います。
主人公の「私」は「若い女のひと」の好意を涙を流さんばかりに感謝している。けれども感謝の気持ちとは裏腹に、心の奥底に何かわだかまるものがある。人間の気持ちというものはそういうものです。
ボランティア活動におけるサービスを「提供する」側と「受ける」側との関係、つまり「やってあげる」「やってもらう」関係も同じことが言えるでしょう。とくに「受ける」側は「……してもらう」という意識に苛まれることが多く、心の負担を感じているケースが多いのではないでしょうか。『たずねびと』はそういう「受ける」側の心理を具体的に鋭くえぐり出しています。
「やらせてもらう」という目線
誰しも危ういところで他人にたすけられたという経験があるでしょう。そのときのことを思い返してみてください。
救ってくれた恩人に対して、なみなみならぬ感謝の念を抱きつつも、それとは裏腹な感情、つまり太宰が『たずねびと』でえぐった「にくしみ」に相当する思いをかみしめたことがあるのではないでしょうか。
筆者の私には思い当たることがたくさんあります。私たち家族はボランティアのみなさんのたすけなくては生きてこられませんでした。それは、ながいあいだ重い知的障害のある子どもとともに暮らしてきたからです。
自閉的な症状をともなう知的障害児として生をうけたかれは、成人した現在もいまだに言葉をもっておりません。
言葉がコミュニケーションの手段として有効に機能しない。当然にように周囲との意思疎通がぎくしゃくして、つねにものすごいストレスをかかえています。それでも精神状態が安定しているときは本人も踏ん張って、何とか乗りこえるのですが、人間は誰でも気分のすぐれるときばかりではありません。
情緒不安になると大ピンチです。ある日、とつぜん鬱積した憤懣が一気に爆発して、不眠不休の大パニックがやってきます。
子どものころならともかく、成人した現在は、もう親の手のうちにおさまるわけもなく、親であることがかえって火に油をそそぐ結果につながることもあります。
そんなとき、いつも救いの手をさしのべてくださるのは、昔からかれのことを熟知している人たちです。学校の先生、あるいは施設の職員の方ですが、夜中になんどか駆けつけてもらったこともありました。
私たちにとってはまさに「救いの神」というわけですが、最初のころは、やはり「やってもらう」側の心の負担を痛切に感じていました。あの『たずねびと』に出てくる「にくしみ」に一脈通じる心の動きが私のなかにもあったのです。
ところが……。
あるとき、重石がとれたように、ふいと心が軽くなりました。そのきっかけになったのは、例によって駆けつけてくださったある人の一言でした。
「お父さん、Aくんのこと、私たちに見させてください」
わが子の通う施設とは異なる施設に勤務する職員の方でしたが、「私たちにやらせてください」と、なんども繰り返し、パニック状態にあるわが子を自分の施設に連れて帰り、二晩もケアーにあたってくださったのでした。
「どうか、よろしくお願いします」
と、ごく自然に私の口をついて出たのは、「やらせてください」という言葉のひびきのなかに、その人の「心」のすがたをみたからだったろうと思います。
やらせてください……。その背後にあるのは「~してあげている」という気持ちの全面否定です。
おたがいに困ったときは、人間としてたすけ合って、ともに生きてゆく。ボランティアのサービスを「提供する」側と「受ける」側とは、あくまで対等な人間関係ではければならない。瞬時にしてそういう考えかたが透けてみえたのです。
「かわいそうだから、やってあげる」
そういう発想では「やってもらう」側とのあいだに対等な関係は生まれません。「やってあげる」側は「やってもらう」側を見下ろす関係になってしまいます。そして「やってもらう」側は、「もらってばかり」というわけですから、つねに心理的に大きな負担を感じてしまいがちなのです。
「やってあげる」のではなくて、「やらせてもらう」という目線であれば、対等な立場で人間として素直に向き合い、気持ちをやりとりする関係がうまれてくるでしょう。
ボランティア活動に関わっている人たちに取材させてもらったことがありますが、何人もの方から「いや、助けられているのは、むしろ私のほうなのですよ」という思いがけない声がもれてきて眼をみはりました。
ベトナムのフエ市でお会いした小山道夫さんもそのひとりです。数多くの路上の子を救ってきた小山さんは、「私のほうが、この子どもたちに生かされているんですよ」と、なんども繰り返しておられたのが印象的でした。
「やってあげる」「やってもらう」という関係ではなくて、たがいに心を「癒し」「癒される」関係が実現できたときに、ボランティアをする側もそれを受ける側も、ともにハッピーになる。そのために、まずサービスを提供する側と受ける側とが、たがいに同じ目の高さで、「心」のキャッチボールをする。すべてはそこから始まるのではないでしょうか。
|
|トップへ | essay目次へ |
|