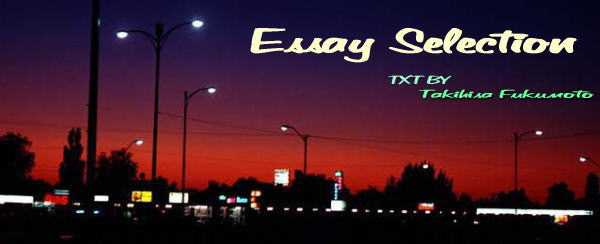 |
福本 武久
ESSAY
Part 1 |
福本武久によるエッセイ、随筆、雑文などをWEB版に再編集して載録しました。発表した時期や媒体にとらわれることなく、テーマ別のブロックにまとめてあります。
新聞、雑誌などの媒体に発表したエッセイ作品は、ほかにも、たくさんありますが、散逸しているものも多く、とりあえず掲載紙が手もとにあるもの、さらにはパソコンのファイルにのこっているものから、順次にアップロードしてゆきます。 |
| わが小説の舞台裏……さまざまな出会い |
|
| 初出:雑誌「地域福祉」(日本生命済生会)1981年1月号 1981.01 |
ともに生きるということ
〝国際障害者年″にあたって
|
|
五年生になるA君は、ある朝突然、学枚へ行きたくない……と全身でむづかり始めた。それ以来、母子とも〈朝〉は重苦しい一日の始まりであり、恐怖の瞬間となった。
〝わがまま″と詰るしか術のなかった母親は、まもなくその原因は、同学年のこどもたちから、下枚時にいじめられるためだ、ということを知る。
〝登校拒否″ 〝いじめっ子、いじめられっ子″の問題は、昨今さしてめずらしい話ではない。
ところが、このA君、実は自分の意思をことばで十分伝えることのできない、障害児学級に通うこどもであり、〝いじめっ子″は同じ学校の健常児であるということになると、事情は少し違ってくる。
ぼくほこの話を聞いて激しい衝撃をうけた。
今日、障害をもつこどもたちの就学は、A君のように普通学枚に併設の障害児学級か、あるいは養護学枚とされるのが一般的だ。
昭和五十四年義務化以来、次第に障害児は、養護学枚就学の行政指導が強化されようとしている。義務化の是非については長くなるからのべない。しかしそのねらいは〝できる″者と〝できない″者をはっきりと区分して、後者を切り捨てて行こうとするところにある。
A君の悲劇は、こうした学校教育行政のあり方に深く根ざしたものであるということができる。同じ学校にありながら、普通児学級と障害児学級、相互の交流の場を奪ってしまうという姿勢が、その裏側に秘められている。
つまりA君の学校では障害児学級は隔離された場であり、健常児と障害児の望ましい日常的な関わりすら指導されていない。事件はその当然の帰着である。
こどもたちは、もともと同じ環境で教育されるべきで、障害のある児も健常児も、すべて地域の学校で、ひとしく生きていける道が、模索されねばならないとぼくは考える。そこで健常児も障害のある児の存在を知ることによって学び、そして障害のある児も健常児との関わりのなかで、潜在的機能を獲得していく。ともに生きることで、人間の豊かさが醸成されていくのではないかと思う。
分離教育のなかで「できる」児の世界をひたすらに生き、競争のなかから生まれたエリートたちによってどんな未来社会が生まれてくるのだろう。少なくとも今の社会の仕組では、彼らこそがお役人となり、やがては福祉行政を操ることになるのである。障害児(者) に関わる術も知らぬ彼らが……である。こうした社会を想像する時、ぼくは薄ら寒くなる。分離教育は双方にとって不幸である。
こども自身は本来的に、障害のある児だからといって差別意識は持たないものである。養護学校が、そして障害児学級があるからこそ、こどもたちの意識を歪め、差別を助長するのではないか。
地域の学校のなかで「障害児」にスポットを当てた「健常児」教育、そして「健常児」にスポットを当てた「障害児」教育という二つの視点が交差する教育が指向されるところにこそ、たがいの未来があるとぼくは考える。
健常児(者)と障害児(者)がともに学ぶ場が、日常生活レベルで形成されるときに始めて、健常者社会の欺瞞に満ちた人間関係が撃たれ、学力中心の教育のあり方も問い直されてくるように思える。
昭和五十六年は「国際障害者年」と規定され〝障害をもつ人の社会への完全参加と平等″がテーマとして掲げられている。
障害者を取り巻く問題は健常者であるぼくたちを含めた人間総体のあり方を問う重要なテーマである。障害者の存在こそがぼくたちのあり方を問うてくる。ぼくたちは、いかに関わり、どのようにして生々した関係を創り上げるかという視点を欠落させてはならないのである。
|
|トップへ | essay目次へ |
|