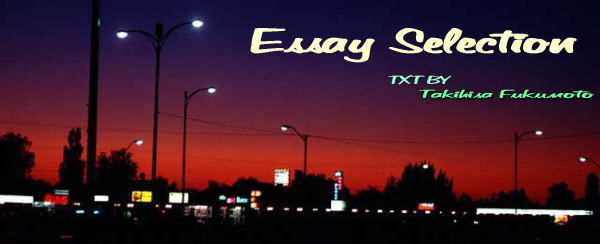 |
福本 武久
ESSAY
Part 1 |
福本武久によるエッセイ、随筆、雑文などをWEB版に再編集して載録しました。発表した時期や媒体にとらわれることなく、テーマ別のブロックにまとめてあります。
新聞、雑誌などの媒体に発表したエッセイ作品は、ほかにも、たくさんありますが、散逸しているものも多く、とりあえず掲載紙が手もとにあるもの、さらにはパソコンのファイルにのこっているものから、順次にアップロードしてゆきます。 |
| わが小説の舞台裏……さまざまな出会い |
|
| 初出:雑誌「新刊ニュース」(東京出版販売)1986年8月号 1986.08 |
わが小説のバックステージ
|
|
実在の人物をテーマにした長編小説をいくつか書いてきた。
親しい友人たちほ、ぼくの顔を見ると、きまって、「おい、あれはどこまでが事実で、どこまでがフィクショソなのだ?」
と、たずねかけてくる。
かれらはストーリーを面白くするために、やたらフィクショソで味つけしていると思っているらしい。
作品の出来栄えよりも、小説書きのバックステージに興味を持つのだからこまりものだ。
「フィクショソといえば、全部がフィクショソだし、事実といえば全部が事実だ」
面倒くさそうにぽくが言うと、かれらはきょとんとしている。
ぼくにしてみれば、そのように答えるしかないのである。
もちろん事実にもとづく小説だから〈史的事実〉は踏まえているわけだが、できあがった作品のなかでは、はっきり色分けできなくなっている。
小説書きとしてのぼくの興味は、あくまで人間にある。その人物が、人間として、いかに生きたかという一点につきる。取材や資料探しのときに、よく研究家にお会いするが、興味の持ち方がずいぶんとちがうなあと思う。
研究の場合は、どちらかというと、解剖学的である。あくまで〈事実〉にもとづく分析に重点がおかれる。だから研究テーマというものは、視点さえ変えれば無限にあって、これで終わりというものはない。
小説は一回性の形象作業である。その人物を生身の人間として、くっきり浮かび上がらせることに全力をあげる。
年譜的〈事実〉などは、主人公の生きた足どりを追体験する手がかりにすぎない。むしろ血肉ある人物として、いかに蘇生させるかにウェイトをおく。そこにフィクショソの要素がからんでくるのである。
対象とする人物を描き切るためにはダミーが必要である。ぽくは主人公とする人物の趣味・嗜好、生理感覚さらこはモノの感じかたから、さりげない癖にいたるまで、自分なりに理解しようとあれこれ思案をめぐらす。
やがて、ぼくのイメージ化した主人公が体内に棲みついてしまう。すると、筆はひとりでに進みはじめる。
あとは付かず離れずで、ダミーを追ってゆきさえすればいいが、あまり接近しすぎてはいけない。だからといって距離を取ってもいけない。後姿を見失ってしまうと、もう書き進めることができなくなるからだ。つねに適度の距離を保つには、かなりの集中力がいる。神経が疲れる作業である。
小説を書いている間、自分では意識しないが、周囲の眼からは、異常にみえることがあるらしい。顔つきまでいつもとちがっているとさえ家人は言う。
食べ物の好みが急に変わってしまったり、無性に人恋しくなって、やたらと電話をかけまくったりすることは、しょっちゅうで、急に涙もろくなったり、猜疑心が強くなったりすることもある。周囲の者は、ずいぶんと面食らっているようだ。
そんなぼくを見て、一人ほくそえんでいるのは、編集担当者だけである。
ナーバスになっているぼくを見るたびに、作品ができつつあるな……と、直感するという。それはやはり、ぼくの体内に別の人間が棲みついていて、折りに触れて顔をのぞかせるからだと思う。
だから小説を書きあげたら、一時もはやく体内から出ていってほしい。ぼくがイメージ化した主人公なのだから、それなりに愛着もあるのだが、居座られてもこまる。
はなはだ身勝手な言い分かもしれないが、ぼくの興味は、もはや別のところに向っているのである。
そんなぼくの冷淡さは、講演の依頼を受けて、たちまち裁かれる。ぼくは執筆が終ると、意識的に取材ノートや資料のほとんどを処分してしまう。本になるころには、その人物について、すっかり忘れてしまっている。
ひとたび体内から脱け出た主人公を呼びもどすには、ものすごいエネルギーが要る。
それに年譜でさえ全く憶えていないから、会場で研究者の顔を見つけると、冷汗が出てくる。
たかが小説書きが研究者の前で、もっともらしい顔をするのも、なんだか面映ゆい。
……小説書きは、雑文であろうがエッセイであろうが全部小説なんですよ。これからお話しすることも小説かもしれません。 ――
だからいつも、こんな前口上で開き直ることにしている。
もしかしたら、この一文も……
|
|トップへ | essay目次へ |
|