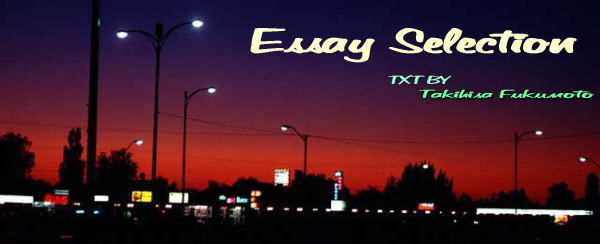 |
福本 武久
ESSAY
Part 1 |
福本武久によるエッセイ、随筆、雑文などをWEB版に再編集して載録しました。発表した時期や媒体にとらわれることなく、テーマ別のブロックにまとめてあります。
新聞、雑誌などの媒体に発表したエッセイ作品は、ほかにも、たくさんありますが、散逸しているものも多く、とりあえず掲載紙が手もとにあるもの、さらにはパソコンのファイルにのこっているものから、順次にアップロードしてゆきます。 |
| わが小説の舞台裏……さまざまな出会い |
|
| 初出:月報「太宰治全集」(筑摩書房) 1998.11 |
あれから二〇年
|
|
ターミネーターにならなくて、ほんとうによかった……。
太宰治賞の復活が決まったとき、しみじみとそう思った。
数ある新人賞のなかでも太宰賞だけは、どこかひと味ちがう。受賞者の顔ぶれ、その作品の質からみて、大人の賞という感があった。だから、この賞を受けて出発できることは、まことに幸せであった。ところが、わずか一カ月あまりで、賞そのものが中断されてしまった。まるで貰ったクルマが、とつぜん製造中止になってしまい、故障しても交換部品もあるかどうか判らない状態で発車してしまったようで、弾んだ気持ちもいくぶん萎んでしまった。
あれから二〇年……。太宰の没後五〇年を機に筑摩書房・三鷹市の共催で賞が復活されることになった。かくして最後の受賞者になりかかっていた私は、にわかに最新の受賞者としてよみがえったのである。
太宰を私にとりもったのは学生時代の友人であった。たまたま最初の授業で隣り合わせたのがきっかけで親しくなり、現在もたがいに〈悪友〉と認め合っている彼は、太宰の熱心な読者だった。
一年の夏休みが終わって、後期の授業が始まったある日だった。本を買いにゆくから、同行してくれ……と、彼はいつになく神妙な顔で言うのである。あれは出町柳あたりだったろうか、それとも京都大学の周辺だったろうか。記憶はあいまいだが、否応なしに連れてゆかれた先は、学生街の古本屋だった。
「よかった。まだ売れていなかった!」
昂ぶった声をあげる彼が指さす書棚にならんでいたのが、細ひもでしばった『太宰治全集』だった。
彼は入学直後から目星をつけていたらしい。夏休みにも郷里に帰らず、京都に居残ってアルバイトしたのは、それを買うためだったというのだった。
別冊も含めて全部で一三冊もあったが、わが友は私にいっさい手を触れさせず、下宿まで一人で持ち帰った。
「やっと念願を果たした」
彼は上機嫌で、とっておきの「ジョニ黒」の封を切ったのだった。
オマエも太宰を読め……と、彼からしきりに奨められたが、ある種の警戒心みたいなものが働いて、素直に入ってゆけなかった。彼の本箱から、ときおり全集の一冊をひきぬいて拾い読みするのだが、最後まで読みきった作品は一編もなかった。目次に「満願」とあるのをみて、「これ、麻雀小説か?」と訊いて、失笑されるしまつだった。
彼が「津軽」への旅を思い立ったのは、三年の春休みだった。その日、彼はとつぜんボストンバッグをさげて、私の家にやってきた。
「おい、旅に出ようや。行き先は津軽。太宰の、あの津軽だ。ええな。今から、すぐ京都駅に行こう。何? 用意ができないって……。トロいこと言うな。バッグに下着と洗面用具だけ詰めとけ。それでええ。金だけは忘れるな。ちょっと待て。コートはあるか? アノラックならあるって。持ってゆけ。向こうは北国だ。きっと、まだ寒い……」
彼はまるで蟹田のSさんのような調子でまくしたて、強引に私を道連れにしてしまったのである。
各駅停車の汽車を乗り継ぎ、気にいったところがあれば、途中下車すればいい。時間に縛られない気ままな旅を楽しもうというのが彼のプランだった。
私たちはその日のうちに、京都から北陸本線まわりで出発したが、彼はだんだんと元気がなくなり、なぜかバネが切れたかのように消沈してしまった。
気分でも悪くなったのか……と訊くと、彼は「いや、そうやない」と首をふり、「実は……」と溜息まじりに語りはじめた。
高校時代から親しかった女友だちが郷里にいる。その彼女が「今日、結婚してしまう」というのだった。
私はまんまとハメられて、彼の失恋旅行に同行させられたのである。津軽というのは口実で、行き先なんかどこでもいいのである。私たちはやたらと途中下車を繰り返し、毎夜のように大酒をくらった。所持金はたちまち底をつき、青森はおろか、山形までもゆけずに京都にもどってきた。就職が決まったら、かならずゆこう。彼はなんどもそう言っていたが、とうとう実現しないままに終わった。
卒業後、ゆくゆく家業の旅館を継ぐという彼は郷里に帰って銀行マンになり、私は繊維関連メーカーの営業マンになった。めまぐるしい時の流れに忙殺される日常、文学などとは無縁の世界にどっぷりつかっていた。
時の奔流がとまったと思ったのは、社会に出て三年目の春だった。健康診断で思いがけず内臓の疾患が発見された。最低でも半年は療養せよというのであった。長期休職がその後のサラリーマン人生にどういう影響をもたらすのか……などという不安はまったくなかったが、いきなり降って湧いたような茫漠とした時のひろがりに面食らった。
本でも読むか……と思ったとき、脳裏に現れてきたのが、かつて執拗に「太宰を読め」と言った彼の顔だった。私はさっそく太宰全集を購入、第一巻から、ゆっくりと読み進んでいった。別巻の巻末にいたるまで一ページも飛ばすことなく読みきったとき、不思議と病のほうも癒えていた。再び舞いもどった日常には何の変わりもなかったが、私自身に変化の兆しが現れ、そのころから小説を書くようになっていた。
太宰賞を受けたとき、新聞記事で知ったらしく、彼はさっそく電話してきた。
「あれ、ほんとうにオマエか?」と、不思議そうに訊くのである。本人が〈そうだ〉と答えても信じられないらしく、「ほうとうに、(賞を)とったのか?、オマエが……」と、なんども念を押すのだった。今でも顔を合わせるたびに、「オマエが、太宰賞とはなあ……」と、溜息をもらす。どうやら、私に太宰を盗られたという想いがあるらしい。
二年ほどまえに新宿で飲んだとき、半ば冗談で宙ぶらりんになっている「津軽」の旅はどうするつもりだと訊いてみた。
「そういうこともあったな」
彼は懐かしそうに眼を細めて考えこみ、相手の腹を探るかのように「命あらばまた他日……」と意味ありげに微笑んだ。
彼の意図を察した私は、「それじゃ、そのときままで、おたがいに〈元気で行こう〉」と応え、たがいに顔を見合わせて笑った。
旅館だけでなく回転寿司屋も経営している今の彼には、〈自分探し〉ともいうべき「津軽」の旅なんか、もう必要ないだろう。
彼の大事な太宰を盗ってから二〇年、私はその罪を贖うかのように作品を読み返してきた。太宰の小説は、みんな哀しく、やるせなく、鬱屈しているが、明るく、華やかで、お洒落で、軽妙、そして滑稽である。何よりも読めば不思議と元気が出てくる。『人間失格』のような暗い作品でも例外ではない。
太宰はなぜ小説を書いたのだろうか。そして私はなぜ小説にこだわって書きつづけているのだろうか。「道化の華」のなかに、たとえば次のような一節がある。
《僕はなぜ小説を書くのだらう。困ったことを言ひだしたものだ。仕方がない。思はせぶりみたいではあるが、假に一言こたへて置かう。「復讐。」》
思わずドキッとするこの「復讐」には、色んな意味があって、とても一筋縄ではゆかない。太宰の作品には、そういうドキッとさせられる言葉やアイロニーにみちたフレイズがいっぱいきらめいている。そういう太宰の小説を読んだからこそ、私は小説が書きたくなり、現在も書きつづけているのだと思う。
|
|トップへ | essay目次へ |
|