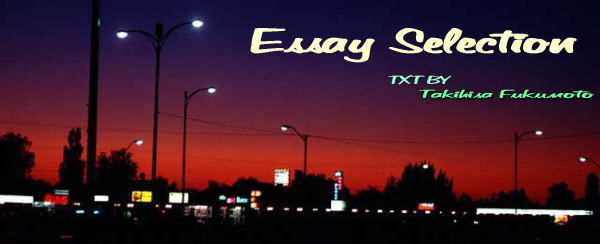 |
福本 武久
ESSAY
Part 1 |
福本武久によるエッセイ、随筆、雑文などをWEB版に再編集して載録しました。発表した時期や媒体にとらわれることなく、テーマ別のブロックにまとめてあります。
新聞、雑誌などの媒体に発表したエッセイ作品は、ほかにも、たくさんありますが、散逸しているものも多く、とりあえず掲載紙が手もとにあるもの、さらにはパソコンのファイルにのこっているものから、順次にアップロードしてゆきます。 |
| わが小説の舞台裏……さまざまな出会い |
|
| 初出:雑誌「新刊ニュース 9月号」(東京出版販売株式会社) 1978.09 |
電車ごっこ停戦後譚
|
|
一つの小説が出来上がり、活字になると、もうそれは作者の手から遠く離れ独り歩きを始める。そればかりか個の存在として作者にすら歯向かってくる。まるで成人した息子が親父に対するさまに似ている。不精髭を生やした息子が置いた親父を胡散臭そうに見下ろしている。そんな構図が眼に浮かぶ。どこか不遜な態度で、そして不機嫌な面持ちで見つめられていたりして思わずギョッとする。第一稿の仕上がった頃に感じた、あのまろやかで、そしてつつましく、それでいて、確かに息づいている、まるで赤児のようなな手触りほ、どこを損じでも見つからい。醜悪であすらある。
「電車ごっこ停戦」が他の一編とともに単行本になることになった。想いはやはり同じである。
けれども何故かホッとした安堵を覚える。ああ、これえでやっとあいつらから自由になれる。そんな開放感にも似た爽快さがある。収録された二作品は、いずれもぼくの手許に長く居候し続けた不肖のの息子たちであるからなのだろうか。
「電車ごっこ停戦」では、障害児と、その両親に日常を父親の視点から切り取った。親は被害者であるとともに加害者である。一方では障害児を持った責任を社会から押しつけられながら、他方では、自分たちも差別者として、そのこどもに相対している。親の視点に立ちながら、ぼくはその親をも突っ放して描いた。
障害のあるこどもをかかえての心中事件が後を断たない。いずれも親の立場から視れば納得できなくはない。生きのびているのは、たかたまそういう機会に恵まれないだけだという気もうる。そしてこの種の事件には、どういうわけか親にのみ世の同情が集まる。自ら望みもしない死を無理強いされたこどもの方は黙殺されてしまう。救われないと思う。これは「福祉社会」を表看板に掲げながらも、障害のある人々を家庭と家族の中に開じこめている現在の障害福祉行政のあり方と奇妙に辻褄が合う。
作品の中でばくは一人の健常でないこども<マサオ>を登場きせた。そしてあえて精神薄弱とも知恵遅れともそれに類することばで注釈を加えなかった。一切を読者にまかせようという意図をひそかに持っていた。そういう既製のことばでもっては、とてもこどもの実態を正確に捉まえることはできないと思うからである。
ある人は精薄といい、ある人は知恵遅れといい、またある人は自閉症児、言語障害児というだろう。ぼくほそれを聞いてひとりほくそえむ。そこで初めて作者と読者のコミュニケーションに発展するからである。けれども「この児の病名は何ですか?」と人に問われるとぼくは絶句してしまう。実のところ作者ですら、的確なことばでそれを表現することはできないからである。
「ぼくは医者ではありません」としか応える術がない。
「電車ごっこ停戦」の一家はその後どうしただろう。一筋縄ではいかぬ連中はかりだから、<マサオ>を中心にやはり、どこかで恰好悪く生きているだろう。
作品を措いた時間的経過からすれば、<マサオ>はもう一年生になっているはずだ。おそらく特殊学級に通っているのだろう。夏休みには海水浴に行っただろうか。なんでも最近、五、六年の女の児がマサオの親衛隊を組織したと聞く。さもあろう。両親に似合わずマサオは端正な容貌の持主である。ワンポイントのキャラクターにさえなりそうだ。親衛隊のかわい児ちゃん達は毎日家にまでやって釆てあれこれ世話をやいてYれるという。母親は急かに多くの子持になったようでうれしい悲鳴をあげ、父親は「あいつばかりが何故モテるのか」と不貞腐れているそうな。(了)
|
|トップへ | essay目次へ |
|