 |
“ŒٹC‘هپIپ@ڈo‰_ژjڈم‚ـ‚ê‚ة‚ف‚鈳ڈںŒ€پI
|
(2006.10.10) |

‚Q–‡ٹإ”آ‚ة‚‚ي‚¦‚ؤپAŒq‚¬‚à‚ج‘Iژè‚àچD‘–
پ@–j‚©‚çژٌ‹ط‚ة‚©‚¯‚ؤ‚جٹ¾‚ھپAڈH‚ج‚â‚ي‚ç‚¢‚¾—zŒُ‚ً›‚ث‚ؤپA‚«‚ç‚«‚ç‚ئŒُ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBƒSپ[ƒ‹‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ‚ذ‚½‘–‚éچ²“،—IٹîپAڈم”¼گg‚ھƒNƒ‹پ[ƒYƒAƒbƒv‚³‚ê‚邽‚ر‚ةپA‚»‚ج–¬‘إ‚آ‘§Œ‚¢‚ھ‚©‚·‚©‚ة•·‚±‚¦‚ؤ‚‚é‚و‚¤‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@“ŒٹC‘ه‚جچ²“،—IٹîپcپcپB‚P”Nگ¶‚ة‚µ‚ؤٹwگ¶’·‹——£ٹE‚جƒGپ[ƒX‚ئ‚¢‚ي‚êپA‚Q”Nگ¶‚ة‚ب‚ء‚½‚¢‚ـ‚ح’ل–ہ‚·‚é“ْ–{’·‹——£‚ج‹~گ¢ژه‚ئ‚ب‚è‚آ‚آ‚ ‚éپBچ،‰ؤ‚جƒˆپ[ƒچƒbƒp‰“گھ‚إ‚حƒCƒ^ƒٹƒAپEƒچƒxƒŒپ[ƒg‚جچ‘چغ‘ه‰ï‚إ5000m‚جژ©ŒبƒxƒXƒg‚ً6•b‹ك‚چXگVپA13•ھ23•b57‚ح“ْ–{—ً‘م6ˆت‚ة‘ٹ“–‚·‚éƒ^ƒCƒ€‚إ‚ ‚éپBٹwگ¶‚ة‚µ‚ؤ“ْ‚جٹغ‚ً”w•‰‚¦‚é’·‹——£ƒ‰ƒ“ƒiپ[‚ج“oڈê‚حپAژہ‚ة‚ذ‚³‚µ‚ش‚è‚ج‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚©‚낤‚©پB
‚U‹و‚ًژ¾‘–‚·‚éچ²“،—Iٹî
 |
پ@ƒSپ[ƒ‹’¼‘O‚إƒTƒ“ƒOƒ‰ƒX‚ً‚ئ‚ء‚½چ²“،پA‚·‚é‚ئ—ح‹‚¢‘–‚è‚ئ‚ح— • ‚ةپA‚¢‚©‚ة‚à‘هٹw‚Q”Nگ¶‚炵‚¢‘u‚â‚©‚ب•\ڈî‚ھ—n‚¯ڈo‚µ‚ؤ‚«‚½پB‚ك‚¸‚炵‚Œم‚ë‚ًگU‚è•ش‚ء‚½‚ج‚حˆ¤›g‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚©پB
پ@چ²“،‚ح‚P”Nگ¶‚¾‚ء‚½چً”N‚ج–{‘ه‰ï‚إ‚ح‚Q‹و‚ة“oڈêپA‚ق‚ë‚ٌ‹وٹش‚Pˆت‚إ“ŒٹC‘هڈ‰گ§”e‚ج‘«‚ھ‚©‚è‚ً‚آ‚‚ء‚½پBچ،‰ٌ‚ح–‚ًژ‚µ‚ؤپAچإ’·‹وٹش‚ج‚U‹و‚ً‚ـ‚©‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@“ŒٹC‘ه‚ح‚R‹و‚ةچً”N‚جƒAƒ“ƒJپ[پEˆة’BڈGچWپA‚U‹و‚ةچ²“،—Iٹîپcپc‚ئپAƒXپ[ƒpپ[ƒGپ[ƒX‚Q–‡‚ً”z‚µ‚ؤپA‚ـ‚³‚ةکA”e‚ةŒü‚¯‚ؤ–œ‘S‚ج‘شگ¨‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@’Z‚¢‹——£‚ً‚آ‚ب‚®ڈo‰_‰w“`‚حپAڈں•‰‚ج‚ن‚‚¦‚ھ‚¢‚آ‚àچإڈI‹و‚ـ‚إژ‚؟‰z‚³‚ê‚é‚ج‚¾‚ھپAچ،‰ٌ‚ح‚ك‚¸‚炵‚پAڈH“ْکa‚³‚ب‚ھ‚ç‚ج‰¸‚â‚©‚³‚إ‚ ‚ء‚½پBƒXپ[ƒpپ[پEƒGپ[ƒX‚ئ‚¢‚ي‚ê‚éچ²“،—Iٹî‚جƒ^ƒXƒL‚ھ‚ي‚½‚é‚ـ‚إ‚ةپA’ا‚ء‚ؤ‚‚é“ْ‘ه‚ئ‚ج‚ ‚¢‚¾‚ة‚P•ھ11•b‚à‚جچ·‚ھ‚ ‚ê‚خپA‚·‚إ‚ة‚µ‚ؤڈں•‰‚حŒˆ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@ژR—œ‚جƒ‚ƒOƒX‚ح‚ح‚é‚©Œم•ûپA–â‘è‚ح‚Qˆت‚ج“ْ‘هپEƒ_ƒjƒGƒ‹‚¾‚ھپA‚P•ھˆبڈم‚جƒ^ƒCƒ€چ·‚ھ‚ ‚ê‚خپA‚²‚‚س‚آ‚¤‚ة‘–‚ê‚خ‚»‚ê‚إ‚¢‚¢پB‹وٹش‚Sˆت‚ئ‚¢‚¦‚خپAچ²“،‚ة‚µ‚ؤ‚ف‚ê‚خ–}‘–‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ھپA‚»‚ê‚ح‹£‚èچ‡‚¤“WٹJ‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚©‚炾‚낤پB
پ@‚©‚‚µ‚ؤچ²“،—Iٹî‚حٹyپX‚ئ“¦‚°پA‚¢‚©‚ة‚àƒŒپ[ƒX‚ج—]‰C‚ًٹy‚µ‚ق‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA‚±‚ê‚ھ‰w“`‚ج‘–‚肾‚ئ‚¢‚ي‚ٌ‚خ‚©‚è‚ةپAƒ^ƒXƒL‚ً‰Eژè‚إچ‚پX‚ئ‚©‚©‚°پAڈخٹç‚إ‚QکA”e‚جƒSپ[ƒ‹‚ة‚ئ‚ر‚±‚ٌ‚¾‚ج‚إ‚ ‚éپB
‹t“]Œ€‚ج‚ب‚©‚ء‚½پuڈo‰_پv‚حڈ‰‚ك‚ؤپH
پ@‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپcپcپB
پ@’Z‚¢‹——£‚ج‰w“`‚ب‚ھ‚çپA‹£‚èچ‡‚¤‚±‚ئ‚ج‚ب‚¢پAٹد‚é‰w“`‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژRڈê‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚ھ‚ب‚¢پBٹدگي‚·‚éƒtƒ@ƒ“‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA‚¢‚³‚³‚©•¨‘«‚è‚ب‚¢‘ه‰ï‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@ڈo‰_‰w“`‚ئ‚¢‚¦‚خƒAƒ“ƒJپ[Œˆ’…پcپcپBƒAƒ“ƒJپ[ڈں•‰‚ئ‚¢‚¦‚خڈo‰_‰w“`پcپc‚ئ‚¢‚¤‚®‚ç‚¢ٹل—£‚µ‚إ‚«‚ب‚¢‰w“`ƒŒپ[ƒX‚إ‚ ‚éپBژ–ژہ‚±‚ج‚ئ‚±‚ë‚T”NکA‘±‚إپAڈں•‰‚ح‚U‹و‚ةژ‚؟‰z‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‚T”N‚ـ‚¦‚ج13‰ٌ‘ه‰ï‚حپAڈ‡“V“°‚جٹâگ…‰أچF‚ھ‹îàV‚جگ_‰®گLچs‚ً”²‚«‹ژ‚ء‚ؤ‹t“]—DڈںپB14‘ه‰ï‚إ‚حپAژR—œ‚ج‚nپEƒ‚ƒJƒ“ƒo‚ھ40•bچ·‚ً‹l‚ك‚ؤپAگ_“قگى‘ه‚ً‘ه‹t“]پB15‰ٌ‘ه‰ï‚إ‚ح‚Qˆت‚إƒ^ƒXƒL‚ًژَ‚¯‚½“ْ‘ه‚ج“،ˆنژüˆê‚ھƒ‰ƒXƒgƒXƒpپ[ƒg‚إ‹î‘ٍˆب‰؛‚ً”²‚«‹ژ‚ء‚½پB16‰ٌ‘ه‰ï‚إ‚ح“ْ‘ه‚ج‚cپEƒTƒCƒ‚ƒ“‚ھ‘O‚ً‚ن‚‹î‘ٍ‚ً‚ئ‚炦‚ؤ‚QکAڈںپB‚»‚µ‚ؤ‘O‰ٌ‚ج17‰ٌ‘ه‰ï‚ح‹î‘ٍ‚جچ²“،گTŒل‚ئ“ŒٹC‚جˆة’BڈGچW‚ھ‹£‚èچ‡‚¢پAˆة’B‚ھˆê‹C‚ة‚ئ‚ر‚¾‚µ‚ؤپAڈ‰—Dڈں‚جƒeپ[ƒv‚ًگط‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@چ،‰ٌ‚ظ‚اƒŒپ[ƒX‚ھ‚½‚ٌ‚½‚ٌ‚ئگi‚فپA‚½‚ٌ‚½‚ٌ‚ئڈI‚ي‚ء‚½‚ج‚حپAڈo‰_‰w“`‚ج—ًژj‚ً‚©‚¦‚è‚ف‚ؤ‚àڈ‰‚ك‚ؤ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚©پHپ@‚ذ‚é‚ھ‚¦‚ء‚ؤچl‚¦‚ê‚خپA‚»‚ꂾ‚¯“ŒٹC‘هٹw‚ھ‹‚©‚ء‚½پB—‘z“I‚ب‚©‚½‚؟‚إƒŒپ[ƒX‚ً‚آ‚‚ç‚êپA‘¼چZ‚ح‚ب‚·‚·‚ׂà‚ب‚”s‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‚P‹و‚جچrگىڈنچO‚ھƒgƒbƒv‚ئ‚»‚ê‚ظ‚اچ·‚ج‚ب‚¢‚Vˆت‚ة‚آ‚¯‚é‚ئپA‚Q‹و‚جگ™–{ڈ«—F‚ھ‹وٹشگV‹Lک^‚إƒgƒbƒv‚ة—§‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB‚»‚µ‚ؤ‚R‹و‚ة”z‚µ‚½ƒGپ[ƒX‚جˆة’BڈGچW‚ھپA‚ا‚ٌ‚ا‚ٌ“¦‚°‚ؤ‚Qˆت‚ج“Œ—mپA‚Rˆت“ْ‘هپA‚Sˆت‹î‘ٍ‚ة‚P•ھˆبڈم‚جچ·‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚جژ“_‚إ‚·‚إ‚ة‚µ‚ؤڈں•‰‚حŒˆ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@“ŒٹC‘ه‚ج‚S‹و‚حچً”N‚T‹و‚إ‹وٹش‚Pˆت‚جٹF‘qˆê”n‚¾‚ھپA—ژ‚؟’…‚¢‚ؤژèŒک‚Œq‚¬پA‚T‹و‚ة“oڈꂵ‚½“،Œ´ڈ¹—²‚ح‹وٹشگV‹Lک^‚ج‰ُ‘–پcپc‚ئ‚ب‚ê‚خپA‚آ‚¯‚±‚ق‚錄‚ئ‚¢‚¤‚ج‚à‚ج‚ھ‚ـ‚ء‚½‚Œ©‚ ‚½‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@ٹدگي‚·‚é‚ظ‚¤‚ح‚¢‚³‚³‚©•¨‘«‚è‚ب‚¢ƒŒپ[ƒX‚¾‚ھپAژہچغ‚ةƒŒپ[ƒX‚ة‚ج‚¼‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ظ‚¤‚©‚ç‚·‚êپA‚ـ‚³‚ة‰ïگS‚جƒŒپ[ƒX‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ ‚é‚ـ‚¢‚©پB
ڈں•‰‚ً•ھ‚¯‚½‚ج‚ح‚P‹و‚©‚ç‚R‹و‚ـ‚إ‚ج—¬‚ê
پ@‚»‚ٌ‚ب‚ب‚©‚إŒ©‚ا‚±‚ë‚ً‚ ‚°‚ê‚خپA‘O”¼‚ج‚P‹و‚ج‚©‚ç‚R‹و‚ج—¬‚ê‚إ‚ ‚낤‚©پB
پ@چإ‹ك‚ج‚P‹و‚ئ‚¢‚¦‚خپA‚ئ‚©‚Œ،گ§‚µچ‡‚ء‚ؤپAƒXƒچپ[‚ج“ü‚è‚ة‚ب‚é‚ج‚¾‚ھپA–¼Œأ‰®‘ه‚ج’†‘؛چ‚—m‚ھڈ¬‹C–،‚و‚¢”ٍ‚رڈo‚µ‚ً‚ف‚¹پA‚»‚ê‚ھƒyپ[ƒX‚ئ‚µ‚ؤ‚حگâچD‚ج—¬‚ê‚ًگ¶‚ٌ‚¾پB‚R‡q‚ـ‚إ‚ح–¼Œأ‰®پA“Œ—mپA–@گپA‹î‘ٍپA—§–½پA’†پEژlچ‘‘I”²پA‘وˆêچH‹ئپA“ْ–{‘هپA“ْ‘ج‚ب‚ا‚ھ‚ذ‚µ‚ك‚«‚ ‚¤“WٹJپA‚R‡q‚·‚¬‚ؤ–@گ‚جڑ¢ˆن‰e•F‚ھˆّ‚ء’£‚è‚ح‚¶‚ك‚½‚ئ‚±‚ë‚إپAژR—œ‚ج‘ه‰z’¼چئ‚ھ‚¶‚肶‚è‚ئ’x‚êژn‚ك‚ؤ‘پ‚‚à’E—ژ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@5‡q‚ج’ت‰ك‚ھ14•ھ32•bپA‚¨‚و‚»10ƒ`پ[ƒ€‚ھڈW’c‚ًŒ`گ¨‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA6‡q•t‹ك‚إڈ‡“V“°‚ج‘هپEگ´–ىڈƒˆêپA“ْ‘ج‘ه‚جکhŒ©’m•F‚ھ‹ê‚µ‚‚ب‚èپA’E—ژ‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@ژR—œ‚ئ‚¢‚¢پAڈ‡“V“°‚ئ‚¢‚¢پA“ْ‘ج‘ه‚ئ‚¢‚¢پA—DڈںŒَ•â‚ئ‚¢‚ي‚ꂽƒ`پ[ƒ€‚ھپA‚±‚±‚إ‘پ‚‚à—Dڈںگيگü‚©‚ç’E—ژ‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB“ŒٹC‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ح“WٹJ“I‚ة‚à‚ك‚®‚ـ‚ꂽ‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚¢پB
پ@‚V‡q‚إ‚ح“Œ—mپA’†پEژlچ‘‘I”²پA–@گپA“ŒٹCپA‹îàVپA‘وˆêچH‹ئپA—§–½‚ج‚Vƒ`پ[ƒ€‚ھƒgƒbƒvڈW’c‚ًŒ`گ¨پAˆںچ׈ں‚ج‹e’rڈ¹ژُپA“ْ‘هپE“y‹´Œ[‘¾‚ھ’x‚êژn‚ك‚éپBچإŒم‚ح‹îàV‚جˆہگ¼ڈGچK‚ھƒXƒpپ[ƒgپA’†پEژlچ‘‘I”²‚ج‚rپEƒKƒ“ƒKپA“Œ—m‚ج‰ھژR—؛‰îپA–@گ‚جڑ¢ˆن‰e•F‚ç‚ًگU‚èگط‚ء‚ؤپA‹وٹشگV‹Lک^‚إƒ^ƒXƒL‚ً‚آ‚ب‚¢‚¾پB
پ@“ŒٹC‚ح14•b’x‚ê‚ج‚VˆتپA“ْ‘ه‚ح20•b’x‚ê‚ج‚Wˆت‚ئپA‚ـ‚¸‚ـ‚·‚جƒXƒ^پ[ƒg‚ًگط‚ء‚½‚ھپAڈ‡“V“°‚ح36•b’x‚ê‚ج10ˆت‚ئŒمژè‚ً“¥‚فپAچً”N‚Qˆت‚ج’†‰›‚ح‚P•ھ02•b’x‚ê‚ج13ˆتپA“ْ‘ج‘ه‚ح‚P•ھ18•b’x‚ê‚ج15ˆتپA‘ه–Cƒ‚ƒOƒX‚ً‚à‚آژR—œ‚ح1•ھ27•b‚à’x‚ê‚ً‚ئ‚èپA‚»‚ꂼ‚ê—Dڈںگيگü‚©‚ç’E—ژ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ˆسٹO‚ب“WٹJ‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@‚Q‹و‚إ‚ح‘وˆêچH‹ئ‚جƒ€ƒ^ƒC‚ًگو“ھ‚ة–@گپA‹îàVپA’†پEژlچ‘‘I”²پA“Œ—m‚ج‚Tƒ`پ[ƒ€‚ھƒgƒbƒvڈW’c‚ًŒ`گ¬پA‚»‚ج‚ب‚©‚©‚ç‚ذ‚ئ‚½‚رƒ€ƒ^ƒC‚ھ”ٍ‚رڈo‚µ‚ً‚ف‚¹‚é‚ج‚¾‚ھپA–@گ‚جڈ¼ٹ_ڈبŒلپA“Œ—mپA‹îàV‚ج–LŒم—Fڈح‚ھ‚آ‚أ‚«پA“ŒٹC‚جگ™–{ڈ«—F‚ھ’ا‚¢ڈم‚°‚ؤ‚‚éپB4.8‡q‚إ‚حƒgƒbƒvڈW’c‚ً‚ئ‚炦‚½گ™–{‚ھگ¨‚¢‚ةڈو‚¶‚ؤپAچإŒم‚ةƒXƒpپ[ƒgپAƒ€ƒ^ƒC‚ًˆب‰؛‚ً‚س‚è‚«‚ء‚ؤ‘ز–]‚جƒgƒbƒv‚ة—§‚ء‚½پB02•bچ·‚إ“ْ‘هپA‹îàV‚ھ‚آ‚أ‚«پA—Dڈں‘ˆ‚¢‚ح‚ظ‚ع‚Rƒ`پ[ƒ€‚ة‚ع‚ç‚ꂽپB
‚P‹و‚جڈo’x‚ê‚ھ‚ذ‚ر‚¢‚½‚©پB’ا‚¢گط‚ê‚ب‚©‚ء‚½“ْ‘ه
پ@‚R‹و‚إƒgƒbƒv‚ً’D‚¤—\’è‚إ‚ ‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚é“ŒٹC‚حپA‚»‚ꂾ‚¯‚ة‚R‹و‚حٹy‚ب“WٹJ‚ة‚ب‚ء‚½پBچً”N‚حƒAƒ“ƒJپ[‚ئ‚µ‚ؤ‹îàV‚ً‹£‚è‚آ‚ش‚µ‚½ˆة’BڈGچW‚حپA‚ ‚ج‚ئ‚«‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ة—]—T‚ً‚à‚ء‚ؤ‚·‚é‚·‚é‚ئ“¦‚°پA‚S‡q‚إ‚حŒم‘±‚ة‚T‚O‚O‚چˆبڈم‚جچ·‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB‚ن‚邬‚ج‚ب‚¢ˆہ’肵‚½‘–‚è‚إپAچ·‚ح‚ذ‚炈ê•ûپcپcپB“ْ‘هپA‹î‘ه‚حˆة’B‚ة‚ث‚¶‚س‚¹‚ç‚ꂽ‚µ‚ـ‚¢پA‚©‚ي‚ء‚ؤ‚Qˆت‚ة‚ح“Œ—m‚ھ•‚ڈم‚µ‚ؤ‚‚éپB‚±‚جˆة’B‚ج‰ُ‘–‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚QکA”e‚ح‚ظ‚ع“®‚©‚ت‚à‚ج‚ئ‚ب‚ء‚½پB
‚R‹وپEˆة’BڈGچW
 |
پ@‹îàV‚جڈںˆِ‚حƒ‚پ[ƒ`ƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“‚جچ‚‚³‚ة‚ ‚邾‚낤پBچً”N‚جڈں—ک‚ح‹ô‘R‚ج—v‘f‚ھ‹‚©‚ء‚½‚ھپAچ،”N‚حˆسژ¯‚µ‚ؤڈں‚؟‚ة‚¢‚ء‚½پcپc‚ئپAٹؤ“آ‚جڈں—کƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚ة‚à‚ ‚é‚و‚¤‚ةپAژ©گM‚ً‚à‚ء‚ؤƒŒپ[ƒX‚ة‚ج‚¼‚ٌ‚إ‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚ ‚éپBژ–ژہپA‘S“ْ–{‚ةڈoڈêŒ ‚ب‚¢“ŒٹC‚ة‚µ‚ؤ‚ف‚ê‚خ” چھ‚¢‚ھ‚¢‚حڈo‰_‚µ‚©‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@‚Qˆت‚ج“ْ‘ه‚ح‚R‹و‚إˆة’B‚ة‚P•ھ‚àپA‚à‚ء‚ؤ‚¢‚©‚ꂽ‚ج‚ھ’ة‚©‚ء‚½‚©پB‚S‹وپA‚T‹و‚حژ‚؟‚±‚½‚¦‚ؤ‚¨‚èپAƒAƒ“ƒJپ[‚ة‚حƒ_ƒjƒGƒ‹‚ھ‚ذ‚©‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚ةپA‰÷‚¢‚ھژc‚é‚ئ‚±‚낾‚낤پBپ@‘O”¼‚حڈمˆت‘ˆ‚¢‚ً‰‰‚¶‚ؤ‚¢‚½‹îàV‚ح‚R‹وˆبچ~‚حگL‚ر‚«‚ꂸپAچإڈI“I‚ة‚ح‚Tˆت‚ةٹأ‚ٌ‚¶‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB’n—ح‚ ‚éƒ`پ[ƒ€‚¾‚¯‚ة‘S“ْ–{‚إ‚ا‚ج‚و‚¤‚ة—§‚ؤ’¼‚µ‚ؤ‚‚é‚©پA‚µ‚ء‚©‚茩’è‚ك‚½‚¢پB
‚R‹وپE“ŒٹC‚ً’ا‚¤‚QˆتڈW’c
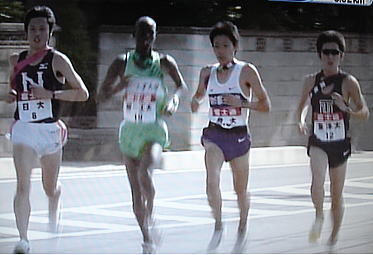 |
پ@ڈ‡“V“°‚ح‚P‹و‚إڈo’x‚ꂽ‚ج‚ھ‚·‚ׂؤپAژه—ح‚ً‚Q–‡‚خ‚©‚茇‚¢‚ؤ‚جڈoڈꂾ‚¯‚ةپAچإڈI‚Xˆت‚ةڈI‚ي‚ء‚½‚ھپAگِچف”\—ح‚ح‚±‚ٌ‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ق‚µ‚ë‘S“ْ–{پA” چھ‚ج‚ظ‚¤‚ھ—ح‚ً”ٹِ‚·‚邾‚낤پB
پ@‚à‚¤‚ذ‚ئ‚آ‚جŒَ•â‚¾‚ء‚½“ْ‘ج‘ه‚ح‚P‹و‚جکhŒ©‚إ15ˆت‚ة’¾‚ٌ‚¾‚ج‚ھŒëژZ‚¾‚ء‚½‚낤پB‚U‹و‚ج–k‘؛‘ڈ‚ھ‹وٹش2ˆت‚إ’ا‚¢ڈم‚°پAچإڈI“I‚ة‚Sˆت‚ـ‚إ‚ ‚ھ‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚ةپAچ،”N‚à•ژ‚ê‚ب‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپB
‘هŒ’“¬‚ج“Œ—m‘ه‚ح‘ن•—‚ج–ع‚ة‚ب‚é‚©پH
پ@‚³‚ç‚ةپA‚à‚µ‚©‚·‚é‚ئپcپc‚ئ‚¢‚¤ˆسٹOگ«‚جٹْ‘زٹ´‚ھ‚ ‚ء‚½ژR—œ‚¾‚ھ‚P‹و‚إ17ˆت‚ئڈo’x‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚حپA‚ا‚¤‚µ‚و‚¤‚à‚ب‚پA‚»‚±‚إƒŒپ[ƒX‚حڈI‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB‚¢‚‚烂ƒOƒX‚ئ‚¢‚¤‘ه–C‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپAٹˆ‚©‚µ‚و‚¤‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚ׂ«‚إ‚ ‚éپB
پ@Œ’“¬‚µ‚½‚ج‚ح“Œ—m‚¾‚낤پB‚P‹و‚إچ·‚ج‚ب‚¢‚Rˆت‚ة‚آ‚¯‚ؤپA—¬‚ê‚ةڈو‚ء‚½پBڈIژn‚QˆتپA‚Rˆت‚ة‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ح‹ء‚‚ׂ«‚إپA‚»‚ج‘چچ‡—ح‚½‚é‚â‚©‚ب‚è‚ج‚à‚ج‚ئ•]‰؟‚µ‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚é‚ـ‚¢پB
پ@چً”N‚ح” چھ‚إ•œکH—Dڈں‚µ‚½–@گ‚à‘O”¼‚حچDˆت’u‚ًƒLپ[ƒvپAچإڈI‚Vˆت‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚ـ‚¸‚ـ‚¸‚ئ‚¢‚ء‚½‚ئ‚±‚ëپB” چھ‚ج”eژز‚إ‚ ‚éˆںچ׈ں‚ج‚Wˆت‚àپAڈo‰_‚ج‚و‚¤‚بƒXƒsپ[ƒh‰w“`‚إ‚حپA‚ـ‚ پA‚±‚ٌ‚ب‚à‚ج‚¾‚낤پB
‚QˆتڈW’cپA“Œ—m‘ه‚ھ”²‚¯‚¾‚·پI
 |
پ@ٹْ‘ز‚ً— گط‚ء‚½‚ج‚ح’†‰›‚إ‚ ‚éپBچً”N‚Qˆت‚جƒ`پ[ƒ€‚إ‚ ‚éپB‚¢‚‚çژه—ح‚ًŒ‡‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ح‚¢‚¦پA10ˆتˆب‰؛‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚낤پBŒ»چف‚ج‚ئ‚±‚ëپAچ،”N‚جگي—ح‚ح‚¢‚ـ‚ذ‚ئ‚آگ®‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚ف‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚é‚ـ‚¢پB
پ@ڈo‰_‚إ‚ف‚é‚©‚¬‚èپA—Dڈں‚µ‚½“ŒٹC‚ح‚ئ‚à‚©‚پA“ْ‘هپA“Œ—m‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚ھڈ‡’²‚ة‚«‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB‹îàVپA’†‰›‚ح‘S“ْ–{‚إ‚ا‚ج‚و‚¤‚ةƒ`پ[ƒ€‚أ‚‚è‚ً‚µ‚ؤ‚‚é‚ج‚©پBƒTƒvƒ‰ƒCƒYˆںچ׈ں‚à‚س‚‚ك‚ؤپA‚ئ‚‚ئŒ©’è‚ك‚½‚¢پB
پ@–â‘è‚ح“ŒٹC‚إ‚ ‚éپBچً”N‚àڈo‰_‚إڈں‚؟‚ب‚ھ‚çپA‘S“ْ–{‚جڈoڈêŒ ‚ح‚ب‚پA‚»‚ج‚ـ‚ـ” چھ‚ةŒü‚©‚ء‚½‚ھپA—DڈںŒَ•â‚ج•M“ھ‚ة‚ ‚°‚ç‚ê‚ب‚ھ‚çپAژS”s‚ةڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚éپBچ،”N‚à“¯‚¶ƒvƒچƒZƒX‚ً“¥‚ٌ‚إ‚ن‚‚ي‚¯‚¾‚ھپA‹ك”N‚حپAڈo‰_پA‘S“ْ–{‚جƒXƒeƒbƒv‚ًŒo‚ب‚¢‚إ” چھ‚ًگ§”e‚µ‚½—ل‚ھ‚ب‚¢‚¾‚¯‚ةˆê–•‚ج•sˆہ‚ھ‚ ‚éپB
پ@چً”N‚جٹwڈKŒّ‰ت‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ةٹˆ‚©‚µ‚ؤ” چھ‚ة‚ج‚¼‚ٌ‚إ‚‚é‚ج‚©پB‚ئ‚ة‚©‚‚»‚ج‚ ‚½‚è‚àٹـ‚ك‚ؤ“ŒٹC‚ج“®Œü‚ة‚ح‹»–،گ[‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپB
|
|
|
|
|
 |
|
| ڈoڈêƒ`پ[ƒ€&‰ك‹ژ‚ج‹Lک^ |
|
|
 |
| ٹض کA ƒT ƒC ƒg |
|
|
 |
|
