| 7:50 鏡島付近スタート 加納宿手前の本荘の辺りに中山道の道案内が掲示されていた。 この辺りは岐阜市の街なかで、どの道が中山道か迷うところ。 丁寧な道案内の表示があったおかげで迷わずに歩けた。 |
 |
| 8:30 加納宿の街並み 加納宿そのものは濃尾地震と戦災で古い家は殆ど無くなったらしいが、雰囲気を残した家もある。 |
 |
| 8:35 加納宿 加納宿は岐阜駅の南側すぐの辺り。駅前の高層マンションが町並みの向うにそびえる。 何故かはわからないが、この加納宿には秋葉神社が多い。宿の町内だけで4〜5カ所あるようだ。火の神様だから、火事が出るたびに建てたのかもしれない。 |
 |
| 8:35 岐阜駅前 岐阜駅南側300mのところを中山道が通っている。 |
 |
| 8:40 加納宿にある下水の蓋 この加納宿の路側帯の下水の蓋はここ専用のもの。 でも面白いことに同じ加納宿でも東の方はデザインが変わる。 (次の写真参照) |
 |
| 9:05 加納宿東側にある下水の蓋 さっきの蓋との違いは下半分に「御鮨街道」という言葉が入っていること。どちらも結構最近のもののようで設置している途中で気が変わったのか。 確かに、この辺りは、名古屋に向かう尾張街道で、江戸時代に長良川の鮎で作った鮨を、岐阜から4日で江戸の将軍に届けた御鮨街道と言われている。この辺りの町並みを整えている人の気持ちはわかるが、ここまでこだわるか? |
 |
| 8:45 加納宿道しるべ 順序が前後するが、道沿いにあった道しるべの標石。 字体がきれいなので結構新しいものかもしれない。 |
 |
| 8:50 旧加納町役場 加納宿があったところは昭和15年に岐阜市になるまで稲葉郡加納町だったところ。その当時の町役場。武田五一の設計で大正15年竣工だが水洗トイレがあったのが自慢。1階が町役場、2階は議場だそうだ。 戦後は米軍が使っていたらしい。今は危険なので立ち入り禁止。 近江の旧豊郷小学校のような騒ぎにならないようにきちんと保存して欲しい。 |
 |
| 9:00 南広江の道しるべ ここは、岐阜道と中山道の交差点。真南には加納城がある。中山道は左の加納城の大手門まで進み、そこで右手西方向に曲がる。 岐阜道はここを右、北方向に進むと岐阜城城下に至る。 この道標は最初は江戸中期に作られたが、明治初年に「左西京道」と「右東京道」という言葉が追加された。正面の中山道の文字は江戸時代、左の西京道は明治時代ということ。 明治時代は「西京」、「東京」と呼び分けていたということだが、いつから「西京」という言い方がなくなったのだろうか? |
 |
| 9:05 加納宿の町並み この辺りは戦災で焼け残ったのか古い家が見られる。 |
 |
| 9:05 加納宿加納柳町の旧家 大きな構えの家。大正の頃か? |
 |
| 9:10 加納宿東の枡形 加納宿は枡形が多く、6回直角に曲がる。何故道に迷わないのかという理由がこの写真。 中山道だけカラー舗装されている。この茶色の舗装を辿っていけばいい。 先の下水の蓋といい、このカラー舗装といい、こだわりは半端じゃない。 この勢いで、旧加納町役場も保存してくれればいいのだが。 |
 |
| 9:10 安良町の道しるべ石 「左 西京」「右 岐阜 谷汲」 明治18年の銘。 こうして見ると中山道が一番賑わっていたのは明治、大正の頃ではないかという気がしてくる。もちろん江戸時代のものも多いが、道標などは明治以降のものが結構ある。中山道がということではなく世の中全体の人の動きが活発になったということかもしれない。 |
 |
| 9:15 茶所(ちゃじょ)近くの新荒田川 川沿いの大きな旧家の復刻版? なかなか雰囲気がいい。 |
 |
| 9:30 地蔵堂の道しるべ 「西京道 加納宿(まで)八丁」「伊勢名古屋ちかみち 笠松(まで)一里」とある。 この手前でJR東海道線は南へ離れて行ってしまう。今までずっと東海道線に絡みながら歩いてきた。その線路が離れていくと、何となく文化の薫りから無骨な田舎に変わっていくような気がする。(これはあくまでも私の気分) 話は違うが、笠松とはあのオグリキャップの笠松競馬。木曽川沿いにある。 |
 |
| 9:35 細畑の一里塚(9334歩) 両側現存している一里塚は初登場。美濃の山中には結構両側残っているのは多いが、こんな街中に両側残っているのは貴重。 植わっている木は榎木。 加納宿から3.3kmのところ。 |
 |
| 9:45 細畑付近の旧家 家と言うよりお屋敷と言うべきでしょう。りっぱな門がついた塀。黒を基調に漆喰の白を強調。これでどうも個人の家のよう。 |
 |
| 9:45 切通から見た金華山(岐阜城) 河渡までは金華山の西方になるが、ここは金華山の南方にあたる。 線路は名鉄各務原線。 |
 |
| 9:50 切通の旧家 大きな倉を二つも備えた旧家。造り酒屋か、味噌倉か? |
 |
| 10:10 手力雄神社参道前 ここで中山道は左に曲がる。電柱の脇の道標には「左 東京 善光寺」とある。これも明治以降の設置だろう。 |
|
| 10:45 新加納立場の道標石(15561歩) 加納宿と鵜沼宿の間は17kmと離れているので途中の新加納に立場(間の宿としての休み処)を設けた。 「左 木曽?」、「右 京みち?」と書かれてあるようで鉄柱で支えてある。 ここは、宿場のお約束の枡形(直角曲り)となっている。 立場とは言え、ここには陣屋もあって、昔の地図によれば、町外れに牢獄まであった。 新加納辺りで少し標高が上がり20mとなって濃尾平野とはお別れ。 |
 |
| 10:55 新加納付近の町並み 旧街道は、ほとんど真っ直ぐな道がない。人の踏み跡がそのまま道になったためだろう。 この微妙にうねる道筋を辿っていれば中山道を外すことはまず無くなった。 |
 |
| 12:10 各務原 新加納から鵜沼の間は台地となって、江戸時代は何もない原野だった。そのためか街道らしさはなく、ひたすら国道21号線をトラックと一緒に歩く。 空を見上げると、グライダーが音もなく旋回していた。 各務原の航空自衛隊基地から離陸したものだろう。優雅に2機で舞っていた。 |
 |
| 12:15 各務原 川崎重工 航空自衛隊基地に隣接する川崎重工宇宙航空部門。 この各務原の基地は、飛行場としては日本最古で、大正6年に設営された。2700mの滑走路を持っているが両端で10mの高度差の傾斜がある。この基地は軍用機の試験をやっているところだが、満載の輸送機が上り勾配で離陸するのは大変だろうな。 |
 |
| 13:20 鵜沼羽場町 津島神社皆楽座(28240歩) 近郊の農民の集ったであろう古い舞台。明治24年の濃尾地震で倒壊し明治32年に再建したとある。大きな梁が何本も見えて力強い美しさを見せる。 格子のところが舞台で、観客は手前の地面に筵を敷いて見たという。 近江の神社には、四方から見える神楽殿の形で神社の前庭に置かれた舞台があったが、ここは完全に観客を意識した劇場形式で住民主体。 |
 |
| 13:30 鵜沼宿手前より犬山城を望む 中山道は標高40m程度の台地を進むが、鵜沼宿に近づくと南側が低くなり木曽川に続く。その木曽川越しに犬山城が見えてきた。 犬山城がある山の裾を木曽川が流れている。中山道は、木曽川の右岸を山越えし太田宿で木曽川を渡る。 犬山は愛知県。中山道は愛知県には入らず岐阜県を通っていく。 |
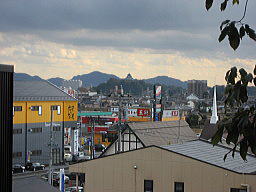 |
| 13:35 路傍の石仏 元禄十一年(1698年)の銘のある観世音菩薩や馬頭観音。 いよいよ、山里に入ってきたなという感じ。 これから木曽路に向かって道祖神や馬頭観音などの石仏が路傍に見られるようになる。 |
 |
| 13:40 鵜沼宿 茗荷屋 160年前に建てられた旅籠。鵜沼宿で唯一濃尾地震で倒壊を免れた家。江戸時代の建物はこれのみ。 |
|
| 13:50 鵜沼宿 菊川酒造 豆蔵 明治から大正にかけて建てられた造り酒屋の本蔵と豆蔵。 |
 |
| 13:50 鵜沼宿 絹屋 旅籠を営んでいたが、明治時代には郵便局になっていた。 濃尾地震で倒壊し再建したが、江戸時代の旅籠の形式を踏襲している。 |
|
| 13:55 鵜沼宿 大安寺橋(31454歩) 鵜沼宿の東端にある木造風の大安寺橋。ここからも犬山城がよく見える。 鵜沼宿は木曽川から離れた高台にある。この辺りの木曽川の流路が確定したのは江戸時代の初めのようで、木曽川の氾濫の怖さからここに置かれたのであろう。 |
|
| 14:00 うとう峠入り口 木曽川岸が切り立った日本ラインと呼ばれる地帯を越えるため、ここから山道に入る。一山越えて太田宿にたどり着く。 |
|
| 14:10 赤坂の地蔵堂(32200歩) 左がうとう峠に続く道。このお地蔵さんは道標にもなっていて、「左ハ江戸併せんこうし」「右ハさいしょみち」とあり、宝暦十三年(1763年)・女人十二講中とある。 この辺りの道標には、ほとんど善光寺の案内があるところを見ると中山道は善光寺詣での講中で賑わっていたのだろう。このお地蔵さんの記載を見ると女性も講を組んで旅をしていたことが伺えて面白い。 今日の中山道の旅はここで終了。 |
 |
| おまけ。 せっかく鵜沼まで来たからには木曽川を眺めてから帰ろうといことで。 14:25 犬山橋 木曽川にかかる犬山と鵜沼を結ぶ鉄橋。ここは11年前までは道路になっていて電車と車が一緒に走っていた。結構ぎりぎりで、おそるおそる電車に並行して走った記憶がある。 2000年に右側に道路橋が出来て電車専用になった。 |
 |
| 14:30 犬山城と対岸の伊木山 木曽川の左岸にそびえる国宝犬山城は室町時代の1537年築城。 現存する最古の天守閣と言われている。 ここからの眺めは最高で眼下の木曽川、各務原の飛行場、遠くは名古屋市内も見え、国宝のお城なのに展望台気分になる。 蛇足ながら、名古屋市の水道の取水口は、このお城の下にある。 |
|
| 14:30 木曽川上流を望む 犬山側から見たうとう峠の山並み。木曽川はここから13kmに渡って日本ラインと呼ばれる急流となる。 その上流も恵那峡や木曽の寝覚めの床など切り込まれた谷筋となっているところが多い。 |
 |